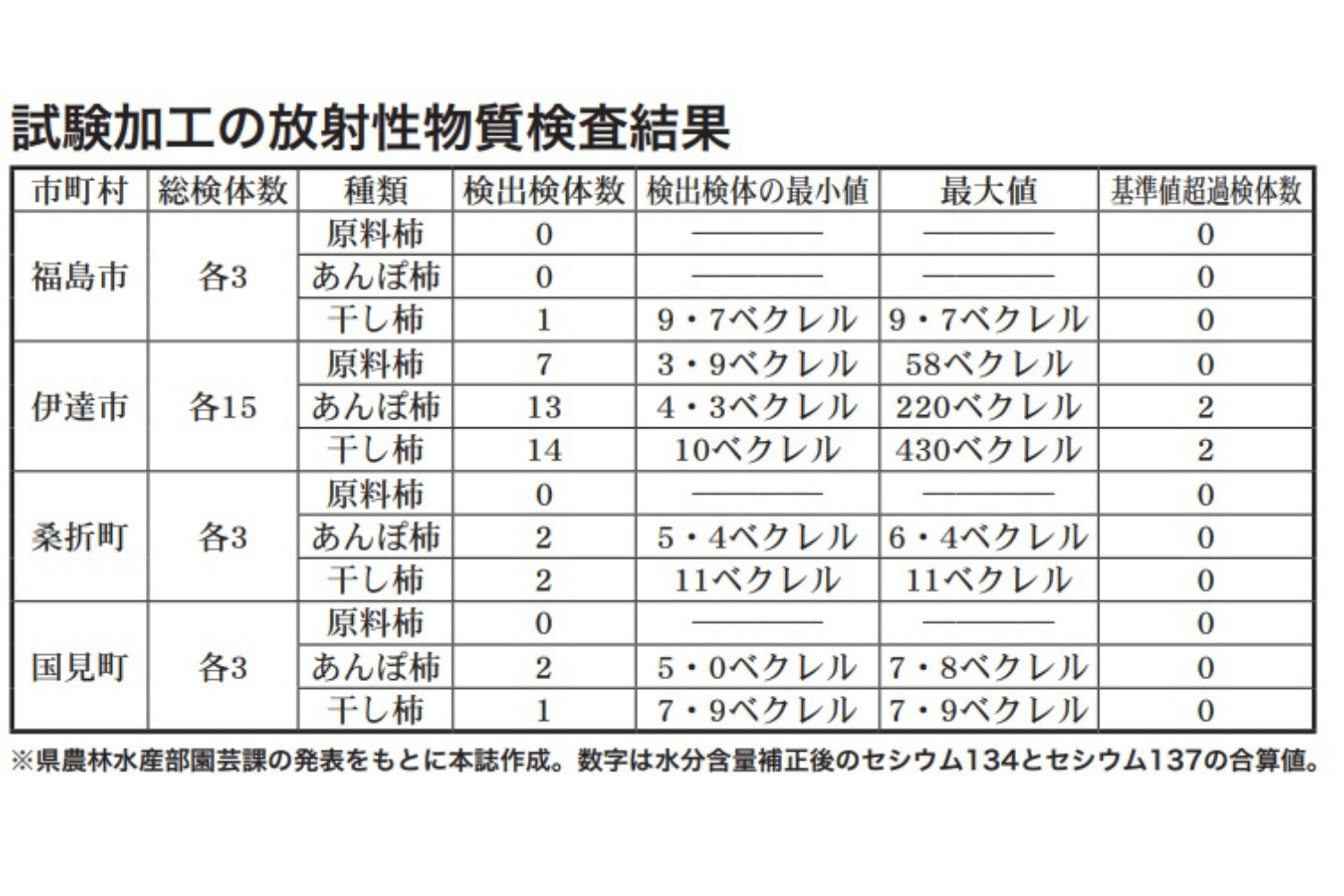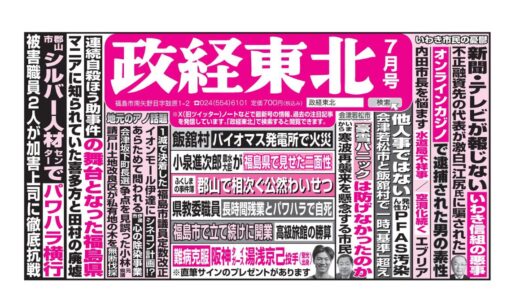震災遺構――。東日本大震災の教訓を後世に語り継ぐ目的で、被害を受けた建造物を保存するもの。ただ、震災から10年以上が経つと、震災遺構の維持管理費の問題が取り沙汰されるようになった。県内では浪江町の請戸小学校が唯一、震災遺構として保存されているが、同町の状況はどうか。
県内唯一の浪江町請戸小学校は入館者横ばい

震災遺構は国により制度化されたもので、当時(2013年11月15日付)、復興庁が発表したリリース「震災遺構の保存に対する支援について」には次のように記されている。
× × × ×
1、趣旨
東日本大震災の津波による惨禍を語り継ぎ、自然災害に対する危機意識や防災意識を醸成する上で一定の意義があるほか、今後のまちづくりに活かしたいとの要望も強い。
(中略)こうしたことから、以下の通り、津波による震災遺構の保存に向けた支援の方針を示す。
2、対応方針
震災遺構の所在する市町村において、課題を整理の上、①復興まちづくりとの関連性、②維持管理費を含めた適切な費用負担のあり方、③住民・関係者間の合意が確認されるものに対して、復興交付金を活用して以下の通り支援する。
○各市町村につき、1箇所までを対象とする。
○保存のために必要な初期費用を対象とする(目安として、当該対象物の撤去に要する費用と比べ過大とならない程度を限度とする)。
○維持管理費については、対象としない。(後略)
× × × ×
震災遺構の保存・整備のために、復興庁が支援するというものだが、これについて、当時、双葉郡内の現職議員は次のように話していた。
「震災の教訓を語り継ぐこと、そのために被害を受けた建物を保存すること自体はいいと思う。ただ、(前出のリリースにあるように)国が(財政的に)面倒を見てくれるのは最初の整備費用で、その後の維持管理費は見てくれない。だから、国の支援を受けて整備したはいいものの、後に重荷になるのではないかと危惧している。最初は多くの人が来てくれるだろうが、年月の経過とともにそういう人は減るだろうから」
実際、この間の全国紙やブロック紙などの報道を見ると、この議員が指摘したようなことが起きている。
例えば、宮城県気仙沼市の気仙沼向洋高校旧校舎。校舎4階まで津波が到達し、高層階の教室に車やがれきが流された光景がそのまま残され、津波の恐ろしさを伝えている。前述の復興庁の制度を活用して、2019年3月に「東日本大震災遺構・伝承館」として開館した。
2020年度は目標を上回る約8万1000人が訪れたが、2023年度は約6万2000人だった。今年度は1月末時点で約4万8000人だから、最終的には5万人台前半くらいと予想される。
運営は指定管理者制度を採用しており、今年度の指定管理料は約3160万円。そのほか、自動ドア、プロジェクター、駐車場の柵などの修繕で約150万円を支出した。来年度は指定管理料の増額に加え、施設劣化に対する修繕費なども計上する予定という。
自治体には、指定管理料を含め、数千万円規模の負担が生じるということ。同市の担当者によると、「入館料だけでは厳しい」とのことで、語り部や企画展示などの実施事業や、ガバメントクラウドファンディング(寄付)を募るなどしているという。
請戸小学校の状況

ほかにも、岩手県宮古市の「たろう観光ホテル」は、高さ17㍍超の津波被害を受け、4階まで浸水し、2階までは柱を残して流失したが、倒壊することなく留まり、震災遺構として保存された。その維持管理のため寄付を募っており、2014年度から2018年度は年間700万円から1200万円が集まったが、近年は200万円から400万円台に減った。
年月の経過とともに入館者や寄付は減少傾向にあり、維持管理費の問題が浮上しているのだ。言い換えると「風化との戦い」ということになる。これはどこも似たような状況だろう。
県内では浪江町の請戸小学校が唯一、震災遺構として保存されている。同小学校は直線距離で2、300㍍先に海があり、東日本大震災時は15㍍を超える津波が押し寄せた。2階建ての校舎は浸水被害を受けたが、教職員や在校中の児童93人(このうち1年生11人は地震発生時には下校済み)は高台の大平山に避難して全員無事だった。ゆえに「奇跡の学校」とも言われている。
その後、同町は全域が原発事故による避難指示区域に指定され、請戸小学校がある請戸地区は2017年春に避難指示解除されたが、学校は再開されず閉校となった。前述の復興庁の制度を活用し、約3億5000万円をかけて整備され、「震災遺構 浪江町立請戸小学校」として2021年10月に開館した。
最初は町直営で運営していたが、昨年10月から指定管理者制度を採用した。5年契約で指定管理料は年間660万円(初年度は10月から3月までの半年間のため半額)。前段で紹介した気仙沼市の例と比べると、指定管理料は5分の1程度にとどまる。入館料は300円(団体割引等あり)でそれが主な収入源。入館者は、昨年度は約6万4000人で開館以来ほぼ横ばいという。
「福島県の場合は、いまも避難先に留まる人が多く、被害が現在進行形です。そういった背景もあり、岩手・宮城両県とは状況が違い、来館者が横ばいで推移しているのだと思います。指定管理者も、いろいろとアイデアを出してくれて、工夫を凝らして、今後も多くの人に入館してもらえるようにしていきたい」(同町の担当者)
町では、「この間の経過を含めてありのままを見てもらう」といった方針。そのため、例えば2022年の福島県沖地震では壁が剥がれるなどの被害があったが、そのままにしているという。とはいえ、吹きさらしの状態のため、入館者の安全確保のための修繕などは今後必要になる時期が来るだろう。
町の担当者が話したように、福島県(原発被災地)は被害が現在進行形のため、いまはまだ来館者減少、それに伴う維持管理費の問題には直面していないようだが、いずれはその問題が出てこよう。それまでに対策を考えておく必要がある。