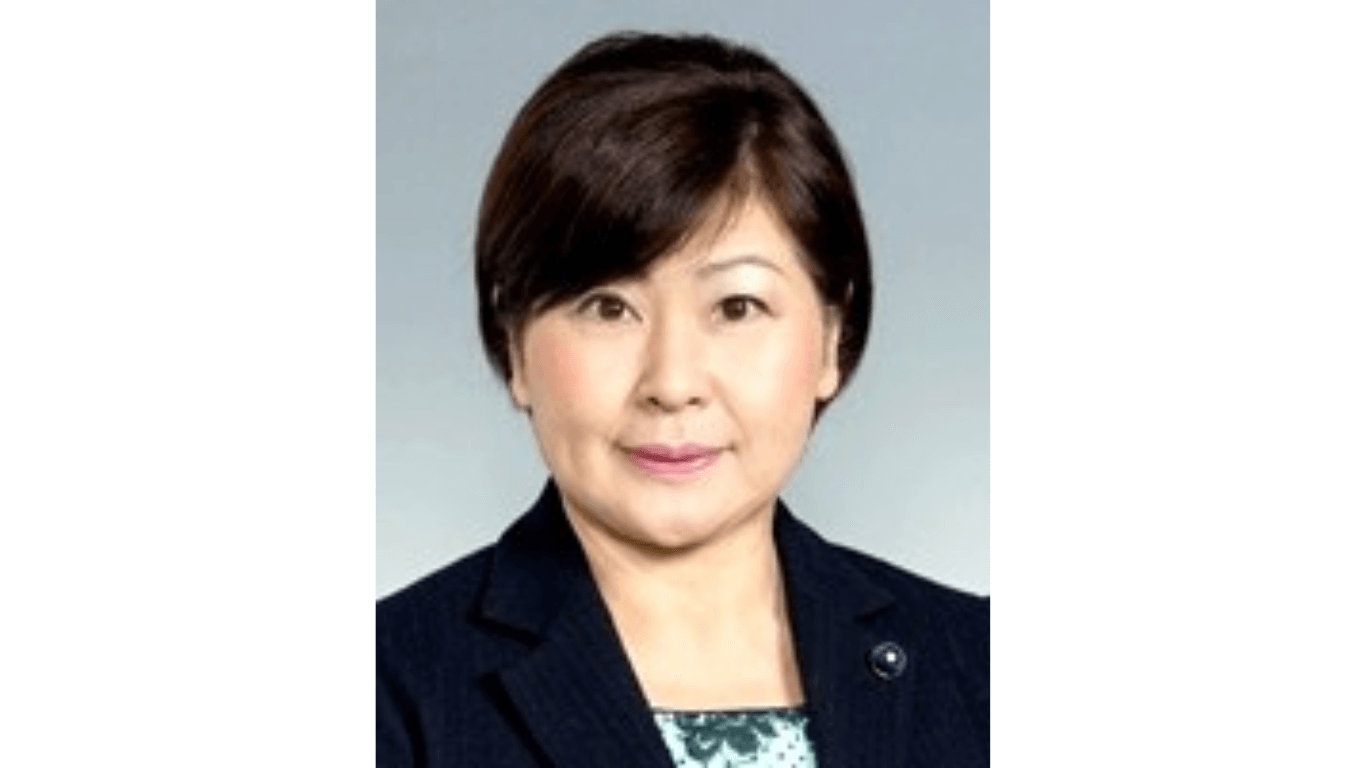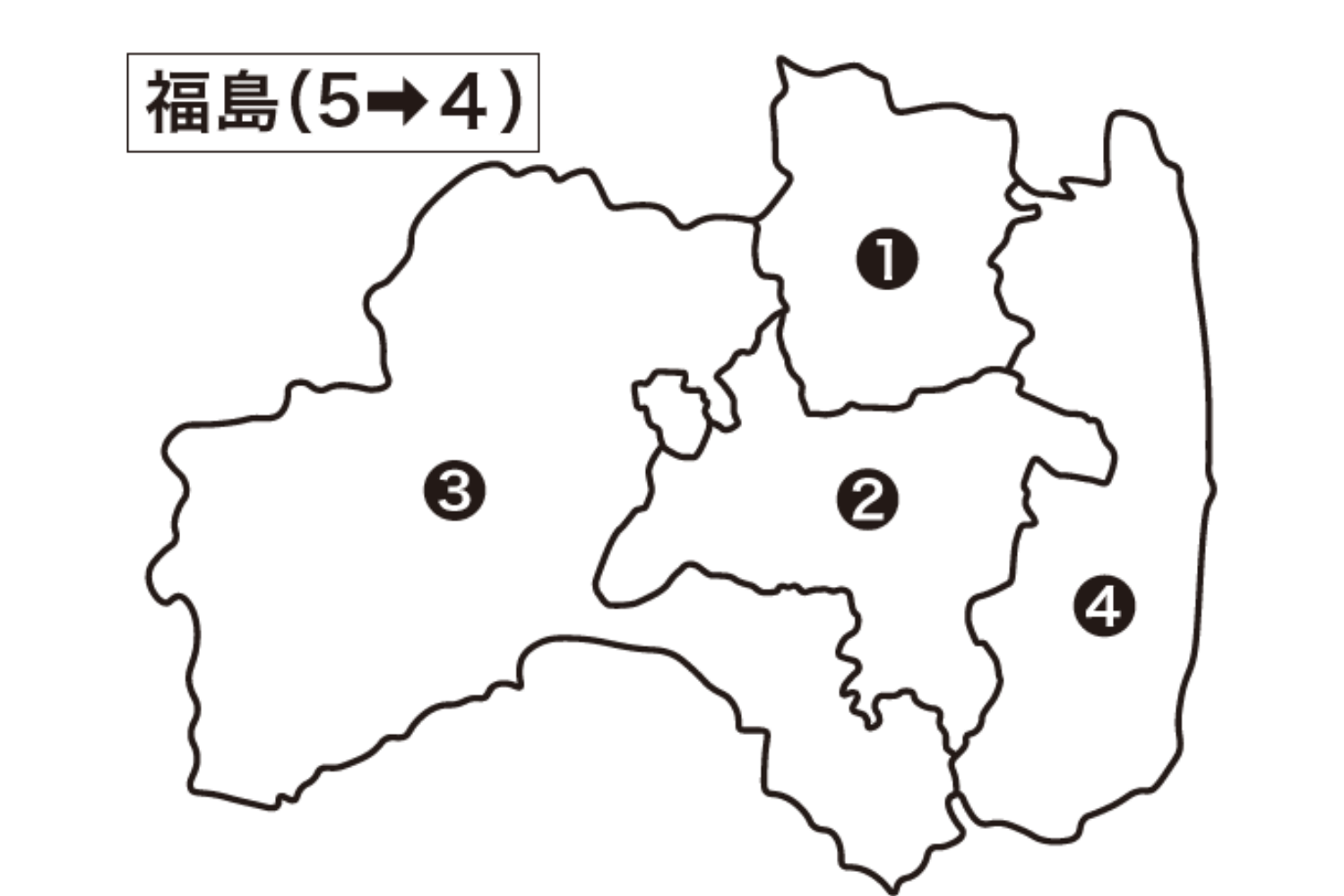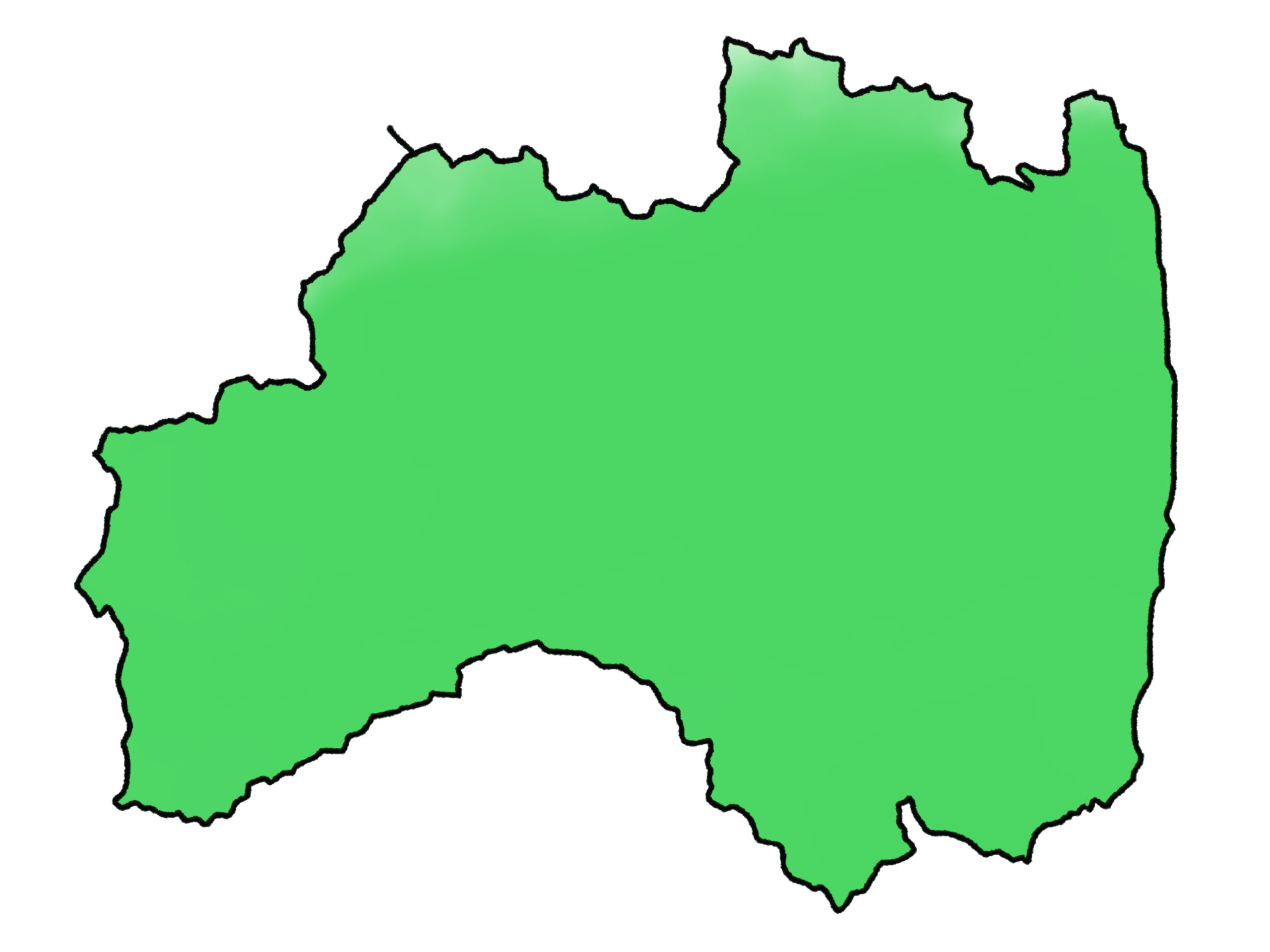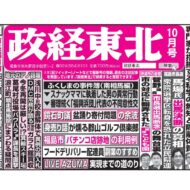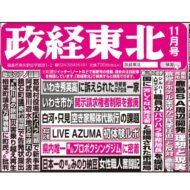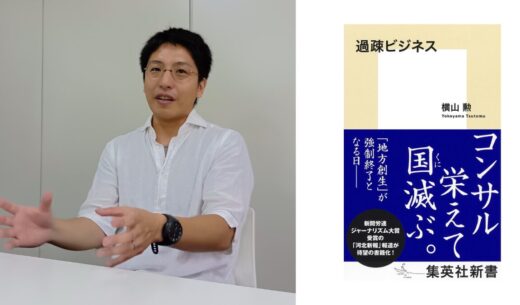自公与党は裏金事件の大逆風を浴びて昨年10月の総選挙で過半数を割ったものの、立憲民主党も野党を束ねて連立政権を誕生させることができず、少数与党の第二次石破政権が発足した。野党の一部の賛成を取りつけなければ、予算案も法案も成立させることができない厳しい国会運営が続く。

さめじま・ひろし 京都大学法学部を卒業し1994年に朝日新聞入社。2013年に「手抜き除染」報道で新聞協会賞。21年に独立し「SAMEJIMA TIMES」創刊。SNSで政治解説動画・記事を公開し、サンデー毎日やABEMAなどにも出演・寄稿。著書に『朝日新聞政治部』(2022年、講談社)、『政治はケンカだ〜明石市長の12年』(泉房穂氏と共著、2023年、講談社)。
「自公国」では安定政権につながらない理由
国会の花形である衆院予算委員長のポストを立憲民主党の安住淳・元財務相に明け渡したのは、少数与党の現実を映し出す象徴人事だ。衆院予算委員長に野党議員が就くのは実に30年ぶりである。
自公与党は、これまでは野党からスキャンダル閣僚の更迭を要求されても突っぱねて予算案を強行採決できた。安住委員長は閣僚更迭に応じない限り、予算案採決を認めないだろう。通常国会は閣僚辞任ドミノが発生し、内閣支持率がじりじり下落していく可能性が高い。
自公与党(221議席)は、総選挙で躍進した野党第三党の国民民主党(28議席)の目玉公約である所得税減税を受け入れて与党陣営に引き込み、予算案や法案の可決に必要な過半数(233議席)を確保していく方針だ。本来なら国民民主党の玉木雄一郎代表を閣内に取り込み「自公国」連立政権を発足させ、過半数を安定的に回復したいところである。
しかし、7月には参院選が控えている。国民民主党が連立入りすれば「自公政権の延命に手を貸した」との批判は免れず、参院選惨敗の恐れがある。玉木代表は連立入りを明確に否定し、個別政策ごとに是々非々で賛否を決めていく「部分連合」の立ち位置を鮮明にした。年末の予算編成・税制改正で所得税減税(非課税枠103万円の引き上げ)やガソリン税減税(トリガー条項の凍結解除)を自公与党にのませ、少なくとも予算が成立する今春までは共同歩調をとる戦略だ。
国民民主党は「与党」と「野党」の中間の「ゆ党」に転じた。自公与党は過半数を割っているものの、野党もバラバラで過半数に届かず、「ゆ党」の国民民主党がキャスティングボートを握る新しい国会勢力図が出来上がった。
石破茂首相は玉木代表と破格の厚遇で接している。昨年11月の臨時国会召集に先立って玉木代表を首相官邸に招いて党首会談を行った。野党党首との会談は国会内で行われるのが通例だ。玉木代表を「与党党首」として扱ったと言ってよい。
国民民主党が反旗を翻して野党陣営に立ち返れば、予算案や法案を成立させることができなくなるばかりか、いつ内閣不信任決議案が可決されてもおかしくない状況に陥る。国民民主党に譲歩を重ねて与党陣営につなぎ止めるしか政権継続の道はなく、国民民主党に政権の命運を握られた格好だ。
ただ、少数与党への転落が皮肉なことに石破政権の延命を下支えしている側面も否定できない。自民党内では総選挙に惨敗した石破首相への不満が渦巻いているが、いますぐ「石破おろし」の狼煙があがる気配はない。誰が首相になっても少数与党の厳しい現状に変わりはないからだ。
3月末の予算成立までは石破首相を予算審議の矢面に立たせ、その後に「石破おろし」を仕掛けて退陣に追い込み、首相を差し替え7月の参院選に臨む。新内閣の支持率が跳ね上がれば自公与党の過半数回復を狙
って衆参ダブル選挙をうかがう――。麻生太郎元首相や茂木敏充前幹事長ら非主流派は、予算成立後に照準をあわせている。当面は石破首相が予算審議で野党に吊し上げられるのを冷ややかに見守っていく腹づもりだ。
自民党内の権力闘争は「嵐の前の静けさ」が続く。石破首相は内閣支持率を引き上げて「石破おろし」を封じ込めるほかないが、防戦一方の予算審議をしのぎながら支持率を維持するのは至難の業であろう。
玉木代表はかねてから「批判より提案」と訴え、立憲民主党と一線を画してきた。立憲が呼びかけた「企業団体献金禁止」の野党案づくりにも加わらず、自公寄りの立場を鮮明にしている。しかも、石破首相との党首会談で原発の新増設を要請。立憲党内に原発推進への反発があることを承知の上で「安全保障やエネルギー政策など基本政策で一致できない以上、政権を共に担えない」という政治的メッセージを発したと言っていい。
とはいえ、7月の参院選まで自公協調を続ければ厳しい選挙戦を強いられる。予算成立後は対決路線に転じ、参院選では政権批判票を取り込むほうが得策だ。総選挙で掲げた消費税減税を再び持ち出し、自公と決別する大義名分にすることも可能である。「国会では与党寄り、選挙では野党寄り」が「ゆ党」の巧みな立ち回りと言えよう。
「石破退陣後」の行方
玉木代表は総選挙後に発覚した不倫問題で役職停止3カ月の処分を受け、3月3日まで代表としての活動を停止した後に復帰する。年末の予算編成で所得税減税など国民民主党の主張が盛り込まれれば、年明けの通常国会に提出される予算案には賛成するしかない。3月の予算成立まで、国会では立憲民主党や日本維新の会が石破政権を激しく追及するのは必至だが、国民民主党は見せ場がなくなる。その間は代表としての活動を停止してもさほど影響はないという算段だろう。
予算成立後は7月の参院選に向けて①自公与党との連携を強化するか②自公と決別して立憲民主党や維新との選挙協力に転じるか――という戦略上の重大な岐路を迎える。その前に代表に復帰する必要がある。そこから逆算して役職停止3カ月の処分を決めたというわけだ。参院選が迫る中で国民民主党は②に傾く可能性が高いと私は見ている。
いずれにせよ、石破政権と国民民主党の呉越同舟は3月の予算成立をもって終了し、それに合わせて自民党内からも「石破おろし」の狼煙があがって石破首相は退陣へ追い込まれていく展開が最有力だ。自民党総裁選が再び行われ、新政権が誕生して7月の参院選へなだれ込むのが、今年上半期に想定される政局の大きな流れであろう。
石破退陣後の総裁選の行方は見通せない。9人が乱立した昨年9月の総裁選の第1回投票で首位に立ち、決選投票で石破首相に逆転負けした高市早苗氏は勢いを失っている。そもそも無派閥で党内基盤が弱く、総裁選でも推薦人20人の確保に四苦八苦した。石破退陣に伴う緊急の総裁選は党員投票が行われず、国会議員票だけで決するため、高市氏にとっては極めて不利だ。
しかも総裁選で高市氏を支持した安倍派の中堅若手は総選挙で大量落選し、高市氏の党内基盤は痩せ細っている。昨年9月の総裁選では「反石破」の立場から麻生氏や茂木氏が高市氏支持に回ったが、次回は支持を得られる保証はない。
小泉進次郎氏は総裁選で菅義偉元首相に擁立され、当初は本命視されたものの党員投票が伸び悩んで失速し、決選投票に進めなかった。選択的夫婦別姓の法案提出を宣言したことで保守層に敬遠されたのに加え、憲政史上最年少の首相になることへの不安が広がり、想定外の惨敗を喫した。石破政権では選対委員長に起用されたが、総選挙惨敗の責任を取って辞任。泥舟の石破政権からひと足先に逃げ出したと言えるが、惨敗の後遺症は深く、次回の総裁選出馬には躊躇するだろう。
惨敗で方針転換した維新
非主流派で麻生氏と歩調をあわせる茂木氏はポスト石破に意欲をみせる。岸田政権下で麻生氏と茂木氏は国民民主党や連合との交渉窓口を務めた経緯があり、国民民主党がキャスティングボートを握る今の政局状況は大歓迎だ。予算成立後の「石破おろし」で国民民主党や連合と水面下で連携することも可能だ。
年明けに米国でトランプ政権が誕生することも麻生・茂木両氏には追い風だ。麻生氏は昨年春、岸田文雄首相がバイデン大統領からワシントンに国賓待遇で招待された直後にニューヨークへ飛んでトランプ氏と会談、「もしトラ」にいち早く備えた。
トランプ氏は前回の大統領時代に安倍晋三首相と蜜月関係を築き、安倍政権の経済再生相として日米貿易交渉を担った茂木氏とも相性があった。石破政権の後見人として存在感を増している岸田氏がバイデン氏に近かったのに対し、麻生・茂木両氏はトランプ氏に近いのは自分たちであると自負している。この点からも茂木氏は出馬に強い意欲を抱いているのは間違いない。
とはいえ、茂木氏が参院選の顔として期待が高まるかは疑問だ。昨年9月の総裁選では党員投票が伸びずに6位に沈んだ。石破退陣後の総裁選は国会議員票だけで決まるとはいえ、参院議員たちはやはり「選挙の顔」を求める。この点は茂木氏に逆風になろう。
石破政権でキングメーカーになった岸田文雄首相は林芳正官房長官を担ぐとみられる。高市氏を支持した麻生氏は副総裁を外れて非主流派に転落。小泉氏を担いだ菅氏は決選投票で石破氏支持に回って副総裁に起用されたものの、小泉氏惨敗の後遺症は深く、健康不安説も浮上して影響力が低下した。その中で岸田氏は岸田派ナンバー2の林氏を担いで4位と健闘し、決選投票では早々に石破氏支持に動いて存在感を増した。
石破首相は岸田氏の意向に沿って林氏を官房長官に留任させ、党4役にも岸田派から小野寺五典政調会長、木原誠二選対委員長を迎える厚遇ぶりだ。石破政権が参院選前に倒れた場合、森山裕幹事長を軸とした現主流派の枠組みを維持したまま林政権に移行することを岸田氏は想定しているのではないだろうか。
高市氏は「保守が分裂したら『今官邸におられる方』(林氏)に勝てない」と明言して林氏への対抗心を隠さず、総裁選で5位に食い込んだ若手代表の小林鷹之氏との連携を目指している。石破退陣後の総裁選は本命・林氏、対抗・茂木氏、大穴・高市氏の展開となろう。
誰が新首相になっても(あるいは石破首相が支持率を維持して退陣を回避したとしても)7月の参院選に合わせて衆院を解散し、衆参ダブル選挙で一気に過半数を取り戻すほど自民党が勢いを回復する気配はない。参院選は自公過半数を維持するための「防戦」に終始し、衆院過半数割れの少数与党政権が続くシナリオが最も現実的である。
参院選さえ終われば当面は国政選挙はなく、野党が連立入りするハードルは下がる。自公与党はここから連立政権の枠組み拡大へ動きを本格化させていくだろう。
第一のターゲットは国民民主党だ。3月の予算成立後も協力関係を維持して参院選に突入すれば、「自公国」連立への機運が高まってくる。しかし、参院選で国民民主党が自公との対決姿勢に転じれば、関係修復には時間がかかる。
さらにやっかいなのは、仮に国民民主党が連立入りしても、次は連立離脱を食い止めるため、いつまでも主導権を握られる羽目になることだ。「自公国」連立はあくまでも一時しのぎにすぎず、本格的な安定政権にはつながらない。
同じことは維新にもあてはまる。維新と国民民主党を天秤にかける国会対策はそれなりに効果があるが、「自公維」連立に発展したところで維新は次々に「身を切る改革」を主張して政権内部から揺さぶり続けるだろう。
維新は総選挙惨敗後、自公協調に軸足を置いてきた馬場伸幸代表が退き、吉村洋文・大阪府知事が新代表に就任した。吉村代表は「野党第一党は目指さない」と明言。立憲民主党を敵視して野党第一党を奪う従来の路線を転換し、自公との対決姿勢を鮮明にした。参院選では自公過半数割れを最重要目標に掲げ、1人区では野党候補一本化のため予備選実施を検討するとも踏み込んだ。
さらに国会議員団を率いる共同代表に、国民民主党を離党して維新に加わった前原誠司元外相を指名。自公に近づく国民民主党に対抗し、立憲民主党との連携を重視する布陣をしいた。
前原氏は民主党時代から自民党に対抗し、野党結集を目指す二大政党論者として知られる。2017年総選挙で小池百合子・東京都知事が旗揚げした希望の党に合流したのも、非自民・非共産の大同団結を目指したからだった。吉村・前原体制が崩壊しない限り、維新が自公連立に加わる可能性は低い。
鍵は森山―安住ライン
私が本命視しているのは、自民党と立憲民主党の大連立である。国民や維新を自公連立に引き入れても、本格的な安定政権は実現しない。むしろ自民・立憲の大連立のほうが政権基盤は固まる。参院選が終われば当面は国政選挙がなく、大連立に踏み切るには絶好のタイミングだ。
ポスト石破の本命である林氏は自民党税調インナーを長く務めてきた大物財務族だ。立憲民主党を率いる野田佳彦代表も財務相を経験した大物財務族で、首相時代に消費税増税をめぐる自公民3党合意を進めた張本人である。財務省が橋渡しして消費税増税を旗印にした大連立を仕掛ける可能性は十分にあろう。
大連立構想を水面下で練り上げるのは、自民党の森山幹事長と立憲民主党の安住予算委員長のラインだ。二人はかつて与野党の国対委員長として気脈を通じた。財務省は予算を編成するだけではなく、国会で着実に成立させるため国会対策に精通しており、与野党の歴代国対委員長とは親密な関係を築いてきた。森山―安住―財務省のラインで大連立構想を描き、林―野田の大連立合意へ道筋をつける。それが参院選後、今年下半期の政局の底流になるのではないか。
年明けに始まる通常国会で、立憲民主党の安住予算委員長は自民党の森山幹事長と水面下で示し合わせ、石破首相を予算審議で追い込む議事進行を展開するに違いない。石破退陣・林政権への移行、そして参院選後の大連立を見据えた布石はすでに打たれている。その視点で通常国会の予算審議を眺めれば、与野党激突の国会風景の裏側がぼんやりと浮かんでくるだろう。