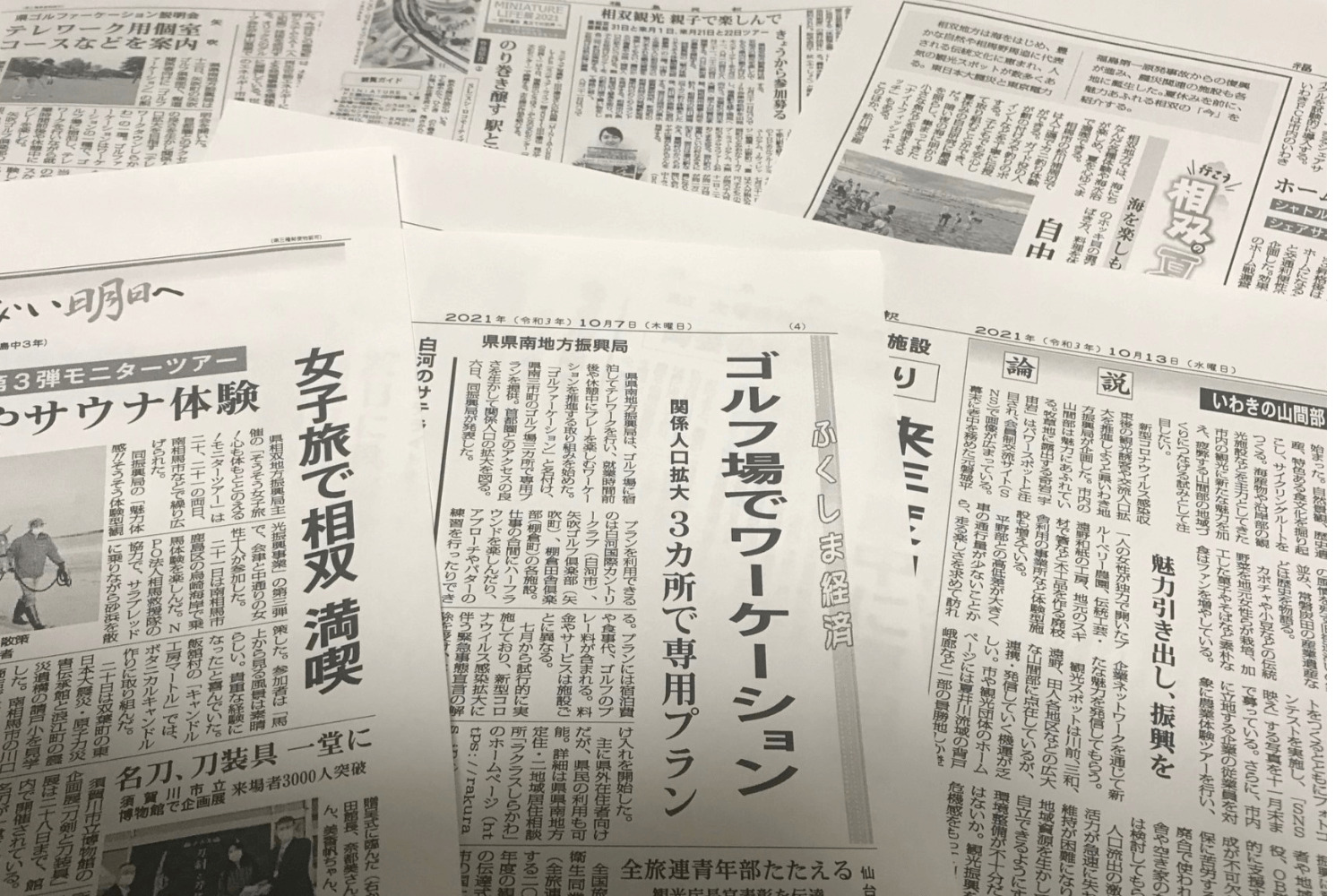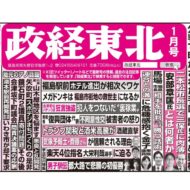環境省は東京電力福島第一原発事故に伴い発生した除染土の再利用に関する省令案について、国民から意見を募るパブリックコメント(パブコメ)を行い、3月28日に結果を発表した。それによると、意見総数は20万7850件で異例の数に上ったが、実態は一字一句違わない、いわゆる「コピペ意見」が96%を占めていたという。「反対団体が見せかけの数の力で事実を捻じ曲げた。許されることではない」などと批判されたこの問題の本質に迫る。(末永)
意義が感じられない除染土再利用
原発事故に伴う除染作業によって発生した汚染土壌、いわゆる「除染土」は、双葉・大熊両町に設置された中間貯蔵施設に運び込み、2045年3月まで適正管理した後、県外で最終処分することになっている。その量は1400万立方㍍に上るが、環境省は管理する土壌の容量を減らし、県外での最終処分をしやすくするため、除染土を建設資材などに再利用する方針を示している。
今回の省令改正はそれに関するもので、正式名称は「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」。この中で「復興再生利用」という新しいフレーズが用いられ、除染土再利用を推進していきたい考え。この省令案について、環境省は1月17日から2月15日まで、意見募集(パブリックコメント)を行った。
浅尾慶一郎環境大臣は3月28日、閣議後の記者会見で、同省令改正の同日公布と4月1日からの施行を明かしたほか、パブリックコメントの結果も発表した。以下は大臣会見録を要約したもの。
「全体では20万件の意見があったが、一字一句完全に一致した意見があり、それを1件とすると、8000件。20万件の4%になる。同一者からの大量投稿も複数見られ、同一内容の意見を1000件以上投稿した方もいた」
「パブリックコメントの趣旨は意見の多寡ではなく、その内容に着目して行われる」
「職員は全ての意見に目を通す必要があるが、同一の方から同一の意見が大量に送られると、行政事務の適正な執行の妨げにつながる可能性もある」
正確な意見数は20万7850件で、このうち19万9573件(約96%)が一字一句違わなかったという。それを除くと、実質的な意見数は8277件になる。1人が同じ内容で1000件以上投稿した例もあった。ネットやSNS上にある意見を、いわゆる「コピペ」して提出したケースが多数あり、それを扇動するような動きもあったという。
当然これには「反対団体が見せかけの数の力で事実を捻じ曲げた。許されることではない」といった批判が噴出した。
確かに、「1人が同じ内容で1000件以上投稿した」という行為は、前述のような批判を受けてもやむを得ない。中には、ネット上にある意見をコピペして提出し、例えば1万件目とか、9999件目など、「キリ番」や「ゾロ目」などを狙い、「キリ番(ゾロ目)ゲット」などとSNSで投稿した〝愉快犯〟もいたという。それらは浅尾大臣が指摘したパブリックコメントを妨げる行為と言われても仕方がない。
とはいえ、この問題はそれで済ませられるものではない。
除染土再利用に反対の意向を示している「放射能拡散に反対する会」という市民グループがある。東京都新宿区、埼玉県所沢市で除染土再利用の実証事業計画が浮上したのを機に結成された団体で、この間、環境省との意見交換会(直接交渉)などを行っている。
同会関係者は今回の件について「迷惑だ」との認識を示した。
「実質的な意見数は8277件になるとのことですが、まずそれ自体が異例の数と言えます。しかも、そのうちの99・9%は除染土再利用に反対意見だったそうです。そのことを真摯に受け止めなければならないのに、『提出意見数は20万7850件で、その96%が全く同じものだった』ということばかりが取り沙汰され、われわれのようにきちんと(省令案を)分析して提出した意見までもが胡散臭いもののように捉えられてしまっています。論点をずらされた格好で、真面目にやっているわれわれからしたら、(96%のコピペ意見や愉快犯は)迷惑でしかない」
パブコメ様式の問題点

一方で、この関係者はこんな問題点も指摘する。
「今回のパブコメに当たり、われわれは元大学教授などの専門家を交えて公開資料を読み解きましたが、その数は膨大で非常に分かりにくかった。これを一般の人が理解して意見を提出するのは簡単ではない。本当に広く意見を募る気があるのかと疑うほどです」
本誌も今回のパブコメに当たり、公開されている資料を見たが、省令内容は法令文のようなものなので、すぐに理解するのは難しい。ネットで公開されている関連資料等を見る(クリックする)と、中間貯蔵施設情報サイトに飛び、「中間貯蔵施設における除去土壌等の再生利用方策検討ワーキンググループ」の過去の経過、同会合で配布された資料、議事録など、かなりの数の関連資料が出てくる。別の関連資料を見ようとすると、今度は原子力規制委員会の「放射線審議会総会」のページが表示され、そこにも10を超える資料があった。
それらをすべて頭に入れて理解を深めようと思ったら、相当な時間と労力、読解力が求められる。こうしたパブコメの様式を見ると、「放射能拡散に反対する会」関係者が指摘したように、国は国民の理解醸成のうえで除染土再生利用を進めようとしているとは到底思えない。
そんな中で、同会のような団体が分かりやすく解説し、「われわれはここに問題があると考えている」と、ネットやSNSなどで公開した例はいくつかある。それを見た人が「難しいことは分からないが、この団体の主張に賛同できる」と思ったら、それは1人の人間の1つの意見ということができるのではないか。
もっとも、浅尾大臣のコメントにもあったように、パブコメの趣旨は意見の多寡ではなく、どんな内容かが問われる。そのため、「〇〇団体と同意見だ」というパブコメに意味があるかは分からないが、どうしても意思表示をしたいなら、そういう手法もあるということだ。
もちろん、その場合は「〇〇という団体がこういう声明を出していた。自分もそれに賛同できるから、同趣旨で今回の省令案には反対だ」ということを明記すればいい。完全コピペの〝愉快犯〟は論外だが、そうではなく前述のような趣旨なら、そのように対応すれば今回の問題は起きなかった。
もう1つは、そもそも除染土再生利用に意味があるかということ。冒頭で書いたように、除染土再生利用は管理しなければならない除染土の容量を減らし、それによって県外最終処分を現実的にするのが狙いとされる。中間貯蔵施設で管理される1400万立方㍍の除染土が、例えば「1000万立方㍍以下になるなら、最終処分を受け入れてもいい」というところがあるなら話は別だが、そういう問題ではないだろう。除染土再生利用(容量減少)が最終処分場確保に結び付くとはどうしても思えない。