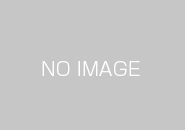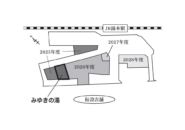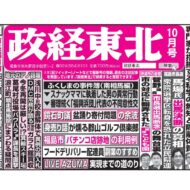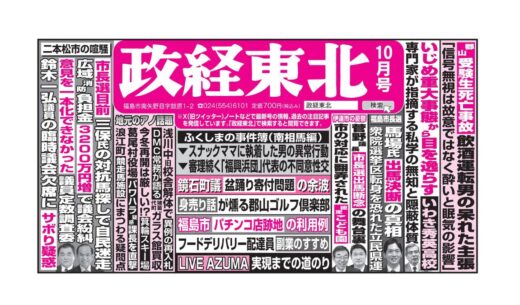県は5月8日、今年の大雪による農業関係の被害額を発表した。それによると、被害額は約3億0500万円で会津地方では過去最大規模となった。こうした事態を受け、県では補助メニューを設けて再建を支援しているが、「実際はそう簡単にはいかない。中には営農を諦める人も出てくるに違いない」との声もある。
補助金はあっても資材高騰で大きな負担
別表は県農林水産部発表(5月8日付)の「令和7年2月4日以降の大雪による農林水産業被害状況について」を基に本誌がまとめたもの。会津地方は桧枝岐村を除く16市町村で被害が確認されており、中通りの郡山市、須賀川市でも被害があった。とはいえ、大部分は会津地方での被害になる。
市町村別の被害状況
| 市町村名 | パイプハウス等 | 果樹の樹体 | 果樹棚 | 家 畜 | 農作物 果樹以外 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会津若松市 | 3755万円 | 627万円 | 116万円 | ―――― | 1765万円 | 6265万円 |
| 郡山市 | 356万円 | ―――― | 49万円 | ―――― | ―――― | 406万円 |
| 須賀川市 | 9万円 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | 9万円 |
| 喜多方市 | 1965万円 | 340万円 | 10万円 | 24万円 | 154万円 | 2496万円 |
| 南会津町 | 450万円 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | 450万円 |
| 北塩原村 | 103万円 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | 103万円 |
| 西会津町 | 1348万円 | 211万円 | ―――― | ―――― | ―――― | 1559万円 |
| 磐梯町 | 654万円 | 106万円 | ―――― | ―――― | ―――― | 761万円 |
| 猪苗代町 | 731万円 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | 731万円 |
| 会津坂下町 | 1042万円 | 1638万円 | ―――― | ―――― | ―――― | 2681万円 |
| 湯川村 | 1567万円 | ―――― | 1万円 | ―――― | ―――― | 1568万円 |
| 柳津町 | 1312万円 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | 1312万円 |
| 三島町 | 139万円 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | 139万円 |
| 金山町 | 78万円 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | 78万円 |
| 昭和村 | 2004万円 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | 2004万円 |
| 会津美里町 | 2936万円 | 4822万円 | 1357万円 | ―――― | 172万円 | 9289万円 |
| 下郷町 | 675万円 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | 675万円 |
| 只見町 | 2万円 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | 2万円 |
| 合 計 | 1億9134万円 | 7747万円 | 1535万円 | 24万円 | 2093万円 | 3億0535万円 |
大雪による農業関連被害については、当初から「相当な規模になる」と言われていた。過去には2014年に約12億5000万円の被害が出たが、この時は県内全域に及んだため、それだけの被害額になった。この時の会津地方の被害額は約3000万円だったから、今回はそれを遥かに上回り、会津地方に限ると過去最大規模になる。
詳細を見ていくと、パイプハウス等の施設関連の被害が1億9134万円で最も多い。そのほか、果樹樹体被害が7747万円、果樹以外の農作物が2093万円、果樹棚が1535万円、家畜が24万円となっている。
市町村別では会津美里町が9289万円で最も多く、会津若松市6265万円、会津坂下町2681万円、喜多方市2496万円と続く。会津美里町はブドウ、ナシ、リンゴ、ウメなどの栽培が盛んで、それら果樹被害が大きかった。果樹被害全体の6割超が同町での被害だった。そのほかでは、やはりパイプハウス等の被害額が大きく、会津若松市3755万円、会津美里町2936万円などとなっている。
県の発表には「被害額は経過年数を加味した残存価値を評価したものであり、再建に要する経費と異なります」との注意書きがある。
パイプハウス等の耐用年数は構造によって異なるが、5年から14年とされている。それを超えたら帳簿上は価値がなくなるが、実際は例えばビニールハウスのビニールは定期的に替えなければならないものの、骨組み自体は耐用年数を超えても使うことができる。残存価値がないが、まだ使えるものを含めると、被害額はもっと増える。
JA会津よつば営農部によると、「被害を受けた施設などの復旧・再建には23〜24億円程度かかるのではないか」との見通しを明かした。県発表の被害額の約8倍だ。
県では「令和6年度大雪農業災害特別対策事業」として、各種補助メニューを用意している。主なものでは、パイプハウスや果樹棚など、農業用栽培施設の復旧(修繕・再建)にかかる経費は、県、市町村がそれぞれ3分の1ずつ補助する。つまり、農業者の負担は3分の1で済む。
果樹農家の苦悩

ただ、ある農業者は「自己負担は3分の1で済むと言っても、実際は決して軽い負担ではない」との見解を述べる。
「私のところでは、2棟のパイプハウスがあり、1つは5年くらい前、もう1つは10年くらい前に建てた。それがどっちもダメになったのだけど、いまは資材高騰などの影響で、当時(以前にパイプハウスを建てた時)と比べると建築費は3倍くらいになっている。だから、自己負担は3分の1と言っても、実際は5年前、10年前に建てたときと同じくらいか、ひょっとしたらそれ以上の負担になるかもしれない。そう考えると簡単ではないよ」
果樹農家はもっと大変だ。果樹樹体被害が7700万円超になることは前述したが、復旧・再建(樹体の植え替え)をしたとしても、実際に収穫できるようになるまでには、品種によって異なるが、数年は見なければならない。
会津美里町のブドウ農家は次のように話す。
「うちではいくつかのほ場があるが、小規模なものを含めると、すべてのほ場で何らかの被害がありました。そのうちの1つは再建を諦めました。当然、それに伴い収穫量は減ります。もし、ブドウの樹を植え替えるとしたら、収穫までには4、5年はかかるでしょうね。高齢の農家だったら植え替えたはいいものの、ようやく収穫できるようになったころには、もう営農が難しいということも起こり得る。だったら、最初から諦めるという人も出てくると思います」
会津美里町によると、本誌取材時の5月中旬時点で、前述した県と市町村の補助の受付は開始していないという。
パイプハウスなどは再建すればすぐに使うことができるが、果樹は植え替えたからすぐに栽培・収穫できるわけではないから、前出のブドウ農家が話したように営農(再建)を諦める人も出てくることが予想される。そういった点で果樹農家はより大変だが、果樹農家に限らず、施設復旧の負担や年齢・後継者の問題などから、営農再開を諦める人も出てくると予想される。
ある農家は「知り合いに、いわゆる脱サラして農業を始めた人がいるが、農繁期が始まろうとする時期になっても、何も手付かずの状態になっている。今回の件で心が折れたのかもしれない」と話す。
こうした証言からも、農業をやめる人は出てきそう。今後、補助申請の相談などが本格化すれば、その辺も明らかになっていくだろう。
順番待ちのハウス再建
ところで、「パイプハウスなどは再建すればすぐに使うことができる」と書いたが、これだけ広範囲かつ相当数の被害が出ているため、追い付いていないようだ。本誌はパイプハウスの施工などを手がける事業者に問い合わせたが、担当者に話を聞くことができなかった。言い換えると、それだけ忙しく動き回っているということだろう。
会津坂下町の農家によると、「パイプハウスの修繕は年内いっぱいくらいまで待たないといけないようだ」と明かす。
「うちは育苗用と機械をしまっておくパイプハウスがあり、育苗用は田植えが終わったらビニールを外すから骨組みは大丈夫だった。ただ、機械をしまっておくパイプハウスは雪の重みで壊れてしまった。育苗用に比べると優先順位が低いから、順番待ちで年内には何とかということだった」

写真は被害を受けた農機具収納用のパイプハウス。ビニールが破け、骨組みが歪み、コンバイン(写真左)にぶつかっている。「コンバインの出番は秋だから、まだ稼働していない。コンバインの上部にぶつかってちょっと凹んだけど、稼働には問題ないんじゃないかと思う」とのこと。
ハウスなしで育苗
一方で、育苗用のパイプハウスが被害を受けた農家に話を聞くと、「間に合わないから、ハウス外で苗を育てている」という。会津美里町のコメ農家の話。
「田植えの(苗を育てた)後、ビニールハウスでトマトを栽培していたから、そのままにしていた。そのため、今回の大雪で倒壊してしまった。ビニールハウスは2棟あって、1つは5、6年前、もう1つは7、8年前に建てたもの。ビニールは定期的に替えるけど、骨組み自体はまだまだ使えた。(県と市町村の補助で)自己負担は3分の1といっても、いまは何でも値段が上がっているから、痛い出費だよね。そもそも、今年の田植えには間に合わないことが分かっていたから、ハウスを使わずに苗を育てている。初めての試みだけど、やっぱり育ちは(気温が高いビニールハウスと比べると)遅いね。中には苗を買った人もいるようだけど、それは何か違うなと思って」

写真(上)はその光景。もともとこの場所にはパイプハウスがあったが、倒壊したため撤去して、路地で苗を育てている。ただ、苗の育ちは遅いようで、「田植えも例年より少し遅れるかも」とのこと。
県の大雪農業災害特別対策事業では、パイプハウスや、果樹棚など倒壊した農業用栽培施設の撤去費用は県補助2分の1、自己負担2分の1となっているほか、農産物の再生産に必要な種苗等の購入費用は、パイプハウスの復旧(修繕・再建)費用と同様に、県、市町村がそれぞれ3分の1ずつ補助し、自己負担は3分の1。
そのため、今年は苗を買う農家もいたようだが、前出の会津美里町のコメ農家は、「それは何か違う」と思い、ハウスを使わずに苗を育てた。ただ、やはり苗の育ちが遅いため、田植えの時期を例年より遅らせることになりそうと話していた。
ちなみに、本誌取材時の5月中旬時点では、周辺ではまさに田植えをしている最中のところもあれば、まだ水が入っていない田んぼもあった。時期的には5月中旬から下旬にかけて田植えをするところが多いという。
JA会津よつばによると、「管内の生産量、生産額については、多少は下がるだろうが、大きく落ち込むとは考えていない」とのこと。加えて「少しでも自己負担が軽くなるよう、国にも補助を出してほしいと要望を行っている」という。
それが実れば再建の負担は軽くなるだろうが、生産者の高齢化や後継者不足など、農業分野の以前からの問題も絡んでくるため、やはり、簡単な問題ではないと言える。