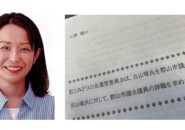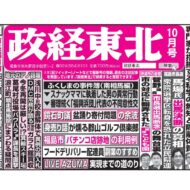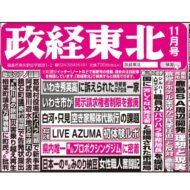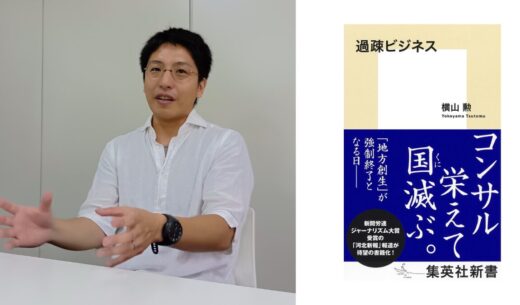福島市議会は2023年12月に「議員定数に関する調査特別委員会」を立ち上げ、議員定数のあり方について議論を進めてきた。この間、15回の委員会を開催し、6月議会で委員長報告が行われた。
議論の中で「市民の意見」は見えず
同調査特別委員会の経過は本誌昨年9月号「福島市『議員定数議論』を追跡 報酬のあり方にも踏み込むべき」という記事でリポートした。
同市議会は2023年7月に議員選挙が行われ、それに先立ち2022年6月に、当時の議長から議会内の組織である議会改革検討会に「議会の活性化に資する議員のあり方に関する検討について」の諮問があった。検討会は2023年3月に答申書をまとめ、その中で、議員定数については次のように答申した。
× × × ×
議員定数については前回条例改正を行った平成26(2014)年12月から10年近くが経過した。
本市においても定数を検討する指標の一つとなる人口は、この間、減少を続けているなど、前回の定数改正から様々な状況が変化していることも踏まえ、議会が主体的に適正な定数についての議論を開始する必要がある。
一方、地方分権が進展する中で、多様化する住民の意思を市政に反映させることなど、議会の役割はますます重要性が増しており、単純に人口の減少や他市の状況にあわせ削減を前提とした議論をすべきではない。
(中略)よって、本年に予定されている福島市議会議員選挙の結果も踏まえ、改選後において本市議会のあるべき適正な定数について協議を開始し、慎重に検討すべきである。
× × × ×
これに基づき、2023年12月に「議員定数に関する調査特別委員会」(半沢正典委員長)を立ち上げ、議論をスタートさせた。
その中で真っ先に確認されたのが、議会における基礎ルールである「福島市議会基本条例」(2014年3月施行)の規定に基づいて議論していく、ということだった。同議会基本条例では次のように定められている。
《議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮するとともに、市民又は学識経験を有する者からの客観的な意見を参考にするものとする》(議会基本条例31条)
《議員定数の基準は、人口、面積、財政状況及び市の事業課題並びに類似市の議員定数と比較検討し、決定するものとする》(同2項)
これに倣い、調査特別委員会では類似自治体(人口25万人から30万人の市区)のデータ収集をしたり、河村和徳東北大学准教授(当時、現在は拓殖大学教授)を参考人として呼んで意見聴取したりした。
河村氏は同委員会で「議会は地域の産業構造を反映し、住民の縮図に近くしなければならない。そのため、定数削減ありきの議論は適切ではない」といった意見を述べたという。
ここまでが本誌昨年9月号でリポートしたおおまかな流れ。
共産党が削減に反対
その後、調査特別委員会は神奈川県横須賀市、栃木県小山市を視察した。両市を視察地に選んだのは①比較的視察に行きやすい地域、②自治体の規模が大きく離れていない、③最近、議員定数の変更(削減)を実施、④定数変更に当たり、じっくりと議論した――といった理由から。
両市の視察後はそれを参考にしつつ、議会基本条例で定められた基本的な考え方に従って議論を深め、最終的な報告書をまとめた。6月議会で半沢委員長が報告した。
それによると、議論の中で人口減少を考えると削減は避けられないといった意見や、人口が減っても市域面積は変わらない、市民ニーズが多様化している、市政の課題が山積しているといった観点から、現状維持あるいは増員すべきといった意見も出たという。
ただ、最終的には定数削減の必要はあるものの、最小限にとどめるべき、との意見が大勢となり、「現在の定数35から1減とし、34とすることが適当」との結論に至った。
委員長報告が行われたのは6月12日で、その後、18日に行われた本会議で、白川敏明議員(真政会)から「福島市議会議員定数条例の一部を改正する条例」の議案が追加提案された。先の調査特別委員会の報告に基づき、定数を1減とする条例改正案である。
これに対し、山田裕議員(日本共産党福島市議団)が反対討論を行った。内容は「市政の課題は山積しており、それらに取り組む議員の役割が問われている。削減は市民の手段・選択肢をせばめるため好ましくない」というもの。
その後、採決に移り、賛成30、反対3の賛成多数で可決された。反対したのは前出の山田議員のほか、佐々木優議員、村山国子議員の3人で、いずれも共産党。ほかの会派はすべて賛成に回った。これに伴い、次回市議選(2027年7月に任期満了)から定数34となる。
議員定数議論の本質
筆者はこれまで県内自治体の議員定数に関する議論を幾度となく取材してきた。以下はその経験から述べていきたい。
本誌は以前から、議員定数削減には否定的で、むしろ議員は増やすべきと指摘してきた。その場合、議員報酬・期末手当を下げ、全体の議会費が上がらないようにすることが求められる。同時に、仕事(会社勤め)をしていても議員になり、その務めが果たせるよう、選挙のあり方、さらには議会開催の方法なども変えていく必要がある。議会のあり方を考えるのは、定数、報酬、選挙や議会開催の方式などをセットで考える必要があるということだ。
一方で、いくら議員を増やすべきと言っても、議会自らがその判断をしたら住民はどう感じるか。おそらく「保身」と捉える人が大半ではないか。議会主導で議員定数増を進めては住民の理解は得にくいということだ。
そこで指摘しなければならないのは、当人たち(議会)が議員定数を決めるのが適切かということ。その点で言うなら、今回の福島市のケースは、議会基本条例で「市民又は学識経験を有する者からの客観的な意見を参考にする」とあり、学識経験者の意見は聴取したが、「市民の意見」というのは議論の中で見えてこなかった。
議員定数については一応の目安は国から示されているものの、絶対的な「正解」は存在しない。そのため、今回の福島市議会の判断が正しいか否か、時流に合っているかどうかを判断するつもりはない。ただ、強いて言うなら、住民が議会に何を求め、どんな形を望んでいるか、そのためにどれだけの議員が必要かということがその自治体にとっての「正解」に近い存在になる。その部分が見えなかったことは残念だ。