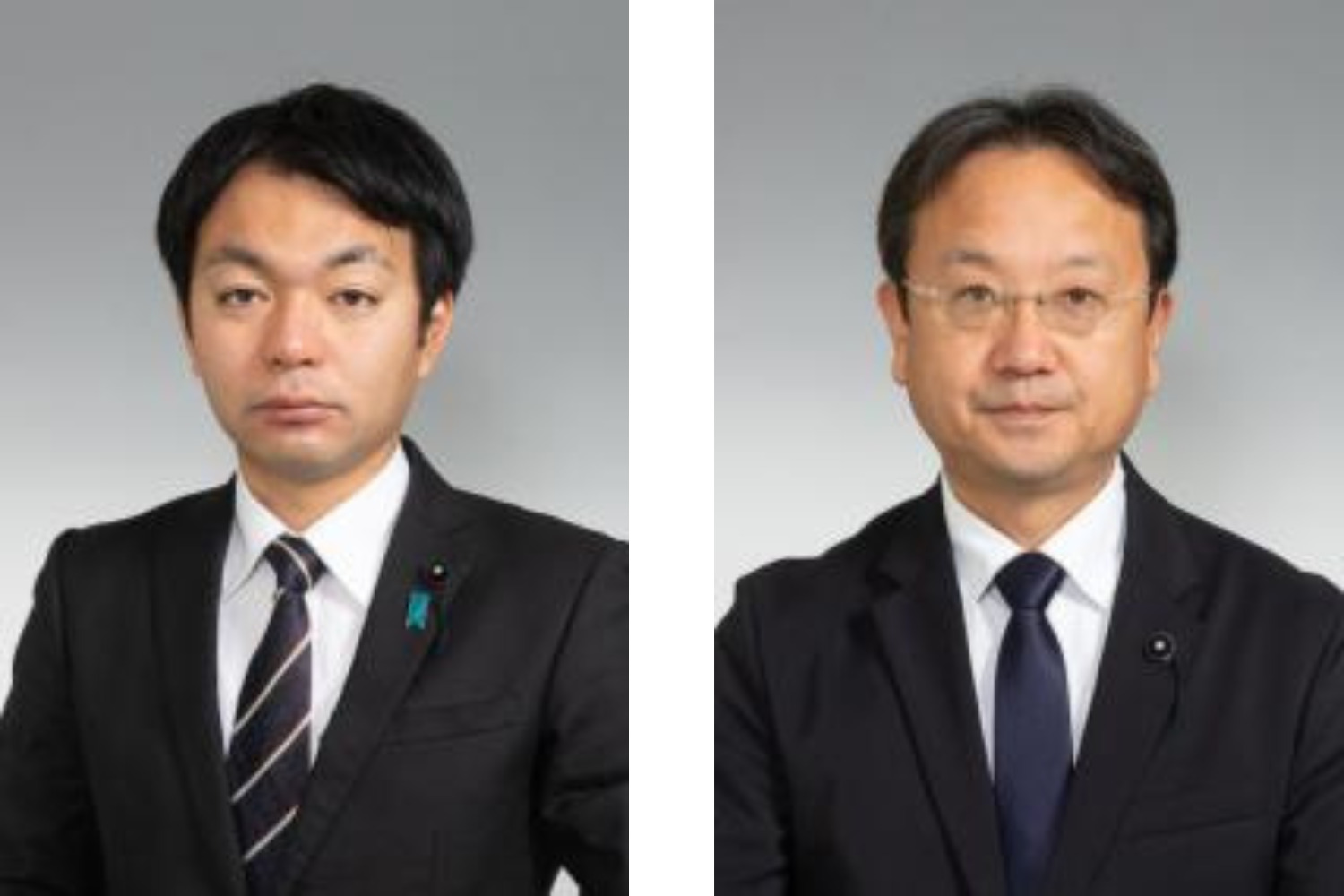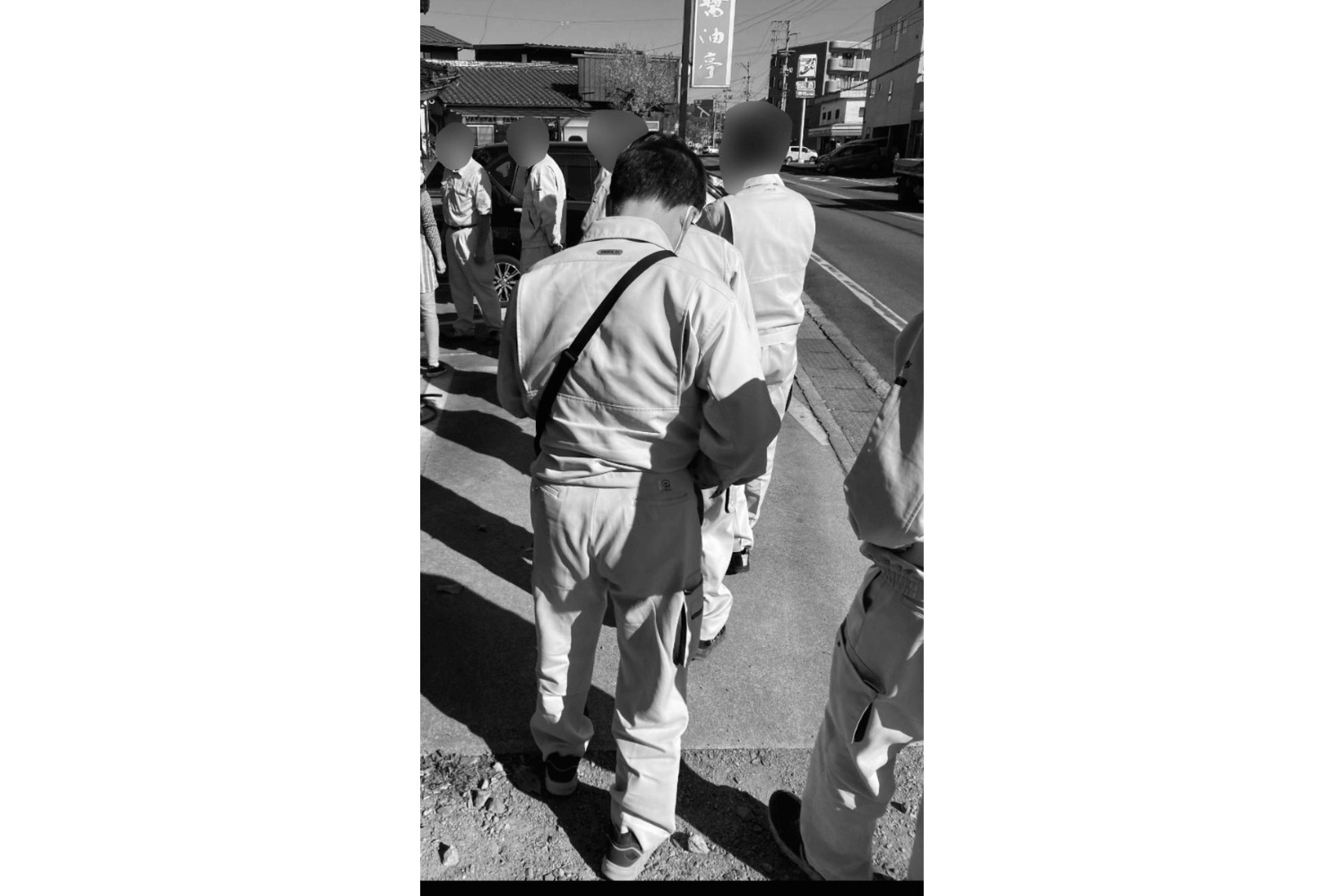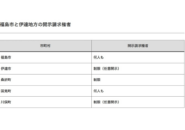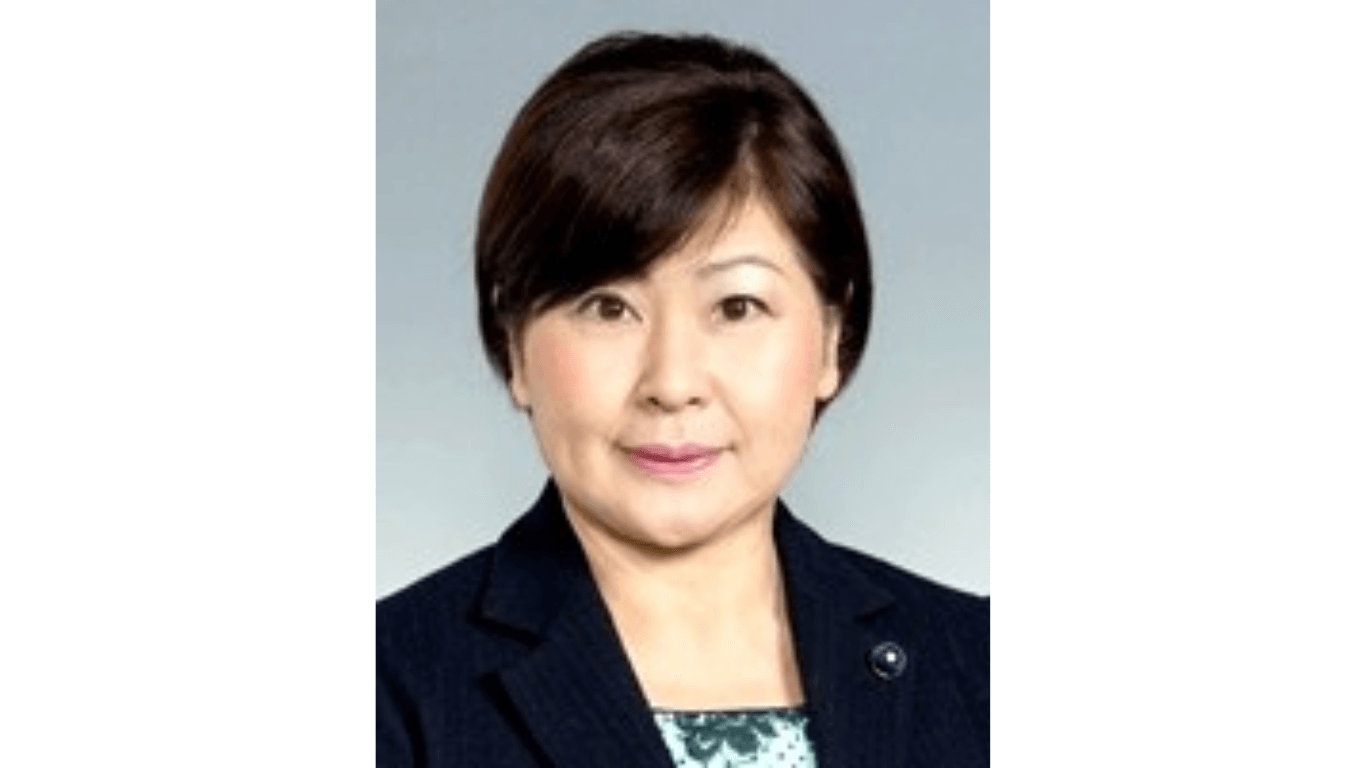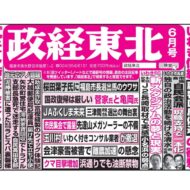県人事委員会は10月2日、県職員の給料月額と期末・勤勉手当(ボーナス)の引き上げを県当局・議会に勧告した。公務員の待遇は、人事院(国)、人事委員会(都道府県・政令指定都市)の毎年の勧告によって決まり、その勧告内容は表向きは民間給与との比較によって決まるとされている。ただ、実際は民間給与の実態とかけ離れている。
バブル期並みの引き上げ勧告
この号が店頭に並ぶころには、知事や市町村長、議員、公務員のボーナス(期末・勤勉手当)に関する報道が出ていると思われる。それを国民・県民はどう捉えるだろうか。
ボーナスを含む公務員の待遇は、人事院(国)、人事委員会(都道府県・政令指定都市)の毎年の勧告によって決まる。人事院は「公務員給与実態調査」と「民間給与実態調査」を行い、職種、地域、学歴、役職、年齢などを加味して両者を比較し、給与勧告を行う。この勧告は一般職の国家公務員が対象となる。
今年は8月8日に人事院勧告が行われた。内容は、月給を平均1万1183円(2・76%)、ボーナスを0・10カ月引き上げるよう勧告するもの。月給の引き上げは、1991年の1万1244円以来、33年ぶりの高水準という。
そのほか「給与制度のアップデート」と題して、①初任給の大幅引き上げ、管理職は職責重視の体系に刷新、②地域手当を都道府県単位に広域化、③通勤手当の上限を月15万円に引き上げ、新幹線通勤の要件緩和、④配偶者に係る扶養手当を廃止、子に係る手当を増額――といった内容も盛り込まれた。
一方、都道府県・政令指定都市の実態調査は各自治体の人事委員会が実施する。
福島県人事委員会は、委員長・齋藤記子氏(会社役員)、委員(委員長職務代理者)・千葉悦子氏(大学名誉教授、福島県青少年育成・男女共生推進機構副理事長兼福島県男女共生センター館長)、委員・大峰仁氏(弁護士)の3人で、事務局職員は県職員。
県人事委員会では毎年、県職員と民間の給与実態調査を行っている。民間の調査対象は企業規模50人以上・事業所規模50人以上の県内事業所で、今年は866事業所のうち、層化無作為抽出法によって抽出した174事業所を対象に調査した。
それによると、今年4月分として支給された職員給与は36万8969円、民間給与は37万9303円で1万0334円(2・8%)の開きがあった。さらに、民間の昨年8月から今年7月までの1年間で支給されたボーナスの割合は4・58カ月分で、県職員の年間支給月数は4・45カ月分を、1・3カ月分上回った。
こうした調査結果から、「民間給与との格差(2・80%)を埋めるため、若年層に特に重点を置きつつ、全ての号給の給料月額を引き上げ」、「期末手当及び勤勉手当を引き上げ(0・15カ月分)、民間のボーナスの支給状況等を踏まえ期末手当に0・05カ月分、勤勉手当に0・1カ月分を配分(※計4・6カ月分)」との報告・勧告を行った。
このほか、「人事院勧告の内容を踏まえた給与制度のアップデートのための改正」として、①給料表(中堅職員は給料月額の最低水準の引き上げ、管理職は職責重視の給料体系に見直し)、②通勤手当(支給限度額の引き上げ、新幹線等の利用に係る支給要件の緩和)、③扶養手当(配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当を増額)なども盛り込まれた。
引き上げ勧告は3年連続で、今回の引き上げ率2・8%(前年度0・88%)は、33年前の1991年以来の高水準という。1991年と言えばバブル末期で、県人事委員会は当時と同程度の経済・社会情勢にあると判断したということか。筆者はいわゆるバブル期を体験していない(まだ子どもだった)が、いまがその時のような状況にあるとは思えない。むしろ、相当厳しい経済・社会情勢にあるという認識だ。
そもそも、報告・勧告の内容は、ほぼ人事院勧告に倣ったもの。それも毎年のことだ。本当に無作為で調査して、人事院調査と同じ結果になっているとしたら、相当〝持っている〟と言える。そんな〝持っている〟組織があるなら、その集団に県政を委ねた方が面白い。
他の調査との違い
厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」を見ると、福島県の給与額(所定外賃金を含む)は、企業規模10人から99人が28万0900円(平均年齢46・3歳、平均勤続年数12・0年)、同100人から999人が29万8200円(平均年齢43・7歳、平均勤続年数12・7年)、同1000人以上が35万7800円(平均年齢43・0歳、平均勤続年数14・3年)で、これらすべての平均値は30万6100円(平均年齢44・5歳、平均勤続年数12・8年)だった。
年間賞与、その他特別給与額(全区分の平均値)は71万3700円で、これを前述の給与月額(平均値)で割ると、2・33カ月分となる。企業規模1000人以上の大型事業所に限定しても、年間賞与、その他特別給与額は109万2200円で、3・05カ月分になる。
県商工労働部が実施した「令和4年 労働条件等実態調査」では、2023年7月に支給された所定内給与額(基本給など)は28万5000円(平均年齢42・1歳、平均勤続年数14・3年)、所定外給与額(時間外手当など)は3万8000円で、合わせて32万2000円だった。なお、同調査では、ボーナスについては記されていない。
県人事委員会の調査で示された民間の給与月額と、厚労省調査、県商工労働部調査ではだいぶ開きがある。厚労省調査の企業規模1000人以上の大型事業所と比較しても、人事委員会調査の方が高い数値(給与額、ボーナス支給額)が出ている。
なぜ、両者の調査にこんなに違いが出るのか。それは人事院・人事委員会の調査対象が「企業規模50人以上・事業所規模50人以上」とされているから。これに該当するのは国内全事業所のわずか数%しかなく、大部分の事業所が調査対象に入っていないのである。この時点で、大前提である「民間準拠」は成立していない。さらに、調査対象の事業所は公表されていない。これでは、調査の妥当性を検証する余地がなく、「優良企業」だけをピックアップしていても外部からは分からない。むしろ、厚労省調査の企業規模1000人以上の大型事業所と比較しても、人事委員会調査の方が高い数値になっていることを考えると、何らかの〝手心〟を加えていると疑うべきだろう。
そもそも、厚労省や県商工労働部で給与実態を調査しているのだから、それを用いればいいだけの話。人事委の職員は県職員で、自分たちの給与に関する調査を、自分たちでしているからこうなる。
民間準拠を謳うのであれば、誠実にそうすべき。これまでの〝超優良準拠〟を続けるのであれば、それを正直に提示して国民・県民の審判を受ければいい。民間準拠を装って、実際は〝超優良準拠〟という国民・県民を欺く行為は許されない。