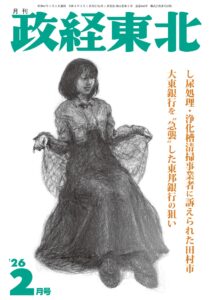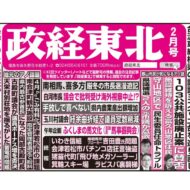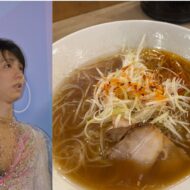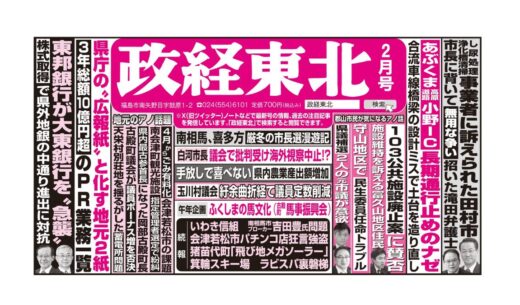他人事ではない昭和的な組織風土 地域活動家・小松理虔さん
いわしん(いわき信用組合)に関しては、活動をPRする仕事を引き受けたことがあります。本部で本多洋八理事長(当時)をはじめ幹部の皆さんと何度か打ち合わせをしましたが、その際、彼らから聞いた「金融包摂」という考え方が心に残りました。地銀で融資を受けられない人たちにもお金を借りてもらう機会をつくり、経済活動への参加を促して、生活基盤の安定や所得の向上につなげていく――というものです。
本多理事長は「組合員に預けてもらったお金はそういう形で地域のために活用していく。ぜひ組合員になってほしい」と話しました。私は「まるでクラウドファンディングのような現代的な取り組みだ」とすっかり感動して、いわしんに口座を開設したのです。
ところが朝日新聞の特ダネ記事や第三者委員会の調査報告書で、巨額かつ組織ぐるみの不正融資が明るみに出ました。特定の企業を存続させるため、法に抵触する行為を繰り返していたのは明らかに行き過ぎており、信用組合を存続させて地域経済を支えるという目的があったとしても許されるものではありません。怒り、裏切られた思いが強いです。
不正融資の指示を出したのは江尻次郎元会長だったと言われています。ただ、江尻元会長を知っている人に印象を尋ねると「とても面倒見がよくて豪快なおじさん」と言います。おそらく「俺がいいって言っているんだからその通りにやれ。責任は俺が取る」という、家父長的なリーダーだったのではないでしょうか。こういうタイプのリーダーは頼りになるが、周囲が意見を言えなくなってしまう傾向があります。
市民は語りたがらない
職員は第三者委員会の調査に非協力的で、証拠隠滅をはかったとされています。おそらく「組織や〝おやじ〟である江尻元会長を守らなければならない」という使命感を抱いていたのでしょう。客観的に見れば明らかな犯罪行為であり、発覚すれば大問題になると分かっていたはず。それでも自浄作用が働かず、組織を守るため隠蔽に走ったのは、日本社会に根強い事なかれ主義や同調圧力を象徴しているようにも感じます。
取り返しのつかないレベルにまで不正融資の金額が膨れ上がっていたので、職員も「これが発覚したら俺らも首が飛ぶ。いわしんと一蓮托生だ」という感覚を持っていたのかもしれません。
いわきの人たちはあまりこの問題を語りたがりません。いわしんと取引があったり、職員に知り合いがいたりして、身近な金融機関であるという事情はあると思います。
それに加えて、いわしん的な家父長的リーダーを中心とした組織風土が市内の企業や団体にも残っていて、自分たちにも思い当たるフシがあるだけに問題について語りにくい、ということがあるのではないかと感じています。ニュースや新聞の解説記事を見ると、金融史に残る不正融資が組織ぐるみで行われていたことに組合員として怒りを覚えるのですが、一方で、自分が所属する地域・組織にもどこか似た体質があるというか、地続きの感覚を抱いてしまいます。
もし自分がいわしんの職員だったら、江尻元会長という絶対的なリーダーに対し「それはダメですよ」と言えたかどうか分かりません。いわしんを徹底的に批判すれば自分自身に跳ね返ってくる気がして、言葉を飲み込んでしまうのだと思います。
いわき市では、市水道局の工事入札を巡る贈収賄事件が発覚し、私が住む小名浜地区の管工事会社の社長が贈賄容疑で逮捕されました。社長は私もよく知る人で、地元では事件が表面化した背景などがウワサされています。そうした点も含めて、「昭和」的な体質から抜け出せていない地域だとあらためて感じます。
いわき市では「ジェンダーギャップを解消し、女性が暮らしやすい環境をつくろう」、「若者を地元にとどめて人口増を目指そう」と呼びかけています。ただ、地域や組織に古い家父長的な体質が残っていれば、女性や若者は「暮らしにくい」と感じて他地域に流出してしまうかもしれません。
自分が所属するコミュニティーは「昭和的体質」、「田舎の悪しき同調圧力」から脱し切れているのか。自分は若い人たちとフラットなコミュニケーションができているのか。いわしん的な組織風土は自分が所属している地域や組織の中にもあるということを正面から受け止め、自分ごととして考えていく必要があると考えています。
私の周囲には「あれだけ悪質な不正行為をしていた金融機関に口座を設けていること自体が、コンプライアンス的に見ればリスクがあると捉えられる」と考え、いわしんの口座を解約し、地銀に口座を新設した人がいます。一方で「いわき信用組合にお世話になったから、この苦しい時期に口座を解約するわけにはいかない」という人もいます。どちらの考えも理解できます。
組織が生まれ変わる好機
私がいま一番興味を持っているのは、いわしんが本当に新たな組織に生まれ変われるのか、ということです。働いている人たちは「私たちがしっかりやっていかなければ」と思っているのか。特にこれからのいわしんを担う若手・中堅職員の声があまり聞こえてこないのが気になります。これだけ大きな不正融資が発覚したので、失望して退職する職員が出ても不思議ではないですが、それもどれぐらいいたのか地元の組合員にも聞こえてきません。
信頼構築の道は険しいと思いますが、ある意味、うみを出し切って健全な組織に生まれ変わる好機でもあります。組合員のお金で経営が成り立っているのだから、再建案をもっとオープンにして共有し、いわしんと組合員がこれからの経営再建について、平場で語る機会をもっと作るべきだと思います。
現状では、まだまだ役員が密室で方針を決めているイメージが拭えません。どういうふうに生まれ変わろうとしているのか、これまでの組織風土をどのように変えていくのか、プロパーを役員に残した今回の人選は問題がなかったのか、なども含めて議論していく必要があります。