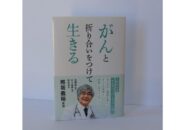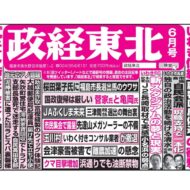高校野球秋季東北大会で7年ぶり2度目の優勝を果たした聖光学院。来春のセンバツ(甲子園)出場を確実にすると同時に、11月には新チームになって最初の全国大会である明治神宮大会に出場した。今夏の甲子園に続き、神宮大会初戦を現地取材した。(末永)
来春センバツでの逆襲に期待

明治神宮大会は、北海道、東北、関東、東京、東海、北信越、近畿、中国、四国、九州の10地区の優勝チームが出場する。出場校は別掲の通り。
明治神宮大会出場校
| 北海道 | 東海大札幌 |
| 東北 | 聖光学院(福島) |
| 関東 | 横浜(神奈川) |
| 東京 | 二松学舎大付属 |
| 東海 | 大垣日大(岐阜) |
| 北信越 | 敦賀気比(福井) |
| 近畿 | 東洋大姫路(兵庫) |
| 中国 | 広島商業(広島) |
| 四国 | 明徳義塾(高知) |
| 九州 | 沖縄尚学(沖縄) |
いずれも各地区大会を優勝しただけの実力を備えた強豪だが、このうち、横浜、敦賀気比、東洋大姫路、広島商業、明徳義塾、沖縄尚学の6校は、甲子園の春夏いずれか、もしくは両方で優勝経験がある。残りの4校のうち、東海大札幌(旧校名の東海大四高時代)、二松学舎大付属、大垣日大の3校は準優勝の経験がある。つまり、聖光学院だけ甲子園の決勝に進んだことがないのだ。甲子園常連校で、強豪として全国に知られる聖光学院からしても、出場校はすべて甲子園での実績(最高成績)が上のチームということになる。
10校によるトーナメントなので、1回戦は2試合だけ。6校は2回戦からの登場となる中、聖光学院は1回戦からの組み合わせとなった。相手は近畿地区優勝の東洋大姫路で、今大会の優勝候補にも挙げられていた。特に、エースの阪下漣投手は大会ナンバーワンと評されていた。強豪揃いの近畿大会を制しただけあり、実力は疑いようがない。
東洋大姫路の甲子園出場は夏12回、春8回の計20回で、1977年夏に優勝を果たしている。ただ、近年は甲子園常連ではなくなっていた。2000年以降で見ると、甲子園出場は2000年春、2001年夏、2003年春、2006年夏、2008年春、2011年夏、2022年春の計7回。聖光学院の計25回に比べるとだいぶ少ない。
近年の実績だけで言えば聖光学院の方が上で、東洋大姫路はオールドファンからしたら「古豪」というイメージだろう。
ただ、東洋大姫路は2022年4月に、それまで履正社高校(大阪)の監督を務めていた岡田龍生監督を招聘し、強化を図っていた。岡田監督は同校卒業生で、母校の監督に就任した格好になる。
岡田監督は履正社を率い、2019年夏の甲子園で優勝を果たした。大阪桐蔭と並び「大阪2強」時代を築いた監督としても知られる。
聖光学院とは、履正社を率いていた2010年夏の甲子園3回戦で対戦したことがある。当時の履正社には現ヤクルトスワローズの山田哲人選手、現阪神タイガースの坂本誠志郎選手らがいた。対する聖光学院は、阪神、ヤクルトなどでプレーした歳内宏明投手がいた。試合は山田哲人選手のホームランも飛び出したが、5―2で聖光学院が勝利した。
聖光学院にとって、全国大会(公式戦)で東洋大姫路との対戦は初めて、岡田監督との対戦は二度目ということになる。
難しい条件が重なる

試合前の注目ポイントは、東洋大姫路の阪下投手に聖光学院打線がどれだけ対応できるか、左の変則で東北大会で大活躍した大嶋哲平投手のデキはどうか、だった。
大嶋投手は本調子とは言えず、初回から捕まり、ホームランを浴びて3失点。その後も失点を重ね、変わったピッチャーもその流れを止めることができず、0―10で5回コールド負けとなった。打線も2安打に抑えられ、出したランナーはいずれも併殺でチャンスを作ることができなかった。
ランニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
| 聖光学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東洋大姫路 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1× | 10 |
聖光学院の安定した強さの1つに「底地の高さ」がある。例えば、チームの実力が100だったとする。ただ、常に試合で100の力が出せるとは限らない。試合の流れ、チーム全体の状態、選手個々の調子などによってその数値は変動する。そんな中でも、聖光学院はどんなにチーム状況や流れが悪くても、70〜80くらいの力が出せる。そのためのメンタル面のトレーニングを多く取り入れており、斎藤智也監督はその部分の指導に定評がある。この「底地の高さ」こそが安定した強さにつながっているのである。
ただ、この日の聖光学院は全くと言っていいほど力を出せないまま敗戦した。この間、甲子園で大差で負けたことはあったが、甲子園ではコールドがないため、甲子園常連校と言われるようになってから、コールド負けは初めての経験だったのではないか。
当然、それだけ相手の実力が上だったということはある。一方で、いろいろと難しい状況もあった。
試合当日は小雨が降り、かなり肌寒い天候だった。神宮球場は人工芝で、濡れるとバウンドした際に玉足が速くなり、経験がないと守りは難しい。もちろん、条件は対戦相手も一緒だが、県大会、東北大会と堅い守りで勝ち抜いてきたにもかかわらず、この試合は5回までで2つのエラーが出るなど苦しんだ。
先発した大嶋投手は指先の感覚が良くなかったのか、制球が定まらなかった。相手の阪下投手は力のあるボールを投げるが、それと違い大嶋投手は細かなコントロールで打者を打ち取るスタイルだけに、制球が定まらなければ痛打を喰らう。フォアボールも2イニングで2つ与え、エラー、四球のランナーを返されるという苦しい展開だった。
ちなみに、記者は気になったことをスマホにメモしながら見ていたが、スマホを操作する手が上手く動かないくらいの寒さだった。球威ではなく、コントロールを生命線とする大嶋投手(聖光学院投手陣)からしたら、難しい気候だったと言える。
もう1つは、東北大会は10月20日に決勝戦があり、神宮大会までは1カ月日程が空いた。これに対し、他地区は11月まで大会を行っていたところもあり、近畿大会の決勝は11月4日だった。つまり、神宮大会まで2週間ちょっとで、実戦感覚の部分でも差があった。
相手の実力が上だったのは間違いないが、こうしたさまざまな難しい状況が重なり、予想外の展開になってしまった。
試合後、斎藤監督は「こういう展開もある程度は想定していたが、守って守って、凌いで凌いで、何とか相手より1点でも上回るという形で勝ってきたチームが守備で崩れてしまい、打開策がなかった。リズムに乗り切れず、アッという間に終わってしまった」と振り返った。
続けて、こう話した。
「見逃し三振は2つあったが、空振り三振はなかった。速い真っ直ぐに対応する練習もしてきた。何とか接戦に持ち込んで、(バッターが)3巡目、4巡目に入った時に(阪下投手のボールに)どれだけ目が慣れてくるか、どう対応するかというのは見たかった。その楽しみもなく終わってしまった」
「(先発投手の)大嶋は(変則フォームから繰り出される)角度と制球力が武器だけど、これだけ乱れた。いいボールもあったと思うけど。本来はフォアボールで崩れるピッチャーではない。守備もそうだけど、自分たちが売りにしてきた大事なものを(フォアボールやエラーによって)自分たちで手放したら、何倍にもなって返ってくるということを、あらためて感じましたね」
「これだけやられた……というか、自滅ですけどね。初めての経験なんで、自分たちの弱さを自覚して、この冬に力を蓄えたいと思います。それにしても姫路さんはすごいね。ファールになった打球でも110㍍、120㍍くらい飛ばしているもんね。低反発バットでも、これくらいの(パワフルな)野球をしているところもあるということは励みにしたいですね」
斎藤監督の話にあった低反発バット(新基準バット)は、昨年のセンバツ大会から採用された。平均すると約15%の飛距離ダウンになると言われ、当然、打球速度も遅くなる。
この間、何人かの指導者に聞いたが、一様に「旧基準バットにくらべらたら、とにかく飛ばない」という。新基準バット採用以降の昨年春・夏の甲子園でホームランが激減したことからもそれが分かる。
聖光学院は、その時々のメンバーにもよるが、もともとは守備や走塁などを鍛え、小技を駆使して勝ち上がる「スモールベースボール」が得意だった。ただ、それだけでは全国の強豪校と渡り合うのは難しいと考え、幾度かの甲子園出場を経て、ある程度パワフルな野球も追い求めるようになっていった。
新基準バットが採用され、高校野球全体が以前の形に戻りつつある。聖光学院のようなチームが、より優位性を持つようになったと言える。その一方で、東洋大姫路には旧基準バット時代のようにパワフルな打線で圧倒された。そういったチームにどう対抗していくかかという点では、今後に向けていい経験になったはず。
〝本番〟は来年の甲子園大会。出場が確実視されるセンバツまでは3カ月以上ある。冬期は対外試合が禁止されているため、チーム内での鍛錬期間になる。もともと聖光学院は全国の強豪校に〝教えられて〟強くなっていった歴史がある。今回の敗戦、悔しさが選手たちを大きく成長させることを信じ、センバツでの活躍を期待することにしよう。