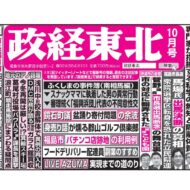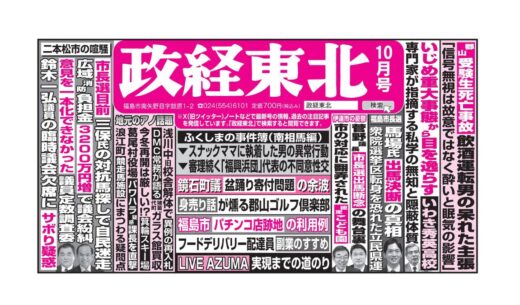甲子園球場(兵庫県西宮市)で行われた「第96回選抜高校野球大会」(通称・センバツ)に、33年ぶりに出場した学法石川。初戦で健大高崎(群馬県)に0―4で敗戦したが、地元は大きな盛り上がりを見せ、地元メディアでも大きく報じられた。チームに新たな歴史を刻んだ一戦を振り返る。
今後は県内2強時代に突入か

学法石川のセンバツ出場は1991年以来、33年ぶり4度目。夏を含めても、1999年以来の甲子園出場となった。
同校は昨秋の東北大会でベスト4に入った。今年から、東北地方のセンバツ出場枠が1増の3校となり、準決勝で敗退した2校(学法石川と、一関学院=岩手県)のどちらかが選出される可能性が高かった。つまり3枠目は、学法石川と一関学院で、五分五分の状況だったのだ。
通常、センバツに選ばれるのが確実な情勢であれば、冬季間も実戦形式の練習を多めにする。逆にセンバツの可能性がなければ、冬季間は実戦形式の練習はほとんどせず、基礎体力強化などが中心になる。春以降に実戦形式の練習を取り入れ、夏の大会に向けて準備をする。
ちなみに、高校野球は冬季間の対外試合が禁止されている。解禁になるのは3月の第一土曜日で、これはセンバツに出る・出ないに関係なく適用される。もっとも、センバツ出場が確実な情勢であれば、前年の秋の段階から、対外試合解禁と同時に数多くの対外試合(練習試合)をスケジューリングしておく。逆に言うと、センバツ出場が正式に決まってから(1月末以降)では、目ぼしい相手と練習試合を組むのは難しいということになる。
その点、学法石川は五分五分だったため、いろいろな面で調整が難しかっただろう。そんな中、3月上旬から静岡県内で合宿を行い、対外試合解禁後は、同県内の強豪校と練習試合を重ねて準備をした。
3月8日、大阪市の毎日新聞大阪本社で組み合わせ抽選会が行われ、大会2日目第3試合で、健大高崎(群馬県)と対戦することが決まった。昨秋の群馬県大会優勝、関東大会ベスト4で、2年連続7回目の出場(※うち1回は中止になった2020年)。今大会の優勝候補に挙げるスポーツ紙や専門誌もあるほどの強豪だ。
その試合を振り返る前に、今大会は1つ大きなトピックがある。バットがこれまでのものが使えなくなり、新基準バット(低反発バット)を使用しなければならなくなったことだ。これにより、平均すると約15%の飛距離ダウンになると言われている。分かりやすく言うと、従来のバットで100㍍飛んでいた打球が85㍍しか飛ばない計算。100㍍の飛距離があれば、ポール際ならホームランになるが、85㍍なら外野フライになってしまうこともあるだろう。そのくらい違うのだ。
学法石川の佐々木順一朗監督は、新基準バットについて、次のように話していた。

「新基準バットは、(秋季大会が終わり)寒くなってから使い出したこともあるでしょうけど、間違いなく飛ばないですね。例えば、当たり損ないが外野をオーバーしたりとか、そういったことはなくなると思います。当然、ホームランなんて、なかなか打てませんし、本当にちゃんと捉えた場合のみ、外野を抜ける感じですかね。一昔前に戻ったような印象です。生徒たちは、一昔前といっても分からないでしょうけど。もっとも、ウチはもともと点数をいっぱい取るチームじゃないから、ピッチャーを中心に、内野の動きとかも重要になるのかなと思っています。あとは足の速いチームが有利になるのかなという感じもします」
一昔前の高校野球と言うと、送りバントなどの小技を駆使して、少ない得点で守り勝つイメージ。実際、健大高崎との試合前、佐々木監督は「どんな形でもいいので先制して、ロースコアの接戦に持ち込みたい」とゲームプランを語っていた。
一方、佐々木監督は新基準バットになり、「足の速いチームが有利になるのかな」とも語っていた。その点で言うと、対戦相手の健大高崎は「機動破壊」が代名詞で、機動力(足)を使った攻撃が売りの1つ。その辺もかなり警戒していた。
試合レビュー
ランニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 学法石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健大高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
試合は、序盤は凌ぎ合いの展開。その中で、「どんな形でもいいので先制したい」という佐々木監督の言葉通り、学法石川はワンアウトからでも送りバントでランナーを進めようとした。初回、2回、3回、6回と4度、ワンアウト1塁のケースで送りバントを試みたが、3回以外はいずれもバント失敗。相手投手、守備陣にプレッシャーをかける場面をつくれなかったのが痛かった。7回まではいずれも先頭バッターが出塁することができなかった。
一方、先発した背番号10番の佐藤翼投手は、序盤は毎回ランナーを背負ったが粘りのピッチングで5回までゼロを並べた。6回は味方のエラーと内野安打でピンチをつくったが、相手の送りバントを3塁で封殺して「ゼロで乗り切れる」という雰囲気になった。ところが、そこからバッテリーエラー(暴投)が2つ出て先制を許してしまう。結果的には、相手の送りバントを封じて「行ける」という雰囲気になった後だっただけに、2つのバッテリーエラーが響いた格好。
7回裏の守りは四球と送りバントを絡めて、3本のタイムリーヒットを浴び、0―4とされた。終盤での追加点だけにかなり痛かった。
8回表の攻撃でようやく先頭バッターが出塁したが、点差が4点に開いた後だっただけに、強攻策に出るしかなく得点できず。
最終回は連打と四球でチャンスを作ったが、あと一本が出ず0―4のまま敗戦。
学法石川として痛かったのは、線番号2番、キャッチャーで秋季大会はマウンドにも上がり、打者としても中心選手だった大栄利哉選手がケガで先発出場できなかったこと。それでも、佐々木監督の教えである「ピンチでも笑顔で」を実践して、「らしさ」は出すことができた。これからチームがさらに強くなるための一歩になったのは間違いない。
以前、県内絶対王者として君臨する聖光学院の斎藤智也監督に「学法石川は一度甲子園に出て、目に見えない自信のようなものを手にしたら、その先、かなり強力なライバルになるのでは」と聞いてみたことがある。斎藤監督の答えは「ウチがまさにそうだったよね」。
聖光学院は一度甲子園に出て、そこで「全国レベル」を痛感させられた。ただ、その試合を見た野球少年たちが「自分が入って、このチームを強くしたい」、「このチームに入り、このユニフォームを着て甲子園に出たい」と、同校に入ってくるようになった。それに伴い、選手のレベルもどんどん上がっていき、いまや全国でも強豪校になった。
そのくらい一度の甲子園出場は大きいことなのだ。学法石川は久々の甲子園で初戦敗退となったが、そういった意味でもこの経験は必ず生きる。今後は、聖光学院と学法石川の県内2強時代突入を予感させる。