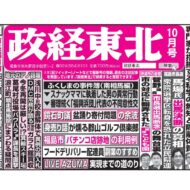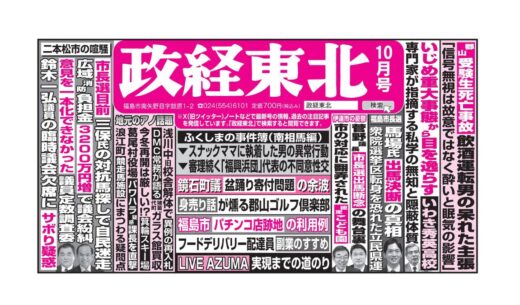たけのした・せいいち 1951年生まれ。鹿児島市出身。群馬大医学部卒。福島県立医科大附属病院長、同医大副理事長などを歴任し、2017年4月から現職。
福島県立医科大学(福島市)は、福島県が大熊町の県立大野病院跡地に整備する病院の附属化を受諾し、双葉地域の医療支援に本格的に取り組む方針を示している。研究技術を生かした民間企業との連携、医師確保にも積極的に取り組み、近年は国際連携に力を入れている。同大学の竹之下誠一理事長(3期)に同大学の取り組みや今後の見通しについて話を聞いた。
「世界的な知見を持ちながら、地域に根差した研究や課題を解決する」
――昨年、大熊町の県立大野病院の後継病院が県立医科大学の附属病院となる方向性が示されました。
「昨年7月、県から『福島県立医大の附属病院化を検討してほしい』という依頼があり、直ちにワーキンググループを設置して検討を重ねました。その結果、双葉地域の復興の中核を担う病院を福島県立医科大学の附属病院とすることは、福島の復興を医療面から支え、『県民のこころと体の健康を長期的に見守り、福島の復興の中核となる』という本学の歴史的使命の実現につながりますので、受諾する旨、県に回答いたしました。手術や診療などの遠隔医療を可能にするスマートホスピタルを目指し、東京電力福島第一原子力発電所に近いことも考慮して、廃炉作業を医療面から支えていくという役割を担っていきたいと考えております。現在、県で建築設計等の準備を行っております。双葉地域における中核的病院が、地域に密着し、住民が安心して生活するための連携の核となり、また、地域の発展に貢献できるよう県と連携しながら準備を進めてまいります」
――大学に併設されている附属病院本館が老朽化していることから建て替えを計画しているそうですね。どのような施設になるのでしょうか。
「コンセプトは『環境の変化に適応し、進化する大学病院』です。最先端の医療・教育・研究を追究し、臨床教育施設、研究施設を充実させ、県民がより安心して治療を受けられる環境を整備します。
現在の附属病院と隣接する外来駐車場の場所に建設する予定です。病床数は、現在の778床から695床に減らしますが、高度治療室(HCU)を設けて高度急性期の機能を充実させます。病室は全て個室で、差額料金を取らない個室を半分以上設けるほか、県民の健康増進のために健診機能を持つ『疾病予防センター(仮)』も設置します。2月に再整備基本計画を策定し、今後は基本設計・実施設計を進めて、2030年度の開院を目指します」
――昨年、メッセンジャーRNAを活用した医療品・ワクチン研究開発を進めるべく、県内の民間業者2社と業務提携されました。
「本学の医療―産業トランスレーショナルリサーチセンターが中心となって進めている事業です。株式会社アルカリスの南相馬市への進出を支援するなど、浜通りの医薬品関連産業の集積・振興に努めています。
本学の強みである抗体研究の鍵となるのがワクチンを含む『抗原』であることから、抗原と抗体を車の両輪として研究開発を進めたいと考え、ご案内のとおり、昨年11月には、アルカリス、一般財団法人福島医大トランスレーショナルリサーチ機構、そして本学が、メッセンジャーRNA医薬品、ワクチンの研究開発及び製造に係る協業関係を進めていくことに関する包括業務提携を締結しました。
本学では世界で初めてコロナウイルスに対する抗体を直接採取することに成功しました。この技術とアルカリスのワクチン製造技術を組み合わせることで、変異の速いコロナウイルスにも迅速に対応できるワクチン開発が可能になります。
今後は、新型コロナウイルスなど感染症のワクチンだけでなく、がんワクチンなど、さまざまなワクチンや抗体医薬品の開発につなげていきたいと考えています。『福島、すなわち浜通りの抗体が世界を救う』という意気込みで研究を進めていきます」
各地域の健康課題を分析
――福島県は、メタボリックシンドロームに該当する人の割合が全国ワースト4位で、慢性的にメタボ率が高い傾向にあります。
「これは本県にとって長年の課題であり、なかなか解決に至っていないのが現状です。本学の健康増進センターが中心となり、県からの委託を受けて、医療レセプトや特定健診など保健・医療・介護のデータを蓄積した『福島県版健康データベース(FDB)』を用いて市町村ごとの健康課題を分析し、それぞれ健康増進策を支援しています。
生活習慣病予防のために、食習慣、運動習慣、飲酒、喫煙、睡眠などの改善を呼びかけています。また、県民一人ひとりの健康意識を高める狙いから『いきいき健康づくりフォーラムin会津若松』を開催するなど、さまざまな啓発活動も行っています。
県からの委託で、働き盛り世代に向けた運動方法などを解説した動画を制作したほか、健康増進センター公式ユーチューブチャンネルにも動画がアップされているのでぜひご覧いただきたいです。今年度、メタボリックシンドロームの割合が県全体と比較して高い状態にある双葉郡を対象に、食習慣調査を実施し、食行動の改善に向けた保健指導などに活用していただく予定です」
――県内の人口10万人当たりの医師数は全国下位に低迷します。医療人材確保に向けた対策について。
「本学は、地域医療を担う医師の育成に力を入れるとともに、県内の臨床研修病院と連携してネットワークを形成し、医学生の医療人としてのキャリア形成を支援し、卒業後の本県医療機関への定着促進、県内医師の確保を図っています。派遣した若手医師の育成・キャリア形成の向上を図るため、その派遣先に県外から指導医・専門医を招聘しているほか、地域間の医師偏在を解消することを目的に、修学資金を貸与していた医師を3カ月ずつ、医師不足地域の医療機関に常勤医として派遣する、新たな取り組み『福島モデル』を令和6年度から開始しました」
――最後に今後の抱負を。
「理事長兼学長となってからの8年間、『ピンチをチャンスに、変化を進化へ』をモットーに邁進してまいりました。多くの困難に立ち向かうことができたのは県民の皆さまのご理解とご協力のおかげです。あらためて感謝いたします。震災・原発事故、コロナ禍で医師・職員も影響を受けましたが、さまざまな分野で成果を出していただいたことに感謝しています。本学の先端臨床研究センターでは世界で初めて放射性物質『アスタチン』を用いたがん治療薬の研究・開発を行っています。今年3月には保健科学部1期生が卒業し、4月には大学院に保健科学研究科保健科学専攻修士課程が開設されました。医学部だけでなく、看護学部、保健科学部があり、それらの大学院も擁する医療系総合大学は全国でも少ないので、その強みを生かしていきたいです。
1月には本学に在籍していた後藤あや特任教授が主任教授を務めるハーバード大学公衆衛生大学院の学生15人が来学し、原発事故後の対応などを学習していったほか、韓国原子力医学院とも先端核医学・原子力災害医療の連携強化を目的とした覚書を締結しています。本学としては、世界的な知見を持ちながら、地域に根差した研究や課題を解決し、必要とされる医療を提供していくという姿勢が重要だと考えており、今後もその姿勢で取り組んでいきたいと考えています」