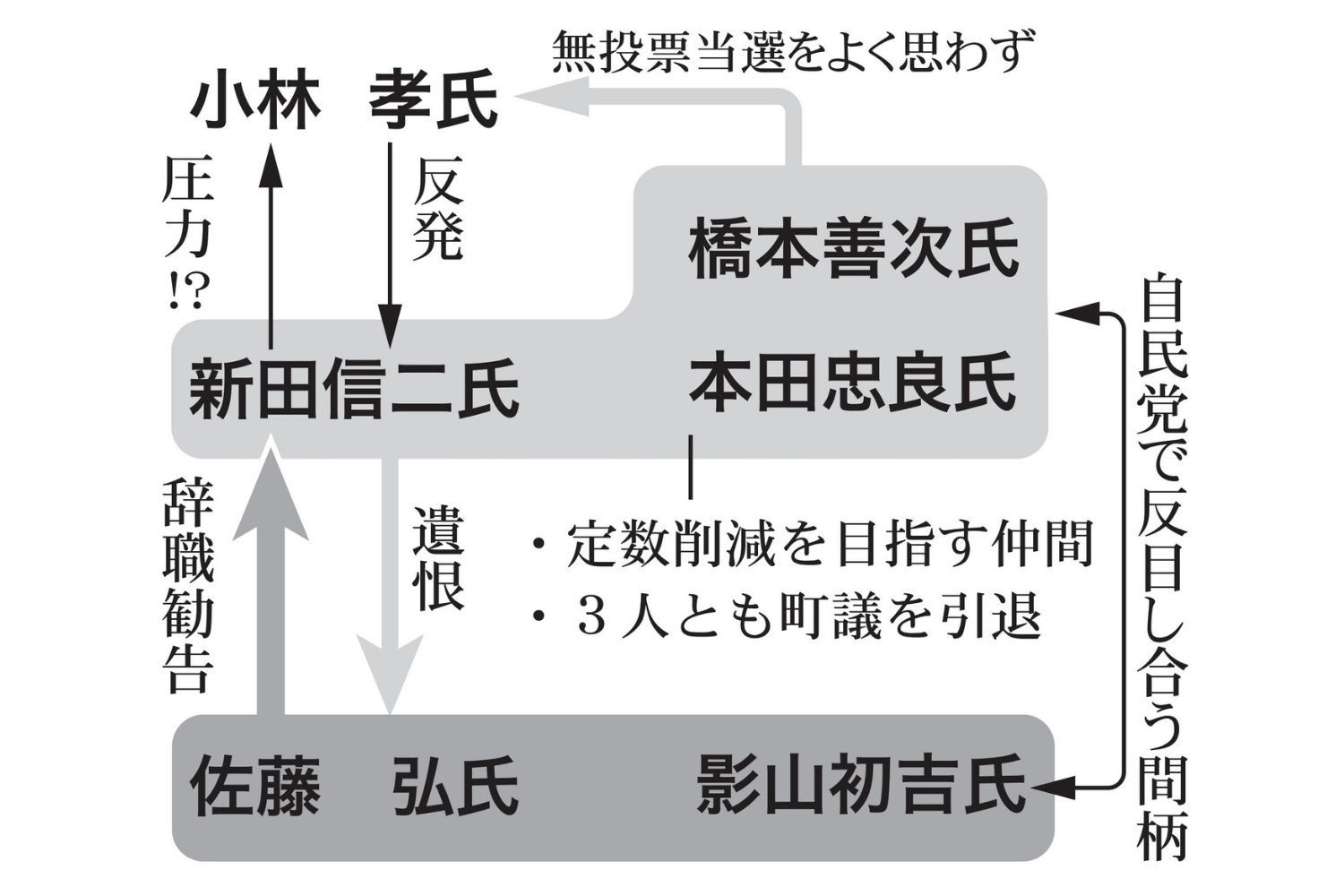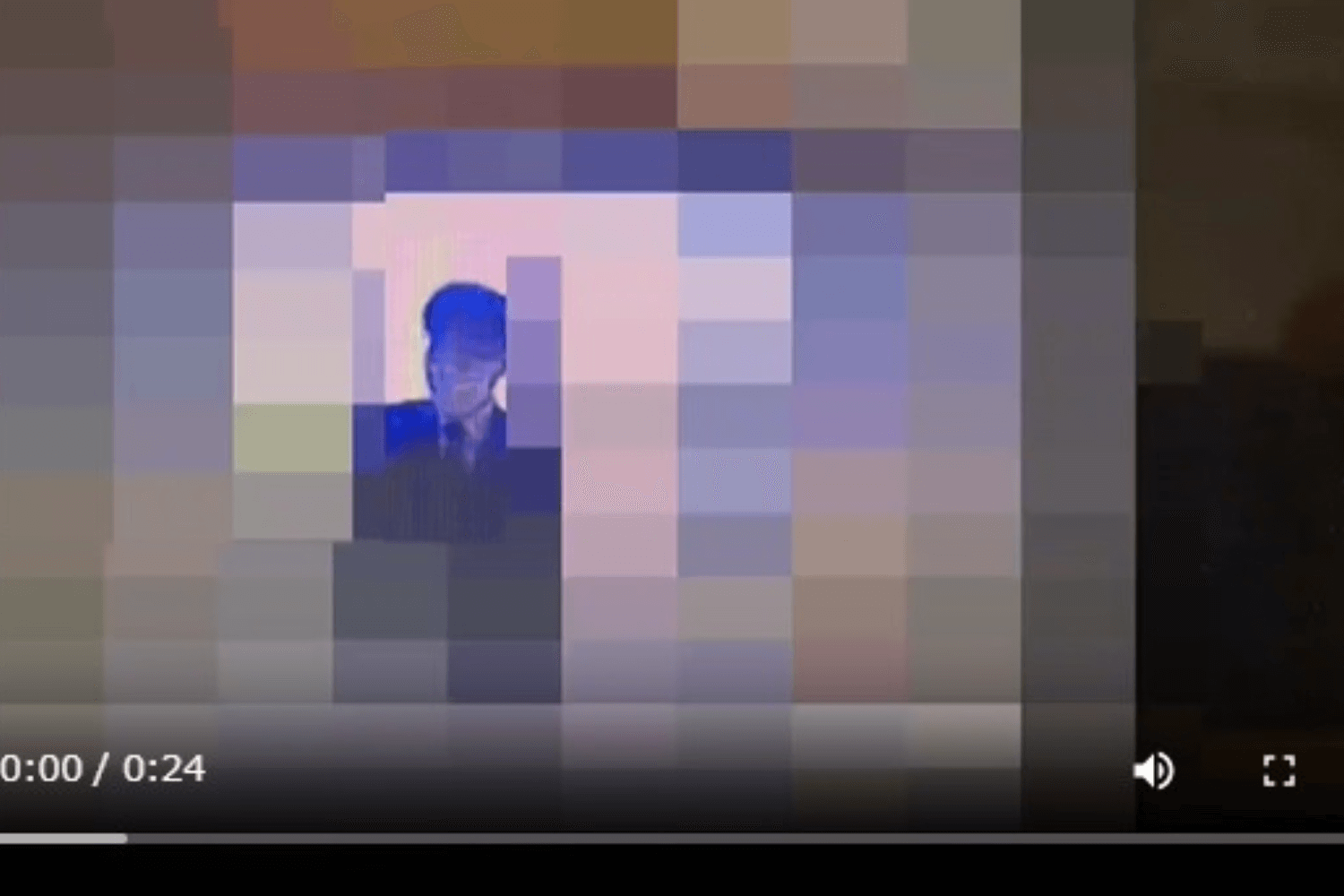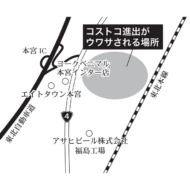さめじま・ひろし
京都大学法学部を卒業し1994年に朝日新聞入社。99年に政治部に着任し、菅直人、竹中平蔵、古賀誠、与謝野馨、町村信孝ら与野党政治家を担当。2010年に39歳で政治部デスクに抜擢される。13年に「手抜き除染」報道で新聞協会賞受賞。21年に独立して「SAMEJIMA TIMES」を創刊。ユーチューブやウェブサイトで政治解説動画・記事を公開し、サンデー毎日やABEMA、プレジデントオンラインなどにも出演・寄稿している。著書に『朝日新聞政治部』(2022年、講談社)、『政治はケンカだ~明石市長の12年』(泉房穂氏と共著、2023年、講談社)。
「吉田調書」
新聞社が埋もれた事実を自力で掘り起こし、自らの責任で権力者を追及する「調査報道」がめっきり減った。そればかりか、週刊誌が報じた「疑惑」に世間の耳目が集まっても、何事もなかったようにやり過ごす光景が繰り返されている。
芸能界に君臨したジャニー喜多川氏の性加害問題、岸田文雄首相の最側近である木原誠二官房副長官の妻が元夫の不審死事件の重要参考人として事情聴取されながら捜査が不自然に打ち切られた疑惑……。具体例は枚挙にいとまがない。
警察や検察が捜査に動かない限り、行政が発表しない限り、当事者が不正を自ら認めて謝罪しない限り、「疑惑報道」に踏み切って抗議を受けるリスクを背負うことは避ける。それが主要メディアのたしなみであると言わんばかりに、新聞は振る舞っている。各紙が示し合わせたかのように疑惑を「なかったこと」として片付ける様子は業界談合そのものだ。
新聞がこれほど不甲斐なくなったのはいつからだろう。
福島第一原発の事故直後、現場で事故対応を指揮した吉田昌郎所長の証言録「吉田調書」を朝日新聞が独自入手してスクープしたのは、安倍政権下の2014年5月だった。政府が伏せ続けてきた歴史的証言録を白日の下にさらす大キャンペーンを手掛けたのは、記者クラブを主要拠点とする政治部や社会部ではなく、調査報道に専従する特別報道部だった。私はその取材班を率いるデスクを務めていた。
安倍政権は報道当初、「吉田調書」の公表を拒否し、他紙も「なかったこと」として黙殺した。約3カ月後、第一報のタイトルや文中表現に対してネット上に批判が広がると、安倍政権は一転して「吉田調書」を公表して反撃を開始し、他紙は安倍政権の主張に沿って「朝日批判」に一斉に踏み切った。
朝日新聞の経営陣は2014年7月時点で「吉田調書」報道を高く評価し、新聞協会賞に申請していたのに、安倍政権や他紙から集中砲火を浴びると持ち堪えられず、9月になって記事全文を「誤報」として取り消し、社長の引責辞任に加え、デスク(私)や取材記者を懲戒処分にすると表明したのである。
第一報のタイトルや文中表現の是非について見解が割れるとしても、意図的な捏造報道でもないのに記事全文を抹消し、歴史的スクープを丸ごと「なかったこと」にしてしまったのは、組織防衛を優先した過剰対応だったと言うほかない。朝日新聞が編集責任を負う立場にある管理職にとどまらず、「吉田調書」を独自入手した取材記者まで懲戒処分にしたことは、ジャーナリズムの自殺行為であった。取材記者はネット上で「捏造記者」「売国奴」などと罵詈雑言を浴び、バッシングの矛先は家族にも向けられたが、朝日新聞はこの事態を放置し、取材記者を守らなかった。
詳細な経緯は拙著『朝日新聞政治部』(講談社)に記したが、「吉田調書」事件は、調査報道を仕掛けた朝日新聞が国家権力の反撃に屈服した事件としてメディア史に刻まれたのである。
朝日新聞に限らず新聞業界全体に「権力批判」に対する怯えが広がった。警察や検察が立件したり、行政が発表したり、当事者が不正を認めたりするまではリスクを冒して報じることを避ける「保身文化」が蔓延したのである。
朝日新聞は「吉田調書」事件後、特別報道部を縮小し、2021年春には廃止した。私は同年春に退社して「SAMEJIMA TIMES」を創刊し、ウェブサイトやユーチューブで政治解説を中心に発信している。政府広報紙と化した現在の新聞の不甲斐なさを目の当たりにするたびに、「吉田調書」事件は新聞ジャーナリズムが凋落した転換点だったと思わずにいられない。当事者として結果責任を痛感している。
朝日新聞特別報道部は当時、福島第一原発事故を題材にした長期連載「プロメテウスの罠」と「手抜き除染」のスクープ報道で、新聞協会賞を2年連続で受賞して勢いに乗っていた。私は同部の立ち上げから深くかかわってきたが、政治部、経済部、社会部などから引き抜いたエース記者と、他社から引き抜いた腕利き記者が切磋琢磨する異色の組織だった。
なかでも「プロメテウスの罠」のデスク役を務めた依光隆明記者(高知新聞)、「手抜き除染」のメインライターだった青木美希記者(北海道新聞)、大阪地検による証拠改竄をスクープした板橋洋佳記者(下野新聞)ら地方紙出身の記者の活躍はめざましく、朝日新聞に新たな息吹を吹き込んでいた。永田町・霞が関で国家権力に肉薄してきた記者と、全国各地で地道な調査報道を重ねてきた記者の個性が融合し、新基軸の調査報道集団が生まれつつあった。
私は特別報道部次長として「地方紙と連携した調査報道」に可能性を感じ、ある原発立地県の地方紙幹部と水面下で交渉を重ね、「共同調査報道」の合意寸前までこぎつけていた。東京を拠点とする全国紙は中央省庁との結び付きが強く、国家権力追及に及び腰になる傾向がある。一方、地方紙は県庁や県警に加えて、電力会社など地域の看板企業に弱い。双方の弱点を補い合うため「原発利権」をテーマに共同取材班を立ち上げ、双方の紙面で同時キャンペーンを展開しようと考えたのだ。
これらの構想も「吉田調書」事件ですべて吹き飛んでしまった。
地元メディアと政治家の関係性
今年5月に上梓した泉房穂・前明石市長と私の共著『政治はケンカだ!~明石市長の12年』で印象に残ったのは、泉市長と神戸新聞との緊張関係だった。
泉氏は2011年4月の市長選で自民、民主、公明が相乗りして兵庫県知事が全面支援する元知事室長との一騎打ちを69票差で制した。全政党、全業界を敵に回して当初はマスコミに泡沫候補扱いされたが、市民の草の根の応援だけを頼りに激戦を勝ち抜いたのである。就任当初は市役所にも市議会にも味方がいない四面楚歌の状態だった。
それにも増して手を焼いたのは神戸新聞との関係だった。泉氏は市の税金が購読料や広告費などとして神戸新聞やグループ企業に流れ込んできたことを知り、「税金で番組を買わなくても普通に報じてもらえばいい」と指示し、予算を削減した。これが神戸新聞上層部の逆鱗に触れ、泉市政を糾弾する記事が急増したのだという。
地元で圧倒的シェアを誇る地元紙を敵に回すことは、知事や市長に大打撃を与えかねない。他方、県や市の予算を収入源の大きな柱とする地元紙は、国の批判にはためらいがなくても、地元自治体の追及には及び腰になりがちだ。この「持ちつ持たれつの関係」が崩れたのが明石市だった。初当選から12年、泉市長と神戸新聞の関係はぎくしゃくし続け、市役所や市議会からのリーク情報とみられる記事が繰り返し掲載された。

こうした事態を避けるため、大概の知事や市長は地元紙と良好な関係を維持し、「権力とジャーナリズムの緊張関係」は希薄になる傾向がある。
さらに露骨なケースもある。香川県立高松高校で私と同級生だった立憲民主党の小川淳也衆院議員は「香川1区」で自民党の平井卓也衆院議員と熾烈な戦いを繰り広げてきたが、最も頭を悩ませてきたのは、香川県内でシェア6割を誇り、系列テレビ局もあわせ持つ四国新聞を「平井一族」が経営していたことだった。

最近では石川県の馳浩知事と地元紙の北國新聞との関係が注目された。馳知事は石川テレビが制作したドキュメンタリー映画「裸のムラ」に自身や県職員の映像が許可なく使用されたことに抗議し、定例記者会見の開催を拒否。県政記者クラブ(14社加盟)は総会を開いて早期再開の申し入れを協議したが、北國新聞とテレビ金沢は賛同せず、全国紙などの有志で申入書を提出することになった。地元メディアと知事の濃密な関係をうかがわせる事態である。
北國新聞は地元の大物政治家・森喜朗元首相のインタビューを継続的に掲載している。最近では自民党安倍派の会長を争う5人衆(松野博一官房長官、高木毅国会対策委員長、世耕弘成参院幹事長、西村康稔経済産業相、萩生田光一政調会長)の人物評を言い募り、萩生田氏だけを絶賛する森氏のインタビューが永田町の話題をさらった。一連のインタビューについては「地元の大物政治家と地元紙の密接な関係」を疑問視する声がある一方、「全国紙では引き出せない森氏の本音を報じた意義は大きい」と評価する声もある。
仮に石川県内の報道機関が北國新聞だけならば、大物政治家との密接な関係はマスコミの権力監視機能を低下させ、看過できない。一方、複数の報道機関が存在する場合は、権力者との近さも含めてそれぞれが独自性を発揮し、相互批判を通じて健全性を維持できるという考え方も成り立つであろう。
最も危険なのは、報道各社が行政に忖度した報道を横並びで展開することだ。地方政治と地方有力紙の癒着は、全国紙や他の地方メディアが徹底追及して牽制すればよい。地方有力紙に対抗するメディアが地域から消滅し、メディアの相互監視機能が失われることだけは絶対に避けなければならない。
報道の多様性は、ジャーナリズムの生命線である。
地方紙に期待される役割


東京では全国紙や在京テレビ局と国家権力中枢の癒着が、地方紙と知事や市長との関係よりも深刻な問題として存在する。
先述した朝日新聞特別報道部は、政治部と首相官邸、経済部と財務省、社会部と警察・検察といった癒着構造から解き放たれ、記者クラブを離れてしがらみなく国家権力の疑惑に切り込めるところに最大の強みがあったが、その分、各部との関係は緊張して社内的に孤立する場面が多かった。現在では週刊文春など雑誌メディアが全国紙と国家権力の癒着に風穴を開ける役割を果たしているが、私は同様の役割を地方紙に期待したいと考えている。
私は1999年に朝日新聞政治部に着任し、官邸記者クラブや与党記者クラブに長く在籍した。有力地方紙はここに若干数の記者を常駐させている。それぞれの地方紙の将来を担う精鋭たちだ。
なかでも記憶に残っているのは、森喜朗氏が首相に就任してまもない2000年5月に「日本は天皇を中心とする神の国」と発言して批判を浴びた時、西日本新聞が放ったスクープだった。
西日本新聞の記者は官邸記者室のコピー機付近で、神の国発言をめぐって記者会見で厳しい追及を受けることが予想されていた森首相に対して「質問をはぐらかす言い方で切り抜けるしかありません」などと指南する内容の文書を拾った。内々に取材を進め、この「指南書」を書いたのはNHK記者であると確信して報じたのだ。
報道機関の政治部記者が首相に対し、記者会見の「切り抜け方」を指南していた――。政治家の番記者としてオフレコ取材を重ね、濃密な関係を作り上げていく全国紙の政治部記者たちからは決して生まれないスクープだった。官邸記者クラブに常駐しながら権力中枢とは一線を画している地方紙だからこそ、躊躇なく取材し、覚悟を決めて報道に踏み切ることができたと言えるだろう。
必要な「全体としての健全性」維持

どんな相手にも臆することなく、厳しく追及して闇を暴く。それがジャーナリズムの理想である。だが、いつ何時もその姿勢を貫く完璧な報道機関や記者は多くない。どんなに立派な記者も間違うことはあるし、怯むこともある。だからこそ、ジャ
ーナリズムは多様性を守り、誰かがどこかで追及し続けるという「全体としての健全性」を維持することが絶対に必要なのだ。
地方紙は知事や市長、県警に弱いかもしれないが、中央省庁には気兼ねなく切り込める。全国紙はその逆だ。闇を暴くのはいつも同じ報道機関や同じ記者である必要はない。それぞれがそれぞれの強みを発揮し、それぞれの弱みをカバーしあえばよい。全国紙と地方紙はそのような補完関係にあると私は思う。
地方紙は活動領域を地域テーマに限定させる必要はない。もっと広げればよい。ネット時代は世界に向けて発信することも可能だからだ。
朝日新聞政治部の後輩である南彰記者が今秋に退社し、沖縄に拠点を移して地方紙記者として活動するという。近年は新聞労連委員長を務め、SNSでも積極的に発信し、政治報道のあり方を批判する著書も上梓した。ところが、朝日新聞は「吉田調書」事件以降、記者の社外活動を厳しく制約するようになっている。南記者が新聞労連から政治部に復帰した後も風当たりは強く、まもなく人事異動になった。社内の管理統制を強める朝日新聞の将来に限界を感じ、新天地として沖縄を選んだのであろう。朝日新聞が地方紙から腕利き記者を引き抜いたのは今は昔。閉塞感が漂う全国紙から地方紙へ転身する新たな動きとして注目したい。