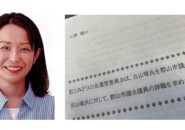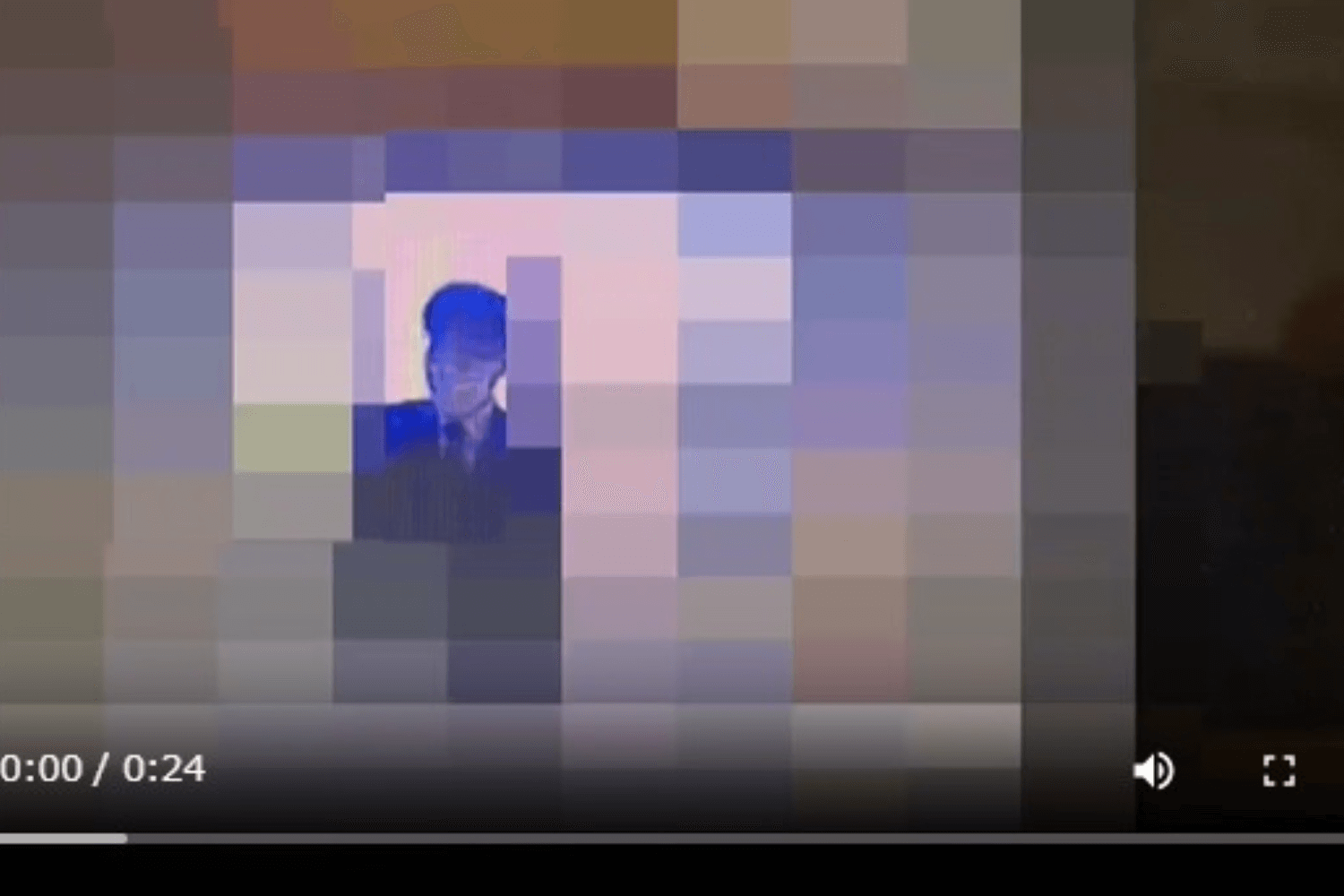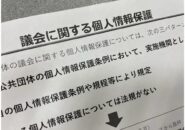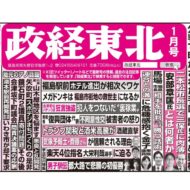郡山市は新年度(今年4月1日付)から、農林部と産業観光部を統合し「農商工部」とする。これにより、農商工連携による農業と産業の活性化を図る狙いがあるという。これに対し、JA福島さくらと安積疏水土地改良区は、連名で統合の延期と、農林部単独での存続を求める請願書を市議会に提出した。一部では「市と農業団体が対立」といった捉え方をする人もおり、それだけ波紋を広げたと言える。一方で、品川萬里市長は今期限りでの引退を表明しており、議論を呼んだ農商工部が本格的に動き出した直後には、市長は交代していることになる。
物議を醸したまま引退する品川市長

農林部と産業観光部の統合案が最初に公になったのは昨年11月22日の市長定例会見。そこで、品川市長が「農商工部」新設を含む、組織改編案を明かした。
これを受け、JA福島さくらと安積疏水土地改良区は市議会に請願書を提出した。その内容は次の通り。
(前略)市制施行100周年を迎えた郡山市は東北第2の都市として発展を続けておりますが、明治初期の安積平野開拓・安積疏水開削の国家プロジェクトの成功の前は大槻原を始め水利が悪く、各村の入会地になっておりました。
明治9(1876)年、明治天皇の東北巡幸の前に内務卿・大久保利通が視察に訪れ、その後、猪苗代湖疏水の開削と士族移住による安積平野開墾という大事業を、国家の一大プロジェクト第1号として展開する最初の条件が整えられ、進めることになりました。今から148年前の事業です。安積疏水工事は延べ85万人、3年の歳月を費やし、明治15年8月に完成しました。農作物の作付けに必要不可欠の水の提供は、安積平野を潤したばかりでなく、豊富な水量と落差を利用して沼上発電所が建設され、豊かで低廉な電気料は、製糸、紡績、製材、精米業をはじめとして多くの企業を育て、大正6年には東洋曹達(現・保土ヶ谷化学)、翌大正7年には日本化学が進出してくるなど、郡山市の工業化にとっても大きな役割を果たしました。
安積平野で生産されるコメ(コシヒカリ・ひとめぼれ)の生産量は質・量ともに全国の上位を占め、豊富な水とため池を利用した鯉の生産量は、市町村別で日本一を誇り、畜産業ではうねめ牛を、園芸作物では御前人参や佐助ナスなど14種類のブランド野菜の生産につなげるなど、安積疏水開削と安積平野の開拓は、100年以上の歴史の中で連綿と子孫に受け継がれてきておりました。それらの事業を展開する中で、大きな役割を果たしてきたのが郡山市農林部であります。
今回の組織改編は、「部」を含めた統廃合であり、前述した歴史を見ても農林部の統合は、歴史を正しく反映したものとは見られません。今回の組織改編案は、11月22日の市長記者会見で表明され、その後、新聞報道で知るところとなり、市民の理解を得られる時間があまりにも少ないために、実施日の延期と農林部の独立存続を求めます。
つきましては、以下の事項について請願いたします。
請願事項
1、2025(令和7)年4月1日付け行政組織改編案を延期すること。
2、農林部は統合しないで、独立の部として存続すること。
4月から農林部と産業観光部が統合され、「農商工部」となることに対して、延期と農林部の単独での存続を求める内容である。
同請願は昨年12月定例会で、総務財政常任委員会に付託され審議された。そこで出された請願への賛成・反対の意見はおおむね以下のようなもの。
議会でも統合案に賛否両論
賛成意見
○農林部を存続させ、小規模農家の支援をより強固にすべき。
○統合しなくても、部局横断することで対応可能。また、行政のスリム化、効率化の名目で職員・事業の縮小が懸念される。
○1人の部長が農業、商業、工業のすべてにおいて、責任を持って担うことは難しいと考えられる。農業を核として発展してきた東北地方で、農商工が1つの部になる例はなく、なぜ、本市のみがこのような飛躍したことをする必要があるのか。部の統合などにかかわる組織再編はもっと時間をかけて議論すべき。
反対意見
○農商工部の設置は国の示す流れに沿ったものであり、1次、2次、3次産業の一体的な取り組みによる農業のさらなる成長を促すことが必要。
○今回の組織改編はトップダウンではなく、ボトムアップで具現化したものであり、農商工連携についても必要なことと考える。
○本市の主要な農業団体から請願が出されたことを重く受け止めるべき。ただ、農林部でこれまで所管していた農道や林道関係の事務が建設構想部(※今回の組織改編で建設部から建設構想部に改称)へ、農村公園や森林公園関係の事務が都市構想部へ移管し、一括で管理するなど合理的な面もある。農商工部が発展的に連携することで、6次化が推進される。
○農林部の統合は庁内関係部局で30回以上にわたり検討を重ねたものであり、将来を考えると、農商工連携で農業をさらに活性化させていくことが必要。
常任委員会では賛成少数で不採択となり、本会議でも賛成15、反対22の反対多数で不採択となった。
同議会では関連議案「行政組織の改編に伴う関係条例の整備に関する条例」が出された。「部設置条例」に基づき、部の改編がある場合は、条例改正について議会の議決を求める必要があるため。同議案は、賛成21、反対16の賛成多数で可決された。
請願では、農林部と産業観光部の統合を延期し、農林部の単独で存続させるべきと考える議員が「賛成」になり、行政組織改編に伴う条例改正の議案では、統合すべきでないという議員が「反対」になる。そのため、文字化すると真逆になるが、この両者が一致することになる。ただ、前者は15対22、後者は16対21で、1人は請願と行政組織改編に伴う条例改正で違う立場をとっている。もっとも、今回の組織改編は農林部と産業観光部の統合だけでなく、部・課・係の改称や、所管事務の移管など多岐にわたるから、農林部の問題とは別に賛同できないところがあったということ。
いずれにしても、だいぶ割れていることが分かる。それだけ、議論が巻き起こった証拠でもある。
JA福島さくらの栁沼智代表理事専務によると、最初にその話を聞いたのは、組織改編案が発表された昨年11月22日の市長定例会見よりも前で、農林部長が来て話をされた。その時は、「そんな検討をしているんだ」という程度の認識で「それほど重く受け止めていなかった」(栁沼専務)という。
ところがその後、前述の定例会見で組織改編案が発表された。これを受け、請願書を提出したという流れになる。
「請願書にも書きましたが、郡山市は安積疏水開削によって、農業が先行して発展してきたまちです。そういった意味でも、もっと農の重要性を認識してほしいと思いますし、東北地方では中核市でも、どこも農林部は単独であります。市は6次化の推進を挙げていますが、農業は6次化だけではありませんから。(統合して)1人の部長が農業、商業、工業のすべてを見ていくのも大変だと思います。そういった観点から請願書を提出しましたが、決まった(不採択となり、統合に関する条例が議決された)以上は、受け入れるしかありません」(栁沼専務)
一方、安積疏水土地改良区は「請願書にあるように、郡山市は農で発展してきたまち。そうした中で、われわれの思いは伝えてきました。結果は受け入れており、今後、さらにどうこうというのは考えていません」とのことだった。
当初案の名称は「経済部」
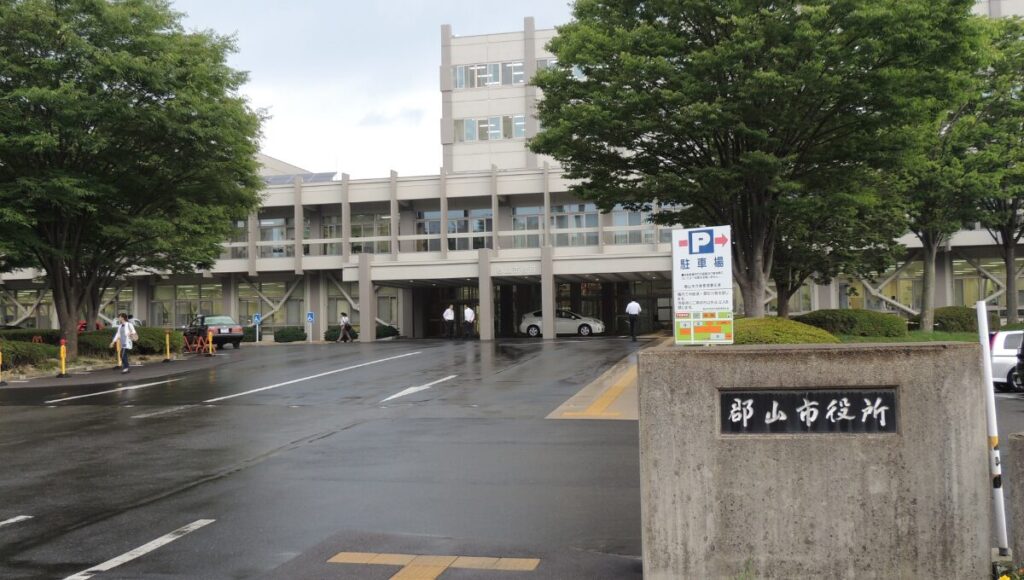
実は、市の当初案では農林部と産業観光部の統合後の名称は「経済部」だった。これに対し、JAや土地改良区から「『農』という文字がなくなるのは容認できない」旨の指摘があり、市が譲歩して「農商工部」となった格好だ。ただ、統合自体は譲らず、議会での議決を経て正式に決定した。
市総務部行政マネジメント課は次のように説明する。
「全国の中核市の事例を見ると、農林関係や商工関係の部は『経済部』や『産業部』としているところが多く、最初は『経済部』という案でした。ただ、農業団体との話し合いの中で『農』は入れてほしいとのことだったので、『農商工部』とすることにしました。統合しても、政策や体制は変わりません。それよりも、高齢化や遊休農地増加といった問題がある中、農家の所得向上のためにもほかの産業と一体的に取り組む必要があると思っています。6次化の推進や、国内外への売り込みなども一体的に進めていくことが可能です」
これまで、農林関係の課は本庁舎東側、産業観光関係の課は西庁舎に配置されていた。統合後は同じフロアに集まり、「普段から顔を合わせ、1人の部長のもと、課や係をまたいだ連携がスムーズになり、打ち合わせ等の効率化も図られます」(行政マネジメント課)という。
JA福島さくらと安積疏水土地改良区は市内でも大きな団体。どちらも「決定は受け入れる」との見解を示したが、本当に納得しているかという点では、必ずしもそうでない面もあろう。議会での審議を見ても賛否両論あった。
一方、品川市長は年始に新聞社を訪問した際、「4月に予定する『農商工部』の新設など組織改編の決意も述べた」(福島民友1月8日付)ほか、1月6日に開かれた市賀詞交歓会でも「これからは農商工や一次、二次、三次産業を分けて考えるのではなく、融合が必要になる時代。年始の農業新聞を読んで思いを新たにした」と挨拶した。
それだけ思い入れがあることがうかがえるが、当人は4月13日告示、20日投開票の市長選に立候補せず、今期限りでの退任を表明した。つまり、これだけ議論を呼んだ農商工部が本格的に動き出した直後には市長は交代しているのだ。
そのため、関係者からは「だったら、このタイミングで農林部と産業観光部の統合を進める必要はあったのか」、「引っ掻き回して、当人はいなくなるような状況」といった意見も聞かれたが、確かにそんな印象は残る。