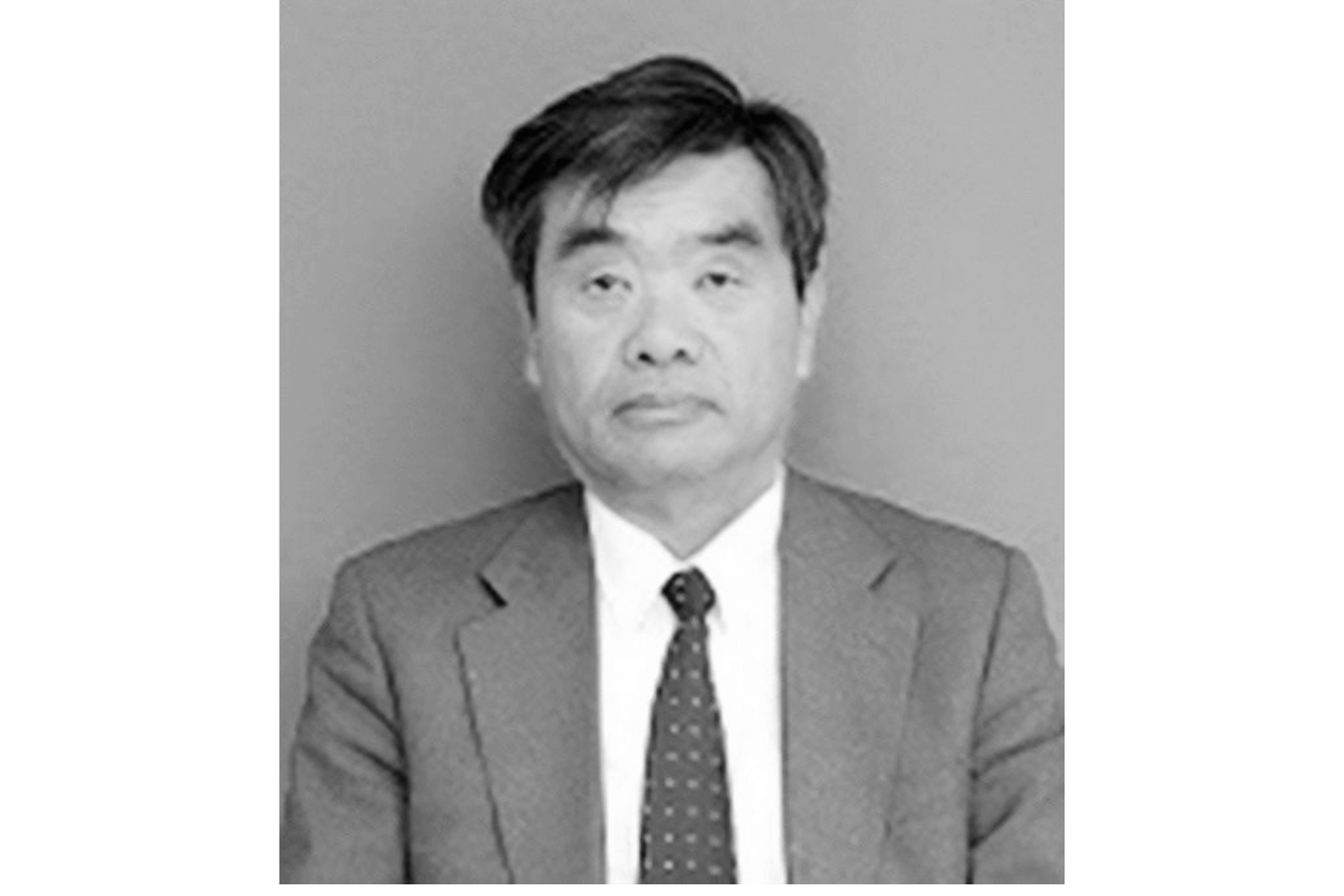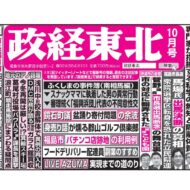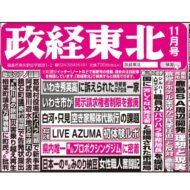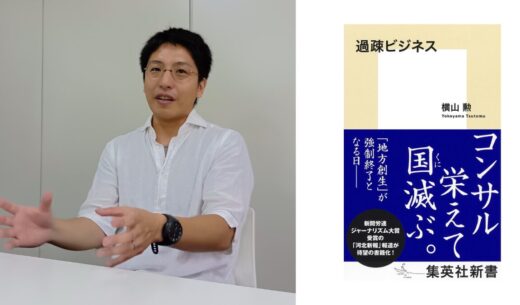白河市議会(定数24)の3月定例会で、2025年度一般会計当初予算案が19対4の賛成多数で可決された。この採決の際に行われた「反対討論」が話題を集めた。(志賀)
独自解釈で反対討論に圧力をかけた副市長

白河市の2025年度一般会計当初予算は総額333億円で、前年度から20億円(6・4%)増加した。昨年度に引き続き「少子化対策」、「未来への投資」、「居場所づくり」を予算編成の3本柱に据えた。
予算案の採決は3月17日に行われた。同市議会で予算案に反対するのは、例年「開かれた議会をめざす会」(日本共産党)の深谷弘市議(8期)1人だった。だが、今年は深谷市議に加え、同じく「開かれた議会をめざす会」に所属する大竹功一市議(7期)、さらに無所属の緑川摂生市議(4期)、大木絵理市議(2期)が反対に回った。
予算案への反対票がこれだけ増えた背景には、執行部が提出した農業法人参入促進事業費として旅費415万円が計上されていたことがある。
市農政課によると、オランダで6月に開かれる農業関連の見本市視察を想定したもの。オランダは農業大国で、環境制御技術など高度な技術の活用、気候に左右されない全天候型の安定栽培により収益を得るノウハウが確立しており、日本でもオランダ式の次世代型園芸拠点施設が全国に整備されている。
そのオランダで行われる最先端の見本市に足を運び、今後の施策の参考にするとともに、現地法人や日本から参加している農業法人との関係を構築する狙いがある。
というのも、同市では数年前から農業法人の誘致に取り組んでおり、昨年は総合環境制御コンピューターを用いてトマトを生産する「みちのく白河農園」(農産物生産・販売業の㈱サラダボウルの農業生産部門)が操業開始した。農業法人が複数進出して農業団地が整備されれば遊休農地解消にもつながるということで、市農政課では同農園に続く農業法人を誘致したい考えがあったのだ。
ところが3月7日、菅原修一市議(5期、躍進しらかわ)が予算に関する総括質疑で予算の詳細を確認したところ、旅費は鈴木和夫市長と市職員合わせて3人分ということが分かった。単純計算で一人当たり約138万円ということになる。
それを知って動いたのが前出・大木市議だった。同17日、各常任委員長の報告の後、予算案に関する討論で壇上に立った。

大木市議は菅原市議の総括質疑で詳細が分かったことを明かし、「事業調査をしたが、オランダへ行く必要性を見いだすことができませんでした」と述べた。その理由として、以下の4点を挙げた。
①オランダで行われる見本市と国内で行われる農業フェアの違いは何か。国内でも国際農業資材EXPOを筆頭に世界各国から数百社が集まる農業見本市が全国各地で行われている。オランダの企業関係者と会っても言葉の壁で話すのが難しそうだが、国内では相手に通訳がついているので、交渉がスムーズにできる。
②オランダ型農業は日本全国各地で展開されており、2012、13年ごろには食品関連企業と大学、研究機関が集積した「フードバレー」の取り組みを日本でも取り入れるべき、という議論が強まった。政府が進める戦略特区の一環で新潟市や北海道などでフードバレー構想が進められており、高知県の取り組みも注目されている。国内でもそのノウハウや法人を視察したり、誘致に向けた交渉は可能なはずだ。
③現地法人を誘致するとしても、誘致までの交渉にかかる予算や、誘致そのものにかかる予算は国内企業の何倍かかるのか。今後かかる予算も含め、議員は慎重に審議すべきだ。また、「未来への投資」ならば本市で農業を営んでいる方々や新規就農者のためにこの予算を活用するのが本来のあり方。農業を下支えする仕組みの強化や新機種の支援拡充、農家同士のコミュニティー形成などに重点を置くことを優先すべき。
④鈴木市長はこれまで様々な企業を本市に誘致してきた。その手腕は市長が持つ人望や人間性のたまもの。オランダへ行ったからといって熱意が伝わるとは限らない。市長の手腕があれば渡航せずとも優良な企業を誘致できると期待している。
反対討論の結びには「予算執行において1円たりとも税金を無駄にしないという立場でチェックしていく。それが私たち議員に課せられた仕事だと思います」と述べた。
反対討論めぐるゴタゴタ
なぜ例年の〝慣習〟を破って反対討論を行おうと考えたのか。議会終了後、大木市議に話を聞いたところ、市議に事前配布される予算の概要には、新規事業として農業法人参入促進事業費が掲載されていなかったという。菅原市議の総括質疑で初めて詳細を知ったが、すでに一般質問も終わっていたので議場でただすことができず、その後、農政課長と話をした。だが、わざわざオランダまで行く必要性は感じられなかった。
「物価上昇で家庭では節約して何とかやりくりしている中、市民感覚とずれていると感じる。農家も苦労しているのに、農林水産部の予算を3人分の旅費として使うことにも疑問を抱きました」(大木市議)
本誌ではこの間、首長や議員の視察・出張について冷ややかな視点で報じてきた。現場で先進的な技術を実際に見ることによって施策に生かすほか、情報発信・販路拡大などの狙いがあるとされるが、これらの目的が本当に達成されているかは微妙なところ。①そこまでして行きたいなら私的旅行として自分のお金で行ってはどうか、②そもそも自ら行く意味があるのか、③費用対効果が低い――というのが本誌の考えだ。
トップセールスに関しては、「首長が直接現地に足を運ぶ効果は大きい」という意見も聞かれるが、今回は「オランダの見本市で最先端技術に触れつつ、国内外の農業法人と知り合う」のが目的。それであれば、大木市議でなくとも「わざわざオランダに行く必要があるの?」と聞きたくなってしまう。
この問題をめぐっては、大木市議の反対討論の是非をめぐり舞台裏でゴタゴタがあったとも言われる。
複数の市議によると、農業法人参入促進事業費に疑問を抱いた大木市議はまず「修正動議を出そう」と考え、石名国光議長(6期)に動議案を提出した。ところが、議会の申し合わせ集の中に、「修正動議は開会日までに議長に提出すること」と定められていたことを指摘され、見送ることになったという。

そこで反対討論を行うことを決め、採決前に行われる質疑でも意見を述べることを議長に伝えた。だが、石名議長から「6月定例会の一般質問で聞く形でもいいのではないか。反対討論の必要はないだろう」と言われた。質疑に関しても「そもそも委員会の中で農業法人参入促進事業費に関する質疑がほとんどなかったので、委員長がそのことを質問されてもうまく答えられない可能性が高い」、「反対討論で十分目立つので、質疑までやる必要はないのではないか」と止められた。
大木市議は質疑を断念して反対討論で意見を述べる考えを固め、あらためて通告して、インスタグラムの自身のアカウントで周知した。そうしたところ、採決前日の同16日、井上賢二副市長から石名議長に申し入れがあった。
その内容は「一般質問や質疑でただすことなく討論で一方的に反対意見を表明するのは執行部として承服しかねる」、「議会は『言論の府』であり、言論での決定を重ねていくことが重要なのにその手続きがなされていない」、「議会側で協議してほしい」というものだった。
前述の通り、大木市議は一般質問が終わった後の総括質疑で農業法人参入促進事業費に疑問を抱き、質疑で意見を述べようとしたが、それも止められたので、反対討論をしようと考えた。ところが、井上副市長はそのことを指して「一方的に反対意見を表明するのは執行部として承服しかねる」と指摘するわけ。
申し入れを受け、大木市議は石名議長から再度考え直すよう説得され、周囲の市議も石名議長から大木市議の説得を依頼されたという。
採決当日、議会全員協議会が開かれ、井上副市長からの申し入れについて話し合われたが、「特にルールで定められているわけではないので、市からの申し入れを受けて討論を制限する必要はない」という見解でまとまり、「大木市議の反対討論を見合わせるべきではない」という結論に達した。
「執行部から議員の発言について注文が入るのは二元代表制の根幹を揺るがす出来事だと感じましたが、あまりに一方的に言われたのでつい『議会の慣習に従わない自分が悪いのかな』とも感じてしまったのも事実です」(大木市議)
副市長・議長の見解
ちなみに「一般質問や質疑でただすことなく討論で一方的に反対意見を表明する」ことについては、地方自治法や条例で禁じられているわけではない。井上副市長はどういう考えで申し入れを行ったのか。同市役所秘書広報課に事実確認の問い合わせをしたところ、以下のような回答が寄せられた。
「申し入れは事実です。本会議の議員と執行部、あるいは議員間の議論は、議案の内容や事業効果などについて、さまざまな見地から意見を交わし、民主的な合意形成を進め、民意を集約して団体意思を決定する重要なものと考えております。このため、一般質問や質疑を経ずに一方的に反対の意を表明することは、議論を経て決議する議会の役割にそぐわないことから、執行部の意見として議長に伝えたところです。申し入れの根拠となる法令等はありません。副市長が総務部長と協議し、議長に申し入れを行いました」
「今後、反対討論をする場合は、一般質問などで十分な議論を経たうえで行っていただきたいと考えております。執行部としては、引き続き議会と真摯な議論を交わし、住民福祉の向上に努めてまいります」
石名議長にも考えを聞きたいと思い、取材の申し込みと取材日程の調整を議会事務局に依頼したところ、同事務局を通じて「副市長から申し入れがあったのは事実だが、反対討論は行われたので特に問題はなかったと考えている。私が止めたという事実もないです」とコメントが寄せられた。ただ前述の通り、大木市議は石名議長から反対討論を考え直すよう何度も説得されたと話しており、両者の主張は根本から食い違っている。どちらの言い分が正しいのか判然としないが、石名議長は一部議員の信頼を失っている状況だ。
執行部からの異例の申し入れはどのように受け止めるべきなのか。地方自治総合研究所特任研究員の今井照氏にコメントを求めたところ、次のように述べた。
「議会のルールは憲法や地方自治法に反しない限り、当該議会で策定することができます。白河市議会にそのようなルールがないとすれば(一般質問や質疑でただすことなく討論で一方的に反対意見を表明するのは)ルール違反にはなりません」
「反対討論(賛成討論)の意義については副市長のご指摘のとおりです。しかし、市長などの執行機関を相手とする一般質問や質疑の意義については誤解があると思われます。そもそも議会は議員間で討論をすることを原則とし、市長などの出席は『議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない』(自治法121条)とされていて、必須ではありません。まして『一般質問や質疑でただすことなく討論で一方的に反対意見を表明するのは執行部として承服しかねる』という申し入れがあったとすれば、二元的代表制の原理を理解されていないのではないかと思われます」
井上副市長は独自の解釈で大木市議の反対討論を制限しようとしたが、そもそも議会にそうした申し入れを行うこと自体、二元代表制を理解していないのではないか、と。
本誌2018年6月号「議会を陰で操る⁉鈴木白河市長」という記事では、議長選をめぐる対立になぜか鈴木市長も参戦し、「なぜ○○を応援しているのか」、「××を応援してくれ」と複数市議に連絡していたことを報じた。鈴木市長はその後も議員に意見を述べることがあるようだ。そうした振る舞いを井上副市長も参考にしたのかもしれないが、今井氏のコメントにあるように、執行部の対応としては疑問視されるということを知っておくべきだろう。

さて、農業法人参入促進事業費に関しての予算は可決されたものの、市によると、オランダの見本市に行くかどうかは本決まりではないという。議会対応の在り方と併せてウオッチしていく必要があろう。