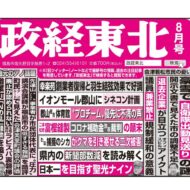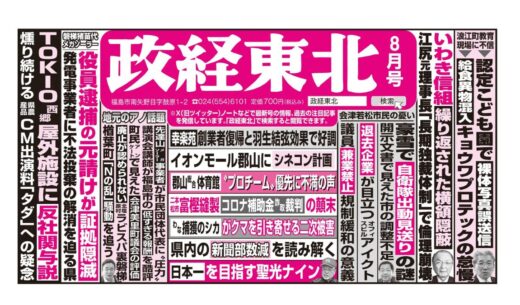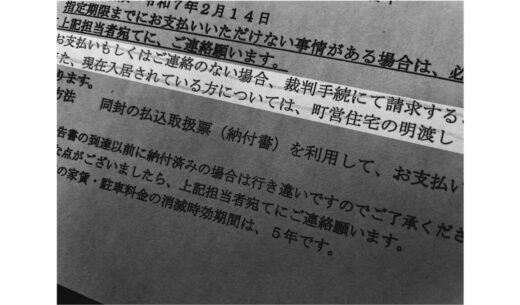二本松市の安達太良山登山の際に多くの登山客が利用する山小屋「くろがね小屋」。建て替え工事のため、2023年3月31日で営業を終了し、2028年度の完成・再開が待たれているが、再建費用は概算で27億円かかる見通し。巨費を投じて再建する必要があるのか。
登山者は待望も問われる費用対効果

くろがね小屋は安達太良山山頂の北西にある沼ノ平火口から東に約1・4㌔離れた山麓に位置する。県開発公社が1964(昭和39)年に建設し、1969(昭和44)年、県に譲渡された。管理業務は公益財団法人県観光物産交流協会に委託されてきた。延べ床面積362平方㍍、木造2階建てRC造地下1階。客室9室、定員50人。
源泉口近くの温泉をかけ流しで楽しめ、山小屋独特の雰囲気も味わえることから、休憩する登山客はもちろん、観光での宿泊客も多かった。県観光物産交流協会によると、2022年度の宿泊者は約4000人、温泉入浴など休憩での利用者は約1000人いたという(トイレ利用のみの人はカウントしていない)。
安達太良山火山ハザードマップでは、気象庁から火口周辺規制(レベル2)が発表された場合の一次避難先としても位置づけられ、ヘルメット防塵マスクや防災メガホンなどが備えられている。
観光と防災、両面の役割を担う公設の山小屋というわけだが、築60年近く経ち、豪雪・強風・強酸性の環境もあって老朽化が進み、雨漏りや建物の腐食が目立っていた。
また、トイレでは浸透式による処理を行い、雑排水も垂れ流しにしてきたが、周辺環境に配慮したトイレ改修も求められていた。
さらには2014年の御嶽山噴火で死者58人、行方不明者5人の被害が出たのを受け、内閣府が示した「活火山における退避壕等の充実に向けた手引き」で「火山噴石などに耐えられる屋根補強工事などが望ましい」とされ、対応を迫られていた。こうした中で、新たに建て替え工事が行われることになったわけ。
新しいくろがね小屋は木造2階建てRC造地下1階。噴火発生時に登山客が避難できるシェルター(最大約80人収容)を地下1階に設ける。浄化槽式の水洗トイレも導入。建物自体は従来と同じ規模となる見通し。
建て替え工事がスタートするのに合わせて2023年3月末で営業休止し、今年度は本体工事に先駆けて電源の引き込みや登山道の補修工事が行われていた。
だが、工事箇所に岩盤が見つかり、工事内容を変更。それに伴い当初は2025(令和7)年度完成予定だった整備スケジュールがずれ込み、来年度解体工事に着手、2028(令和10)年度完成の予定だ。
驚くのはその建て替え費用だ。県によると、建て替え工事の概算金額は建築工事14~20億、電気設備工事1億2000万~1億8000万円、暖冷房衛生設備工事1億2000万~1億8000万円。総額で最大27億4000万円に上るのだ。
新聞報道によると、当初計画では総額10億円程度を想定していたというから3倍近くに膨れ上がったことになる。
事業費が上振れした理由

なぜここまで事業費が上振れしたのか。県観光交流課は「山小屋の建設は何かと費用がかさむのです」と説明する。
「折からの建築資材価格高騰に加え、建設作業員の週休二日制などの影響で工事に時間がかかるようになり、人件費も上がっています。山の中の工事は建築資材をヘリコプターで運ぶなど、輸送に手間がかるし、冬季間は工事を一旦中断せざるを得ないので長期間にわたります」(県観光交流課担当者)
そもそもそれだけの金額をかけるほど宿泊需要が高いとは思えない。安達太良山は初心者でも登山を楽しめる山として知られており、同山周回コースは4時間30分程度。十分日帰り可能だ。
だが、管理業務を委託されていた県観光物産交流協会は「くろがね小屋に宿泊する人は多かった」と話す。
「金曜の夜にくろがね小屋に泊まって翌朝体調や天候を見ながら登山に向かう人、くろがね小屋に一泊しながら2日がかりでゆっくり登山を楽しむ人など、さまざまな登山のスタイルがあります。冬はオフシーズンですが、雪山登山の初心者には『比較的難易度が低くて山小屋もあるので安全に登山できる』と人気で、11月から翌年3月の週末は予約が取れない状況が続いていました。体調不良の登山客がいる場合は消防と連携して受け入れるなど、スタッフが常住している山小屋だからこそ対応できた面もある。登山客の命を預かる場所でもあるので、安全が確保できる建物は必要だと思います」(県観光物産交流協会担当者)
建築設計・施工、森林開発コンサルティングなどを手掛けるADX(二本松市)の代表取締役で、安達太良山に年間15~20回登っているという安齋好太郎氏にコメントを求めたところ、「面積や設備が分からないので建築費用が妥当かどうか分からないが、費用に見合わない建物であれば問題だと思う」としたうえで次のように話した。
「当社は標高が高い場所での建築も多数手掛けていますが、山小屋の工事は条件が厳しいのは事実で、標高1400㍍のくろがね小屋の工事をやりたい会社は少ないかもしれません。ただ、山小屋は大きなポテンシャルを秘めている。海外では快適な寝床やトイレを備えた山小屋があることが、その山にとって一つのステイタスになっている。きちんとした山小屋を整備することで気軽に登山を楽しめるようになり、多くの人が訪れるようになるし、インバウンド需要も増えるかもしれません」
登山客からは工事完成・営業再開を待ち望む声が多く聞こえてくる。11月上旬、記者が実際に登山して感じたのは、トイレ・休憩施設がない影響だ。くろがね小屋近くには個室の携帯トイレ用ブースが設置されていたが、肝心の携帯トイレを持ってない人が多く、やむなく脇道で用を足している男性登山客を見かけた。安達太良山は磐梯朝日国立公園内にあり、自然環境を損ねる排泄物を置いていくことはマナー違反だ。
県の調査によると、2023年の安達太良山の入り込み数は約9万7000人。首都圏からも日帰りで気軽に登山できることから、人気が高い。くろがね小屋が整備されればさらなる集客増が期待できるため、観光業界も建て替えを待ち望む。
一方で県内の登山愛好家からは「30億円もかけて山小屋を造るとは信じられない」という冷ややかな声も聞かれた。トイレやシェルターのみ整備するのであれば、もっと金額を抑えられたのではないか。新くろがね小屋は本当にその金額に見合った施設となるのか。ノスタルジーに浸るだけでなく、冷静にウオッチングしていく必要があるだろう。