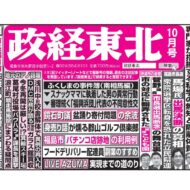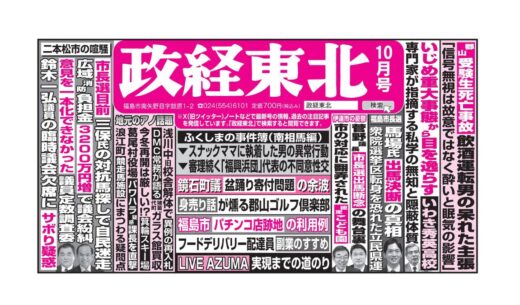巨額の不正融資問題を受けて出直しを図るいわき信用組合(いわき市小名浜)。同信組で起きた不正は三つあり、マスコミが注目したのは本誌先月号でも取り上げた大口融資先への迂回・無断借名融資だが、残る二つも正常な意識が働いていれば起こり得ない不正だったことが分かっている。不正を不正と思わない組織風土はなぜ醸成されたのか。さらに、不正を調査した第三者委員会が提言したのは「外部からのトップ招聘」だったが、なぜプロパーが新理事長に就いたのか、考えてみたい。(佐藤仁)
江尻元理事長の「異常な決断」が見過ごされたワケ
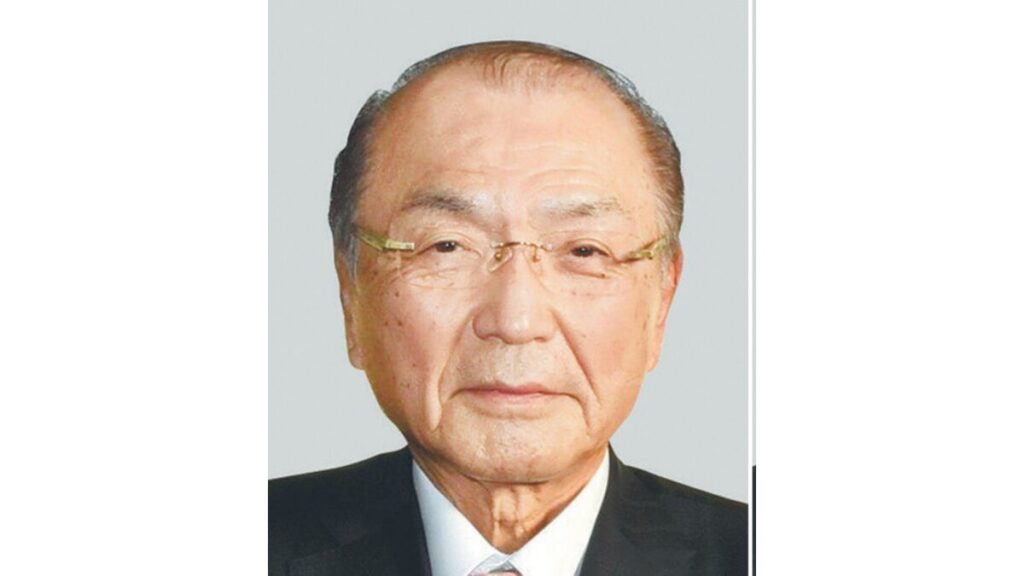

いわき信組が、いわき市内で土木建築業、不動産業、温泉施設運営などを手掛ける「鈴建グループ」に20年間で少なくとも247億円を不正融資した経緯は本誌先月号「新聞・テレビが報じない いわき信組巨額不正融資問題の根幹」という記事で詳報した。
今回取り上げるのは、この不正融資以外の二つの不正だ。いわき信組から不正の調査を依頼された第三者委員会が、5月30日に公表した調査報告書の中で詳細を明らかにしており、先月号では次のようにだけ紹介している。
▽2010年2月から14年8月にかけて、元職員Aが計1億9582万円を横領したが、当時の幹部は事実を把握していたにもかかわらず隠蔽した。
▽2009年6月、元職員Bが帯封のされた100万円の束から20万円を抜き取り、発覚後すぐに弁償したが、当時の幹部は事実を把握していたにもかかわらず隠蔽した。
職員の横領はどの金融機関でも起こり得ることで、それ自体に珍しさはない。問題は、横領を隠蔽するため、当時の幹部が異常な決断を繰り返していたことだ。
以下、二つの横領の詳細を第三者委員会の調査報告書から見ていく。
元職員Aは、遅くとも2009年頃からギャンブルに大きな金額を賭けるようになった。当初は自己資金を使っていたが、次第に「もっと大きな金額を賭けたい」「負けた分を取り返したい」という気持ちが強くなり、いわき信組から職員向けの融資を受ける。だが、負けが込んで手持ちの資金は底をつく。
この頃、Aは役員や上司から、不良債権を回収するための架空融資が存在し、その管理も業務の一つになるという話を聞かされる。鈴建グループへの無断借名融資のことだ。何らかのきっかけで無断借名融資の方法を知ったAは模倣することを思い付く。当時勤務していた支店で、預金担保付手形貸付を利用した横領をするようになった。
第三者委員会の調査によると、Aは2011年12月から13年5月にかけて、発覚の危険が低そうな13人の顧客の口座を勝手に使い、計22件、約1億2573万円の無断借名融資(横領)をしていたことが判明している。
横領の手口はこれだけではなく、総合口座貸越を利用した横領や定期預金の解約・着服にも手を染めた。横領の総額は約1億4000万円に上った。
これらが発覚したきっかけは、支店長がAの口座やAが横領に用いていた口座に不自然な融資の実行があるのを見つけたことだった。Aを問い詰めると、横領を認めた。
支店長から報告を受けた江尻次郎理事長(当時)は他の役員らと対応を協議した。その結果、横領による損失を穴埋めし、隠蔽する方針が決定。併せてAを処分せず、同じ支店に勤務させ続けることも決まった。
江尻理事長が前代未聞の判断を下した背景には、①2012年1月に全信組連を通じて200億円の資本増強支援を受けた直後に多額の横領事件を報告するわけにはいかない、②Aを処分すれば、鈴建グループへの不正融資も明るみに出るリスクがある――という事情があった。
とはいえ、横領による損失は放置できない。第三者委員会の調査に、いわき信組は「江尻理事長ら当時の役員が家族・親族から用立てたり、自宅金庫に保管していた自己資金計1億4000万円で穴埋めした」と説明した。しかし、資金が組合側に渡ったことを裏付ける証拠はなく、一方で、鈴建グループへの無断借名融資から捻出されたとみられる形跡があったことから、同委員会は「自己資金の提供を事実と認定することはできない」と結論付けている。
何の処分も科されず、その後も同じ支店で勤務を続けたAだったが、驚いたことに、1回目の横領が発覚してからわずか1カ月で再び横領に手を染める。
画餅に終わった回収作戦

手口は1回目とほぼ同じだが、ほかにも会社名義の口座を用いて横領したり、Aが本部への異動が決定すると、後任にバレるのを避けるため勘定を不正操作するなどしていた。2回目の横領は2013年6月から14年8月にかけて行われ、計9000万~1億円に上った。1回目の横領と合算すると2億3000万円以上になるが、第三者委員会は最終的にAが横領した総額は少なくとも約1億9600万円としている。
ちなみに発覚のきっかけは、本部の課長が、Aが勤務する支店の諸勘定に異常な取引があるのを見つけたことだった。
二度目の不正に対し、役員の一部からは「Aに処分を科すべき」という意見も出た。しかし、江尻理事長の鶴の一声で見送られ、休職等の措置にとどまった。再度、損失を穴埋めして隠蔽する方針も決まった。
1回目の損失の穴埋めは鈴建グループへの無断借名融資が充てられたが、2回目の損失の穴埋めはどうしたのか。いわき信組は第三者委員会の調査に、事務管理部が管理する手持現金を充てたと説明したが、明確な証拠はなかった。ただ、同委員会では総合的に判断し「手持現金が損失の穴埋めに使われたと考えるのが合理的」としている。
Aは、横領に利用した個人ローンの一部は返済していたものの、大半は返済せず、いわき信組が返済を求めることもなかった。返済を求めないだけでも十分異様だが、江尻理事長はさらに異様な方法でAに返済をさせようとする。Aに不動産会社を設立させ、その収益から返済させることを決めたのである。
こうして設立されたのが、Aを取締役とする不動産会社αだ。驚くのは、会社設立に必要な登記手続きや資本金1000万円の工面までいわき信組が行ったことだ。ここまで来ると、もはや異様を通り越して異常と言うほかない。
α社とAの名義で開設したいわき信組の通帳と届出印は同信組が管理した。α社が収益を得るために所有するアパート(3棟)も同信組が物件を選定した。アパートの購入資金計7700万円も融資した。
アパート経営は順調に滑り出し、横領分の返済も始まった。しかし間もなくして、Aに「何らかの犯罪行為」があったことが判明。いわき信組は「Aに不動産事業をさせるのは危険」と考え、アパート3棟を売却し、融資金を全額回収した。前代未聞の横領金回収作戦は結局、画餅に終わった。
Aにまつわる江尻理事長の数々の決断は、繰り返しになるが異様を通り越して異常と言うほかない。その背景について、第三者委員会の中には「Aと江尻理事長の人的関係が手心を加えた理由の一つではないか」という意見もあったほどだ(最終的には「過剰な手心を加えるまでの深い関係とまでは評価できない」という結論に落ち着いている)。
ただ、第三者委員会の調査では①Aの退職前後に前記・Aの「犯罪行為」にまつわる弁償金をいわき信組が立て替えた可能性がある、②その後、同信組からAの関係者名義に融資し、その融資金から立て替え分を回収した可能性がある――という証言が複数あった。同委員会は「客観的資料を精査できず真偽不明」とするが、事実なら異常さを物語るには十分すぎるエピソードだ。
もう一つの不正、元職員Bによる横領はAに比べれば極めて軽微だったが、江尻理事長が下した決断は相変わらず異常だった。
Bは2009年6月、勤務していた支店の金庫で100万円の帯封現金から20万円を抜き取った。近く予定されていた研修の遊興費として手元に現金を持っておきたかった、というのが動機だ。
後日、別の職員が金庫内を確認すると、100万円の帯封現金の高さが一つだけ低いものが見つかった。事情を聴かれたBは20万円を抜き取ったことを認めた。「すぐに弁償する」と申し入れ、実妹に20万円を用立ててもらい、支店に持参した。
いわき信組はBへの告訴状や被害届の提出を見送り、監督官庁に不祥事件等届出書も提出しなかった。一方で、Bの退職届を受理し、規定通り退職金を支給した。Bへの処分を見送ったのはAの横領の時と同様、Bの横領が公になれば鈴建グループへの不正融資も発覚する危険があると、江尻理事長が恐れたためとみられる。
その後、江尻理事長は同じ支店の職員や横領を知る職員に口外しないよう直接指示した。さらにBは依願退職の数カ月後、不正融資先の鈴建グループの1社で、なこそ温泉関の湯を運営する勿来綜合開発に再就職したが、そこには江尻理事長の紹介があったことも確認された(Bが再就職した時点で、勿来綜合開発はオーナーだった鈴木仁弼氏から同社役員に株式が渡り、同グループから離れている。その経緯は先月号を参照されたい)。
口止めという典型的な隠蔽だけでも聞いて呆れるが、横領した人にわざわざ再就職の世話までしているのだから「盗人に追い銭」とはまさにこのことだ。
教祖に逆らえない信者
AとBの問題も鈴建グループの問題も、共通するのは不正を不正で隠そうとした点にある。組合員を置き去りにし、組織ぐるみで不正にいそしむ姿は地域経済を預かる信用組合の体を成していない。それを主導したのは江尻理事長だが、もしトップの異常な決断に待ったをかける役員がいたら、いわき信組はここまで道を踏み外さなかったのかもしれない。だが実態は、江尻理事長には絶対に逆らえない空気が蔓延していた。
それを象徴する言葉を第三者委員会の調査報告書から拾っていくと、
▽江尻理事長が人事権を掌握していたため、不正を指摘したり拒否することを躊躇せざるを得ない環境にあった。
▽職員へのアンケート結果に「理事長には逆らえない」「理事長に嫌われると出世できない」「理事長の決定は絶対」「上司からやれと言われれば不正と分かっていても断れない」「自分の生活や家族のためには従うしかない」「上司が白と言ったら、黒いものも白と言わなければならない」という趣旨の回答があった。
▽業務命令で不正行為への関与を強いられても、拒否したり告発するといった極めて常識的な判断を多数の役職員ができないくらい上意下達が徹底されていた。
▽「組合を守るためには仕方がない」「いわきの中小企業のために組合が潰れるわけにはいかない」という大義名分のもと、不正を正当化することで多少の不正はやむを得ないと思わせる風土をつくり上げていた。
▽役職員に「組合が潰れて失職すること」と「不正を行うこと」を天秤にかけさせ、不正を強いるやり方は一種の悪質なパワハラだ。
第三者委員会は調査報告書で、こうした状況を「職員の不健全で歪められた真面目さ」と評したが、筆者の感想は違う。さながら役職員は絶対的な教祖(江尻理事長)に逆らえない信者であり、教祖が率いるいわき信組は「歪んだ新興宗教」と化していたのではないか。
その感想を一層強くしたのが、5月30日に開かれたいわき信組の会見だ。当時の本多洋八理事長は、筆者を含む大勢の記者から江尻氏の人物像や責任の所在を何度も質問されたが、江尻氏を悪く言うことは一切なかった。それどころか「私を(理事長に)引き上げてくれた」「上司と部下の関係は簡単に整理できるものではない」と述べたのだ。
普通ならトップとして厳しく叱責する場面だが、この期に及んで感謝や尊敬を思わせる言葉を口にする姿は「教祖のマインドコントロールが解けていない信者」にしか見えなかった。第三者委員会は、役職員が調査に非協力的だったと厳しく批判しているが、彼らがマインドコントロールから目覚めていなかったとすれば、組織や江尻氏にとって不都合な証言をしないのも当然だ。
不正を不正と思わない組織風土はどうすれば変えられるのか。第三者委員会は次のように提言している。
《これまで不祥事案に一定の関与をしてきた役員は一掃して新たな経営体制を構築すべきであるが、その具体的な人選にあたっては、特に当組合としての意思決定をする上で、金融機関としてのコンプライアンスを徹底し合理的判断を行える人材を登用する必要がある。そのため、外部から金融業務についての専門的知見を有する人材を常勤者として招き入れて、業務運営の適正化を図ることも有効である》(調査報告書201ページより抜粋)
合併に向けた地ならし⁉
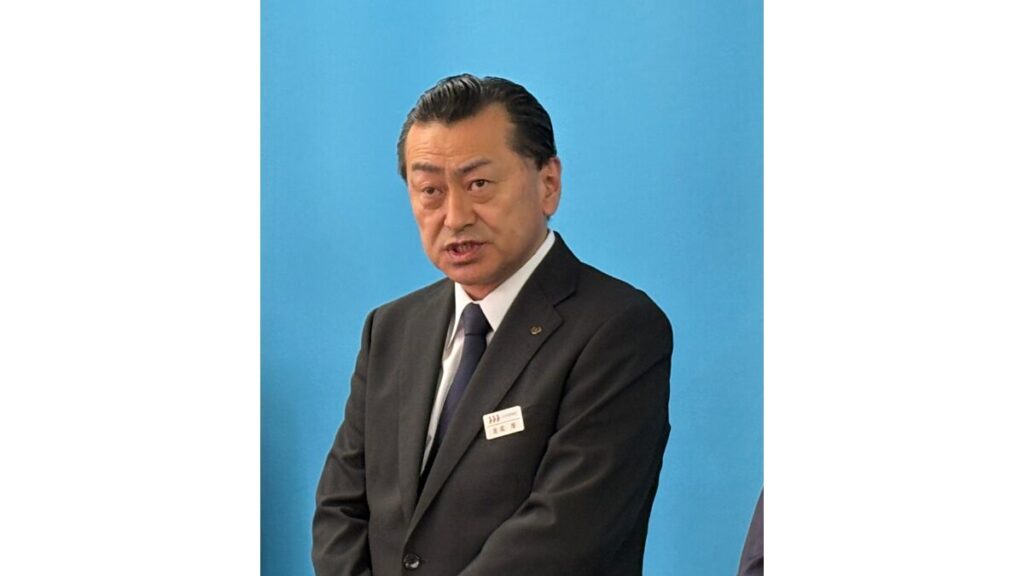
外部からトップを招聘すべきと提言しているわけだが、前出・本多氏の後任として、6月13日に開かれた総代会・理事会で新理事長に選出されたのは経理部長兼総合企画部副部長の金成茂氏(57)だった。
金成氏は同30日に開いた会見で、信頼回復と組織風土の改善に取り組む決意を示す一方、自身も含めた新経営陣は「不正融資には一切関わっていない」と明言した。しかし、直接的には関わっていなかったとしてもウワサくらいは耳にしたはずで、不正の存在を知らなかったわけではあるまい。全く知らなかったことを示す証拠でもあれば話は別だが、そんな証拠があるとは思えない。
プロパーが新理事長に就けば、疑いの目が向けられるのは誰が考えても分かることだ。「ウワサを聞いた程度なら問題ない」と言う人もいるかもしれないが、深刻な不正から出直すからこそ、トップには「まっさらな人」を就けるべきだったのではないか。そのことを、いわき信組が理解していなかったのは残念だ(誤解されては困るが、金成氏個人をダメと批判しているのではなく、プロパーでは誰が就いても疑われてしまうことを言いたいのだ)。
一応、第三者委員会の提言に沿って外部人材を招聘しているが、全国信用協同組合連合会から森貞隆之氏を常勤の常務理事(コンプライアンス統括部担当)に据えただけ。外部からはほかに公認会計士・税理士の丹野勇雄氏と社会保険労務士の奥瀬円氏が非常勤理事に就いたが、外部人材の割合が常勤理事5人中1人、非常勤理事4人中2人では、経営陣の刷新には程遠い。
今回の役員人事は東北財務局の意向が反映され、いわき信組の意思は二の次だったという話が漏れ伝わっている。批判を承知でプロパーを登用したのは、外部人材で経営再建を目指すのではなく、同財務局が、同信組をよく知る金成氏に「他の金融機関との合併に向けた地ならし」を任せたかったのではないかと深読みする地元経済人もいる。同信組のことを知らない外部人材では、確かに地ならしは難しい。
福島県は金融機関の数が多く、他県に比べて合併が進んでいないと言われる。「プロパーの登用は合併への布石」という見方は、あながち間違いとは言い切れまい。