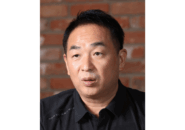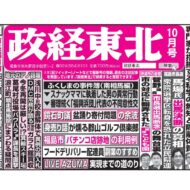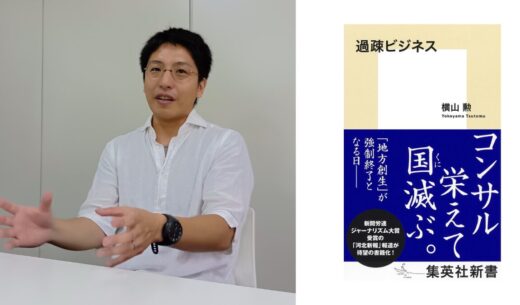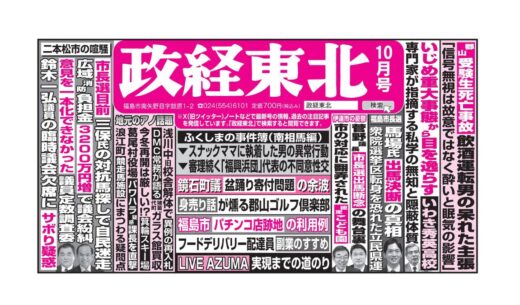はせがわ・こういち 1962年生まれ。法政大卒。堀江工業(いわき市)社長。2019年5月に県建設業協会会長に就き、現在3期目。
建設業界は、自然災害などの際に直ちに出動し、公共インフラの復旧などの役割を担う。一方で、人手不足や従事者の高齢化といった課題を抱えつつ、昨年4月からは、建設業界にも時間外労働の上限規制が適用され、「働き方改革」への対応も求められている。福島県建設業協会の長谷川浩一会長に業界の現状や課題への対応などについて話を聞いた。
――5月に開催された第14回定時総会で会長に再任されました。
「過去2年は、コロナ禍からの回復に伴い、国内の経済活動が活発化し、日常生活を取り戻してきましたが、ウクライナ紛争などの複合的な影響による建設資材などの物価高騰に加え、人件費の高騰など、建設業界においても大変厳しい経営環境が続いています。そのような中、担い手不足と災害や公共インフラの維持管理への対応が喫緊の課題と考えています。担い手確保に向けた働き方改革や処遇改善を推進するとともに、頻発、激甚化する自然災害に対応するため、会員間の連携強化が必要です。今年2月には、会津地域を中心とした記録的な豪雪に伴い、福島県と締結している『災害時における応急対策業務の広域的な支援に関する協定』に基づき、初めて出動しました。中通りの会員に支援をお願いし、県民の安全・安心の確保に努めることができました。こうした経験を踏まえ大規模災害に備えた応援体制の整備に努めていきたいと思います。
加えて、全国的に公共インフラの老朽化が進んでおり、これらを適切に維持・管理する体制が確保されなければ、住民生活はもちろん、経済活動にも大きな影響を及ぼすと懸念しています。地域を守る危機管理産業として『地域建設業』の重要性を訴え、建設業に対する関心を高めながら、これらの課題に対応していきたいと考えています」
――昨年の県内の建設業者の倒産件数は31件で、令和以降最多を記録しています。
「協会員に限れば倒産はありませんが、退会企業は数社ありました。退会理由は後継者不在による廃業や技術者不足による事業縮小など会社都合によるものです。経営者の高齢化や後継者不在、技術者などの担い手の確保など『事業承継』も大きな課題であると考えています。
一方で、建設業者の倒産原因は、県内の東日本大震災や台風災害などの復旧・復興事業収束に伴う、全体的な事業量の減少が大きな理由ではないかと思われます。そこに急激な物価高騰、人件費の高騰、担い手の確保などの問題を起因とした利益率の悪化も大きな要因となっているのではないかと考えます。
協会では、会員企業の経営力、技術力の向上に向けた研修を開催するなど企業力の強化を支援しています。また、入札制度においては、県内各地区で長年にわたり地域の維持・発展に貢献し、技術力、経営力を兼ね備えてきた企業に対する適正な評価を発注者に求めています」
――協会では「給与」「休暇」、「希望」、「かっこいい」の「新4K」を推進されていますが、現状をお聞かせください。
「『給与』については、公共工事設計労務単価が13年連続で引き上げられ、技能者の賃金上昇が続いています。加えて、公共工事の低入札調査基準が継続して引き上げられてきたことなどにより、建設業の営業利益率も改善され、従業員の賃上げも続いてきました。しかし、昨今の事業量の減少による競争の激化や施工単価の急激な上昇に伴い、利益率が低下傾向にあることから、物価上昇に見合った公共工事の施工単価の引き上げなど、これまでの好循環を止めない施策が求められます。
『休暇』については、令和6年度より建設業においても時間外労働規制が適用され、週休2日の導入と併せて働き方改革を推進しています。協会では、会員の要望等を踏まえ、年間休日モデルカレンダーを作成したほか、県内市町村に対する週休2日導入の要望、建築工事を中心とした民間工事の発注者である経営者団体に対しては、福島労働局などと連携し理解と協力をお願いしたところです。引き続き関係機関には週休2日制が導入しやすい環境の整備を訴えるとともに、会員各社においても週休2日制が浸透されるように取り組みを継続し、有給、育児などの休暇の取得推進を図ることで、労働者が働きやすい環境を整え、ワークライフバランスの実現を推進していきたいと考えています。
『希望』については、将来の展望やスキルアップへの道筋を明確にし、若手の定着を図る必要があります。協会では建設キャリアアップシステムへの登録と導入を推進しており、会員の80%を超える企業が登録している状況です。現場での運用を広め、技能者、技術者の適正な評価を推進するとともに、若手社員が希望を持って働くことができるよう、給料、休暇等の水準の底上げを支援し、定年まで安心して働くことができる業界を目指していきたいと考えています。
『かっこいい』については、建設業の正しい現状を発信し、魅力を伝えるため、広報活動を積極的に展開しています。令和6年度より『担い手確保推進広報事業』として、『道の駅ふくしま』でのビデオ放映、パネル展示を実施したほか、重機試乗や仕事体験などが楽しめる広報イベント『ふくしま・けんせつDAY』を開催し、多くの県民の来場をいただいたところです。そのほかにも、建設現場見学会やインターンシップ事業では、建設DXの導入による省力化、効率化が進む現場の実態に触れてもらうなど、学生などに業界に対するポジティブなイメージを持ってもらう取り組みも継続しています」
――建設業は「地域の守り手」の役割を担いますが、県内での具体的な災害対策や地域貢献について、協会として今後どのような役割を果たしていきたいとお考えですか。
「協会と県土木部では令和4年5月に『災害時における応急対策業務の広域的な支援に関する協定』を締結しており、今年2月の会津豪雪で初めて応援要請があったほか、5月には、いわき市の国道399号での土砂崩れ現場への遠隔操作のバックホウを派遣するなど、今後は広域的な支援の機会が増えてくるのではないかと考えています。ほかにも鳥インフルエンザ等の防疫業務など活動が多岐に渡ることから、支部・会員間の協力体制の強化を図り、危機管理産業としての役割を果たしていきたいと思っています。
地域貢献に関しては、発災時の災害対応のほか、防災・減災、国土強靭化への対応、公共インフラの老朽化対策など大きな役割を果たしていると思います。県内それぞれの地域において、建設業が持続的に地域経済、住民生活を支えることで、地域の安全を確保していくことが重要であると考えています」