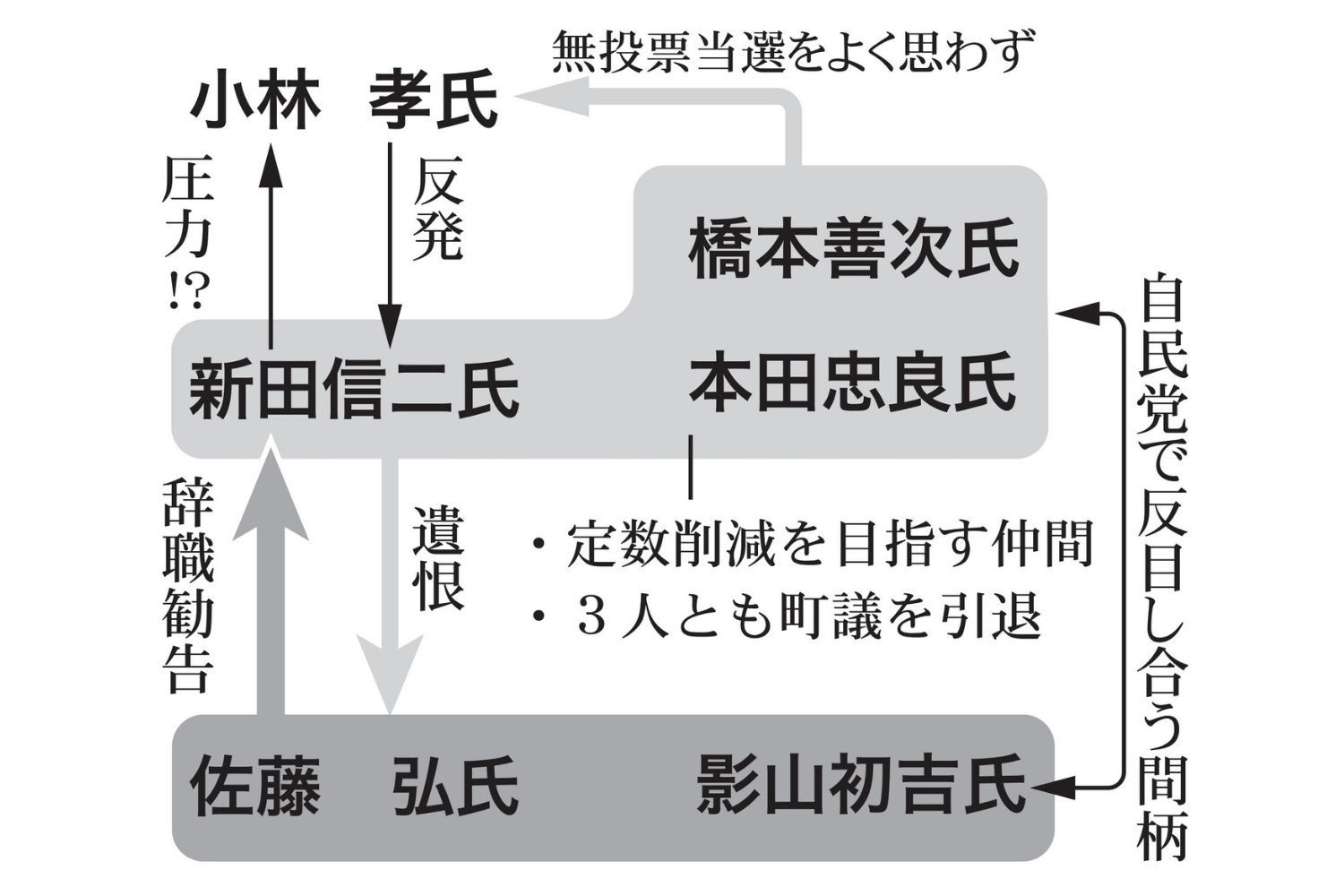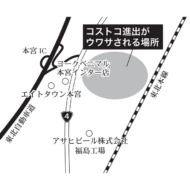国見町で「地方創生」に資するはずの公金が巧妙に食い物にされる仕組みを暴き出した新著「過疎ビジネス」(集英社新書)が7月に刊行され話題を集めている。一連の問題を宮城県を拠点にするブロック紙「河北新報」で報じ、本書を書き下ろした横山勲記者に執筆の背景をインタビューした。

書籍化の経緯を語る横山記者
よこやま・つとむ 河北新報編集部記者。1988年青森県出身。福島総局には2021年4月から24年3月まで赴任。自ら中心となって取材執筆した「『企業版ふるさと納税』の寄付金還流疑惑に関する一連の報道」は第29回新聞労連ジャーナリズム大賞を受賞した。
「地方自治は手でさわれるもの」
――書名“過疎ビジネス”とその片棒を担いだ上に責任逃れに終始する“限界役場”という言葉は、国見町を象徴するパワーワードです。どのように思いついたのでしょうか。
「過疎ビジネスと限界役場は私の造語です。国見町で官民連携で進められた救急車事業を調べると、事業者側が企業版ふるさと納税制度を悪用し『寄付金還流』や『課税逃れ』を画策する見たことも聞いたこともないスキームにたどり着きました。
新しい事象の本質に迫るには、新たな言葉で定義付けすると明瞭になります。似ているなと思ったのが『貧困ビジネス』でした。悪辣な支援事業者が生活保護受給者を施設に囲い込んで給付金を巻き上げる、生活困窮者を搾取するビジネスモデルです。過疎にあえぐ小さな自治体に近づいて、制度を悪用して事業と利益を囲い込み吸い上げる構図は、それと似た点があると思いました。
“限界役場”は、地方消滅への危機感から着想を得ました。日本で人口が増えるのは現実的でなく、縮小する社会を念頭に対策せねばなりません。住民が減り、生活が立ちいかなくなっていく集落を表した限界集落という言葉が既にありました。役場も業務は増す一方で人材が集まらず、機能は弱っていきます。今回の件で国見町役場のガバナンス不全を目の当たりにし、悲しいことに自治体の行政機能もこうやって限界を迎えていくんだと実感しました。
救急車問題の報道が佳境を迎えていた2023年3月時点で、過疎ビジネスと限界役場のワードは着想していました。問題を端的に表した言葉なので、どこかで表現したかったのですが、新聞紙面では造語は使えません。寄稿した東洋経済オンラインで初めて使用しました」
――河北新報での記事、経済誌の週刊東洋経済、集英社新書での書籍化と3媒体で過疎ビジネスの問題を世に問いかけました。書籍化の話はいつ持ち上がったのでしょうか。
「昨年の春頃に集英社から打診がありました。国見町議会の百条委員会、町長設置の第三者委員会が救急車問題を検証した報告書をまとめる前です。私は新聞記者ですから、毎日のニュースを届けるのが役目で、書籍化を想定して取材はしていません。ただ、救急車事業の構図が入り組んでいることもあり、紙幅が限られる新聞紙面では割愛せざるを得ない情報もありました。まとまった形で過疎ビジネスの実態を伝えられるのは願ってもない機会でした」
――執筆時に意識したことは。
「読者が私の取材過程を追体験し、一気に読了できるような構成を意識しました。難解な現実をスムーズに理解してもらうには、ストーリー性を持たせて、読者に私と同じ視点に立ってもらうのが重要と考えました。
他にも『地方紙記者とはどのような仕事か』が伝わるように心がけました。全国紙の記者はテレビに出演する機会が多く、小説や映画でも多く取り扱われているので一般の方の解像度は高いと思います。でも、地方紙記者は何をしているか意外と知られていない。イベント取材はもちろん、本分である行政監視的なことも地道に取り組んでいます。
『オールドメディア』扱いされているように、記者は昔ほど人気の職業ではありません。それでも、意義を感じて目指す人はいる。記者を目指す人、報道に触れる人に地方紙記者の仕事を身近に感じてほしいとの思いも込めて執筆しました。
本書では、上司のデスクや同僚記者をはじめ、出せる名前は全て出しました。河北新報の記者たちが個性を発揮して動いている。そういった地方の新聞記者の働き方、人物像を活写することで、なぜ地方にこそ記者が必要なのかということが伝わればいいなと願っています」
――本書では、国見町の事例を反面教師に地方自治の在り方を問い直します。人口減が進む中、地方自治のあるべき姿をどう考えますか。
「国が『地方創生』を掲げ、甘い制度設計のまま自治体に予算と計画を丸投げ。そして限界役場と化した自治体は、計画を立案する能力と余裕がなく、コンサルに過疎対策をまた丸投げする構図があります。国見町の場合は、事業者がその土地固有の事情を考慮せずに救急車リース事業という枠組みを無理やり当てはめました。国見町である必然性はなく、容易に他自治体にスライドできる、事業者側の効率を優先したビジネスモデルです。施策立案をコンサルに手伝ってもらう場面はあるかもしれませんが、自治の主体は誰なのかを忘れてはいけません。
『型にはめられた地方創生』の対極にあるのが手ざわり感だと思います。国見町と同じ業者が進出していた北海道むかわ町の住民を取材した際のことです。異議を唱えたある住民は、古くなっても愛されて手入れされる建物は長持ちする例を引き合いに出し、『地方は寂れると言っても自分たちが考える寂れ方があるんだ』と言いました。DIY精神と言うのでしょうか。『素人だけど自分たちがやりたいことを自分たちの手で進める満足感』。地方に生きる意味とは手ざわり感を楽しむこと、そして、その暮らしにプライドを持つことではないでしょうか。
現代社会は普通に生きていると、手ざわりといった生の感触を得るのが希薄になっています。偉い人が勝手に物事や仕組みを決めてしまう。不満もあるけどどうしようもない。さわれないというか、手が届かないというか、みんな諦めている。
でも、地方自治って本来は簡単に手でさわれるものだと思うんです。共に暮らす住民や生業だって、役場だって、自治の仕組みも含めて全て手が届く距離にある。手ざわりを感じて生きることが地方自治だと思うし、過疎の時代に地方に生きる意味があるとしたらそこだと思います。
国見町に進出した事業者は本心では『行政機能をぶんどる』『議会は雑魚』などと地方自治を軽んじていました。議会が救急車事業を検証する百条委員会を設置する2023年10月の前のこと、私は議員たちに『雑魚と言われて悔しくないんですか。プライドは無いんですか。僕は地方自治をないがしろにされて悔しいですよ』と詰め寄りました。彼らが出した答えは本書で描いた通りです。
手の届く範囲であがく
現代は、良識とされ守られてきたルールが崩壊する過渡期にあると感じています。自分自身に関わることなのに、自分だけの力ではどうしようもできないことが余りにも多い。河北新報で、そして本書で過疎ビジネスを問えたのは、そうした現実に絶望しながらも、自分がいる場所で自身が信じる良識に従ってジタバタした人たちからの協力や情報提供のおかげです。何も変わらないかもしれないけど、自分の手が届く範囲であがいてみよう。そういう姿に人間臭さを感じ、共感します。私自身も抗い続け、そのような人を応援する記者活動をしていきたいです」