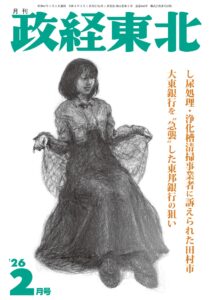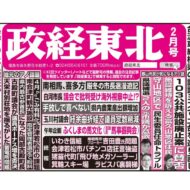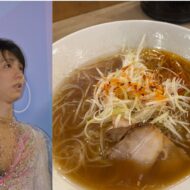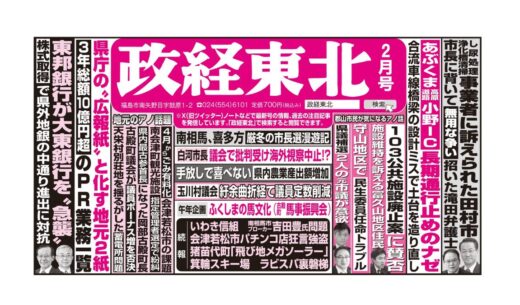県中教育事務所の男性職員(当時57)が2022年4月に自死したのは、長時間残業と上司からのパワーハラスメントが原因だとして、遺族が県を相手取り約8468万円の損害賠償を求める訴訟を起こしている。第1回口頭弁論は5月27日に福島地裁(川渕健司裁判長)で開かれ、県側は答弁書で「自死は認めるが、超過勤務に従事した結果であることは否認」、「違法なパワハラと評価される行為はなかった」と反論し、請求棄却を求めた。提訴を機に、本誌には「末端の教職員の不祥事には厳罰を与える一方で、幹部に責任が波及する問題は曖昧にしている」と県教委幹部を批判する投書が寄せられた。
遺族提訴で噴出する幹部への不満
訴状によると、自死した男性職員は中学校教員として採用され、2019年から県中教育事務所の職員として人事を担当した。21年に同事務所の学校教育課長が交代してから午後9時を越える残業が増えたという。
残業時間よりも少ない時間を記録するのが常態化しており、男性は独自にエクセルに正確な勤務時間を記録していた。それによると、超過勤務は月平均78時間を超えていた。自死する前の3カ月では、2022年1月に109時間、2月に136時間、3月に158時間の超過勤務があった。土日出勤も日常的だったという。
福島県沖地震への対応と職場が新型コロナに集団感染したことが重なり、同年3月には二十数名で回していた業務を4人で回さなければならず、朝6時に出勤し夜0時を過ぎてから帰宅する生活が続いたという。体重は減り、顔色も悪化。4月1日には昇格したが、超過勤務を良しとする風土は変わらなかった。同4日に新型コロナのワクチン接種で微熱があったがそのまま出勤。同8日に自死した。男性の死は労働災害に当たる公務災害に認定されている。
遺族は、自死の原因には残業超過だけでなく上司のパワハラもあると訴えている。生前の男性から次の話を聞いたという。書類の数字の確認作業を別の職員に依頼したところ、上司が「臨時職員に頼むとはいかなるものか、甘えるな! 自分1人でやれ!」と他の職員に聞こえる前で握り拳を震わせながら言い放った。早めに帰ろうとすると、その上司が帰宅を遮る発言を度々行ったなど。
県側は、男性が記録していた残業時間については信用性を積極的に争わず裁判所の判断に任せる方針。ただ、長時間の残業と自死に因果関係はないとする。パワハラも指導の範囲内で違法性はないという。臨時職員に書類の確認作業を依頼したことへの注意も、本人にのみ聞こえる声量で指導しており、「そもそも臨時職員に関わらせるべき仕事でないと事務所内で取り決めていた」と反論した。「上司が帰宅を遮った事実もない」と主張する。
双方の主張を立体的に浮かび上がらせる投書が第1回口頭弁論の数日後、5月28日の消印で本誌に届いた。
《3年前に県中教育事務所職員が自殺した件で、いよいよ遺族が提訴しました。当時は公務災害扱いで決着したように思われていたのですが、家族も納得できなかったのでしょう。あのような優秀な人物ですから納得できようはずがありません。提訴は当然です。そのまま県教委にもみ消されては、遺族も泣き寝入り、自死した本人も浮かばれません。本人は自死により、県の不正を訴えようとしたのでしょうから。
それとは別に、ここには重大な問題が潜んでおり、それは県教委の体質です。県中教育事務所自体の体質(今回の事案があり、今現在はどうだかわかりませんが)、県教育庁の体質は旧態依然のものがあります。
教職員の不祥事には厳罰を与え、自らの事案は不祥事扱いすらせずもみ消そうとする、これは許せません。ここが、県教委の最大の問題です》
内情に詳しい投書
投書は関係者の役職を詳しく記している。本誌だけでなく不特定多数の通報先に送られていると想定して意図を吟味する必要がある。差出人が考える県教委の問題点は、次の5項目。
《①学校におけるいじめ防止を指導する立場にある県教委が、その立場を忘れ同僚職員に対する「大人のいじめ」により自死に追い込んだことは児童生徒に示しがつかない。命は何物にも代えがたく、殺人に匹敵する重大かつ凶悪な犯罪である。
②県教委はこの事実をひたすら隠蔽し続けた。県教委幹部の間では情報を共有し、部下への報告、説明もなかった。いわば、本件について県教委内でタブー視されていたと言ってよい。事実さえ公にしようとはしなかった。ひたすら隠蔽することのみを貫いた。
学校でいじめ自殺事件が起これば、保護者説明会、記者会見を行い説明責任を果たせと指導するが、自らの「大人のいじめ」自死事件についてはひたすら隠蔽しようとしたのは問題である。域内校長会議、教頭会議、教育長会議等での説明責任を果たし、記者会見も行わなければならないのは当然である。
③現場には働き方改革を指導し、自らは深夜に及ぶ勤務を行い、しかも超勤時間の改ざんまで行っていた。現場職員の超勤手当水増し事案については免職の厳罰を与え、自らは「暗黙の了解があった」では済まない。
④自死者が職務を効率的にこなし帰ろうとすると、上司が「オレより先に帰るのか!」と帰宅を引き止めたことは強要罪、刑事罰に該当する。職員の前で叱責することも上司の立場をわきまえない未熟な管理職であり、県教委の任用責任もある。
⑤県教委には教員の懲戒処分は積極的に行い、身内の処分には極めて甘い体質がある。本事案加害者の●(本誌注:役職名が書かれ、個人が特定されるので伏字にする)のみならず、次の事案もある。
3年前、石川中講師によるわいせつ事案の際、42人の生徒が被害に遭い、2回の逮捕にもかかわらず、当時の校長には処分がなかった。それどころか、退職と同時に再任用校長として赴任した。これは、この校長が教育事務所時代に次長を務め、その時の所長が県に異動し、処分に配慮したためである。この種の事例は多い。県教委が優遇される体質はいろいろなところにひずみが出る。外部の者は言わないだけでよく見ている。県教委自体が変わらなければならない。幹部が変わらなければ何も変わらない》
補足すると、②「自死の隠蔽」については2022年に遺族の求めに応じて、県教委が職員らにパワハラの有無を聞き取っているので周囲に自死は伝わっている。③の超勤手当水増し事案は、浅川町の浅川中学校男性主事が記録を改ざんして残業手当46万円余りを不正に受給し、昨年9月に懲戒免職された件を指す。⑤の石川中講師は、懲戒免職後、懲役4年の実刑判決が言い渡された。
男性の遺族から、パワハラをしたりそれを黙認したと疑われている上司らは、2022年4月に転任し、小中学校の校長に就いた。
県中地方のある教育関係者は投書の背景を次のように推察する。
「県教委の事務を担う県教育庁は出世コース。教育現場と事務方を行ったり来たりし、校長や市町村の教育長が上がりのポストだ。県教委は教職員の不祥事を厳しく取り締まっているが、幹部によるハラスメントには甘い点が末端の教職員から不評を買っているのではないか」
県教委幹部への不満は続々と寄せられそうだ。