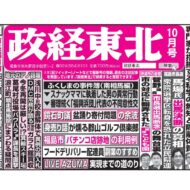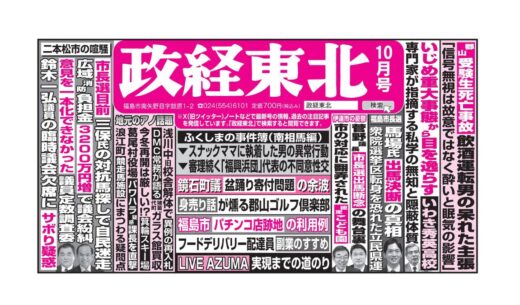いしづか・じんろう 東北大医学部卒。1985年に渡米、テキサス大准教授だった94年に帰国。2011年から田村医師会長。16年より県医師会常任理事を4期務め、昨年6月に県医師会長に就任。
福島県は医療分野において、過疎地域における深刻な医師不足、診療科偏在、医師の高齢化・後継者不在といった課題を抱える。加えて生活習慣病で亡くなる人が多く、県民挙げての改善も求められている中、福島県医師会ではどう課題解決を図る考えなのか。石塚尋朗会長(医療法人慶信會石塚醫院理事長・院長=小野町)に話を聞いた。
2700人の会員と力を合わせて目の前の課題に挑んでいく。
――医師不足が深刻です。若手医師が県内で定着する環境づくりのため、県医師会としてどのような対策を講じているのでしょうか。
「学生向けに交流の場を設け、本県の魅力を感じてもらう取り組みを行っています。具体的には、県立医大の学内サークルとの交流や大学訪問、若手医師が対象の福島県医師会医学奨励賞を設けるなどの取り組みを実施しています。
私自身研究に邁進した時期があり、また指導医を務めた経験がありますので、若手医師のサポートを通して県立医大との連携をさらに強固にしたいと考えています。
論文発表や研修会を通じて広く研修医との交流の機会を持ち、相互理解を深めていく方針です。
研修内容の充実、県内の研修医増員のため、県外から指導医を招くことも視野に入れています。研修病院の地元自治体とも協力していくことが必要だと考えます。
研修医が住みやすく、キャリア形成にもつながる研修の在り方を模索していきます。医師が大学から各地域に派遣される際に主軸となる研修先(メイン病院)に在籍しながら、その病院の医療圏にある過疎地での研修の機会を同時に持っていただく仕組み『地域医療サポートシステム』(仮名)について、県や県立医大と協議したいと考えています」
――県医師会では県からの委託事業として「医業承継バンク」事業にも取り組んでいます。
「バンクが稼働してから23件の承継が成立しました。担当職員の丁寧かつ粘り強いサポートの成果です。医業承継には時間と労力がかかるため、担当人員の増員が必要です。マッチング希望者は予測できず、複数の案件を同時進行でサポートするのも困難です。マンパワー不足で、承継希望者と譲渡希望者を待たせることは避けなければなりません。
県医師会の事務局が担う業務はもともと多くの分野にわたっており、仕事量も増えています。建築費は高騰しており、開業時の建築費負担を抑えられるという点で、医業承継は今後も需要が高まっていくと見ています。『医業承継バンク』は、地域の医療資源の減少を防ぎ、学校医・警察医・産業医など地域社会における役割を果たしていく医師を確保するためにも重要な役目を担っており、今後の機能強化について県とも協議していきたいです。
医業承継によりオンライン診療を活用する診療所も開業しました。確か初診については対面して、オンライン診療の際に職員が患者さん宅を訪問してサポートするという形であったと聞いています。不透明な部分もありますが、まず住民の声をよく聞き取ることが必要です。そのうえで、住民・自治体と話し合いながらサポート体制を構築していただくことが大切だと思います。将来的に特定行為研修修了看護師などがかかわることで、このような形の医業承継は医師不在の地域にとって福利になると考えます」
――医療DX(デジタルトランスフォーメーション=デジタルを活用した事業変革)を推進しています。
「効果的な研修の機会を設け、十分な理解のもとに推進を図ります。医療DXを拙速に進めれば国民や医療関係者に不信・不安を与えるので、安心・信頼を得ながら丁寧に進める必要があります。医療DXは医療人材不足をカバーし、患者利益にもつながる画期的なシステムですが、半面、紙カルテを使用している主に医療資源の乏しい地域の医師などが電子化に伴い廃業する懸念もあります。
このような事態を防ぐため、県医師会では『一人の会員も置き去りにしない医療DX推進』を目指していきます。全国医療情報プラットフォームと、全国各地で運用される地域医療情報連携ネットワークを地域ニーズに合わせて併用するため、『福島県医療情報ネットワーク(通称・キビタン健康ネット)』の運用を合わせて推進していくことが重要と思われます。県医師会としても、6月から医療DXアドバイザリーとして委嘱した専門家と相談しながら『医療DX研修プログラム』を構築していきます。
まずは医療DX初心者向け研修動画を作成・配信する予定です。該当する初心者会員のみならず、すでに医療DX機能を導入した会員の医療機関職員にも繰り返し視聴していただき、県内の全医療関係者に医療DXをよく理解していただくところから始めていきたいと思います」
――県内の男性の6割、女性の5割が高血圧という調査結果もあるなど、健康寿命延伸が県内医療の大きなテーマになっています。
「県医師会では、『健康ふくしま21』に明示された『減塩・禁煙・脱肥満』のスローガンのもと、県民の健康指標改善を図るための取り組みを進めています。
住民への啓発活動として郡市地区医師会長に管区自治体広報誌への寄稿をお願いしました。学校医・産業医会員にも啓発活動へのご協力をお願いし、それぞれの立場で活動していただいております。
さらに、新聞各社のご協力のもと、各分野の専門医による『減塩』、『禁煙』、『脱肥満』をテーマにした記事を掲載することで、生活習慣が健康に及ぼす影響への理解を深めていただき、健康指標改善に向けて県民のモチベーションを高める努力を続けています。
今後はSNSを利用した啓発活動を計画しています。不適切な生活習慣が健康に及ぼす悪影響について、これまで以上に知ってもらう努力が必要です。多くの方は健康を害したときに初めて『健康はかけがえのないものだ』と実感するものです。
そうなる前に、健康指標と生活習慣病の因果関係を知っていただき、発症しないための努力をしていただきたいと思います。今後も県や自治体、さまざまな関係団体、県立医大と協力しながら啓発活動を行っていきたいと思います」
――今後の抱負。
「県医師会を文字通り『2700人の会員の医師会』として運営していき、力を合わせて目の前の多くの課題に挑んでいきます。会員からの意見、提言を反映した医師会運営に努めます。さらに、医療政策に現場の医師の意見を反映させていくことも患者さんに寄り添う医療を目指すうえで大事なので、積極的に考えを発信していくべきだと考えています」