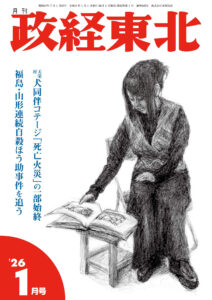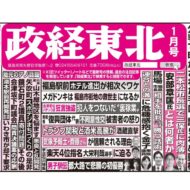はら・きよし 1955年生まれ。会津美里町出身。福島県農業短期大学校卒。1976年、会津高田町農協に入組。旧JA会津みどり常務理事を経て、2016年にJA会津よつば発足後は同JA常務理事、組合長を歴任。
JA福島中央会は6月26日に通常総会を開き、新会長に原喜代志氏(69、JA会津よつば)を選任した。厚生連、全農、共済連、農林中央金庫の県組織の会長も兼任し、JA五連会長として県内JAグループのトップを担う。原新会長にいまの思いや各種課題への対応、今後の意気込みなどを聞いた。
――6月に開かれた総会で会長に選任されました。
「県内のグループのトップに立つということですから、やはり身の引き締まる思いと、その責任の重さを痛感しています」
――JAグループでは、この間、原発事故前の農業生産額2330億円への回復を目指しています。一方で、いわゆる風評被害がいまだに完全払拭されていないほか、度重なる災害による生産基盤・施設などの被害、昨今の原油・肥料の高騰による生産コスト増、生産者の高齢化・担い手不足といった課題が山積しており、なかなか目標達成には至っていません。
「2024年時点の福島県の基幹的農業従事者は、2010年と比較すると半減しており、3万9900人となっています。さらに、平均年齢は71・1歳と高齢化が進んでおり、農業生産基盤の脆弱化に歯止めがかからない状況です。主要な品目の生産地では、販売高の3割から5割を70歳以上の生産者が担っている地域が多数あり、今後5年から10年のうちに生産力が急激に減少する懸念があります。このため、福島県農業の維持と発展には、新しい担い手の確保が喫緊の課題となっています。
これらの課題に対応するため、JAグループ福島では、福島型トレーニングファーム構想を推進しています。これは、JAと生産部会が中心になり、就農を希望する人々を積極的に呼び込み、部会が推薦するベテラン農家による技術研修と、関係機関による研修を組み合わせることで、早期に農業経営者として定着させることを目指す仕組みです。この取り組みは、すでに各JAの地域農業振興計画に位置付けられ、実践プロジェクトが開始されています。
また、前期3カ年計画では、新規就農者の確保と農業経営者としての育成定着に向け、県やほかの農業関係団体と共に、2023年4月に『県農業経営・就農支援センター』を設置しました。県内外から年間1300件以上の相談に対応しており、新規就農者は3年連続で300人を超えています。園芸ギガ団地構想も進められており、新規就農者を含む7品目12カ所で、作付面積の拡大が進んでいます。2024年度には、キュウリの生産額が全農取り扱い分で100億円を突破するなど、各地の主力品目が過去最高の生産量を記録しました。さらに、JA会津よつば昭和かすみ草部会が農林水産祭園芸部門で天皇杯を受賞するなど、明るい話題もありました。
解決すべき諸課題が多いのも確かですが、今後も引き続き顕在化している諸課題の解決に真摯に向き合い、JAグループ福島への結集を通し、さらなるふくしまブランド確立、生産基盤拡充を図りながら、最終的には生産者・組合員の所得向上につながるような取り組みを、グループとして進めていく必要があると思っています」
――現在の「コメ不足」について思うところをお聞かせください。
「『令和のコメ騒動』などと言われるこの問題では『コメの値段が上がった』と言われていますが、我々生産者から見れば、30年前の価格水準に戻っただけです。例えば、肥料にしても、農薬にしても、燃料にしても、30年前からしたら相当上がっています。この間、水稲生産者は生産費も賄えないような中で、消費者の皆さんにうまいコメを食べてもらうべく努力をしてきました。それが30年前の水準に戻って、ようやく生産費を上回る米価になってきたことを、消費者の皆さんにご理解いただけなければ、日本の食料安全保障は決して成り立ちません。
生産者もコメが高ければいいと思っているわけではありません。生産費を賄える価格で安定することを望んでいるのです。ですから、消費者の理解を得る努力をしながら、価格を安定させることが、日本の真の食料安全保障、農業生産力を維持することにつながると思います」
――昨年6月に改正「食料・農業・農村基本法」が施行されました。
「まず、食料・農業・農村基本法は『農政の憲法』とも言われるものですが、25年前にできたものです。この間、農業を取り巻く環境が大きく変わり、『農政の憲法』も現在の実態に合わせて変えていくということが基本にあります。改正『食料・農業・農村基本法』は、食料や生産資材の輸入環境の不安定化、気象変動、自然災害の増加といった懸念を反映したもので、食料安全保障の確保と農業の持続的な発展を基本理念としています。これに伴い、昨年4月には、今後5年間を『農業構造転換集中期間』とし、食料安全保障の強化を目指す新たな『食料・農業・農村基本計画』が閣議決定されました。
福島県においても、この計画に沿って、農地の確保、担い手の育成、コメの生産コスト削減、麦・大豆といった作物の生産性向上に取り組む必要があります。しかし、現状として農業者の急減により生産基盤が弱体化しており、農家が将来に希望を持って農業を続けられるよう、『儲かる農業』の環境を整えることが不可欠です。
そのためには、消費者の理解を得ながら、再生産が可能な農畜産物の販売価格を形成するための法律や、安定した農業経営の確立が必要です。また、生産の核となる担い手の確保、農地の維持、共同利用施設の更新、そして生産性向上やコスト削減に向けた国や県の政策・予算の確保も求められます。
JAグループ福島は、消費者が国産農畜産物を選ぶことが日本の農家の支援につながるという意識を高める活動と、将来を見据えた政策や予算の確保に向けた農政運動の両面から取り組んでいく方針です」
――今後の抱負を。
「やはり、まずは震災前の農業生産額2330億円への早期回復を目指していかなければなりません。復興はまだまだ道半ばで、震災前の50%程度の農業耕作面積にしかなっていないので、復興計画の中で、しっかりと国に予算を付けてもらいながら、『農業生産額2330億円への早期回復』を目指していきます。
もう1つは、『儲かる農業』の確立です。先ほどもお話ししましたが、農業従事者が高齢化している中、トレーニングファームをはじめとした各種取り組みを推進して担い手を確保し、農業生産力を上げ、組合員の皆さんの収入増につながるような形を目指したいと思っています」