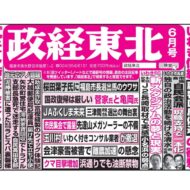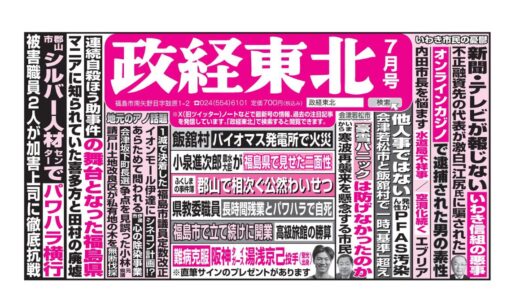震災・原発事故で被災した人たちの住まいを確保するため、県内各地に建設された復興公営住宅。年月の経過とともに入居率は低下し、とどまるのは高齢者が多いこともあり、コミュニティー維持が課題として浮上する。県は被災者という入居条件を徐々に緩和し、昨年10月からは一般公営住宅と同様「住宅に困窮している低額所得者」に拡大した。復興公営住宅の現在の姿を追った。
働き盛りが退去し高齢者がとどまる現実

復興公営住宅は、もともとは原発事故で避難指示を受けた人や地震・津波の被災者が入居対象だったが、2017年からは避難指示が解除された人、19年からは中通りと浜通りからの自主避難者も入居できるようになった。
復興公営住宅は、2013年に策定された第2次県復興公営住宅整備計画で県営4512戸の整備が決ま
ったが、その後123戸の整備を保留。昨年7月、現状の戸数で間に合うとして、いわき市に予定していた72戸と場所未定としていた51戸の整備を取りやめた。
一方、県内には市町村営の復興公営住宅も378戸あるが、これは一部に避難指示が出された川俣町、飯舘村、川内村が住民のコミュニティー維持を目的に自らの町村内に建設したり、葛尾村が主な避難先の三春町内に建設したり、避難者を受け入れていた市町村が避難元の町村との協議を経て建設したことによる。
県営4389戸と市町村営378戸を合わせた4767戸の整備状況は別表①の通り。戸数が最も多いのはいわき市、次いで南相馬市となっている。郡山・福島・二本松・会津若松の4市も大勢の避難者を受け入れていたため多くなっている。
表① 県内の整備状況
| いわき市 | 1672戸 |
| 南相馬市 | 927戸 |
| 郡山市 | 570戸 |
| 福島市 | 475戸 |
| 二本松市 | 346戸 |
| 三春町 | 198戸 |
| 会津若松市 | 134戸 |
| 川俣町 | 120戸 |
| 桑折町 | 64戸 |
| 本宮市 | 61戸 |
| 大玉村 | 59戸 |
| 広野町 | 58戸 |
| 白河市 | 40戸 |
| 川内村 | 25戸 |
| 田村市 | 18戸 |
復興公営住宅は昨年、大きな転換期を迎えた。それまで被災者・自主避難者に限定していた入居条件を緩和し、一般公営住宅と同様「住宅に困窮している低額所得者」に拡大したのだ。
ただし「募集月の前々月末で入居率が80%以下の県営住宅」という条件がつく。背景には退去者が多くなり、空き戸数が増えたことがある。
昨年5月末現在、県営の復興公営住宅は入居戸数3659戸、空き戸数730戸、入居率83・4%となっているが、このうち入居率80%以下の県営団地は49団地中13団地、空き住戸は730戸中348戸に上る。
低額所得者を対象とする入居者募集は昨年10月から始まり、今年2月には今年度6回目となる募集が行われた。その時は二本松市、会津若松市、南相馬市、いわき市の復興公営住宅が入居率80%以下になっていたが、自分が引っ越したいと思っている市町村で空きが出るとは限らないことが見て取れた。
退去者が多くなったのは、原発事故の避難指示が解除され元の自宅に戻ったり、新築した住宅に引っ越す人が出てきたことが要因だが、中には家賃の値上がりで退去する人もいた。
2020年までいわき市議(共産党)を務めた渡辺博之さんは現職時代、市内の復興公営住宅に暮らす人から「家賃が上がって暮らせなくなる」との相談を受け、対応に当たった経験がある。2017年12月4日に配信された「しんぶん赤旗」にこんな記事が載っている。
《いわき市内に16ある災害公営住宅の一つ、豊間市営団地の3LDKに家族3人で入居する××さん(53)=原文は実名表記だが伏せる=は先月、市営住宅の担当者が明かした金額に一瞬、耳を疑いました。
それは来年4月には8万6000円、2019年4月からは11万5000円になるというのです。現在の家賃は3万1800円で、実に3・6倍という大幅値上げです》
《××さんは、夫婦共稼ぎで35万円の月収があるものの3人の子どもを通わせた大学や専門学校の学費などの教育ローンの返済が毎月12万円あり、これに11万5000円の家賃が加われば、ここに住んでいられなくなると訴えました》
いわき市は、当時の渡辺敬夫市長が復興公営住宅の家賃を3年間半額にする減免措置を行っていた。
「急激な家賃値上げは2018年3月で減免期間が終わることに伴い発生した問題でした。当時、入居者らと減免期間延長を求める署名活動をしたり、自民党の市議と協力して住民集会を開くなどしたが、渡辺市長のあとを受けた清水敏男市長はなかなか聞き入れてくれなかった」(元市議の渡辺博之さん)
渡辺さんによると、入居者の多くは①被災前は持ち家に暮らしていたため、家賃のかかる生活が初めてだった、あるいは②被災して住めなくなった持ち家のローンを払い続けていたため、家賃との二重払いを余儀なくされていたという。
「そうした中で家賃が値上げされれば、入居者は安い民間賃貸住宅に移るか、住宅を新築して引っ越すかという選択を迫られるのです」(同)
しかし前者の選択は、避難場所を転々とし、その度に住居を変えてきた人には気の毒すぎる。後者の選択も、住めなくなった持ち家のローンを抱えていたら二重ローンを強いられることになる。
「復興公営住宅に入居した人は、ここを終の棲家と決めた人や、ここでしばらく貯蓄し再び住宅を新築したいと考える人が多い。それだけに家賃の減免は入居者にとって必要な措置だった」(同)
当時、市営薄磯団地で自治会長を務めた大河内喜男さんも市に減免期間延長を求めて活動した一人だ。
「減免措置が終わりに近づく中で退去者が出始めたので、市に署名を提出したり、市議会に請願書を出したりした。その結果、市は県などの動向を見ながら検討する方針を示した」(大河内さん)
そもそも、復興公営住宅の家賃はどうやって決まり、どのような負担軽減策がとられているのか。
別表②は国が定めた家賃算定基礎額だ。同基礎額は入居者の収入月額に応じて変わり、これに市町村立係数、規模係数、経過年数係数、利便性係数を掛け合わせて家賃が決まる。ちなみに、この計算で算出された家賃は入居3年未満までの金額だ。
表② 家賃算定基礎額
| 入居者の収入月額 | 家賃算定基礎額 |
| 0~104,000円 | 34,400円 |
| 104,001~123,000円 | 39,700円 |
| 123,001~139,000円 | 45,400円 |
| 139,001~158,000円 | 51,200円 |
| 158,001~186,000円 | 58,500円 |
| 186,001~214,000円 | 67,500円 |
| 214,001~259,000円 | 79,000円 |
| 259,001円~ | 91,100円 |
ここに二つの家賃対策が加わり、入居者の負担軽減が図られている。
二つの家賃対策
一つは、被災者で月収8万円以下の人を対象とする減免措置。家賃から、月収(0円、1~4万円、4万0001~6万円、6万0001~8万円)に応じて1万0600円から最大3万2500円を引いた差額分を10年間減額する。減額率は最初の5年間が100%、以下、5年超~7年以下は75%、7年超~9年以下は50%、9年超~10年以下は25%。10年かけて減額率が縮小していくため、家賃は徐々に上がっていく。
復興公営住宅は、入居3年以上で一定の収入を超える人を「収入超過者」と認定し、翌年度から月収に応じて家賃を値上げ(割り増し)する措置がとられている。一般世帯は15万8000円、障がい者等がいる世帯は21万4000円を超えた人が収入超過者とされ、割増分は近傍家賃(公営住宅法の規定による近傍同種住宅の家賃)をもとに算定される。ただし、いきなり割増分100%が家賃に上乗せされるわけではなく、例えば月収15万8001円から18万6000円以下の入居者の場合、初年度20%割増、2年度目40%割増、3年度目60%割増、4年度目80%割増となり、5年度目以降から100%割増と段階的に上乗せされる(月収に応じて割増率や適用される年度数は異なる。月収25万9001円以上の人は初年度から100%割増)。収入超過者の急激な負担増を避けるための措置だ。
これら二つの家賃対策は2017~19年にかけて国、県、市町村ごとに行われるようになり、現在も続いている。先の赤旗で紹介されたいわき市の家族は、家賃対策が行われる前だったため急激な値上げを迫られたわけだが、一方で、この家族は夫婦共稼ぎで月収35万円とあり「入居3年以上の収入超過者」に該当するので、結局、値上げは避けられなか
ったと思われる。
原発事故や地震・津波で住む家を失った被災者に、この仕打ちは酷いと感じるのは自然だろう。負担を軽減する目的で行われている前述・二つの家賃対策も、結局は段階的に家賃が上がっていくから、純粋な減免措置とは言い難い。
「家賃がどんどん上がるなら、その分をローンに回して住宅を新築した方がいいと、働き盛りの夫婦ほど退去する傾向にあった。そういう家庭には子どももいるので、結果、復興公営住宅にとどまるのは年金しか収入がない高齢者ばかりになってしまう」(前出・渡辺さん)
「私は既に復興公営住宅を退去したが、家賃が十数万円になってもとどまっている人がいると聞いた。『もう引っ越すのは嫌だ』『子どもを転校させたくない』など様々な理由から仕方なくとどまるケースもあるようです」(前出・大河内さん)
なぜこのようなことが起きるのかというと、復興公営住宅が公営住宅法で定める一般公営住宅と同じ位置付けになっているだからだ。そうなると、原発事故や地震・津波という特殊事情で入居した人たちではあるが、適用される措置は住宅に困窮している低額所得者を念頭に置いた同法に基づく、と。
公営住宅法第28条第1項、第2項を読むと(※欄外参照)復興公営住宅の家賃を段階的に上げる理由がよく分かる。つまり、低額所得者は入居3年を超えてもとどまることができるが、収入超過者になると次に現れるであろう低額所得者のために部屋を明け渡す、つまり退去しなければならないのだ。
国、県、市町村が「減免措置を受けていない民間賃貸住宅や一般公営住宅に入居している人との公平性を確保する必要がある」として、被災者であっても特別扱いしないのはそういうことだ。
長期避難を想定した住まいに関する法律があれば、このような問題は起きなかったが、震災・原発事故から13年経ち、他県でも長期避難を余儀なくされる災害が起きているのに未だに必要な法律がつくられていないことが、被災者でも収入超過者になった途端、高額な家賃で住み続けるか、退去せざるを得ない選択を迫られてしまうわけ。このような法律の不備を放置していいのか。
ただ、県建築住宅課によると昨年12月末現在、県営の復興公営住宅の入居者平均年齢は51歳、平均家賃は2万2000円、平均月収は10万4000円。収入超過者はかなり少ない模様で、これらの数字から入居者の多くは年金暮らしの高齢者と分析される。
減免措置等がなくても低額な家賃のまま住み続けることができる高齢世帯ばかりになる中、入居率低下を阻止するために行われているのが一般の低額所得者も入居を認める措置だ。県生活拠点課によると、今後の課題は復興公営住宅の高齢化率が上がる中、自治会を継続的に組織してコミュニティーを維持できるかということと、入居率が下がった時、1世帯当たりの共益費の負担が増えてしまうことだ。前出・大河内さんによると、沿岸部の復興公営住宅は下水道がつながっておらず合併処理浄化槽のため、その維持管理費も重い負担になるという。
当面の課題は、入居率の低下を防いで共益費の負担を増やさないことだが、長期避難を想定し、被災者が不便・不利を被らないような住まいに関する法律を、公営住宅法とは別につくることも必須だろう。