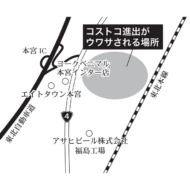第105回全国高校野球選手権記念大会(通称=夏の甲子園)2回戦で聖光学院と仙台育英が激突した。早すぎる東北の「隣県対決」を惜しむ声の中、熱戦は9回2死、松尾学武選手(3年)が空振り三振を喫し、福島県代表として挑んだ聖光学院の夏は終わった。
スコアは2―8。宮城県代表の仙台育英ナインの健闘を称え、夢の続きを託した聖光学院ナインだが、すぐには現実を受け止め切れなかった。ぼう然としたまま、試合後の習性として甲子園球場のアルプススタンドに向かって走り出した。
昨夏も同じ仙台育英に準決勝で屈した。その年、隣県のライバル校は頂点まで駆け上がり、深紅の優勝旗を104回の歴史を誇る大会史上初めて、白河の関を陸路で越えて持ち帰った。伊達市にある聖光学院の野球部グラウンドから東北新幹線がよく見える。ナインはもの凄いスピードで素通りしていったグリーンの車体を「次こそは……」の思いを秘め、眺めていたかもしれない。
悔しさを忘れない。1年間歯を食いしばって鍛え直し、夏の王者・仙台育英と全力で戦い、昨年以上に善戦したが、またも跳ね返された。
アルプス席の前で、聖光学院ナインは横一線に整列して頭を下げた。そして顔を上げた瞬間、声を枯らして応援してくれた控え部員、支えてくれた学校関係者、成長を見守って来てくれた家族の姿を薄暮の中に見た。そして、彼らの感情が堰を切ってあふれ出た。
「最後は笑って終わろうと思っていましたが、スタンドに行った時に涙が出てしまいました」
そう言って号泣し、その涙を泥だらけのユニホームで拭った三好元気選手(3年)は神奈川県出身。聖光学院のユニホームに憧れて門を叩き、2年連続夏の甲子園で福島県代表として戦った。
三好選手だけではない。親元を離れ、追い求めた日本一の目標には届かなかったが、涙の量は努力の量だ。スタンドに並ぶ親しい人たちの顔を見て流した大粒の涙は、今は気づかないかもしれないが、長い人生の中では金色の優勝メダルよりも確かな価値がある。彼らが2年半、福島の地を踏みしめて本気で野球に向き合い、成し遂げたものへの美しい対価だった。
聖光学院の野球部を「外人部隊」と呼ぶ人がいる。100人を超える部員の中から今大会、ユニホームを着てベンチ入りを許されたメンバーは、わずか20人。うち、福島県出身は6人だった。数字だけを見れば、文字通り県外から来た人を意味する「外人」ばかりと揶揄することも、あながち見当違いではないかもしれない。
彼らを「外人」にしているのは誰か
2019年10月14日の産経新聞ネットニュースを紹介したい。
「台風19号の記録的な豪雨により、複数箇所で河川が氾濫、多数の家屋が床上浸水した福島県伊達市の梁川町町裏地区では14日、今夏、福島県代表として13年連続甲子園に出場した聖光学院(同市)の野球部員ら約60人が、復旧のためボランティア活動を展開した。チームメートの自宅が水没し、心配したナインの『友情の輪』が地域全体への奉仕活動に発展した」
記事によれば部員はチームメートの自宅だけでなく、自発的に近隣の家を回って、雨の中、冷蔵庫や畳など力を合わせて運び出したという。たくましく鍛え抜いた球児たちだ。災害の中、不安で困り果てた住民には、さぞや頼もしい存在であっただろう。
現場で「陣頭指揮」を執り、「少しでも役に立てればうれしい」と語った清水正義さんは当時聖光学院の3年生、すでに野球部は引退していたが、その年の夏に出場した甲子園では主将を務めていた。清水さんは大阪府出身の「外人」だ。将来は教師になりたいという清水さんは現在、故郷大阪の大学に在籍し、そこでも野球部の主将を務めている。
「外人」である彼らが3年間で成し遂げたのは野球の成果だけだっただろうか。伊達市在住なら彼らが厳しい冬に市民の生活通路を確保するため、白い息を吐きながらトレーニングも兼ねて雪かきをする姿を見たこともあるだろう。
特別な災害だったから彼らは動いたのだろうか。英雄心でボランティアを買って出ただけだろうか。見知らぬ野球部員に道ばたで「おはようございます!」とあいさつされたことはないだろうか。野球で全国優勝を目指しながら、県外からの入学者であっても彼らは地域に親しまれる住民であろうと努力してきた。それが野球部の方針であるからだ。
「聖光学院は外人部隊だから素直に応援出来ない」。では彼らを「外人」にしているのは誰だろうか。今や聖光学院野球部は全国に名をとどろかせる強豪だ。スポーツの強さは努力の質と量に比例する。それは出身地とは関係ない。勝つために他県から選手をかき集めたと指摘するかもしれない。いや、県外出身者が多いから勝てるわけではない。勝ちたいという強い気持ちで集まってきた選手たちのチームだから強いのだ。
2020年春に突然猛威を振るい始めた新型コロナウイルスは、感染拡大を防ぐ目的で子供たちの活動を大幅に制限してしまった。全国各地の公園、遊び場から子供たちの笑顔が消え、中学、高校生の部活動も目標にしてきた公式大会が中止になるなど、言いようのない虚無感に支配された。
同じ光景を福島県民は東日本大震災、それに続く東京電力福島第一原発の事故で、すでに経験している。テレビのニュースが伝える放射線量に神経を尖らせながら子供たちをなるべく外出させないように気遣っていた長く辛い日々があった。
福島と同じように宮城県民もまた東日本大震災で被災し、強烈な痛みを知っている。仙台育英の須江航監督は、夏の甲子園で初優勝を成し遂げた昨年の高校3年生を「尊敬している」と言った。
2004年生まれが多かった世代は、小学校入学の直前に東日本大震災を体験した。そして高校入学と同時にコロナ禍を経験することになる。彼らは当たり前の日常を知らずに成長してきた。須江監督は「小学生の頃から彼らは当たり前ではないことが日常になっていた。高校に入学したらウイルス。練習も含めて、何をやるにも制約が多すぎて、私だったらきっと嫌になって投げ出している。でも彼らはひた向きに取り組んでくれた。そういう姿を見せられてきたので、私は彼らを尊敬している」と、自身の体験をもとに素直な気持ちを明かした。
日本の少子化は社会問題にとどまらない。国の将来に関わる重大な事態だ。福島県はさらに深刻である。県が発表する推計人口では14歳以下に当たる年少人口は1950年の78万0838人をピークに減少を続け、2022年は19万5798人まで減少。初めて20万人を割ってしまった。2010年には27万6069人だった。原発事故の影響も大きいことが分かる。
覚悟を持って福島の地を踏みに来る
私が生まれ育った須賀川市で地域の子供たちにとって夏の最高の遊び場だった牡丹台プール(正式名称は牡丹台水泳場)がコロナ禍で使用停止となり、利用者が戻らないことから今年で廃止、解体されることが決まった。
市役所に勤務する友人と酒を飲んだ際にそのことを聞かされ、「地域にとって大切な施設だろう。なくすなよ」と抗議した。友人は寂しそうに「じゃあ、なくなる前にもっと使ってくれればよかったんだ」とこぼした。今、県外に住む私は言葉を失った。
私自身が子供の頃、夏休みには町内会でソフトボールやミニバスケットボールのチームが編成され、各地域で大がかりなトーナメントが開催されていた。子供神輿を担げば、町内会の大人たちがご褒美にお菓子をくれた。特に夏は子供たちを中心にした地域の行事が多かった。朝、ソフトボールの練習をして、昼から牡丹台プールで遊んだ。それが当たり前の夏の一日だった。今の子供たちは、そんな夏休みを過ごせていない。
地域から子供がいなくなり、このままでは公園や校庭から聞こえてくる元気な声はもっと減っていくだろう。せめて球場で、競技場で、あるいはテレビの中だけでも「福島の子供たち」の勇姿を見たくなる。ところが、少子化は高校野球界にも暗い影を落としている。福島県高野連のホームページによれば、2016年の3017人を最後に県内の硬式野球部員数は3000人を割った。2023年は2082人。1000人台への落ち込みも現実的になった。加盟校の数も2016年は87校あったが、2023年は69校と、わずか7年で18校も減った。
野球部どころか、高校そのものが少子化の影響で統廃合が進められている。福島県教育委員会の発表によれば、2021年以降、実に22校以上が再編整備の対象となってしまった。
大人が割り出す数値は悲観的で、福島県の未来に影を落としてばかりだ。では聞きたい。福島の子供たちは「震災のせいだ」「新型コロナウイルスのせいだ」「少子化のせいだ」とショボくれていますか?
この夏、北海道で開催された全国高校総体(通称=インターハイ)で、ふたば未来学園のバドミントン部が男子団体で全国優勝、女子団体は準優勝という素晴らしい結果を成し遂げた。高知県で行われた全国中学校大会(通称=全中)では同中学校バドミントン部が男女とも団体全国優勝、中高ともに個人やダブルスでも全国制覇など輝かしい成果を残した。
ご存じのようにふたば未来学園は、東京電力の事故により困難に直面した双葉郡の教育環境を取り戻すことを目的にした「双葉郡教育復興ビジョン」を柱に開校した公立校だ。中高一貫で、「福島県の復興を支え、社会に貢献する人材の育成」に取り組んでいる。バドミントン部は元世界王者の桃田賢斗らを輩出し、現在は休校中の富岡第一中学校、富岡高校の取り組みを引き継ぎ、きらめくような成果を出している。
野球の聖光学院、バドミントンのふたば未来学園、サッカーなら郡山市の尚志高校、陸上なら石川郡の学法石川高校……。いずれも全国で胸を張れる強豪校だ。甲子園で、インターハイで、全国高校サッカーで、都大路の全国高校駅伝で、「福島」の看板を背負った彼らは毎年のように優勝候補として日本中から注目されている。
そして、福島県外の子供たちまでそれらの高校に憧れ、そのユニホームを着るために親元を離れ、覚悟を持って福島の地を踏みに来る。チームを編成することさえ厳しい状況であるのが現実だ。県内の人口が減少する中、県外から参加してくれる子供たちが「福島」のブランド価値を上げてくれている。有り難いではないか。
福島スポーツ界の競技力向上に貢献
スポーツに少子化を食い止める力はないかもしれないが、子供たちを輝かせることは出来る。
それでもあなたは全国的な人気と実力を誇る聖光学院野球部を「外人部隊」と呼んで、素直に応援できないと嘆きますか? 偏屈な識者は聖光学院の「一強」状態が、福島県内の野球競技レベルを下げてしまうと主張する。1995年から2004年夏に聖光学院が止めるまで、福島県代表は夏の甲子園で9年連続初戦敗退を続けていたことを忘れてしまったのだろうか。「聖光学院でしか甲子園に出られないなら野球をやっても仕方ないと子供たちが考える」。本当にそう思うなら、子供たちの夢を見る力を見くびっている。一昨年の夏に甲子園に出場したのは日大東北であるし、今年の夏も学法石川が福島大会の決勝戦で延長タイブレークの大接戦を演じ、絶対王者を脅かした。
あえて県内の子供たちを中心に戦って聖光学院に勝ちたい、というチームが出現して躍進する可能性もある。大谷翔平や菊池雄星らを輩出し、この夏の甲子園ベスト8と健闘した岩手県代表の花巻東高校や2018年夏に旋風を巻き起こし、準優勝した秋田県代表の金足農業高校がそうだ。県内の高校生が「花巻東や金足農が出来るなら自分たちもやれる」と熱を持ってくれるなら、それこそ福島復興の支えになる。それも聖光学院が存在するおかげと言えるのではないだろうか。
そもそも県外出身者ばかりと言うが、聖光学院から過去、日本野球機構(NPB)のプロ野球12球団にドラフト指名されたのは育成も含めて9人。うち現在、千葉ロッテマリーンズで活躍する佐藤都志也など福島県出身者は4人もいる。東北出身者に広げれば、実に9人中7人だ。聖光学院がこれほどの強豪校になる以前、県内から短期間のうちにこれだけのプロ野球選手を輩出したことはない。
聖光学院の存在が県内の野球競技レベルを上げているのは否定しようがない事実だ。そして、バドミントン、サッカー、陸上競技でも同じことが言える。ふたば未来学園、尚志高校、学法石川などの存在が、どれだけ福島スポーツ界の競技力向上に貢献してきただろうか。
彼らは地域の宝で、福島の未来
2011年の夏、東日本大震災の爪痕も生々しい中、聖光学院は甲子園出場を決めた。当時のエース歳内宏明さんもまた被災者でありながら震災で傷ついた福島県民を見て「野球なんかやっていていいのだろうか」と真剣に悩んだという。周囲の期待と復興への希望という重いものを背負わされ、なおかつ前年ベスト8の優勝候補として出場した夏の甲子園は右手の腱鞘炎を隠して覚悟の熱投を続け、2回戦で敗れた。そして、試合後は「チームにも福島の人にも申し訳ない」と泣いてくれた。のちにプロ野球・阪神に入団した歳内さん(2021年現役引退)は、兵庫県出身だ。
それでも、あなたはまだ「聖光学院は外人部隊だから素直に応援出来ない」と嘆きますか。彼らを「外人」にしているのは誰なのだろうか。彼らは太陽の恵みのような福島の子供たちなのだ。それが高校生活の3年間であっても成長を見守ってあげてはどうだろう。
では、どうすればいいのか。簡単だ。別に球場でメガホンを叩いて声援を送る必要はない。ただ道ばたで、駅で、「おはようございます」と挨拶してきた高校生に「おはよう!」と笑顔で返すだけでいい。彼らは地域の宝であり、福島の未来なのだから。
スポーツライター 羽鳥恵輔
はとり・けいすけ 1968年、福島県生まれ。プロ野球、高校野球、Jリーグ、高校サッカー、ボクシングなど広範囲に渡って取材を続ける。東北楽天ゴールデンイーグルスのファン。