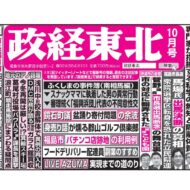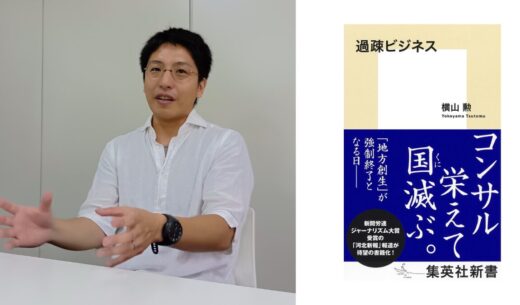福島市は昨年12月議会で「廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正」という議案を上程し可決された。内容は、ごみ集積所に出されたものについて、分別などのルールを守らないものは袋を開封して調査を行うことなどが盛り込まれている。1月には、市内19カ所で住民説明会が行われた。
「悪質排出者」には響かない!?



議会初日(昨年12月2日)の議案提案理由説明で、木幡浩市長は次のように述べた。
「これまで、適正なごみ排出を繰り返し呼びかけてきましたが、地域のごみ集積所へ事業系ごみが不法投棄され、カラスに荒らされる被害が後を絶たず、家庭系ごみにおいても資源物が分別されていないケース等が見受けられます。こうした状況の改善に向け、本定例会議に廃棄物処理条例改正の議案を提出しました。ごみの適正排出を市民の責務として明確化するとともに、悪質な違反ごみの開封調査を導入し、排出者に注意指導して是正を働きかけます。市民、事業者にごみ排出ルールの徹底を促し、ごみ減量化とリサイクル推進を図ります」
説明にあるように、条例改正の狙いはごみ減量化だ。国(環境省)が毎年実施している「一般廃棄物処理事業実態調査 2022年度調査結果」(昨年6月公表)によると、福島県は1人当たりの1日に出すごみの量が1021㌘(「事業系ごみ」と「生活系ごみ」の合計)で全国ワースト。中でも、福島市は県平均を上回る1080㌘で、同規模自治体の中で下位に位置付けられる。
一方で、今回の条例改正には明確な狙いがある。それが中心市街地の飲食店などを中心に、事業系ごみが違法排出されており、その抑制である。生ごみを含んだごみが多く、カラスがつついて周辺に散乱する事態が頻発しているため、地元町内会などから「何とかしてほしい」と要望が上がっていた。2023年度の違反ごみは9240件に上る。
こうした背景から、条例改正が行われ、悪質なごみ排出者の抑制、ごみ減量化につなげていきたい考え。
具体的な内容は、悪質なケースではごみ袋を開封して違反者を特定することができるようになった。特定できた場合は、その違反者に対して一度目は「注意」、二度目は「是正勧告」、三度目は「氏名公表」といった三段階の厳しい姿勢で対応する。
市ごみ減量推進課の担当者は、「野球になぞらえて、ワンアウト(一度目)、ツーアウト(二度目)、スリーアウト(三度目)とアウトが積み重なり、スリーアウトになると、野球ならチェンジ、この場合は氏名公表になります」と説明した。
もう1つは、条例の文言で以前はごみ適正排出について「市民には努力義務がある」といった内容だったが、今回の改正で「市民の責務」として明確化された。その責務を果たさない悪質なケースは、厳しい姿勢で対応するということだ。
これに対し、議会では、プライバシー侵害の懸念などから、ごみ袋の開封や氏名公表に反対する意見も一部議員から出たが、採決の結果、賛成多数で可決された。
この条例改正は3月から適用され、それに先立ち、1月9日から30日にかけ、市内19カ所(支所単位)で住民説明会を実施した。
住民説明会を取材

本誌は清水地区(16日)、北信地区(17日)で行われた説明会を取材した。説明会では、前段に記したような条例改正の中身についての説明があった。
開封調査の流れは①違反ごみ確認→②ごみ収集委託者が黄シール貼付→③市職員が赤シール貼付→④1週間残置→⑤開封調査→⑥対面指導となる。これでワンアウト。同様の流れで調査し、同一人物だった場合は⑥のところが「勧告書」の提示に変わりツーアーウト。同じようにスリーアウトになると⑥が「氏名公表」になる。公表内容は氏名(事業者の場合は事業所名か、代表者氏名)、住所(市民の場合は大字まで)、勧告内容(勧告日、違反内容)で、市のホームページで一定期間継続して残される。
このほか、分別の意識付けを目的に、ごみの区分が名称変更され、その案の募集が行われた。例えば資源物なら「資源物」、「使えるごみ」、「分別ありがとう!資源物」、「何度も使える資源物」、「社会を循環!資源物」、「リサイクルできる資源」、「生まれ変わる資源」、「資 you a 源(see you again)」といった候補が挙げられ、その他も含めて市民の投票で決まる。
こうした説明等の後、意見交換が行われた。そのうち開封調査に関連する象徴的な意見を紹介する。
市民「悪質排出者は氏名公表だけでなく罰則規定が必要ではないか」
市担当者「全国他市では科料を課しているところもある。ただ、それにはいろいろと調整が必要。今回はスピード感を持って取り組んでいるため、そこまでは考えていない」
市民「学校の教育の中でも、ごみ分別、適正排出を指導すべき」
市担当者「そういったことも考えていきたい」
市民「今まで通りの袋で出せるのか、それとも専用の袋を用意しなければならないのか。また、ネームシール等を貼るのか」
市担当者「この質問は他地区でもあり、皆さん気にされていると思う。指定袋はない。今までの袋で出してもらって構わない」
市民「悪質者特定のために、ごみ集積所に防犯カメラを設置することはできないのか」
市担当者「ごみ集積所は市内に7000カ所あるため、市としては難しい。町内会単位で設置しているところはある」
市民「こういう場(説明会)に出席する人は、悪質なごみ出しをするとは思えない。町内会に所属していないようなマンション・アパート住まいの人への指導の方が重要だ。管理会社等を通じて指導する必要があるのではないか」
市担当者「管理会社や仲介会社(不動産会社)への指導は考えていきたい。新規のマンション・アパートでは専用の集積所を設けているところもある。既存のマンション・アパートでも、後付けで専用集積所を設けた例もある」
市民「モノを買うと過剰包装と思うようなことも多々ある。生産者への指導や、生産者を巻き込んだ取り組みが必要ではないか」
市担当者「市として、あらゆる機会を見て、生産者にそういったことを訴えていきたい」
清水地区(清水支所)で行われた説明会には約270人が参加した。市は「多く見積もって200人くらいを想定していた」とのことだから、想像以上の人が参加したことになる。支所の駐車場は満車で、まず駐車するのが大変で、会場(支所の会議室)は立ち見が出るほど。北信地区(北信支所)は約160人が参加し、同支所は清水支所の会場よりフロアが広かったため、立ち見が出るほどではなかったが、駐車場はかなり混み合っていた。ほかの会場でも、同様だったようだ。
それだけ、市民の関心が高いということだが、開封調査に関する質問はそれほど多くはなかった。それよりも、「〇〇(ごみ)はどうやって出せばいいのか」といった質問の方が目立った印象。ここで紹介した市民の意見にもあったが、そういった場に出席する人は意識が高く、ごみ出しルールの理解を深めたいとの思いで出席しているような人たちばかり。開封調査の対象になるようなことはしないだろう。むしろ、悪質排出者に迷惑しているから、市に意見・対策案を述べたかったという人が多かったのではないか。少なくとも、本誌が取材した会場ではそうだった。
言い換えると、今回の説明会では開封調査の対象になるような悪質排出者に、市の考えは届いていないということになる。開封調査、氏名公表は悪質なごみ排出を抑制するための手段でしかない。目的は、ごみ減量、分別強化でそれが達せられて初めてルール変更の意味があったと言うことができる。そのため、評価は今後の実績を見てから、ということになる。