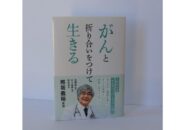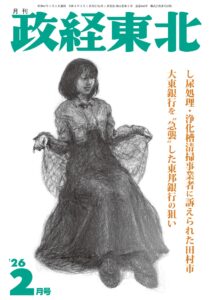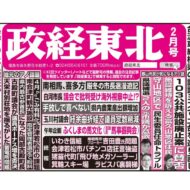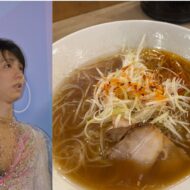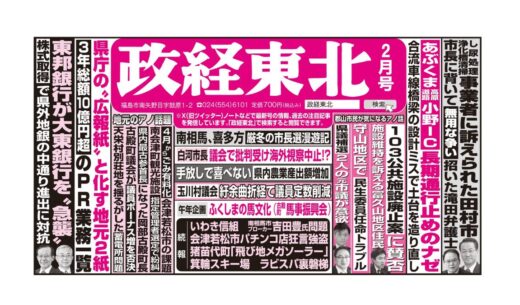聖光学院ナインには毎年楽しみをもらっている。特に今年のチームはその思いが強い。昨年の秋季東北大会が県内開催だったこともあり、現地観戦する機会に恵まれた。そこで優勝したことで明治神宮大会に出場し、私も現地に足を運んだ。センバツでは初戦の常葉大菊川戦を観戦し、聖光学院の甲子園通算30勝の節目に立ち会った。そして、夏の県大会を勝ち上がり甲子園へ。選手にとっても、1年間追いかけてきた私にとっても集大成。期待を胸に甲子園に向かった。(末永武史)
最後まで大嶋投手に託した想い

今年のチームは近年では結果が出ていた。昨年秋の東北大会では、仙台育英(宮城県)や青森山田(青森県)といった甲子園に出たら優勝候補に挙げられるようなチームに勝って優勝した。秋季東北大会優勝は7年ぶり2回目。東北チャンピオンとして臨んだ明治神宮大会では、近畿地区優勝で、優勝候補に挙げられていた東洋大姫路に0―10の5回コールド負けという屈辱を味わった。
今春のセンバツでは、初戦の常葉大菊川戦を観戦し、延長タイブレークの末、4―3で勝利した瞬間を見届けた。次の早稲田実業戦、浦和実業戦はテレビ観戦だったが、ベスト8まで勝ち上がり、夏への期待をさらに膨らませた。夏の県大会は、正直圧倒的な力で勝ち上がるのではと思っていたが、苦しい試合が多かった。それでも、地力を見せつけて優勝し、甲子園の切符を手にした。目標は「日本一」。
ともかく、これでまた大舞台で聖光学院ナインが躍動する姿を見られる。もちろん、頂点に上りつめてほしいが、それ以上に、悔いなく自分たちの力を出し切ってほしい。
勝ち上がるには実力も必要だが、組み合わせも重要になる。そうなると、最初の注目は8月3日に行われた組み合わせ抽選会だ。聖光学院は大会7日目第1試合、2回戦からの登場で相手は山梨学院(山梨県)に決まった。山梨学院は2年前のセンバツで優勝したことは記憶に新しい。山梨県勢として春夏通じて甲子園初優勝だった。
この組み合わせを見た正直な感想は「結構、厳しい相手だな」というもの。ただ、初戦で難敵に勝てれば勢いに乗っていける。
見どころは「聖光学院・大嶋哲平投手VS山梨学院打線」。山梨学院は打力が強いチーム。そこを、変則左腕の聖光学院エース・大嶋投手がどう抑えるかが注目だった。
試合は、5回まで両チーム無得点で、聖光学院は6回までノーヒット。一方、山梨学院は再三チャンスをつくるものの、なかなか得点できない。聖光学院の固い守りがそれを許さなかった。一見すると、チャンスを多くつくっている山梨学院が押しているが、チャンスをモノにできず、むしろ嫌な感じがしているのではないか。逆に耐え凌いでいた聖光学院が先制できれば一気に流れをつかめる。そんな展開だった。
しかし、そうはならなかった。山梨学院が素晴らしかったというしかない。6回裏に山梨学院に先制を許す。1アウト1塁から、サードゴロを打たせ併殺かと思ったが、サードからセカンドに転送された際、ランナーと交錯する形になり、オールセーフでピンチが広がった。不運な形だったが、ここが大きなポイントだった。聖光学院は7回表に反撃に転じる。口火を切ったのはキャプテン・竹内啓汰選手のヒットだった。これがチーム初ヒット。キャプテンの一打に鼓舞され、鈴木来夢選手のタイムリーヒットですぐに同点に追いつく。聖光学院応援団で埋められた1塁側アルプススタンドは盛り上がったが、表攻撃の聖光学院にとって、7回裏の山梨学院の攻撃をゼロに抑えて、はじめて「同点に追い付いた」と言える状況。
大嶋投手、聖光学院守備陣に「ここが頑張りどころだぞ」と念を送ったが、7回裏に1点を勝ち越されてしまった。とはいえ、1点差ならまだ何とでもなる。しかし、8回裏にリードを広げられる。逆転を信じて声援を送るアルプススタンドに応えるように、最終回に粘りを見せ、ノーアウト満塁のチャンスをつくる。1点を返して意地を見せたが、反撃はここまで。2―6で敗戦した(ランニングスコア参照)。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 聖光学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | × | 6 |
「うちのエースなので」
試合後、聖光学院の斎藤智也監督はこう振り返った。
「相手の打線が強いことは分かっていた。序盤(の無失点)は想定以上で、6失点は想定内。勝つとしたら、それ以上に点を取らないといけないと思っていた。ただ、相手ピッチャーを捉えられなかった」
山梨学院の先発は2年生の菰田陽生投手。地方大会ではリリーフ登板がほとんどで先発は予想外だった。190㌢超の長身から投げ下ろす本格派右腕で、球速は140㌔台中盤、その日の球場の球速表示ではMAX147㌔だった。
斎藤監督によると、試合中、聖光学院の各バッターは「球速表示ほど速くは感じない。でも合わない」と話していたという。角度と球質が良かったということだろう。
7回にようやく菰田投手から1点を奪うが、その直後、山梨学院は菰田投手から左投げの檜垣瑠輝斗投手にスイッチした。斎藤監督は檜垣投手が先発で、菰田投手はリリーフと想定していたが、実際はその逆。意表を突かれた。
一方、聖光学院の大嶋投手は最後まで1人で投げ抜き8回6失点だった。斎藤監督は大嶋投手の投球内容を評価する。
「想定を上回る失点の少なさだった。7回まで2失点で粘れるとは思っていなかった」
交代は考えなかったのか聞くと、斎藤監督は「代えるとしたら、8回の4点目を取られたところだったかもしれない。だけど、大嶋に託したかった。うちのエースなので」と話した。
大嶋投手は体が大きいわけでもなく、球速も速くはない。それでも、変則フォームから繰り出される角度のあるボールと、テンポの良さ、抜群のコントロールで、全国トップレベルの打力を誇るチームと渡り合えることを示してくれた。試合終盤は相手打線に捕まったが、最後まで投げ切った。
聖光学院でエースナンバーを背負う重圧は計り知れない。私が取材やプライベートの観戦(応援)で聖光学院を見て強く感じるのは、ベンチ外の選手が〝戦力〟になっているということ。聖光学院野球部には毎年30人から50人の選手が入部してくる。一方で、大会でベンチ入りメンバーに入れるのは20人。毎年その中に下級生が1、2人、多い時だと3、4人は入ってくるから、3年生の約半数はメンバーに入れない。
そうなると、チーム内に不協和音が起こったり、最悪、メンバー入りできなかった選手が腐って不祥事を起こすような事態になっても不思議ではない。しかし、聖光学院ではそういう問題は起きていない。これは、そこに至るまでにチーム内での対話や、斎藤監督、横山博英部長らの指導が徹底されているから。
メンバー入りできなかった選手は、当然悔しいはず。それでも、悔しさを押し殺して、メンバー入りした選手をサポートする。選ばれたメンバーがそれで奮起しないわけがない。仲間の悔しさやさまざまな思いを背負い、チームの代表者であることを自覚して練習に取り組み、グラウンドに立つのだ。ましてや、チームのエースとなれば、背負うものは人一倍大きい。

3年生にとって負ければ終わりという中、斎藤監督の「大嶋に託したかった。うちのエースなので」という言葉は、そういったすべてを物語っているように感じた。「大嶋が打たれて負けるなら仕方がない」――監督や仲間たちにそう思わせることができるのがエースだ。
背負うものが大きいのはキャプテンも同じ。竹内キャプテンは「最後の最後まで自分たちの野球はできたけど、悔しいし、この仲間ともう野球ができないことが寂しい」と涙ながらに話していた。
聖光学院ナインが目指した「日本一」。いつのころからだろうか。聖光学院の選手が「優勝」「全国制覇」ではなく「日本一」と言うようになったのは。これは「甲子園で優勝する」ということだけではなく、「チームの歩みを含めて頂点に立つ」という意味が込められている。歩みという意味では「日本一」に値するチームだった。この思いは後輩たちに受け継がれていく。
私も、聖光学院が甲子園の優勝旗を持ち帰ってくる日が来ることを信じて応援し続ける。
天候との戦い
最後に、余談を2つ。
1つは天候との戦い。組み合わせが決まったのが8月3日。その時点で順調に行けば11日に試合が行われることになっていた。ただ、聖光学院の試合の日が近づくにつれ、天気予報は雨予想が強くなっていった。10日の試合が延期になり、この時点で聖光学院の試合は12日以降になることが決まった。結果的に12日に試合ができたが、その前日も雨予報で、試合ができるかどうか分からない状況だった。聖光学院は第1試合で8時開始だったから、前乗りの必要があり、ホテルを2回予約し直すドタバタ劇だった。
聖光学院の応援に限らず、その前後の試合の観戦者で、同じような思いをした人も多いのではないか。バスを手配して応援団を派遣する学校側も大変だったに違いない。
もう1つは、野球少年の甥っ子2人(小学6年生と中学2年生)と、どこが優勝するかという話で盛り上がった。SNSなどを含めて、そんな話で盛り上がれるのも甲子園の楽しさの1つ。筆者は最初、神村学園(鹿児島県)を挙げようと思ったが、「49番目の登場」のくじ(組み合わせ)を引き、そこは極端に勝率が低い。そこで、健大高崎(群馬県)を推した(聖光学院じゃないのかと突っ込まれそうだけど)。小学6年生の甥っ子は沖縄尚学、中学2年生の甥っ子は東洋大姫路(兵庫県)。沖縄尚学は優勝、東洋大姫路はベスト8まで勝ち進んだ。一方、健大高崎は初戦敗退、ちなみに神村学園も初戦敗退だった。甥っ子たちに完敗だったが、前評判通りにいかないのも高校野球の面白さと言える。