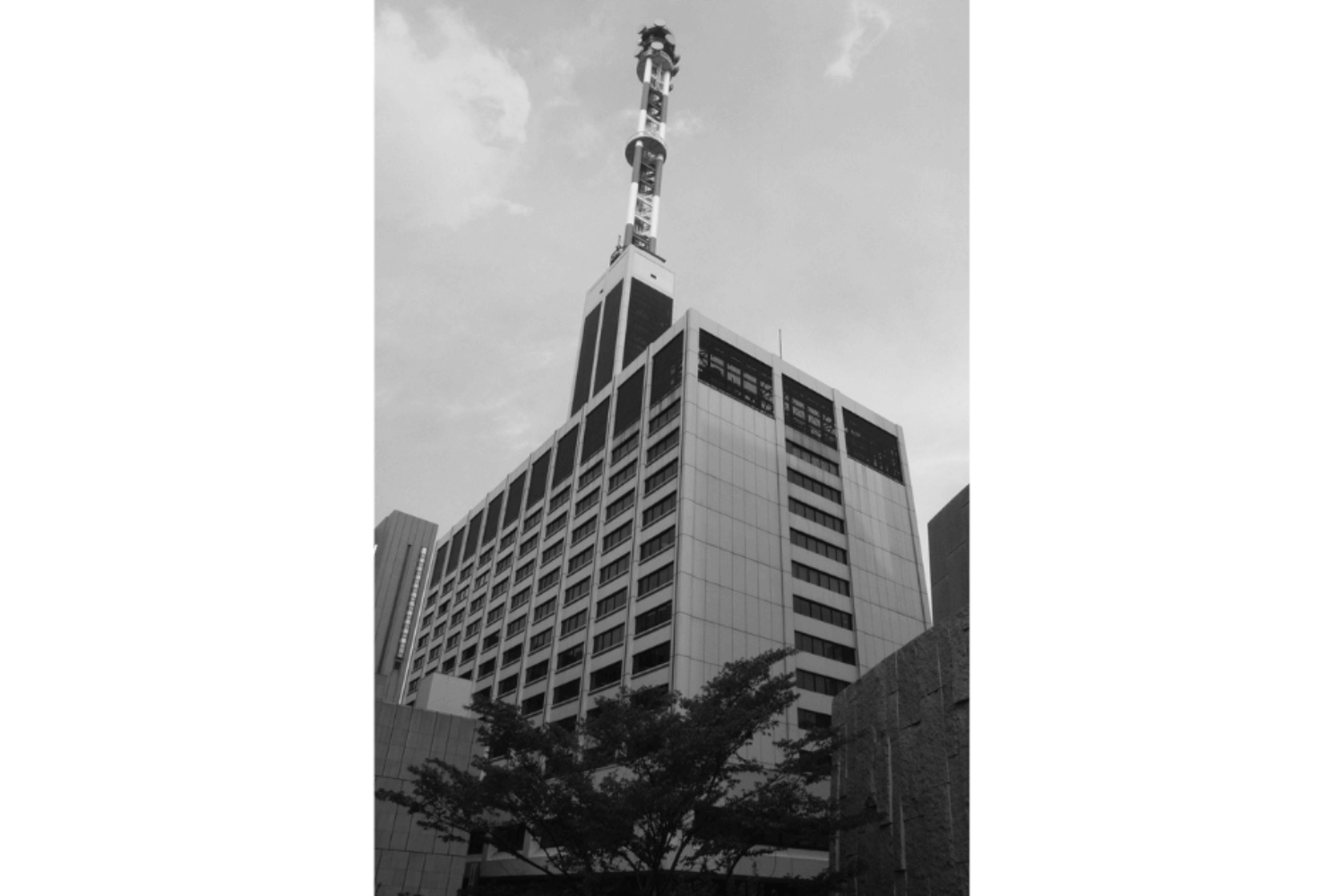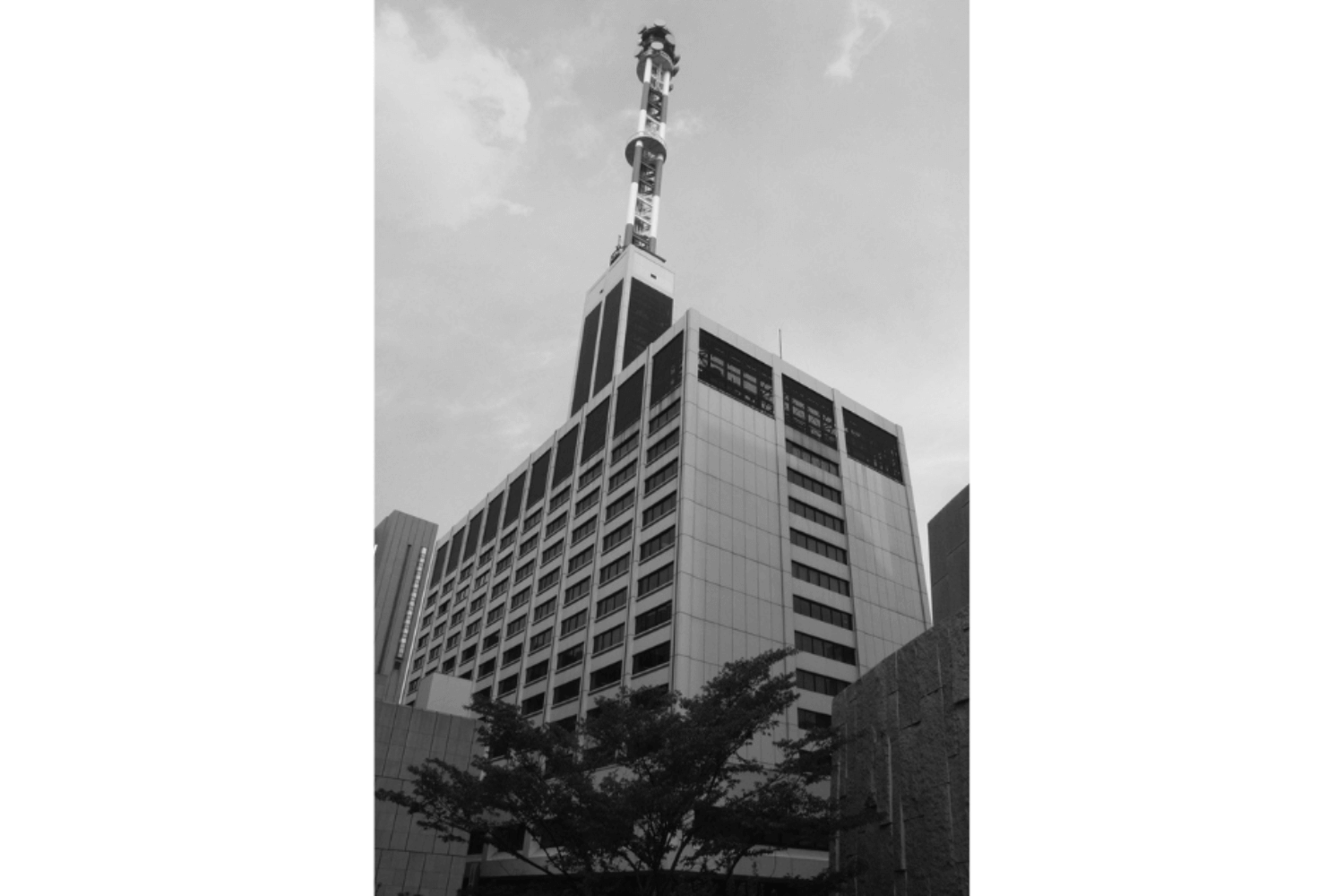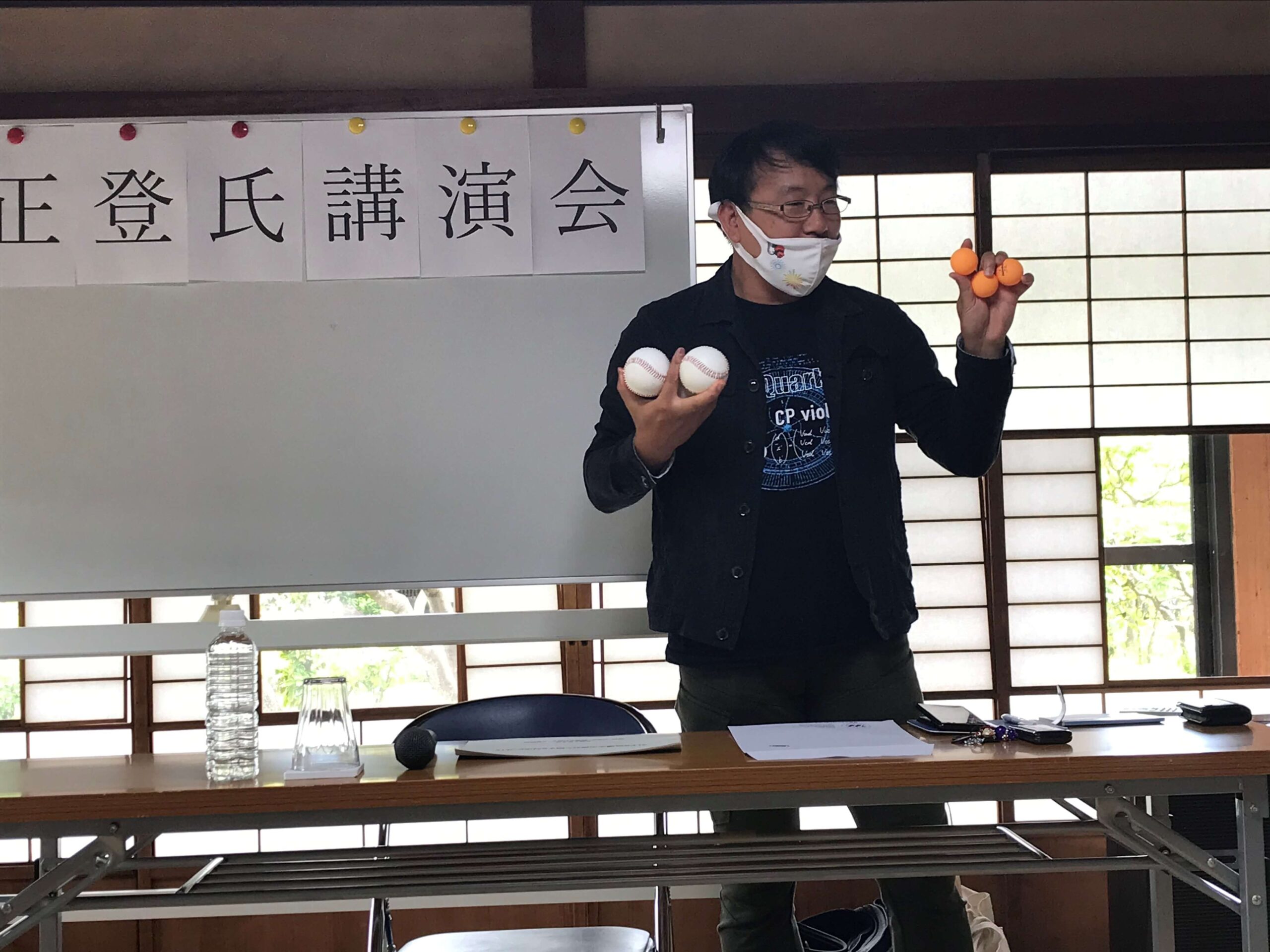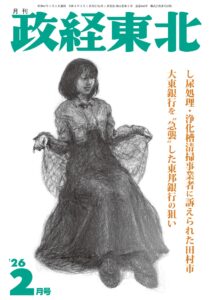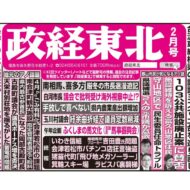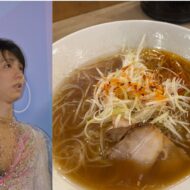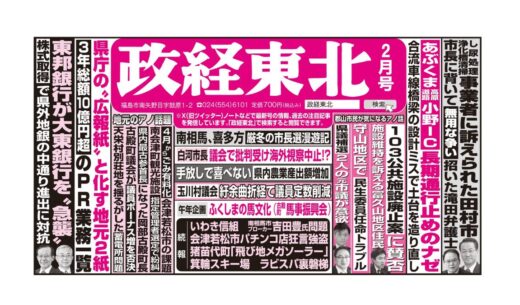原発事故から13年が経ち、帰還困難区域の避難指示が徐々に解除され、帰還も少しずつ増える。国主導で復興事業が行われ、それに伴って移住する人も増えた双葉郡のありようは変わりつつある。復旧事業や除染事業により居住者の構成が変わり、国の直轄地のような様相を帯びる中、福島国際研究教育機構(エフレイ)を置く浪江町の優位性が高まっている。
研究拠点置く浪江町に優位性
東京電力福島第一原発事故により自治体の全域或いは一部地域が避難指示対象となった12市町村に、いわき市、相馬市、新地町を加えた15市町村で国家プロジェクト「福島イノベーション・コースト構想」が本格化している。震災と原発事故による避難で失われた産業基盤と人口を回復させる目的があり、各市町村で関連施設が稼働するが、肝いりの福島国際研究教育機構(エフレイ)本部が置かれる浪江町を最重要視する流れができつつある。事業配分に不均衡を生じさせず、被災自治体がどのように連携していくかが課題だ。
地域の人口回復を図るには、研究機能と産業集積の車の両輪を機能させることがカギになる。特に、原発がある双葉郡は事故による放射能汚染が甚大で、帰還困難区域が残る。産業を支えるには人手が欲しいし、働ける産業がなければ人は来ない。
国が放射線量の高い地域が残る自治体に帰還と移住者の呼び込みを促進しているのは、避難者の意思を受けてもあるがイノベーション・コースト構想の担い手を確保したい背景もあるだろう。
障壁となるのが、帰還困難区域が固定化し居住環境が限られてしまうことだ。現在、帰還困難区域を抱えるのは南相馬市、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の7市町村。比較的線量の低いところを「特定復興再生拠点区域」(以下、復興拠点)とし、除染や各種インフラ整備をした。昨年11月の富岡町を最後に復興拠点の避難指示は全て解除。南相馬市は対象人口が少ないことから復興拠点を定めていない。
問題なのは、7市町村の帰還困難区域計約337平方㌔のうち、復興拠点に指定されたのは約27・47平方㌔で、帰還困難区域全体の約8%に過ぎないのに「復興」が進んでいるかのように喧伝していることだ。そもそも除染は原発事故の加害者である東電が負担すべきだが、全額国費で賄っている。
居住可能な区域は一部に限られるが、帰還困難区域の復興拠点外にさらに「特定帰還居住区域」を設けることで、徐々に広げられる余地が生まれた。特定帰還居住区域では、帰還意向のある住民が帰れるように国費で除染やインフラ整備をする。2月26日現在、大熊町(約4・4平方㌔)、双葉町(約0・5平方㌔)、浪江町(約7・1平方㌔)、富岡町(約2・2平方㌔)で計約14・2平方㌔。これで帰還困難区域の累計12%がいずれ避難指示解除される。ただし「住民の意向」を盾に、放射線量の高い部分があることを過小評価し居住区域を広げてはならない。
一部に帰還困難区域が設定されている自治体のうち、双葉郡の富岡、大熊、双葉、浪江、葛尾の5町村を見る。復興拠点を設け、帰還者は増えた。人数は各自治体がホームページで公表している数値を基にした。長期にわたる避難で、住民基本台帳に基づく人口と実際の居住者数は異なる。
富岡町は2月1日現在、町内居住者数は2335人。町内以外の県内には7473人、県外には1715人が避難し計9188人が帰還していない。住民基本台帳上は2月1日時点で1万1523人の住民がいる。同町には東電など廃炉作業に従事する企業の拠点があり、町内居住者には廃炉関係者が含まれる。
大熊町は2月1日現在、町内居住者は635人。住民登録がない居住者を含めた居住推計人口は1144人で45%が住民登録のない人。避難者が住民票を町外に移し、帰還後にそのままにしているとは考えにくく、居住者の半数近くが各種事業のために町外から訪れている人であることが伺える。県内への避難者が7732人、県外への避難者が2210人いる。住民基本台帳上の人口は1月末時点で9944人。
双葉町は1月1日現在、町内居住者は103人。内訳は帰還者41人、移住者62人。昨年12月末時点で、県内への避難者が3848人、県外への避難者が2695人(出生者含む)いる。住民基本台帳上の人口は1月末時点で5420人。
浪江町は1月末現在、町内居住者は2162人。震災時の町民は1406人が町内にいるから、35%が震災・原発事故後の移住者ということになる。約1万9000人の避難者がおり、うち約1万3000人が県内に避難。住民基本台帳上の住民は1月末時点で1万5109人。避難者は震災時の数字なので、住民基本台帳とずれがある。
葛尾村は2月1日現在、帰還者が322人、避難指示解除後の転入者が170人。県内への避難者は740人、県外への避難者は43人。帰還者、転入者、避難者の合計は1275人。住民基本台帳上の住民は2月1日時点で1274人。
経産省が気に掛ける吉田栄光・浪江町長

町村内居住人口を見ると、双葉郡の中で帰還が先行した富岡町と浪江町が2000人台と多い。中でも優位性が高まっているのが、エフレイがある浪江町だ。復興関連の仕事に従事する関係者が話す。
「吉田栄光町長は元県議会議長だったこともあり、イノベーション・コースト構想やエフレイに関わる経産省がその存在をやたら気に掛けているようだ。今年も3月11日に岸田文雄首相が福島を訪問する予定だが、今回も浪江を視察するかが話題になっているらしい。エフレイの効果は双葉郡全体に波及するが、『本部がある浪江ばかり優先するのか』という話になってしまう」
帰還者と移住者が増える一方で、見なくなったのが廃炉や除染に従事する作業員だ。彼らはいま、どこにいるのか。浜通りで土木工事業を営む男性は語る。
「原発や除染関連の作業員は広野町のホテルや民宿に集まっている。原発事故直後、除染作業と中間貯蔵施設への運び出しがあった時は相馬市、南相馬市はもちろん福島市、郡山市にも作業員がいた。いまは廃炉作業だけだから少なくなったよ」
震災直後に復旧や除染関連の作業が増えたことで、多くの作業員が夜の街に繰り出し、浜通りや中通りでは「復興バブル」が到来した。
「特に南相馬の原町は外国人女性がいるクラブが2020年くらいまでたくさんあったよ。韓国人やネパール人、モンゴル人の女性が接待していた」(同)
震災・原発事故直後は復旧や除染関連の作業がたくさんあったため、それを当て込んだ土木建設業者が県外から押し寄せた。ノウハウを身に付けた作業員が「これはもうかる」と独立して会社を興し、小規模業者の乱立につながった。いまは安定期から衰退(経営破綻)期に入る。
「ゼネコンのナワバリも固定化してきたと思う。大熊町が大林組、浪江町が安藤ハザマ、南相馬市小高区が大成建設といった感じ」(同)
国が多額の予算を投じ、「復興」が片付けられるように進んでいく。ベンチャーや移住者を呼び込み活性化につながっている一方で、地域の急激な変容に違和感を覚え「置き去りになっている」と感じる帰還住民がいることも訴えたい。