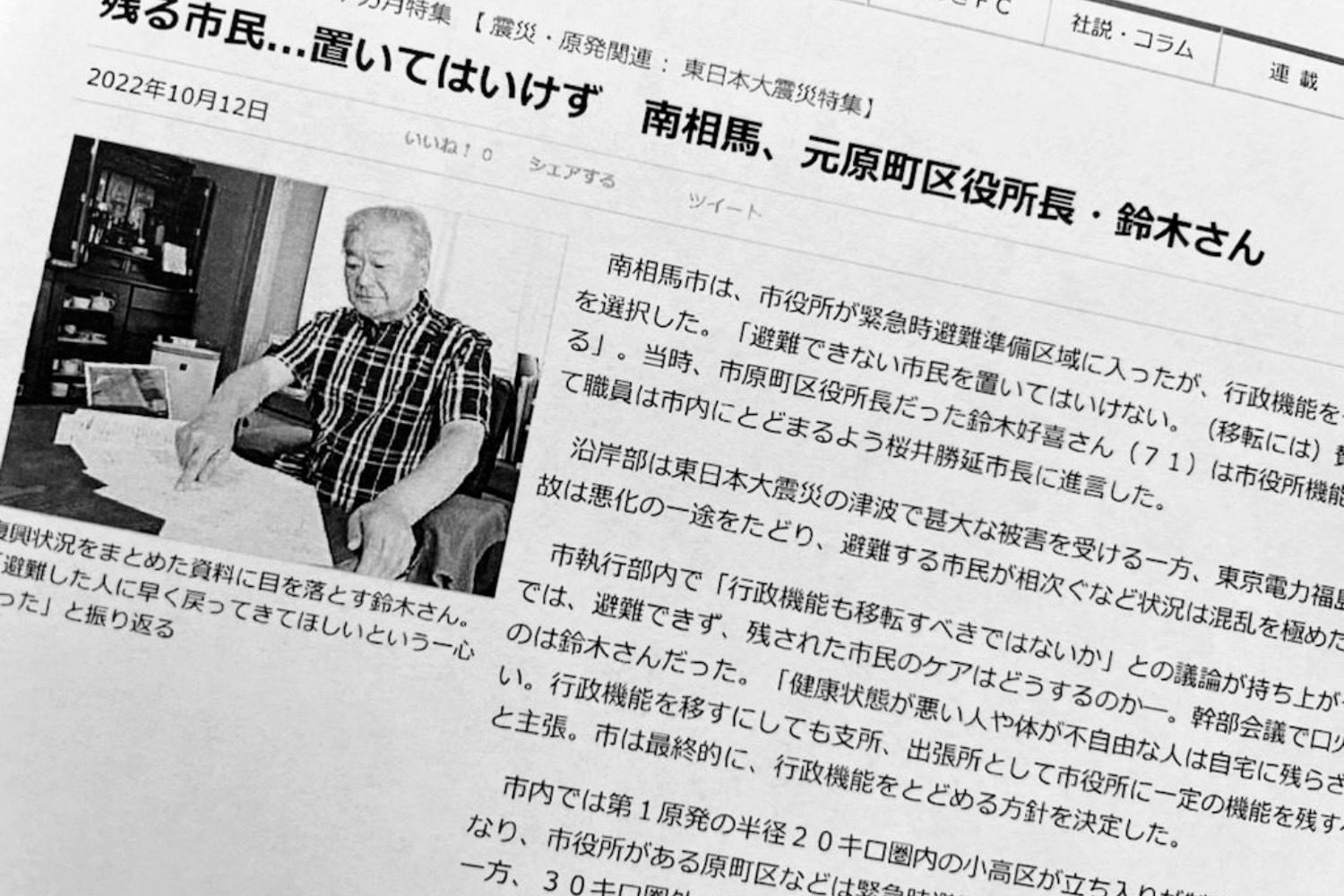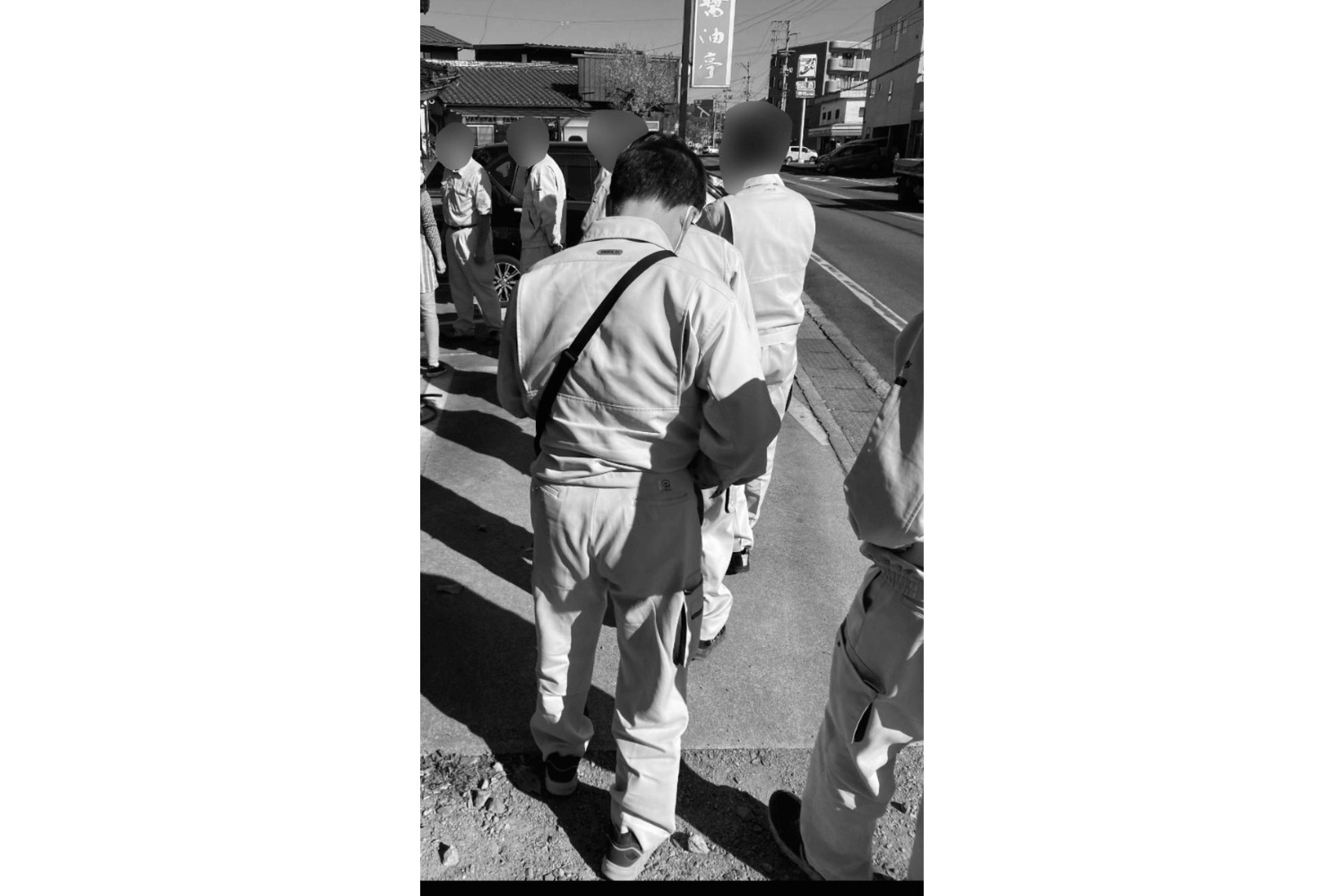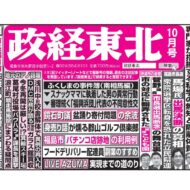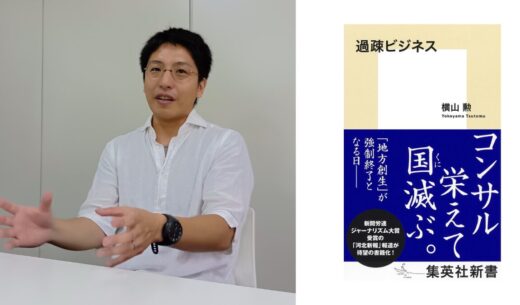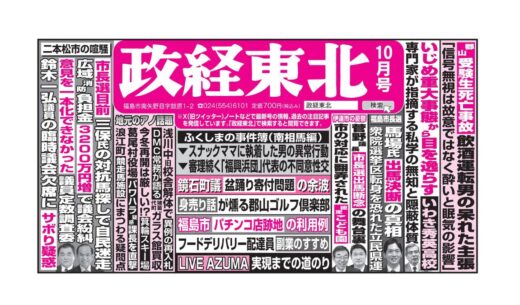シリーズでお伝えしている「立憲民主党研究」。3回目となる今号では、前立憲民主党県連代表の金子恵美衆院議員に話を聞き、かつての民主党政権の総括と反省点、そしてズバリ、立憲民主党が国民から何を求められているか、また国民のために何を為すべきと考えているのか等々を聞いた。
いまはまだ国民から「期待」はされていない。期待される政党に成長しなければならない。

金子氏は1965年生まれ。伊達市出身。カリフォルニア州立大学フレズノ校大学院修士課程修了。2000年に旧保原町議員に初当選し、2期目途中に合併により伊達市誕生後は同市議を務めた。
その後、2007年の参院選に民主党公認で初当選し、以降は活動の場を国政に移す。2013年の参院選では定数削減により、それまで議席を分け合っていた自民党の森雅子氏に敗れた。翌2014年の衆院選(福島1区)に民主党公認で選挙区では自民党の亀岡偉民氏に敗れたが比例復活当選。2017年の衆院選では無所属で立候補し、選挙区では初、通算2回目の当選を果たす。2020年に立憲民主党に合流し、同年10月に立憲民主党福島県連が設立されると、初代県連代表に就任。翌2021年の衆院選は立憲民主党公認で立候補し、3回目の当選を果たした。父・金子徳之介氏(故人)は旧保原町長、衆院議員を務めた。
民主党政権時代の第3次野田内閣(2012年10月から12月)では内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官を務めた。2022年9月に発表された立憲民主党の「次の内閣」ではネクスト農林水産大臣に選ばれている。
もっとも、実際に政権を取らなければ「次の内閣」はさして意味をなさない。もっと言うならば、まずは自身の議席を確保しなければ、すべて画餅になってしまう。
その点で言うと、金子氏は選挙区が変わり、読みにくくなった部分がある。いまの議席(旧1区)は福島市、伊達市、南相馬市、相馬市、伊達郡、相馬郡が選挙区だったが、新1区は南相馬市、相馬市、相馬郡が外れ、二本松市、本宮市、安達郡が加わった。
そこで、まずは新選挙区への思い、手応えについて聞いてみた。
「私は参院議員をしていたので、全県にいろいろな関わりを持って活動してきました。選挙区が変わりますが、心持ちが変わることはありません。ただ、危機感は常日頃から持っています。危機感は緊張感と言い換えることもできます。それはお預かりさせていただいている議席をいかに守りつつ期待に応えるかということに尽きます。また、私は県連代表をしていましたので、所属している政党を理解していただける人を増やしていくという活動をしければならないと思ってきました。そういう意味で、心持ちが変わるということはありませんが、まだ(新選挙区の有権者には)地元の国会議員といった認識は持っていただけていないと思いますので、皆さんにしっかりと認めていただけるように頑張っていきたいと思います。一方で、(旧選挙区の)浜通りの方々にも恩返しをしなければならないと思っています」
県内5選挙区に限ると、立憲民主党3勝、自民党2勝と互角以上に支持を得ている。その要因はどこにあるのか。
「私は、前々回は無所属で出ていますので、働きぶりを認めていただいているのかなと思います。立憲民主党はまだできたばかりの新しい政党です。まだまだ知られていない部分がありますが、(各候補者が)いままでの積み重ねがあったからここまで来ているのかなと思います。あとは、連合を中心とした5者協議ができているので、そこを維持できているということもあると思います」
政権を取るためには、県内のような状況を、もっと広範囲に広げていくことが必要になるが、その方策・戦略はあるのか。
「よく、もともと民主党だったものが(複数の政党に分かれ)バラバラになったと言われます。そういうことであれば、立憲民主党と国民民主党が歩み寄りながら1つになっていく方向になればいいといった話をよくしていて、私は無所属のときに『バラバラになった政党を1つになれるような接着剤になります』ということを言っていました。結果としては、一部、国民民主党、希望の党だった人が立憲民主党と合流して、接着剤の役割を果たせた部分もあります。ただ、残った方もおり、それぞれいろいろな考えがありますから、なかなか1つになっていくのは難しいことだと思います。福島県では連合を中心とした協力体制が築かれているので、中央では別の党派ですが、大きな選挙戦を戦うときは1つになれるという環境がつくられてきました。国民民主党にはここは譲れないという部分がありますし、立憲民主党にもあります。そうした中でも、県内では一緒にやっていけるところを確認しながら、政策協定を結んで推薦をいただくということができています。そこがあるから勝てているのかなと思います。そういう意味では1つのモデルではありますね」
都知事選の分析が必要
さらに、金子氏はこう続ける。
「都知事選の結果は、しっかりと分析しなければならないと思っていますが、福島県民のニーズと大都市のニーズは違うかもしれない。地域性もあるかもしれない。また、私が11年前(2013年)に参院選を戦ったときに、ネット選挙が解禁になりました。国民目線で考えたときに、それが上手く活用できていたか、あるいはできなかったか。そういったところも検証していかなければなりません。もっとも、私はネットは全然上手に使えていなくて、昔ながらの足を運んでやる政治、後援会の皆さんの作り上げる政治というのが中心ですが、それだけでは生き残れないと思っています」
7月7日に投開票された東京都知事選は現職・小池百合子氏が291万票余を獲得し、3選を果たした。立憲民主党は共産党とともに蓮舫氏を支援したが、128万票余で小池氏に遠く及ばなかったばかりか、3位に終わった。大敗である。「ここで勝利し、次期衆院選での政権交代に向けて弾みを付ける」と目論んでいただけに、大誤算だった。次期衆院選に向けては、まずはその検証、そのうえでの対策が必要になる。
さてここからがこのシリーズの本題とも言える部分。いまの自民党にこのまま政権を任せてもいいとは思えないが、かといって立憲民主党に託そうという感じもない。国民の記憶にかつての民主党政権への失望が残っているからだ。当時の民主党の政権運営の問題点や反省点については、どのように考えているのか。
「私も民主党政権時代に短い期間ではありましたが、内閣府大臣政務官、復興大臣政務官をさせていただきました。政権を取る前はすごい議論をして、それを積み重ねて政策づくりをしていました。実際に政権を取って、その後震災が起きて、というところから、実現できたところもありましたが、そうでないところも出てきたように思います」
「脱官僚」宣言の失敗

一方で、金子氏は「いまの政党は違う政党で、本当はそこを理解していただきたいという思いはあります。例えば、小熊(慎司)先生は民主党議員ではありませんでした」とも話した。そのうえで、こう続けた。
「もちろん、過去の失敗の反省はしっかりとやっていかなければなりません。これは民主党であろうと、どこであろうとそうです。それはいち政治としても、いち人間としても同じです。失敗から何を得て、どういう反省をして、それを教訓に、新しい政党の中で何をしてくれるかを示していかなければなりません。ただ、民主党政権がすべて悪と捉えられているような印象もありますが、精一杯やった、やり尽くしたと思うんです。何が失敗だったかというと、官僚の皆さんと対峙してしまっている印象を持たれたこと。私からすると、そうではなかったと言いますか、本当に短い期間ではありましたが、内閣府大臣政務官、復興大臣政務官をさせていただいた中で言うと、優秀な方々の力を借りながら、いい政策づくり、我々が考えた政策の実現をやってきたつもりではあります。ただ、一部、そうではない見え方もしたものもあります」
民主党政権は「政治主導」、「脱官僚」ということを掲げていた。つまり、官僚任せではなく、政治が責任を持つということだが、政策を実現するためにはその実務を担う官僚の力は欠かせない。にもかかわらず、官僚と対立構造が生まれ、物事が進まないといった印象を与えたのは確かだ。
その点について、金子氏は「誤解されている部分もあった」というが、だとするならば情報発信の仕方に問題があったということになろう。物事を動かそうとしたら、いかに多くの理解を得るか、そのためにどのような情報発信をするかが重要だが、その部分が欠けていた。もっと言うと、「政治主導」、「脱官僚」は結構だとしても、それを声高に言う必要があったのかということにもなる。そこは反省しなければならない。
「民主党時代に創設した制度で、いまでも『あれは良かった』と言われることもあります。ただ、予算の確保が十分でない中で進めるなど、経験が足りなかった部分もあります。もう少し経験を積ませていただければ、国民の皆さんにいい政府だと言っていただけるようなものもあったと思います。ただ、それをきちんとプレゼンできていないと言いますか、皆さんにお示しできていない部分もありますから、そこはなおさら反省しなければなりません」
何を為すべきか

最後に、「ズバリ立憲民主党が国民から何を求められているか、また国民のために何を為すべきと考えているのか」と聞くと、こう応じた。
「立憲民主党がどれだけ期待されているかというと、ご承知のように支持率はそれほど高くありません。いま、『私たちは国民の期待を背負っています』と言っても、笑われてしまうような状況なのかなと思います。ですから、期待をされるような政党に成長していかなければならないということに尽きます。そのうえで私たちは、多様性を重んじながら、例えば社会保障の問題についても、議論を積み重ねてきて、そこにしっかりと予算を投じるべきだと申し上げています。実質賃金が上がらない状況が続いており、苦しんでいる人がいる中で、格差をなくすような政策づくりをしていかなければならないと思っています。あとは『政権交代を目指します』と言っても、簡単なことではありません。ですから、国民の皆さん、有権者の皆さんがいる場所に足を運んで、その場で私たちの思いを伝えていくことの必要性を感じています。いま、私たちが試されているのは、立憲民主党の国会議員のメンバーが、本当の意味で国民の皆さんの代表者であると言えるような考えを持ち、日本をしっかりと改革していけるか、ということだと思います。ですから、本当の意味での代表者が立憲民主党の中にいるということを認めてもらえるように、務めていきたいと思っています」
一方、「政治とカネ」の問題にも言及した。
「政治とカネの問題はずっと言われ続けてきたことです。この間、命がけで政治改革を目指してきた人がいますが、それでも変わりませんでした。『体質』というものが根付いてしまっています。申し訳ないですが、いまの与党に、国民のために働いている代表者がいるとは思えません。政治とカネの問題は、国民の皆さんが大きな関心を持っていることだと思いますので、しっかりと浄化していかなければならないと思います。改正政治資金規正法も、私たちの思いとは別になってしまいました。そういった部分も含めて、陳腐な言い方かもしれませんが、クリーンな政治、当たり前の政治に変えていくということを、私たちはしなければならないと思っています」
「政治とカネ」の問題に限らず、いまの自民党が決していいとは思えない。かといって、立憲民主党に任せられるかと言うと、それも疑問符が付く。この間の自民党の体たらくは野党にも責任がある。端的に言うと、自民党は、「多少の下手を打っても取って代わられることはない」と思っているに違いない。つまり、野党は自民党に対して、「下手したら下野してしまう」、「今度失政したら、立憲民主党に政権を奪われてしまう」といった緊張感を与えられていないということだ。
無党派層の大部分は「自民党でも、立憲民主党でも、それ以外でも、どこでもいいから、自分たちの商売や暮らしが良くなるような政治を」と思っているはず。下からの突き上げが上にいる者に危機感を与え、その結果、全体の質が向上する、というのは政治に限らず、どんな組織にも当てはまること。あなたたち(自民党)がダメなら、代わり(立憲民主党)はいますよ、ということを知らしめなければならないのだ。立憲民主党には、まずはその域まで到達することを求めたい。