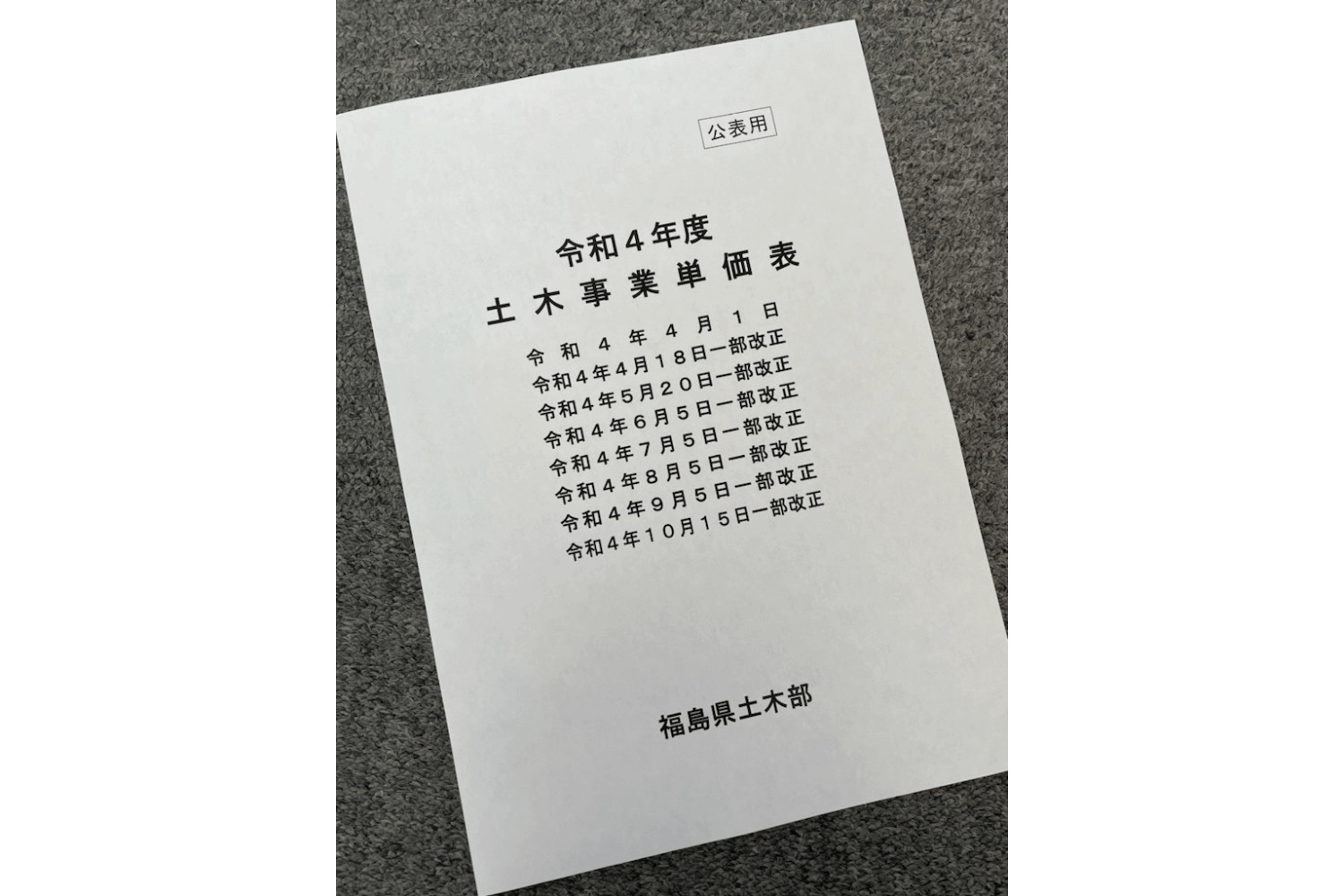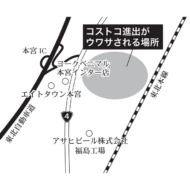ノンフィクション作家 岩下明日香
元自衛官の五ノ井里奈さんが、陸上自衛隊郡山駐屯地の部隊内で受けた性被害を実名告発した後、マスコミと世論が関心を持つまでには時間を要した。告発当初から取材し、五ノ井さんの著書『声をあげて』の構成を手掛けたノンフィクション作家が振り返る。
名もなき元自衛官の女性が閉塞的な日本社会に大きな風穴を開ける。

台風接近により、天候が崩れるという天気予報に憂いた。電車が動かなくなったら東京から郡山までたどり着けないかもしれない。「本当に彼女が自衛官だったかもわからない」「交通費は出さない」と編集部が躊躇していた取材のため、自腹を切った新幹線の切符が紙くずになるかもしれない。そんな心配は杞憂だった。
2022年7月5日、昼過ぎに降り立った郡山は、早足で夏がやってきたかのように汗ばむ真夏日だった。
郡山を訪れたきっかけは、元自衛官・五ノ井里奈さんに会うためだ。五ノ井さんは、自衛隊を6月28日に退官し、その翌日にユーチューブ『街録チャンネル』などの動画を通じて自衛隊内で受けた性被害を告発していた。瞬く間にソーシャルメディアで拡散され、それが雑誌系ウェブメディアの業務委託記者をしていた筆者の目に留まったのだ。
動画のなかの五ノ井さんは、取り乱すことなく、卑劣な被害の経緯を淡々と語っていた。当時、まだ五ノ井さんは22歳という若さ。純粋な眼差しとあどけなさが残っていた。
五ノ井さんを含め、性犯罪に巻き込まれた被害者を記事で取り上げるとき、証言だけではなく、裏取りができないと記事化は難しい。説得力のある記事でなければ、被害者は虚偽の証言をしているのではないかという疑いの目が向けられ、インターネット上で誹謗中傷が膨らむという二次被害のリスクも孕む。
実際に記事にするとはあらかじめ約束できない取材だった。もし記事にできなかったら、追いつめられている被害者を落胆させてしまうから。懺悔すれば、最終的に記事を出すことができなかったことは一度ではなく、その度に被害者を傷つけているような罪悪感に駆られるのだ。
五ノ井さんにも確定的なことを約束せずにいた。被害者の証言を裏付けるものを見つけられるのか。話を聴いてみないとわからないと思い、郡山を目指した。
真夏日の郡山駅に到着してすぐに駅周辺を探索した。当時はまだコロナ禍で、駅ビルのカフェにはちらほら人がいる程度。人目があるとナイーブな話はしにくいだろうと思い、静かな場所を求めて駅の外へ出た。
すると、駅前にある赤い看板のカラオケ店が目に飛び込んできた。コロナ禍の影響で、カラオケ店ではボックスをリモートワーク用に貸し出していた。カラオケボックスなら防音対策がしっかりして静かだろうと思い、店員に料金を聞いてから、早々に駅に引き返し、待ち合わせ場所である新幹線の改札口前で待機した。
改札を出て左手にある「みどりの窓口」付近から発着する新幹線を示す電光掲示板を眺めていると、カーキ色のTシャツに迷彩ズボンをはいた男性がベビーカーを押して、改札前で足をとめ、妻らしき女性にベビーカーを託した。改札を通っていく妻子を見送る自衛官らしき男性が手を振って見送っていた。
近くに駐屯地でもあるのだろうか。それくらい筆者は自衛隊や土地に疎かった。当時はまだ、五ノ井さんが郡山駐屯地に所属していたことすら知らなかった。
しばらくすると、キャップを目深に被った青いレンズのサングラスをかけた人がこちらに向かって歩いてきた。半袖に短パンのラフな格好。
「あっ!」
青いサングラスの子が五ノ井さんだとすぐにわかった。五ノ井さん曰く、駐屯地が近くにあり、隊員が日ごろからウロウロしているため、サングラスと帽子で隠していたという。地方の平日の昼過ぎ、しかもコロナ禍で人の出が減り、わりと閑散としていた駅では、青いサングラスがむしろ目立っていた。「地元のヤンキー」が現れたかと思い、危うく目をそらすところだったが、大福のように白い肌と柔らかい雰囲気は、まさしく動画で深刻な被害を告白していた五ノ井さんであった。
必ず書くと心に決めた瞬間
五ノ井さんは、カラオケ店のドリンクバーでそそいだお茶に一口もつけずに淡々と自衛隊内で起きていたことを語った。淡々とではあるが、「聴いてほしい、ちゃんと書いてほしい」と必死に訴えてきてくれた目を今でも覚えている。会う前までは不確定だったが、必ず書くと心に決めた瞬間があった。五ノ井さんがこう言い放った瞬間だ。
「ただ技をキメて、押し倒しただけで笑いが起きるわけがないじゃないですか」
五ノ井さんは3人の男性隊員から格闘の技をかけられ、腰を振るなどのわいせつな行為を受けた。その間、周囲で見ていた十数人の男性自衛官は、止めることなく、笑っていた。男性同士の悪ノリで、その場に居合わせたたった1人の女性を凌辱していた場面が筆者の目に浮かんだ。目の奥が熱くなって、涙がわっと湧き溢れて、マスクがせき止めた。
自衛隊という上下関係が厳しく、気軽に相談できる女性の数が圧倒的に少ない環境で、仲間であるはずの隊員を傷つける行為。どうして周囲の人が誰も止めに入らないのか。閉ざされた実力集団において、自分よりも弱い者を攻撃することで、自分は強いという優位性を誇示したかったのだろうか。
ときに力の誇示は、暴力に発展する。国防を担う自衛隊は、国民を守るために「力」を備える。だが、それがいとも簡単に「暴力」に変わり、しかも周囲は「そういうものだ」とか「それくらいのことで」と浅はかに黙認する。そして一般社会の感覚とはかけ離れていき、集団的に暴力に寛容になり、エスカレートしていくのではないだろうか。
閉ざされた環境からして、被害者は五ノ井さんだけではないはずだ。取材を続ける意義は大きいと確信した。カラオケボックスにある受話器が「プルルルル~」とタイムリミットを知らせてきたが、2回ほど延長してじっくり話を聴いた。
五ノ井さんがユーチューブで告発してから2週間後、筆者の書いた記事は『アエラ』のウェブ版で配信された。すると、瞬く間に拡散され、同日中には野党の国会議員が防衛省に「厳正な調査」を要請し、事態が大きく動き出した。
さらに五ノ井さんは、防衛大臣に対して、第三者委員会による再調査を求めるオンライン署名と、自衛隊内でハラスメントを経験したことがある人へのアンケート調査も実施。署名を広く呼び掛けるために東京都内で記者会見の場を設けた。オンライン署名は1週間で6万件を突破し、署名サイトの運営者は「個人に関する署名でここまで集まるのはこれまでになかった」というほどの勢いだ。五ノ井さんのSNSのフォロワーも驚異的に伸び、同じような経験をしたことがあるという匿名の元隊員からの書き込みをも出てきた。
だが、現実は厳しかった。7月27日に開いた記者会見に足を運ぶと、NHKの女性記者1人だけ。遅れて朝日新聞の女性記者がもう1人。そして筆者をあわせて、マスコミはたったの3人だった。真夏に黒いリクルートスーツを身にまとった五ノ井さんは、空席の目立つ記者席に向かって、声を振り絞った。
「中隊内で隠ぺいや口裏合わせが行われていると、内部の隊員から聞いたので、ちゃんと第三者委員会を立ち上げ、公正な再調査をしてほしいです」
マスコミの反応が薄かった理由
静かに終わった会見後、五ノ井さんはコピー用紙に書き込んだ数枚のメモを筆者に差し出した。報道陣から質問されそうなことを事前にまとめ、答えられるように用意していたのだ。手書きで何度も書き直した跡が残っていた。なのに、ほとんど質問されなかった。結局、五ノ井さんのはじめての会見を報じたのは、筆者だけだった。
SNS上では反響が大きかったにもかかわらず、当初、マスコミの反応は薄かった。理由はおそらく2つ考えられる。1つ目は、五ノ井さんが強制わいせつ事件として自衛隊内の犯罪を捜査する警務隊に被害届を出したものの、検察は5月31日付で被疑者3人を不起訴処分にしていたから、司法のお墨付きがない。2つ目は、自衛隊に限らず、大手マスコミ自体も男性社会かつ縦社会でハラスメントが起こりやすい組織構造を持っているから、感覚的にハラスメントに対して意識が低い。
一度不起訴になった性犯罪を、あえて蒸し返す意義はどこにあるのか。昭和体質の編集部が考えることは、筆者もよくわかっている。刑事事件で不起訴になったとしても、警務隊や検察が十分な捜査を尽くしていなかった可能性があるにもかかわらず。
マスコミの関心が薄い反面、ネット上では誹謗中傷が沸き上がった。署名と同時に集めていたアンケート内には殺害予告も含まれていた。心無い言葉の矢がネットを通じて被害者の心を引き裂く「セカンドレイプ」にも五ノ井さんは苦しみ、体調を崩しがちになった。それでも萎縮することなく、五ノ井さんは野党のヒアリングに参加した。顔がほてり、目がうつろで今にも倒れそうな状態で踏ん張っていた。
8月31日に市ヶ谷に直接出向き、防衛省に再調査を求める署名とアンケート結果を提出。この時にやっとテレビも報じはじめた。少しずつマスコミと世論が関心を持ちだし、防衛省も特別防衛監察を実施して再調査に乗り出す。
そのわずか1カ月後の9月29日、自衛隊トップと防衛省が五ノ井さんの被害を認めて謝罪する異例の事態が起きた。この日、五ノ井さんから「パンプスがこわれた」というメッセージを受け取っていた。防衛省から直接謝罪を受けるため、急いで永田町の議員会館に向かっている途中で片方のヒールにヒビが入ったらしい。相当焦って家を出てきたのだろう。引き返す時間がないため、そのまま議員会館に行くという。
「足のサイズは?」
「わからないです。二十何センチくらい。全然これでもいけるので大丈夫です!」
筆者も永田町に急いでいた。ヒールにヒビが入ったというのが、靴の底が抜けて歩けないような状態を想像し、それはピンチと思い、GUに駆け込んで黒のパンプスを買ってから議員会館に向かった。到着して驚いたのが、ほんの1カ月半前までは大手メディアからほぼ注目されていなかったのに、この時は立ち見がでるほど報道陣で会場が埋め尽くされた。議員秘書経由でパンプスは五ノ井さんに届けられたが、すぐに謝罪会見は始まり、履き替える時間もなかったのか、ヒビの入ったヒールのまま五ノ井さんが会場に入ってきた。防衛省人事教育局長と陸幕監部らは、五ノ井さんと向かい合うようにして立ち、頭を下げて謝罪すると、五ノ井さんも小さく頭を垂れた。
郡山で取材をした時には、淡々と被害を語っていた五ノ井さんだったが、この日は悔しさがにじみ出るように目が赤かった。防衛省・自衛隊に向けて言葉を詰まらせた。
「今になって認められたことは……、遅いと思っています」
もし自衛隊内で初動捜査を適切に行っていたら、被害者が自衛隊を去ることも、実名・顔出しすることもなく、誹謗中傷に苦しむこともなかっただろう。
後日、五ノ井さんはばつが悪そうに言うのだ。
「パンプス、ぶかぶかでした」
100円ショップで中敷きを買って詰めてもぶかぶかですぐ脱げるようだ。その場しのぎで買った安物を大事に履こうとしてくれていた。
裁判所を出る被告3人を見届ける

防衛省・自衛隊がセクハラの事実を認めてからも、五ノ井さんの闘いは続く。10月には加害者4人からも対面で謝罪を受け、12月には5人が懲戒免職になった。
さらに、不起訴になった強制わいせつ事件を郡山検察審査会に不服申し立てをし、2022年9月に不起訴不当となり、検察の再捜査も開始。2023年3月には不起訴から一転、元隊員3人は在宅起訴された。6月から福島地裁で行われていた公判で、3人はいずれも無罪を主張。五ノ井さんは初公判から福島地裁に足を運び、被告らや元同僚の目撃者らの発言に耳を傾けた。そこにはいつも、実家の宮城県から母親が駆けつけていた。
4回目の公判。被告人質問を終えた被告3人が裁判所から出ていく姿を、母親と筆者は見届けた。
「親が娘の代わりに訴えることはできるんでしょうか……」
涙を目に溜めながら言う母親に返す言葉が見つからず、背中をさすった。被告の1人が、五ノ井さんを押し倒して腰を振った理由を「笑いをとるためだった」と公判で発言したのを、母親も間近で聞いていた。被告に無罪を主張する権利があるとはいえ、被害者はもちろん、その家族もどれほど心をえぐられたことか。それでも親子は半年間にわたるすべての公判を傍聴し続けた。
福島地裁は12月12日、被告3人にそれぞれ懲役2年執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。
被害から2年以上が経過し、五ノ井さんは現在24歳。希望と可能性に溢れていたはずの20代前半を、被害によってすべてを奪われ、巨大組織と性犯罪者と対峙してきた。その姿にいま、世界が目を向けている。
英『フィナンシャル・タイムズ』による「世界で最も影響力がある女性25人」を皮切りに、米誌『タイム』は世界で最も影響力がある「次世代の100人」に、英公共放送BBCも「100人の女性」(2023年)に五ノ井さんを選出した。
判決の翌日、外国特派員協会で会見を開いた五ノ井さんは、前を向いて堂々と語った。
「世の中に告発してから約2年間、自分の人生をかけて闘ってきました。被害の経験は必要ありませんでしたが、無駄なことは何一つありませんでした。誹謗中傷も、公判も、人との関わりも、そのすべてが自分の人生を鍛えてくれる種となり、生きていく力に変わりました。私にとってはすべてが学びでした」
閉塞的な社会に風穴を開けた功績は、ロールモデルとして人々に勇気を与えていくだろう。
いわした・あすか ノンフィクション作家。1989年山梨県生まれ。『カンボジア孤児院ビジネス』(2017、潮出版)で第4回「潮アジア・太平洋ノンフィクション賞」を受賞。五ノ井里奈さんの近著『声をあげて』(2023、小学館)の構成を務める。現在はスローニュースで編集・取材を行う。