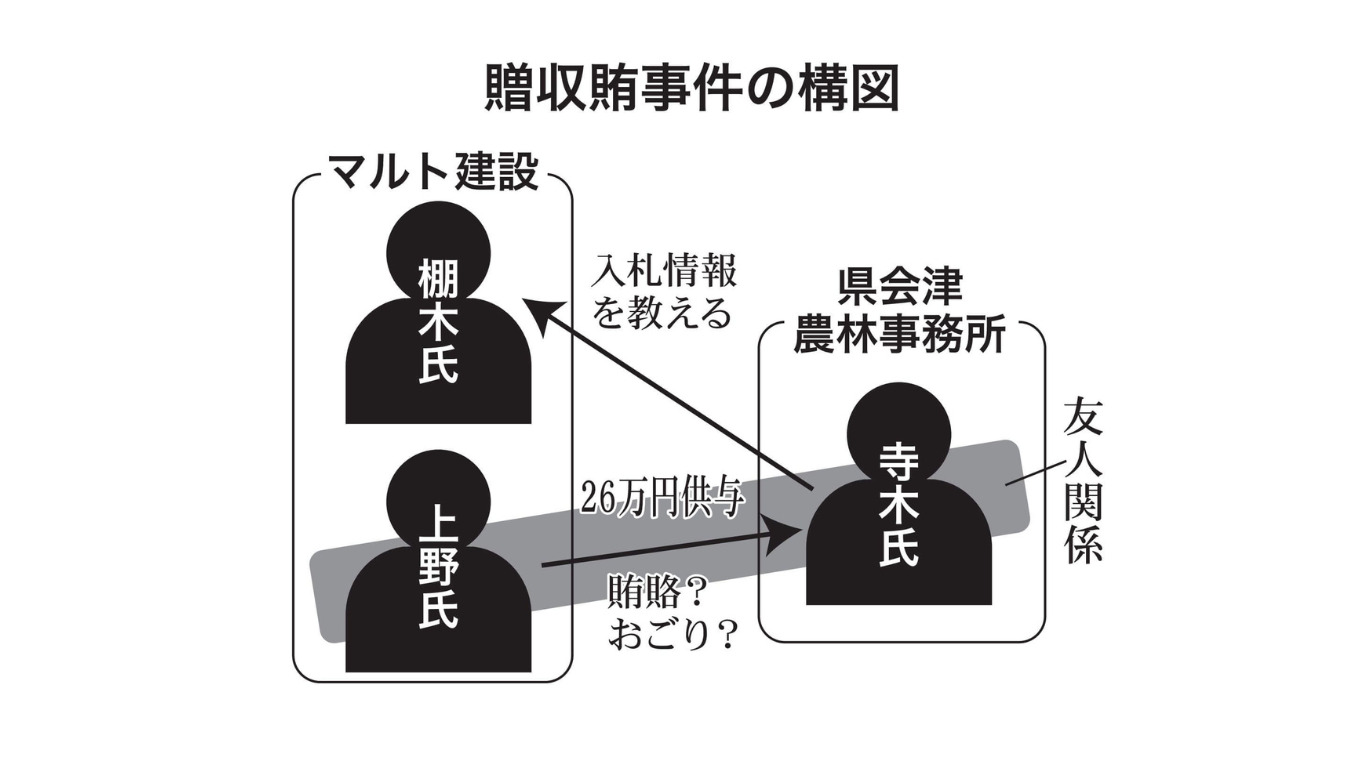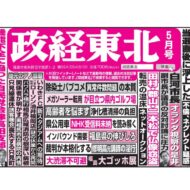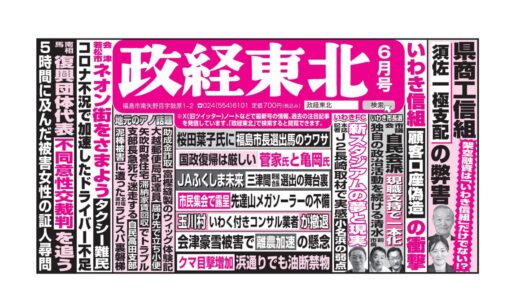阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)で行われる「第97回選抜高校野球大会」(通称・センバツ、3月18日開幕)の出場32校を決める選考委員会が1月24日、毎日新聞大阪本社で開かれ、聖光学院が選出された。センバツは3年ぶり7回目の出場になる。同校は出場校を決める際の重要な参考資料になる秋季東北大会で7年ぶり2度目の優勝を果たしており、出場は確実な情勢だったが、正式に決まり、気持ちを入れ直してリベンジの機会に燃えている。(末永)
センバツ出場決定

センバツ出場校発表当日、伊達市の聖光学院高校第一校舎礼拝堂には、多くの報道陣が詰めかけた。発表は15時半からだが、15時前には選手たちも礼拝堂に入り、会場に設置されたテレビを前に「その時」を待っていた。最初に21世紀枠、一般選考は北から順に発表された。
聖光学院の吉報は15時40分ごろ。画面越しの選考委員が「(東北地方の)1校目は聖光学院」と述べ、選考理由を語り出す。しかし、大きな歓声が上がるわけでもなく、静かに選考委員の説明を聞く。
説明が終わったところで、新井秀校長がお祝いの言葉とエールを送り、斎藤智也監督と竹内啓汰主将が決意を述べた。
その後はグラウンドに移動し、監督・選手らが写真撮影や取材対応した。取材する側の本誌が言うのもおかしな話だが、「監督・選手は大変だな」と思ってしまう。ただ、甲子園に出場するのはそれだけのことでもある。選手たちはそれを実感したのではないか。


さて、冒頭(リード文)で、「リベンジの機会に燃えている」と書いたが、斎藤監督も「リベンジじゃないけど、選手個々がどれだけ自分の力を発揮できるか。もっともっとアグレッシブになってほしい」と述べていた。
春の舞台は聖光に合う
ここで言うリベンジは明治神宮大会を受けての言葉だ。聖光学院は昨秋の東北大会で、仙台育英(宮城県)、青森山田(青森県)などの強豪校に勝利して優勝を決めた。11月には聖光学院のほか、北海道、関東、東京、東海、北信越、近畿、中国、四国、九州の全国10地区のチャンピオンチームが集まる明治神宮大会に出場した。
この大会で、近畿地区優勝の東洋大姫路に0―10の5回コールドで大敗した。東洋大姫路は、神宮大会の優勝候補にも挙げられ、特にエースの阪下漣投手は大会ナンバーワンと評されていた。強敵であったのは間違いないが、ここまでの大敗は予想外だった。甲子園常連校と言われるようになってから、初めてと言っていいくらいの屈辱だったのではないか。

聖光学院のグラウンドのスコアボードには、「2025 春53 夏168」という数字が掲げられていた(写真)。センバツ開幕まで53日、夏の福島県大会開幕まで168日ということを示している。これはセンバツ出場校発表日の1月24日時点の数字で、毎日そこから減算していき、来たるべき日に向けて鍛錬を積んでいくという意味がある。この掲示は例年の光景(センバツ出場の可能性がない場合は春の数字は掲示していない)。
ただ、今年はその横に、神宮大会のランニングスコアも掲示されていた。これはあの悔しさを忘れないということにほかならない。そういう意味で「リベンジ」なのだ。
高校野球は冬季間の対外試合が禁止されている。解禁になるのは3月の第一土曜日で、これはセンバツに出る・出ないに関係なく適用される。対外試合解禁からセンバツまではわずかな期間しかない。つまり、実践練習が少ない中で大会に入っていかなければならない。
とりわけ、バッターは調整が難しい。野球はピッチャーがボールを投げたところからプレーが始まる。ピッチャー主導で、バッターは受け身の立場。そのため、バッターの方が実践感覚を養うのに時間を要する。当然、対外試合ができない中でも、チーム内の紅白戦などで実践練習はするだろうが、やはり特徴などを知り尽くした自チームのピッチャーではなく、他校のピッチャーの「生きたボール」を見ないと、目と体が慣れない。
もっと言うと、夏は7月ごろから各都道府県大会が行われ、8月に甲子園大会に入っていくが、センバツは秋季大会から4、5カ月日程が空く。そのため、ピッチャーはフレッシュな状態で甲子園に乗り込んでくる。さらに、気温の関係で春は1試合をこなした後の疲労感、そこからの回復も夏に比べたら全然違う。
そういった諸々の理由から、春はピッチャー有利、バッター不利の投高打低になりやすい。
その点で言うと、今年の聖光学院はピッチャーを中心に守り勝つスタイル。もともと守備や走塁を鍛え、小技を駆使して勝ち上がる「スモールベースボール」が得意なチームだけに、春(センバツ)の舞台は合うだろう。リベンジに向け、機は熟したと言える。