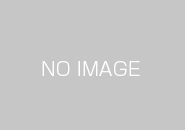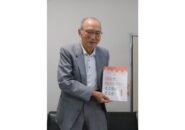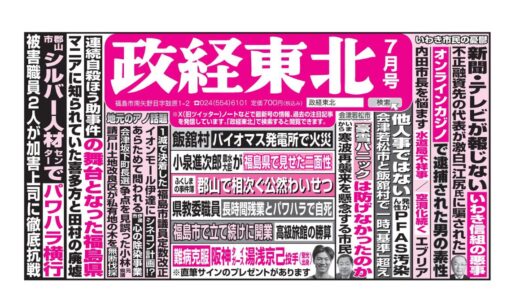浪江町社会福祉協議会を今年3月に退職した職員が、町社協に不利益処分の撤回を求め、地裁いわき支部に提訴したことが分かった。処分撤回を求めているのは、本誌が2022年11月号で報じた、複数の職員からパワハラ行為を指摘されていた元職員だった。
団体交渉後に相次いだ職員の退職

本誌は2022年11月号の記事「浪江町社協 パワハラと縁故採用が横行」で、複数の職員や町関係者の情報を基に浪江町社会福祉協議会事務局内でパワハラに悩む職員がいることを報じた。一部を抜粋する。
《2022年6月、浪江町に複合施設「ふれあいセンターなみえ」がオープンした。JR浪江駅に近く、帰還した町民の健康増進や地域活性化を図る役割が期待されている。敷地面積は約3万平方㍍。デイサービスなどの福祉事業を担うふれあい福祉センターが入所し、福祉関連の事業所が事務所を置いている。福祉センター以外にも、壁をよじ登るボルダリング施設や運動場、図書室がある。
福祉センターは社会福祉法人の浪江町社会福祉協議会(浪江町社協)が指定管理者を務めている。業務を開始して3カ月以上が経った福祉センターだが、ピカピカの新事務所に職員たちは後ろめたさを感じていた。開設に尽力した人物が去ってしまったからだ。
「指定管理者認定には、40代の男性職員が町と折衝を重ねてきました。今業務ができるのも彼の働きがあってこそです。ところが、彼はうつ病と診断され休職しています。10月に辞めると聞きました。今は代わりに町職員が出向しています。病気の理由ですか? 事務局の一職員からのパワハラがひどいんです。これは社協の職員だったら誰もが知っていることです」(ある職員)》
同記事では、町内のふれあいセンターにある浪江町社協の事務局に勤める女性職員が、同僚職員に対し難癖をつけて困らせている実態を報じた。例えば、職員が備品の購入や出張の伺いを立てる書面を、上司の決裁を得て女性職員に提出しても「何に必要なのか」「今は購入できない」などの理由をつけて跳ね返し、書類の提出が滞ったという。時には人格を否定する言葉で罵倒することもあったと、当時勤めていた複数の職員が証言した。
休職し、退職を余儀なくされた男性職員は女性職員より上の役職だった。しかし、女性職員から高圧的な態度を取られ、部下からは「なぜ指導できないのか」と突き上げを食らい、板挟みとなった。2022年10月にこの男性職員を直撃したところ、
「2021年春ごろから体に異変が起こり、不眠が続くようになりました。心療内科の受診を勧められ、精神安定剤と睡眠導入剤を処方されるようになり、今も通院しています」と窮状を訴えた。
男性職員は心ない言葉を浴びせられていたとも話した。
「2022年春に子どもの卒業式と入学式に出席するため有給休暇を取得しました。その後、出勤すると女性職員から『なんでそんなに休むの?』と聞かれ、『子どもの行事です』と答えると『あんた、父子家庭なの?』と言われました」(同)
同記事では《子どもの行事に出席するのに母親か父親かは関係ない。他人が家庭の事情に言及する必要はないし、女性職員が嫌みを言うために放った一言とするならば、ひとり親家庭を蔑視している表れだろう。そもそも、有給休暇を取得するのに理由を明らかにする必要はない》と本誌の見解を述べた。
2022年11月号の記事では、当時の事務局長にパワハラを把握しているかどうか尋ねたが「全事務局の職員に聞き取りをしなくてはならないと思っている」と答えた。その後、同社協は弁護士を交えて県内外に複数ある拠点の職員も含め、全職員を対象にアンケートを行った。本誌が再び取材した2023年2月20日に時点では、当時の同社協会長(理事長)が「パワハラに関与したとされる職員への対応、社協内でのハラスメント対策をどうするかも含め、弁護士と相談しながら進めている」と話し、女性職員については「処分するかどうかの話までは発展していない」と答えた。
本誌が最後に取材してから1年半余り。その間に、同僚から「パワハラ行為の加害者」と指摘された女性職員は退職し、元職場を訴えた。いったい何があったのか。
裁判を傍聴しようと地裁いわき支部に訴訟日程を確認すると、「浪江町社協が被告の民事裁判は行われているが、非公開審理のため教えられない」という。
そこで同社協を訪ねると、事務方トップの佐藤祐一事務局長(常務理事を兼務)が対応した。
「当該職員については、懲戒審査委員会を開いて昨年4月に出勤停止5日の処分を下しました。当該職員は今年3月に退職し、出勤停止処分の撤回と、出勤していた場合に支払われるはずの給料を求めて当社協を相手に裁判を起こしました」
同社協が訴状を受け取ったのは今年5月。本誌が報じたパワハラが原因なのか。
佐藤事務局長は「係争中のため回答は控えます」と口をつぐんだ。
複数の職員がパワハラを訴えていたとしても、処分を下すまでには事実の認定や、本人から弁明を求めるなど段階を踏んだ手続きが要る。懲戒審査委員会は正当な手続きを経たのか。佐藤事務局長は誰が委員を務めているかは明かさなかったが、外部有識者、職員代表など3人からなる委員が審査したという。
共産系労組が団交を支援

町関係者によると、元職員は裁判に至るまでに1人から加入できる労働組合の支援を得て、同社協と団体交渉に臨んできた。同社協事務局が入居する複合施設「ふれあいセンターなみえ」には福島国際研究教育機構(エフレイ)の仮事務所がある。団体交渉の様子が同社協やエフレイの職員など多くの目に触れることになり、本誌にも情報が回ってきたというわけだ。
佐藤事務局長に「団体交渉でトラブルが顕在化し、ふれあいセンターなみえに出入りしている者に浪江町社協が揉めていることが広まった。本誌にも団体交渉の情報は届いている」と伝えると、佐藤事務局長は、元職員は在職中の昨年7月から団体交渉を開始したと認めた。
元職員を支援する自治労連傘下の福島公務公共一般労働組合(郡山市)にコメントを求めた。安斎通執行委員は「問題の発端は『政経東北』の記事だ。記事を基に社協が処分を下した。その点を考えるとコメントすることはない」という。
労組の連合関係者によると、「立憲民主党や国民民主党と関係が深い連合に対して、自治労連は共産党系の全労連の傘下にある。組織率が年々低下しており、公務公共労組は存在感が薄くなっていたが久しぶりに耳にした」という。
同社協のある職員によると、団体交渉が始まって以降、管理職が組合対応に追われ落ち着きを失っていたという。昨年末から今年3月にかけては、管理職が相次いで辞めた。この職員は、元職員を念頭に「自分のしたことがハラスメントだという自覚が本人になければ、周りはどうしようもない」と述べた。
人手不足に拍車がかかり、懸念されるのが浪江町内の福祉サービス低下だ。同社協は訪問介護事業を担っている。「終の棲家はやっぱり古里」と町へ帰還した人々は、その時は自分で身の回りのことができても、いずれは誰かの助けが必要となる。町が帰還者を増やすつもりなら、介護サービスは欠かせない。
佐藤事務局長は「かねてからの人手不足もあるが、職員が複数人辞めたこともあり、事業は拡大できていない。現状維持だ」と打ち明ける。労組の団体交渉が職場に負担を与えたのではないかと聞くと、「労働基本権は保障されなければならない。団体交渉への対応は民主主義国家で使用者側が払うべきコストと考えている」と述べるにとどめた。
福島国際研究教育機構でも職場問題

エフレイ予定地
事務局から同社協の執行機関である理事会には、今年5月30日の定例会で、提訴されたことが報告され、議決機関の評議員会には6月21日に報告された。元職員が起こした訴訟への対応は代理人の弁護士に一任している。
佐藤事務局長は町の介護福祉課長などを務めた元町職員。昨年4月に就任した。同社協は、名目上は民間の社会福祉法人であるが、他の多くの社協と同じように、独自に福祉事業を行うというよりは自治体の仕事を受注し、予算上も依存しているため「町の外郭団体」という位置付けにある。同社協の事務局長は代々、町職員経験者が務めており、会長に至っては2022年5月までは浪江町長が兼ねていた。現在の会長は、昨年6月に就任した元町教育長の畠山熙一郎氏。他に人員不足を補うため町職員2人が出向しており、いわば町とは一心同体だ。町は同社協のトラブルにどう対応するのか。
浪江町社会福祉協議会の役員一覧(敬称略)
| 役職名 | 氏 名 | 備 考 |
| 会 長 | 畠山熙一郎 | 元浪江町教育長 |
| 副会長 | 青山 信一 | 浪江町民生児童委員協議会会長 |
| 副会長 | 佐藤 秀三 | 浪江町行政区長会会長 |
| 理 事 | 佐藤 祐一 | 浪江町社会福祉協議会事務局長 |
| 理 事 | 鈴木 辰行 | 浪江町行政区長会 |
| 理 事 | 佐藤 幹治 | 浪江町行政区長会 |
| 理 事 | 竹添 武 | 浪江町行政区長会 |
| 理 事 | 中西總一郎 | 浪江町行政区長会 |
| 理 事 | 大倉 満 | 浪江町行政区長会 |
| 理 事 | 末永 一郎 | 浪江町行政区長会 |
| 理 事 | 松本トミ子 | 浪江町婦人会会長 |
| 理 事 | 半谷 珠代 | 浪江町民生児童委員協議会副会長 |
| 理 事 | 小椋 正吉 | 浪江町老人クラブ連合会会長 |
| 監 事 | 原 芳美 | 業務の精通者等 |
| 監 事 | 佐藤 孝子 | 業務の精通者等 |
町介護福祉課の松本幸夫課長は、「訴訟を起こされたことは、今年5月に社協から報告を受けている。社協は弁護士に一任し、町として対応できることは今のところないと考える。相談があれば応じたい」。
最後に、同社協と同じく「ふれあいセンターなみえ」に仮事務所を置くエフレイも、ハラスメントとは無縁ではない。職員とみられる人物から、パワハラを訴えるメールが本誌に届いた。
エフレイの職場では、出向官僚の第一陣が「『第一村人』にあいさつされちゃった」と地元採用職員の前で嬉々として発言したことに代表されるように、地方を見下す言動が目立つなど、始動当初から霞が関出向官僚と地元採用職員の間でわだかまりが続いている(本誌2023年5月号「福島国際研究教育機構職員が2日で出勤断念 霞が関官僚の高圧的態度に憤慨」参照)。
海外から研究者を招く施設でハラスメントが横行していては、世界の研究者に忌避される。本誌としては改善を促すため、今後も「ふれあいセンターなみえ」内から被害情報が寄せられれば続報し、エフレイ関連の問題については英語版のネット公開も検討している。