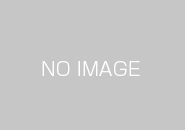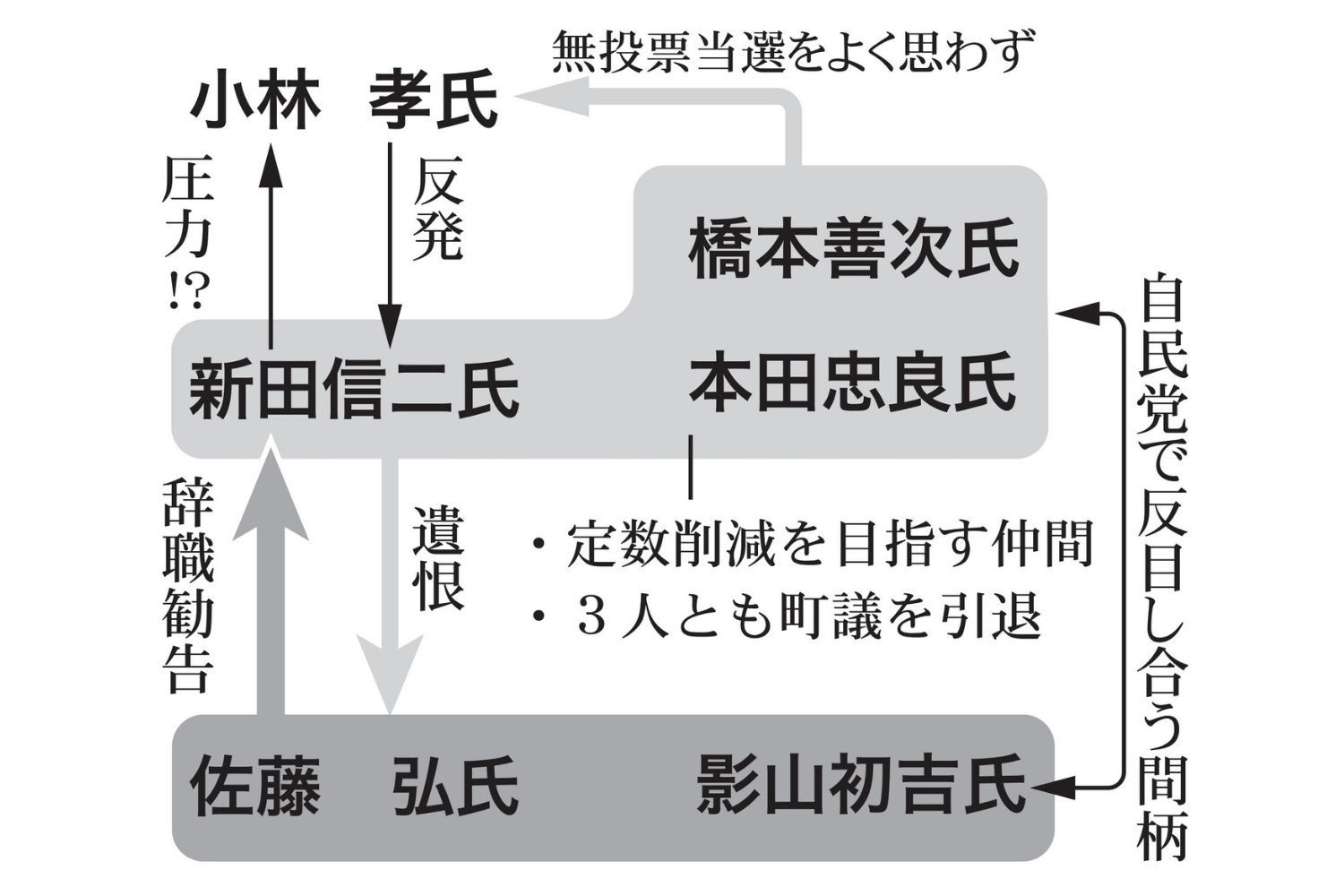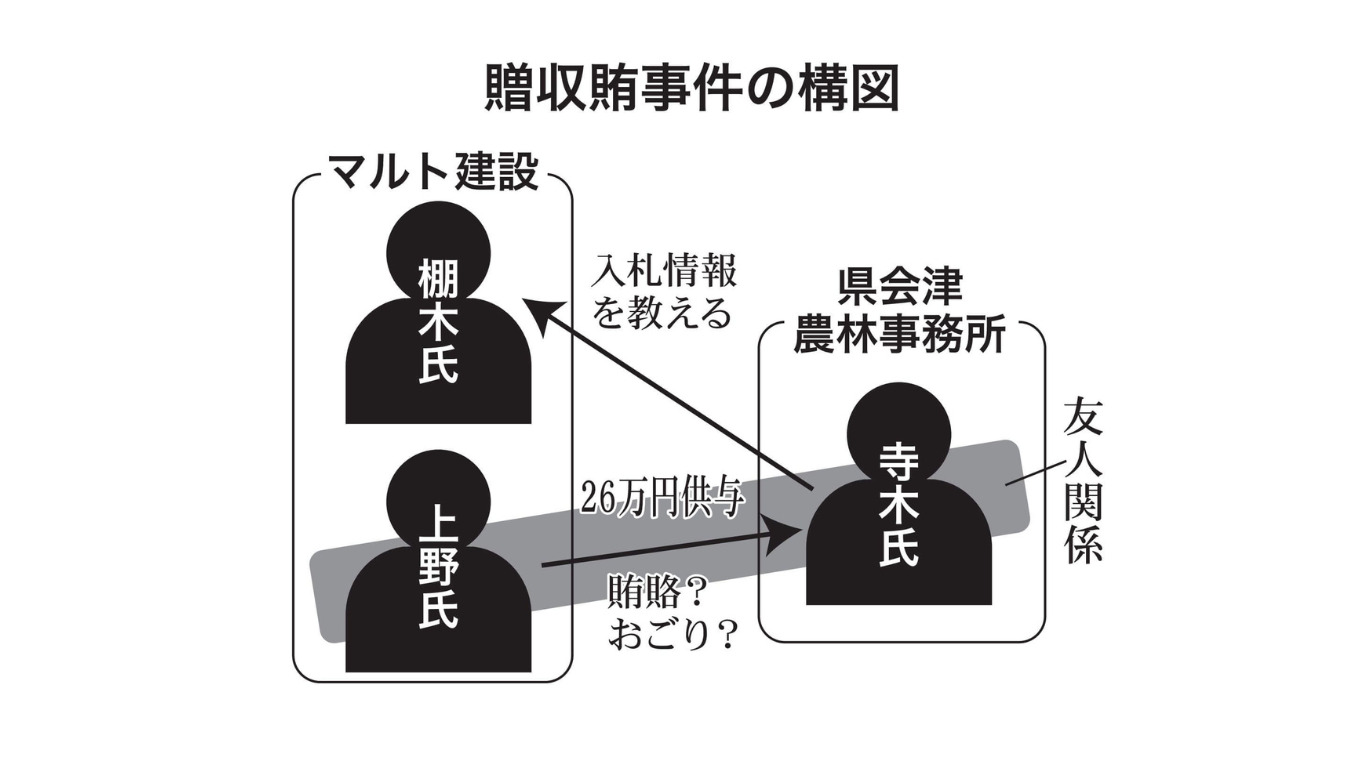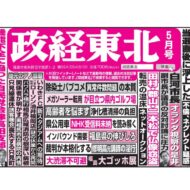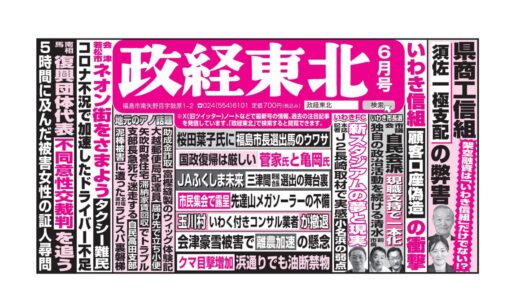【国のかたち①】敗戦から見た日米地位協定の歴史的背景
日米地位協定について論ずるときは歴史的な経緯を踏まえる必要がある。ざっと要約するとーー。
1945年8月 敗戦。
1945年9月 連合国軍最高司令官総司令部(GHQ、最高司令官マッカーサー)進駐。
1945年10月 GHQが幣原内閣に5大改革(内容省略)を指令。指令とは命令のこと。
1946年4月 女性の参政権を認めた新選挙法の下で衆院選総選挙を実施。第一党は日本自由党。
1945年5月 帝国議会が召集され、帝国憲法改正案を審議・議決し、同年11月、同改正案が日本国憲法として公布された。
※帝国憲法を改正して現在の憲法になったという筋書きには違和感がある。また、敗戦後の混乱が収まらないなかで国民投票を行うのは困難だったとしても、やれば新憲法の正当性を獲得し、理解も進んだ。
新憲法の特徴は、戦争放棄・戦力不保持と基本的人権尊重など民主的な条文。前者は連合国の総意、後者はGHQ左派の意向とされる。
当時、非現実的な「平和憲法」に異を唱えなかったのは、敗戦による精神的混乱と経済的困窮、さらにGHQへの過度な畏怖と忖度による。
1950年6月 冷戦が激化するなか、北朝鮮軍が南下して朝鮮戦争が勃発。GHQは吉田内閣に警察予備隊(自衛隊の前身)設置を指令した。
※GHQの指令一つで憲法9条が容易に踏みにじられたことになる。ただ、あからさまな再軍備は国民の支持が得られないから「警察予備隊」としたわけ。発足時、日本が交戦状態になったら警察予備隊は米軍の指揮下に入ることになった。自衛隊はそれを継承しているとされる。国会で何度も展開された不毛な戦力論争については触れない。
1951年9月 吉田首相がサンフランシスコ平和条約に調印。同時に、米軍の駐留を認める日米安全保障条約を締結。
1952年2月 同条約に基づいて日米行政協定(日米地位協定の前身)が締結され、日本は駐留軍(在日米軍)に基地を提供し、駐留費用を分担することになった。
地位協定の内容は、いずれ詳述するが、要約すると、米軍が必要とする土地(基地)、空域、海域を占有するほか、国内を進駐(占領)時と同様自由に行動できるようにするための取り決めで、憲法及び法律に拘束されない。
時間的には、平和条約→安保条約→地位協定となっているが、実際は地位協定を結ぶための安保条約→平和条だった。
直接統治は広範な反対運動をまねくだけでなく、行政コストが膨大にかかるため、間接統治・部分占領に切り替えた。
一方、吉田首相は国民が血を流さないで「独立」を果たすため〝売国的取り決め〟に応じた。そして今日に至るまで、吉田氏の後継者たちが主権回復のために尽力することはなかったから、「その後」の対応策はなかったと見てよい。
尊皇意識の強かった吉田氏が、国のかたちを大きく変える問題を、昭和天皇に上奏しなかったとは考えにくい。新憲法は天皇及び皇族のあり方が旧憲法と大きく異なるものの、「新憲法でも国体(天皇制)は維持された」と認識したのだろうか。それとも、「戦争に負けたのだから勝者のGHQに従うしかない」と諦めたのだろうか。
【国のかたち②ー1】日米地位協定の概要とその特異性
日米地位協定(安保条約に基づく在日米軍の地位を保障するための協定)は28条で構成されている。
第1条から第28条まで全条説明しても意味がないから、興味深いところを要約してみる。
第7条 「在日米軍は日本政府の各省庁機関が管理している公益事業及び公共役務を優先的に利用できる」
第9条2 「在日米軍の構成員は旅券及び査証に関する法令から除外される。また、軍人及び軍属並びにそれらの家族は外国人登録及び管理に関する法令から除外される」
要するに、米兵はパスポートもビザもなしで、自由に入出国でき、軍属と家族は出入国管理法の対象外となっている。
話は飛ぶ。オバマ大統領が広島を訪問したとき、軍用機で米軍横田基地(東京都福生市)に着き、ヘリコプターで米軍岩国基地(山口県岩国市)に向かい、そこから原爆資料館(広島市)を訪れた。大統領は最高司令官だから軍人だが、随行員は軍人ではない。
おそらく、怪しい人物でも米軍とつながりのあるアメリカ人は米軍基地から日本国内に自由に出入りしているに違いない。
トランプ大統領が訪日したときも横田基地から入国した。
日本政府はアメリカ政府に対して「国家・国民を辱めることになるから、大統領一行は表玄関の成田空港か羽田空港を利用してほしい」と、なぜ要請しないのか!?
再び話は飛ぶ。自衛隊元幹部の著書に「米軍横田基地で、米軍機でやって来た韓国の軍人に会った」との記述があった。日本は朝鮮国連軍とも地位協定を結んでおり、「国連軍兵士」は韓国内の米軍基地から日本の米軍基地に旅券・査証なしで出入りできる。基地のゲートは米軍が管理しているから、基地外に出ることも可能だろう。
米軍には、日本と韓国の間に国境がないのである。
沖縄県内で新型コロナウイルスが蔓延したとき、ノーチェックで入国した米兵が原因ではないかと噂になったことを付記しておく。
【国のかたち②ー2】日米地位協定における特権と法的免除
日米地位協定の条文を続ける。
第11条2 「米軍及び軍属並びにそれらの家族が使用するための物品に関税を課さない」
第12条3 「日本国内で公用のため調達する資材などの物品税、通行税、揮発油税、電気ガス税は免除される」
第12条7 「軍属は雇用条件に関して日本の法令に服さない」
第17条は刑事事件の裁判権を規定している。要約すると「軍人・軍属が公務中に刑事犯罪を犯した場合、米国の軍法裁判で裁かれる」としている。日本の警察・検察が扱えるのは米軍が身柄引き渡しを認めた場合に限られる。
1995年、沖縄の米兵3人による少女暴行事件の際、公務中でないにもかかわらず、米軍は身柄引き渡しに応じなかった。大規模な抗議集会が開かれ、米軍側の「好意的配慮」によって運用が改善された経緯がある。
ここまで書いてきて、条文を追っていくのがつまらなくなったので、思いつくまま書くことにする。
2004年、沖縄国際大学に米軍ヘリコプターが墜落した。現場は米軍兵士が規制線を張り、警察が立ち入れなかった。米軍は残骸をすべて運び出し、墜落現場から去った。
最近、連続して起きた米軍のオスプレイの墜落事故や着水事故の際も、日本側は見守るしかなかった。基地外でも、こうなのである。また、民間空港への戦闘機などの着陸が増えている。
かなり前のことだが、多数の死傷者を出した米軍機墜落事故の際は、脱出したパイロットは業務上過失致死傷罪に問われなかっただけでなく、被害者への補償は日本政府が行った。
十数年前、安達太良山の山小屋にいたとき、米軍機が爆音を立てて谷筋を急降下していった。日本の航空法は最低安全高度を定めているのにお構いなしだ。さらに「米軍基地内の地下水と土壌の汚染が深刻」と報道されている。
米軍及び米軍基地に日本の法律が及ばないルールになっている。
日米地位協定は1960年1月、ワシントンで締結された。署名したのは、日本側が岸信介、藤山愛一郎、石井光次郎、足立正、朝海浩一郎、アメリカ側がクリスチャン・A・ハーター、ダグラス・マッカーサー2世、J・グレイアム・パースンズ。
【国のかたち③】日米合同委員会の実態と日本の主権問題
日米地位協定第25条は協議機関として日米合同委員会の設置を規定している。
合同委員会の下に民事裁判管轄権分科委員会など25分科委員会と在日米軍再編統括部会、さらに施設分科委員会の下に施設調整部会など9部会があり、ほとんどの省庁が名を連ねている。
合同委員会のメンバーは次の通り。
《日本側》外務省北米局長(日本側代表)、法務省大臣官房長、農林水産省経営局長、防衛省地方協力局次長、外務省北米局参事官、財務省大臣官房審議官。
《アメリカ側》在日米大使館公使、在日米軍司令部第5部長、在日米陸軍司令部参謀長、在日米空軍司令部副司令官、在日米海軍司令部参謀長、在日米海兵隊基地司令部参謀長。
協議は月2回、ニュー山王米軍センター(東京都港区)と外務省が設定した場所で行われている。
議事録はつくられているものの、公開されていない。
日本側は全員文民だが、アメリカ側は公使を除いて軍人である。おそらく、米軍側の要求に対し、日本の省庁がいかに協力できるかを議論していると見られる。
そもそも日米地位協定も日米合同委員会も法的な根拠がない。協議内容は関係省庁のトップに報告されていると思うが、詳細かどうかは分からない。
協議内容が非公開なのは、あまりに主権を侵害する事案が多く、それが広く国民に知られると「反米・反米軍」感情が高まりかねないからだ。要するに、面倒なことになりかねないから公開しない方がよい――というもの。
与党政治家は「日米同盟は対等な関係」と強調するが、実際は従属というより隷属に近い。
日本はなぜ、こんな国になってしまったのか。それを検証するため、この原稿を書いている。
【国のかたち④】明治期の影響と敗戦の帰結
NHKが司馬遼太郎氏の『坂の上の雲』を再放送する。かつて、彼の著書を熱心に読んだ。だが、現在は「ちょっと違うんじゃないか」と思っている。
司馬氏は「明治期の日本人はまともだったが、その後はどうしようもない」と指摘する。本当にそうか。
「その後」の終着点(敗戦)を育んだのは、実は明治期のあり方そのものだったのではないか。
日清戦争では国家予算の3~4倍の賠償金と台湾を獲得し、日露戦争では引き分けにもかかわらず、アメリカの助力で樺太の南半分と千島列島を手に入れたほか、朝鮮半島及び中国東北部への覇権を確保した。
帝国主義の時代だから対外進出が不可避だったとしても、日本の政治家と軍人は二つの戦争に勝利したことで「戦争は儲かる」と確信したのは間違いない。
タダ同然に徴兵することができ、死傷者に対してわずかな補償で済んだから儲かるのも当然だ。犠牲者への配慮と敬意が徹底して欠けていたと言える。
昭和のエリート軍人たちは明治期の成功物語だけを継承し、より先鋭化させていった。そして、行き着いたのが悲惨な戦いを繰り返した挙げ句の敗戦だった。
石油の専門家の著書を読んでがっかりしたことがある。
石油を求めて日本軍はインドネシアの油田地帯に進攻したものの、タンカーが米軍の潜水艦に沈められ、原油を国内にほとんど持ち込めなかったという。日本軍には商船を守るという考えがなかったのである。そこがアメリカと大きく異なる。
もう一つ。日本が占領していた旧満州に大きな油田(大慶油田)があったのに見つけられなかったという。
15年にわたる長い戦いで多くの命が失われたのに、その責任が問われることなく今日にいたっている。
【国のかたち⑤】明治政府と戦争の影響:歴史の再評価
学校で「江戸幕府は頑迷固陋、明治政府は新時代にうまく対応した」と教わった。本当にそうか。
若いとき、司馬遼太郎氏の『竜馬がゆく』を熱心に読んだ。後年、坂本龍馬記念館で龍馬の絵手紙を読み、違和感を覚えた。
龍馬は家族への手紙のなかで近況を報告したあと、「多額の金策をしなければならない」と愉快そうに書いている。思い返せば、長州に大量の銃を届けたり、商船を所有したり、大金を動かしていた。根拠もなく推測すると、外国の武器商人がスポンサーだったのではないか。
薩摩や長州の思想的な背景などはよく知らないが、彼らが維新以降の政治と軍事のありようを決めたのは間違いない。
さらに言うと、日清・日露両戦争、軍閥台頭、戦線拡大、日米戦争を主導したのは薩長の藩閥政府であり、その帰結が敗戦だったのも疑いようがない。
明治政府は、廃藩置県、王政復古・華族令、学制(義務教育)、徴兵制、地租改正のほか、神仏分離令、一村一神社制、歴代天皇確定などさまざまなことを定めた。
現在、当然のように受け入れているルールや事象の多くが、意外にも維新後につくられている。
【国のかたち⑥】戦後の総括と隠蔽された歴史
敗戦が必至になると、軍部は戦犯に問われることを恐れ、歴史的資料と言える軍事関連文書を大量に処分した。それによって上からの命令だった証拠がなくなり、戦地の兵士が戦犯に問われて断罪された。
特に捕虜収容所を管理していた軍人・軍属は収容者の恨みを一身に買って過酷な報復を受けた。日本軍は兵站を軽視していたので、日本兵でさえ食料に窮するなか、捕虜はさらに窮した。それが虐待とされたのである。当時の食料事情を軍の公文書で明らかにできたらもっと軽い判決になったかも知れない。
占領地で「虐殺」とされている事件も、軍の公文書があれば犠牲者数などが分かり、被害者側の言いなりにならずに済んだ。具体的には、中国が「30万人」としている南京事件が好例である。
戦後、米軍による都市への焼夷弾攻撃や原爆投下を「戦時国際法違反」と声高に言えないのは、日本軍が行ったすべての行為を明らかにしないからだ。
不可解な事件もある。細菌を研究していた関東軍防疫水防部(731 部隊)は、米軍に研究結果を提供することで戦犯を免れた。似たケースはほかにもあるに違いない。
実は、都市への無差別爆撃を始めたのは日本軍が初めてで、中国・重慶が大きな被害を受けた。加害を認めるのは辛いが、被害の実態を調査して真実を明らかにしない限り、米軍の残虐な行為を糾弾できない。
戦後の出発点として、少なくとも1930年から敗戦までの15年間の日本軍の行動を総括しなければならなかったにもかかわらず、戦勝国による戦犯裁判にすべて委ねたのである。
こうして、無謀な作戦を企図し、多数の兵士を戦死、病死、餓死に追いやった参謀たちは責任を免れた。これは自虐史観ではない。
言い換えると、敗戦の総括を怠ったから、アメリカへの隷属に違和感を覚えないような国のかたちがつくられたのだ。
もちろん、混乱のなか、食うために面倒なことは考えたくないのは理解できる。しかし、政治家やリーダーがそうでは、国の未来は暗いと言わなければならない。
吉田茂元首相は高知の板垣退助の腹心だった竹内綱の5男として東京・神田で生まれ、吉田家の養子になった。岳父(妻の父)は旧薩摩藩士の牧野伸顕。牧野の父は大久保利通で、その次男だった。何度も大臣を歴任した政界の重鎮。
吉田氏が「薩摩」の薫陶を受けたのは間違いない。敗戦から80年になるのに、いまだに敗戦・占領状態から抜け出せずにいるのは、吉田氏及びその後継者に国家百年の計がなかったから――と断言する。
【国のかたち⑦】地位協定改定の必要性と日本の未来
日米地位協定を根本的に改定するには、政治家、官僚、国民が一体とならなければ実現しない。それは、日本の置かれた屈辱的な現実を世界にさらすことになる。それでも必要なのだと思う。
安倍晋三元首相の対応は「アメリカ(軍)さん、日本から出ていかないでくれ」というもの。
確かに、中国の軍事的脅威は深刻で、在日米軍を必要としている。だからと言って、これまで通りでよいことにはならない。
これまで述べてきたように、日米地位協定は日本政府とアメリカ軍(在日米軍)との取り決めで、アメリカ政府及び国務省の関与と影響力は小さい。
現在、土地、空域、海域を無償で提供しているほか、毎年6000~8000億円(駐留経費の七十数パーセント)を負担し、さらに高額な武器を毎年購入している。また、通貨、貿易、国債購入など、日本はアメリカに大きな貢献をしてきた。戦後復興の借りは十分返したと考えてよい。
問題なのは、在日米軍が米軍にとっては大きな利権になっていることだ。容易に手放すはずはなく、激しい抵抗が予想される。容易に考えられるのは、日本の政治家・官僚・マスコミが〝アメリカの代理人〟のように地位協定改定に難癖をつけること。効果的なのは、推進者のスキャンダルを暴くことだ。
もっと怖い話もある。ロシアに亡命した元CIA職員のスノーデン氏は「米軍は、日本がアメリカから離反したら通信や電力や交通機関などがマヒする仕掛けをしている」と述べたことがある。どれくらい信憑性があるのか分からないが、つくり話ではあるまい。
イラク軍がクウェートに侵攻する前、中東駐在のアメリカの女性外交官がフセイン大統領に「アメリカは(イラクによる)クウェート侵攻に関心がない」と囁いたことを思い出す。イラク軍がクウェートに侵攻し、果ては拘束されて殺されたのは周知の通り。いわゆる湾岸戦争である。
周知のように、イラクに大量破壊兵器はなかったから、石油をめぐる戦争だったことが分かる。そのときの日本政府の対応は、確信がないのにアメリカの言いなりだった。恥ずかしくないか。
歴史は繰り返す。アメリカが「尖閣諸島に米軍は関与しない」と中国にささやくことも考えられる。あくまで想像だが、アメリカは何でもやりかねないことを承知しておくべきだ。
どんな国も、占領ならともかく、100年にわたる同盟関係は考えにくい。また、隷属的な関係を続けると国益を大きく損なう。
アメリカが覇権を断念し、かつての孤立政策に回帰するのを待つ考えもあるが、それでは遅すぎる。
【国のかたち⑧】憲法9条と在日米軍の矛盾: 自衛隊の合憲性を問う
日本の左派は憲法9条の改正に反対してきた。だが、憲法9条によって非武装となり、それを補完するため米軍が駐留することになった。だが、憲法が国のの基本なら、在日米軍は憲法に違反する存在と言わなければならない。「違反しない」と言うなら、在日米軍は憲法を超える存在となる。それで立憲主義、法治主義と言えるのか?
憲法9条を守れば、米軍がいつまでも駐留することになる。それでよいのか?
明らかに在日米軍も自衛隊も憲法9条に違反する。米軍の駐留を認めながら、自衛隊を憲法違反と批判する論理に正当性があるとは思えない。日本の官僚と政治家は屁理屈を重ねて自衛隊を合憲とし、装備などを拡充してきた。
ただ、左派の心配は分かる。自民党の政治家に軍事を委ねるのは危ない、と。
これにはニュートラルな軍事評論家が日本にいないことも影響している。一方、マスコミに登場する軍事評論家は自衛隊OBばかりで、武器の性能や戦術などを語れても、米軍の強い影響を受けているから日米地位協定など政治的なテーマを議論するのに適していない。
もう一つ心配なのは、日本の政治家が国家間の紛争に発展しかねない問題に鈍感なことである。現在、アメリカ(米軍)というクッションがあるから深刻な事態にならなくて済んでいる。
ロシアや中国にとって、日本が「虎の威を借る狐」のように映ることをもっと自覚すべきだ。
安倍元首相のように、国のかたちをはっきりさせないまま在日米軍と自衛隊を一体化すると、自衛隊は在日米軍の下部組織(下請け)に陥る。
昔の話をする。昭和30年ごろ、自衛隊員は制服を着て街を歩く「憲法違反」とか「税金泥棒」などと罵声を浴びた。憲法9条の考えが浸透していたというより、国民は戦争と敗戦の傷が癒えず、自衛隊(員)を怒りの対象としたのだ。
小泉純一郎元首相は「尊い犠牲があったから、今日の繁栄がある」と恥ずかしげもなく述べた。
戦争の犠牲が繁栄につながったのか?つながらないから戦争の悲劇があるのてはないか?まして、アメリカの隷属的なあり方を望んだはずはない。
そもそも在日米軍は日本を守るために駐留しているのではなく、覇権国家としての立場を維持するため敵対するロシアや中国を監視・牽制が主目的だ。日本防衛はついでに過ぎない。
【国のかたち⑨】 沖縄と首都圏の米軍基地問題: 日本の独立性を脅かす現状
日本に在日米軍基地は70数カ所あり、その70数%が沖縄に立地している。特に問題なのは、首都圏を囲むように米軍の横田基地、厚木基地、横須賀基地が存在することだ。さらに、都内港区にニュー山王米軍センターた赤坂プレスセンターの2施設があり、米軍関係者はヘリコプターで往来している。これは首都圏が米軍の人質あるいは盾になっているようなもの。こんな独立国はどこにもない。
アメリカ政府を説得するには「ニューヨークやワシントンDCの近くに外国の軍事基地があることに耐えられますか」と尋ねればよい。
アメリカが民主主義と国家主権を尊重するなら、日本の要望を理解してくれるはずだ。
もちろん、心配なこともある。アフガニスタン・イラクのテロ容疑者を超法規的に拘束していたキューバのグァンタナモ米軍基地は1903年に租借し、1959年の革命後も返還を拒否している。
これを見ると、アメリカが覇権を放棄しても、日本から米軍が完全に撤退しないことも考えられる。
核兵器についても触れたい。そのような危険な兵器を必要としない世界であってほしいと思うが、現実はそうではない。一人の独裁者の判断ひとつでで核戦争が可能な状態に変わりなく、それを国際的な取り決めで抑止することはできない。したがって、現在の国際的なルールを守って核兵器を開発するのは至難だが、ハードルが下がったらすぐつくれるよう研究すべきだと思う。
話を地位協定に戻すと、改訂は必要で、時間をかけて円満に解決するほかないということになる。それには、前にも述べたように、政治家、官僚、マスコミ、国民が一体となってアメリカに求め続けなければ少しも進まない。(終わり)