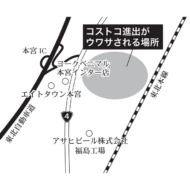男性の育児休業の取得が国を挙げて進められている。家庭と仕事の両立と、女性の労働力参入を意図し、前向きな企業への助成金も拡充した。ただ、制度は充実しても休業者の代替要員の確保は難しい。育休取得で雇い止めにあった公務員もおり、スムーズに取れるようになるまでに解消しなければならない課題は多い。(小池 航)
本誌男性記者の体験で見えた課題

県が常勤労働者30人以上を雇用する県内の民営事業所1400事業所を対象に聞き取りをした労働条件実態調査(2022年7月31日現在)では、21年度に出産し育休を取得した人は男女合わせて1035人。性別の取得状況は女性830人(取得率97・1%)、男性205人(同20・4%)だった。
男性の取得率はここ数年で大幅に伸びている。だが、平均取得日数は女性の297・7日に対し、男性は27・2日と乖離がある。常勤労働者30人を下回り、余剰人員がない小規模事業所はそもそも反映されていないので、現実の数値は男女ともに下回ると考えておくべきだ。
本誌を発行する㈱東邦出版は従業員10人以下の小規模企業。県の統計には反映されないが、29歳男性の筆者は育休を取った。
5月に第一子が生まれた。妻は県外の実家に帰省し里帰り出産した。夜中に産気づいたとの知らせが来て、福島市の自宅から車で向かうと着いた時には既に産まれており、出産には立ち会えなかった。病院は感染症対策を徹底していたため、母親の入院中に親族一組が病棟の待合室でしか対面できず、筆者は義母と会いに行った。
産科病棟に入ると、「おぎゃあ、おぎゃあ」と泣き声が聞こえる。自分の腕の中で力いっぱい泣き、一心に母親の乳を吸う様を見て、我が子と長い時間一緒にいたいという思いが強くなった。
職場に戻ると「育休を取りたいんですが」と切り出した。弊社の佐藤大地社長は「いいよ。取ろう。当面は育休の間にどう仕事を回すかを目的にしよう。体験記も記事にしといて」と言った。
育休は育児休業のことで、労働者が会社に対して子育ての休みを取れる制度。産前産後の女性が取得する産休とは別に取れる。育休は子どもが1歳になるまで取得可能。保育所の入所先が見つからないなどやむを得ない事情がある場合は、最長子どもが2歳になるまで取れる。休業中は180日まで給料の67%が、それ以降は50%がハローワークから労働者に直接支給され、社会保険料が免除される。事務の同僚に申請を頼むと、「育休取得はあなたが初めて」と言われた。
収入が減るのは痛いが、入社が浅くまだ収入は高くないので、67%の給付に代わってもダメージは少ない。何よりも子どもとの時間を大事にしたかった。
2020年度に厚労省から委託され、⽇本能率協会総合研究所が行った「仕事と育児等の両⽴に関する実態把握のための調査研究事業」の調査では、男性が育休を取らなかった理由(複数回答)の筆頭に「収入を減らしたくなかったから」(41%)が上がった。次が「取得しづらい雰囲気と上司の理解が得られなかった」(27%)、「自分しかできない仕事があったから」(21%)。男性が稼ぎ頭を自認し、仕事につきっきりであることが示された。
育休・介護休業は、出産・育児や介護といった人生の一大事で離職が進むことを、本人だけの不利益と捉えるのではなく、企業から人材が離れ生産力が低下する社会的損失と考え、労働者の家庭と仕事の両立を図る狙いがある。そもそもは「男は仕事、女は家庭」と性別的役割分業に基づいて、女性側に家事・育児や介護といった無償労働の負担を強いてきたことがジェンダー平等の観点から問題視されてきた。
さらに、雇用機会は増えているのに女性の職場復帰が叶わないのは、産業界にとっても有能な人材の未活用を意味する。人口減少による人手不足が深刻な日本では、家庭と仕事の両立と「女性活躍」は、自己実現を支える目的ももちろんあるが、政府・産業界がより女性を家庭外の労働に従事させるのが本来の思惑だ。
子育て中も十分に稼がなければならない。食費・学費は物価上昇に伴い上がるが、所得はなかなか上がらず、経済的な面から共働き世代がいまや主流だ。2000年は共働きが約940万世帯、専業主婦が約910万世帯だったが、2022年は共働き世帯が約1200万世帯、専業主婦世帯が約500万世帯となっている。男性が育休を取得し、子育てで主体的な役割を果たすことは、女性活躍=労働人口維持となり、人口減少下の社会が求めていると言える。
外部ライターに発注で対応

妻は今年3月まで勤めていた非正規職を辞め、出産したので無職。産休・育休はない。初めての出産ということもあり、生後3カ月ほどは実家のリラックスした環境で体を休めながら子どもと過ごした方が良いと、里帰り出産を選んだ。
生後間もなくの我が子と一緒に暮らしたいという思いはあったが、里帰り出産で夫である筆者が安堵したのも事実だった。親とは同居しておらず、気軽にサポートを得るのは難しい。夫の筆者が出産直後の回復期にある妻に代わり、家事の全てをこなさなければならない。出張があり、締め切りが近づけば帰宅は夜遅くなる。両立できるか不安で、妻の実家に甘えた。
育休は母子が福島市に帰ってくる8月末から29日間取ることにした。迎えるに当たり、時間に余裕が欲しかったからだ。日常生活を送りながら家事の分担を決め、役所や銀行の手続き、子どもの安全のために家具の再設置、親類への挨拶などを終わらせたかった。職場復帰を想定して家事や子どもの世話をする感覚も掴みたかったので、期間と時期は間違っていなかったと思う。
職場復帰後は、おむつ交換、子どもが朝起きる前に居間を掃除、洗濯物を干す、出勤、帰宅して子どもを風呂に入れ、寝かしつけるのがルーティーンになった。自らに「やったつもりになるな」とは言い聞かせている。
育休を取るに当たって業務の穴埋めを考えた。9月に編集した10月号の発行には加わらなかった。筆者は毎月発行する雑誌に記事を書く編集部員なので、業務期間の区別が付きやすい。空いたページを誰が埋めるかが問題だ。10月号は7月ごろから外部筆者に業務委託した。
本誌は従業員10人未満の小規模企業。人繰りが難しく、1人が抜けるだけでも大きな打撃だ。企業の負担を軽減するために、中小企業対象の助成金に出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)がある。男性従業員が子どもの出生直後に育休を取った場合、事業者に20万円が支払われる。肝は休業者の代替要員を雇った場合、さらに20万円が加算される。
「うまくできている」と思ったが、主な要件に「子どもの出生後8週間以内に開始し、連続5日以上の育休を取ること」とある。筆者は、育休を取る時は既に生後5カ月を過ぎていたため対象外だった。子育てパパ支援助成金は、出産直後で身体的・精神的にダメージを受けている妻を夫が付きっ切りでサポートすることを想定している。
子育てパパ支援助成金による中小企業への補助は出生直後のみだが、筆者のようにその時期以外にもニーズがあること、経営者が積極的に男性の育休を浸透させるためにも、金額を調整しつつ対象期間を広げても良いのではと思う。
外部ライターに原稿を発注することで、筆者は育休を取ることができ誌面の質も維持できた。ただ、同じ従業員でも営業部門は替えが効かない。編集部員は特集の方針こそ決めるものの、各記事は1人で書き、引き継ぎは比較的簡単に済む。一方、営業部員は各々が広告主などの顧客と関係を築き、チームで緻密に売り上げを積み重ねている。引き継ぎは容易でないだろう。
給料水準が低いことで、地方と中小企業を襲う慢性的な人手不足も頭を悩ます。前出の子育てパパ支援助成金で、代替要員と認められるのは直接雇用や派遣会社を通じて雇用した従業員。本誌で育休期間を補う臨時社員を募集し、ちょうどその時期に採用できるかというと現実的ではない。求職者も給与額と安定性の面から、有期よりは無期、短期よりは長期の雇用を希望する。
従来からあった育児休業とは別に22年から出生時育児休業(産後パパ育休)制度も始まった。子どもが生まれてから8週間以内に最大4週間休みが取れる。分割して取ることも可能だ。最大の特徴は、労使協定に基づいて労働者の側が希望すれば、休業しながら少しの間であれば就労ができる。引き継ぎや代替要員の確保が難しいといった現状を鑑みた。
育休を終え雇い止めに遭った臨時職員

ここまで男性が育休をどう取るかを書いてきたが、女性ですら育休を取りづらい実態がある。また、非正規職員は取れたとしてもその間に職を失ってしまう。
県内のある自治体に勤めていた30代女性が語る。
「私は年度ごとに雇用契約が更新される会計年度任用職員でした。上司は『若手が少ないから今あなたに休んでもらったら困る』と求めるほど職場の人数は最低限度でした。一昨年夏に第2子が生まれました。1年の育休を取ろうと上司に相談すると応じてはくれたのですが、『長すぎるんじゃないの』と言われました。説得され、9カ月の育休に縮めることで折り合いました」
夫は夜勤もある仕事で拘束時間も長いため、育児の負担は女性にのしかかる。乳幼児とその上の子を育てる大変な時期を乗り越えた後、保育所に預けて職場復帰しようと準備を進めていた昨年初頭、上司から「契約を更新しない」と言われた。
会計年度任用職員について多くの自治体は、「採用の門戸を広げるため」と国の方針に則り「〇年目以降は公募で合格した者のみ」と条件を設け実質雇い止めをしている。女性はまだ勤め先の自治体で定めた期限を迎えてなかった。
「有職者であることを証明し保育所の入園手続きをしていたが、無職になるので入園できません。家計のために共働きは必須です。育休明けで職場復帰に意気込んでいたのに求職しなければならなくなった。子育て支援を牽引する行政が、育休取得者に不利益を与えているのは許せません」(前出の女性)
女性は自治体の予算が減額され、雇用人数を減らす中、ちょうど育休中だった自分に白羽の矢が立ったと受け止めている。
家庭と仕事を両立させるには男性の育休を増やすことが重要だが、都道府県や企業ランキングの上位に食い込むための「目的」になってはいけない。育休がキャリアで不利益となることを恐れ、取りたくても申請を控えている人が多く潜在していることに目を向ける必要がある。