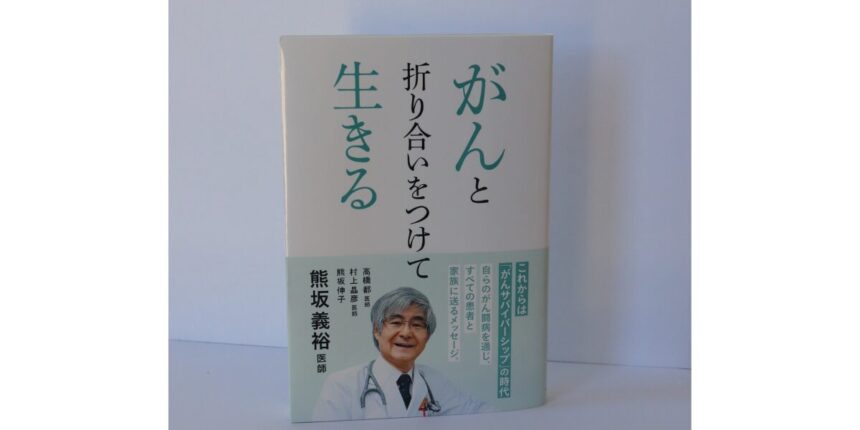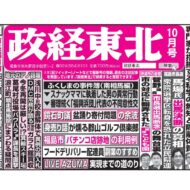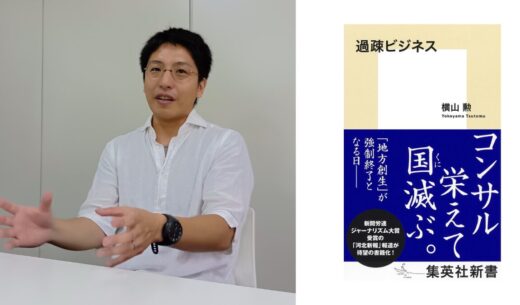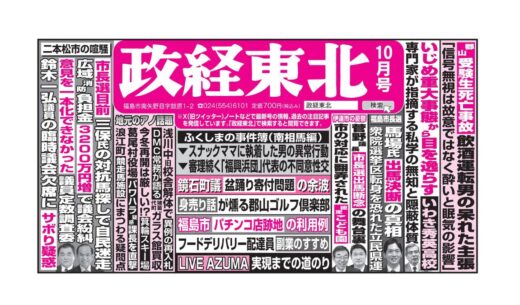10月26日、久しぶりに送られてきたメールに目を疑った。「昨年11月に前立腺がん(ステージⅣ)であることが判明し、3月末で医師生活にピリオドをうち、東京の病院でロボット手術を受けた。いまは静かに療養中」と書かれていた。
遅れている日本のがんサバイバーシップ支援
送り主は医師の熊坂義裕さん(72)。福島高校OBで元岩手県宮古市長。2014年の福島県知事選に立候補したこともある。その後、取材を通して熊坂さんと知り合った私は「政経東北の誌面で連載コラムを持ってほしい」と依頼。2015年4月号から2020年3月号まで『駆けて来た手紙』を連載していただいた。
しばらく連絡が途絶えていた熊坂さんからの衝撃のメール。さらにそこには「療養の暇にまかせて本を書いた」ともある。自身のがん闘病経験を綴ったという。
何が書かれているかは著書を読めば分かるが、どんな思いを込めて書いたのか、いまどんな気持ちで毎日を過ごしているのか、熊坂さんの率直な胸の内を知りたいと思い『駆けて来た手紙』以来、久しぶりに本誌への寄稿をお願いした。
熊坂さんの声に、読者の皆さんと一緒に耳を傾けてみたい。(佐藤仁)
◇ ◇ ◇
昨年11月14日に岩手日報社から上梓した『がんと折り合いをつけて生きる』について、本誌の佐藤仁記者から出版の経緯等についての寄稿を頼まれましたので以下に書かせていただきます。ちなみに2015年4月から2020年3月まで、本誌に60回にわたって毎月連載させていただきました『駆けて来た手紙』は、お陰様で2020年12月に同じ書名で幻冬舎から出版することができました。
最初に、私自身のがんについて記します。
2023年11月9日の朝、青森市で内科を開業する平井裕一先生(弘前大学医局の後輩)から私のPSA値(前立腺がんの腫瘍マーカーである前立腺特異抗原)が異常に高いとの連絡ありました。正に青天の霹靂でした。前立腺がんの患者さんもたくさん診てきましたので、この段階で自分が前立腺の進行がんに罹患していることを確信しました。
自らが糖尿病学会専門医にもかかわらず、今まで散々ほったらかしてきた持病の糖尿病の治療を目的に、前日の8日に平井先生を受診したのですが、「糖尿病のためだと思うが夜中に1、2回トイレに起きる」と話しましたら「念のためPSAも調べておきましょう」ということになったのでした。この検査が、その後の私の運命を左右することになったのです。
翌10日に東京都三鷹市にある東京国際大堀病院院長の大堀理先生を受診しました。大堀先生は、東京医科大学泌尿器科教授時代に日本で最初に前立腺がんのロボット手術を手掛けた前立腺がん医療の我が国の第一人者です。
触診、超音波検査、CTにてステージⅣの前立腺がんと診断されました。CTで肺、肝臓には転移を認めませんでしたが、PSAが高い場合は高率に骨への転移がありますので、この段階で腹を括りました。同日からステージⅣの標準治療である内分泌療法が始まりました。
同月14日に武蔵野赤十字病院放射線科にて骨への転移の有無を調べる骨シンチグラフィー検査を受けましたが、幸いなことに明らかな骨転移は無く、予後に一縷の望みを持ちました。
ただ、何のがんでもそうですが、自身の臨床経験からもステージⅣの場合は、いつ何が起きるか予断を許しません。患者さんに迷惑が掛からないように、今後のことを考え2024年3月末に診療を後継の医師に託し、46年に及んだ医師人生にピリオドを打ちました。
ステージⅣの前立腺がんに対しては、手術の適応はほとんどありませんが、一方で将来、骨盤内臓器に転移が起きた際に前立腺が無い方が尿路障害等をコントロールし易いとされていますので、大堀先生執刀の下で4月16日にロボット手術(全身麻酔)で前立腺全摘並びにリンパ節郭清をして頂きました。
現在は、経過観察をしながら再燃(再発)した場合はその都度治療(内分泌療法、放射線療法、化学療法等)を選択していくという状況です。
以上が今日までの経過です。
手術後最初に受診した大堀先生の外来診察の際、術後の病理診断の結果をお聴きし、「予断は許しませんが、もう少し時間(命)を与えられそうなので、これから何か世の中の役に立てることをやってみようと思います」と話しました。大堀先生からは、「是非やって下さい」と温かい励ましの言葉をいただきました。
職業柄もありますが、昔から「メメント・モリ」(ラテン語で「死を想へ」、つまり「自分もいつか必ず死ぬことを忘れるな」という意味)という言葉が好きでした。前立腺がんに罹患するまでは、概念的に「メメント・モリ」を理解していたに過ぎませんでした。「死ぬからこそ今を生きていることに喜びを感じられる」とはよく言われますが、罹患後は世の中の景色が変わって見え、今生きていることに感謝する毎日です。
自身ががんになって気づいたことがあります。これだけがんになった人がたくさん暮らしているにも関わらず、がんになった本人は、家族や職場や地域社会とどう折り合いをつけたらよいのか、逆に周囲は、がんになった本人にどのように接していけばよいのか、よく分からないという現実が日本社会に広く存在するということです。
これらの問題を解決していく研究分野が「がんサバイバーシップ学」ですが、日本は、がんの診断・治療は世界トップレベルであるにも関わらず、がんサバイバーシップへの取り組みはまだ始まったばかりと言わざるを得ません。このことへの懸念が、この分野の研究では我が国の第一人者である高橋都医師との鼎談を思い立った理由です。
また近年、コロナ禍の影響もあり、がん検診を受ける人が減少しています。検診を受けるかどうかは本人の自由意思に委ねられますが、検診受診率の減少は、がんの早期発見が減ることに直結します。勿論、定期的に検診を受けていても進行がんが見つかることがあり、私も日常診療で度々経験してきました。これらのことに対する思いが、同じく本書で岩手県対がん協会トップの村上晶彦医師との鼎談を希望した理由です。
私が運営法人の代表理事を務める国内最大の24時間無料電話相談「よりそいホットライン」でも、今回調査分析をした結果、がんに関わる相談が少なくないことが判明しました。今後、この分野の相談対応にも力を入れていこうと思っています。
がんに罹ってはいるけれども死なない人が、今後ますます増える社会になっていくわけですから、「がんと折り合いをつけて」、自身や家族ががんになってももっと暮らしやすい日本社会になるために、本書がその一助になれば幸いです。(熊坂義裕)
『がんと折り合いをつけて生きる』(岩手日報社刊、2024年11月14日発売、280ページ、税込み1540円)は各書店の他、福島民報本社・支社・支局、販売店でも取り扱っています。