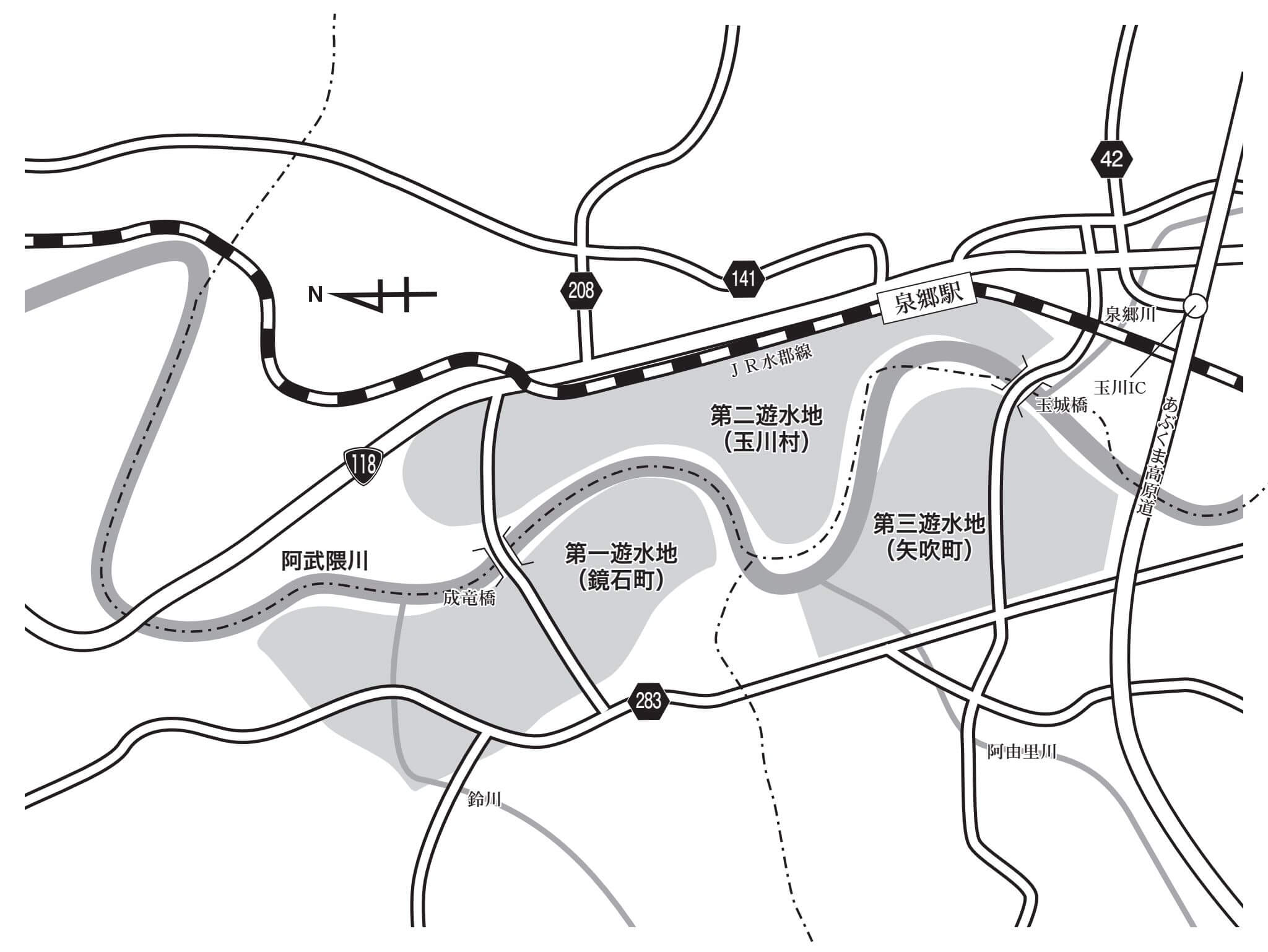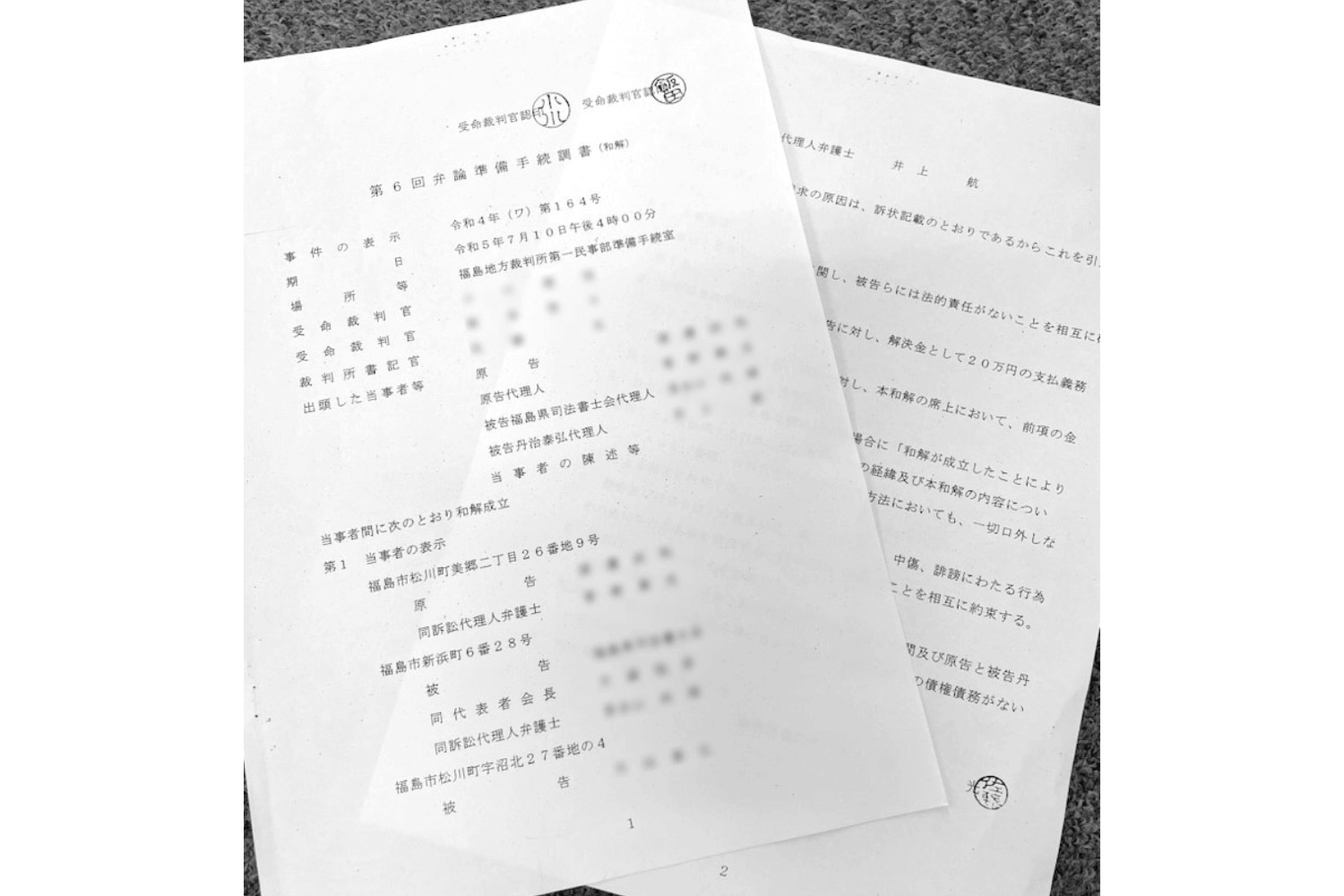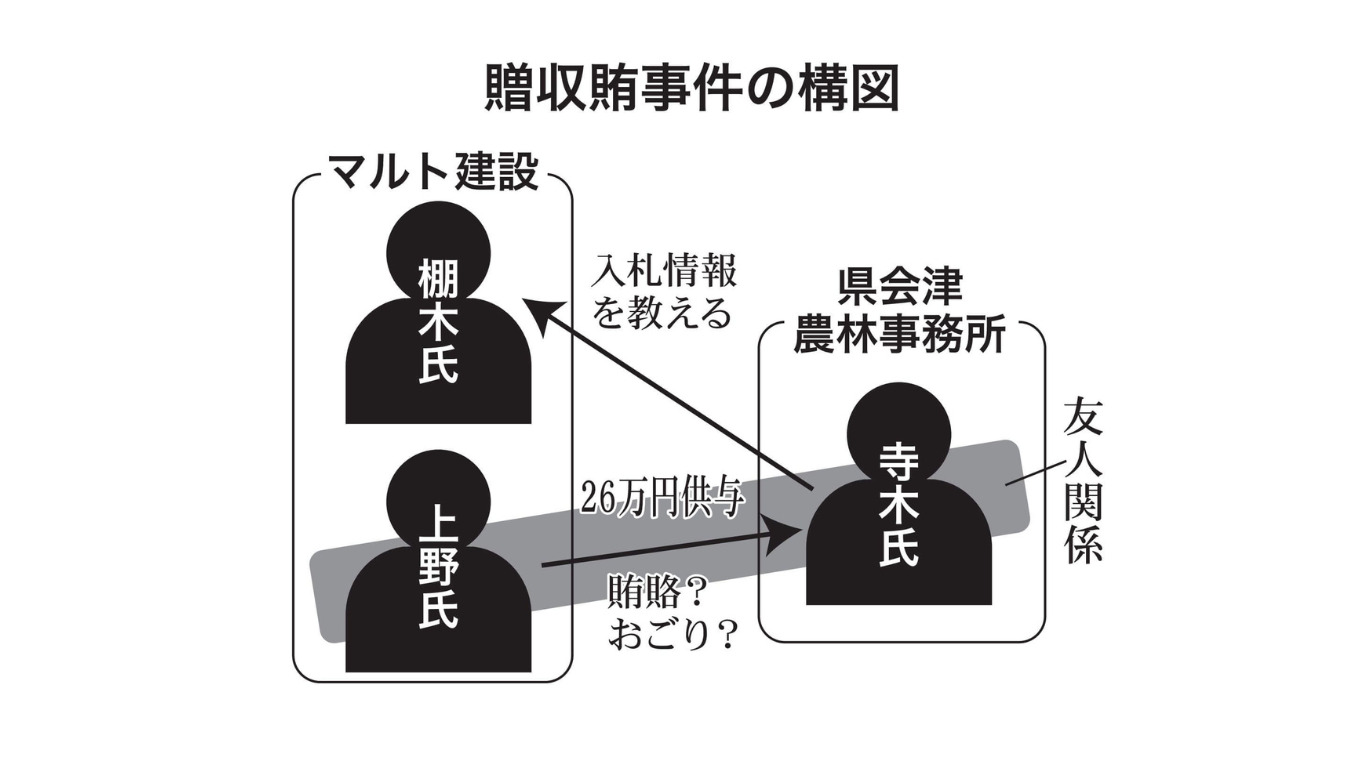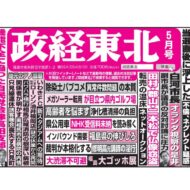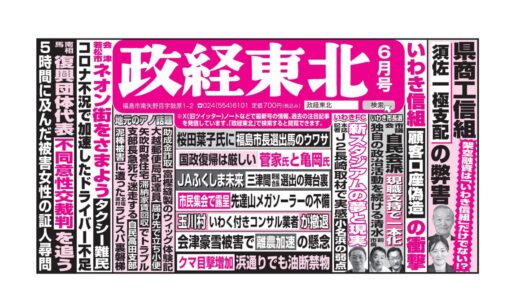福島成蹊コーチで甲子園出場・プロ選手輩出を目指す
福島成蹊高校野球部コーチに元プロ野球・楽天の横山貴明氏が就任した。横山コーチは聖光学院、早稲田大学、楽天、メキシカンリーグ、国内独立リーグなどを経て、地元県内に戻ってきていた。夏の県大会開幕直前の7月上旬、同校のグラウンドを訪ね横山コーチを取材した。
横山コーチの球歴

まずは横山コーチの球歴を振り返る。浪江町出身で、1991年4月生まれの33歳。小学校2年生で野球をはじめ、最初は内野手だった。中学時代は学校の部活でバドミントンをしており、むしろそちらに熱中していた時期もあったという。
「プロに入ってからも、感覚が良くないときなどにバドミントンのラケットを振って、腕の振りを確認することがあった。バドミントンをやっていてよかったと思います」(横山コーチ)
その経験が後の野球人生にも生きたのだ。同時に、中学時代は地元の野球チーム・相双中央シニアに所属し、1学年上のチームメイトには、プロ野球のオリックス・バファローズ、横浜DeNAベイスターズでプレーした赤間謙投手(楢葉町出身)がいた。
横山コーチは、当時のことを「赤間謙くんは本当に凄すぎて。自分は本当にへたくそだったんで」と振り返る。
転機が訪れたのは中学3年生のとき。新しいコーチが就任し、ピッチャーになることを勧められた。「絶対、プロに行けるから」と、自身の潜在能力を発掘してもらったという。そこから本格的にピッチャーをはじめた。
中学卒業後は聖光学院に入学。1年生の秋から主戦投手として活躍した。聖光学院は2007年から2019年まで夏の県大会13連覇(※コロナで甲子園大会が中止になった2020年の県独自大会を含めると14連覇)という大記録を達成したが、横山コーチの在学期間はその最初の年(2007年)から3年目(2009年)まで。1年生の夏はメンバー(ベンチ)入りしていないが、2年生の春、夏、3年生の夏と三度甲子園を踏んだ。最高成績は2年夏のベスト8。
3年夏は初戦(2回戦)で優勝候補のPL学園(大阪府)と対戦した。3―6で敗れたが、強力PL打線を相手に11奪三振を記録した。高校時にプロ志望届を出しても、指名された可能性があったと思われるが、プロ志望届は出さず、卒業後は早稲田大学に進学した。
大学の3学年先輩には、高校時代に「ハンカチ王子」として有名になり、全国制覇を果たした斎藤佑樹投手のほか、後にいずれもドラフト1位指名を受けプロ入りした大石達也、福井優也の両投手がいる。
横山コーチによると、「1年生が4年生と話すことはほとんどないというか、許されないような環境でしたが、その中でも福井さんにはいろいろと教えてもらい、よくしていただきました」という。
一方で、1年生から2年生に進級するタイミングで、東日本大震災・東京電力福島第一原発事故が発生した。浪江町の自宅は原発事故に伴う避難指示区域に指定され、家族は伊達市に避難した。
さらに、自身もケガに悩まされたが、そうしたさまざまな苦難を乗り越え、主に救援投手として活躍。大学4年時の2013年のドラフト会議で、東北楽天ゴールデンイーグルスから6巡目で指名を受けた。
プロでは、1年目に初登板で1球を投げただけで勝ち投手になるという珍しい記録も持っている。2年目にはキャンプ、オープン戦で結果を残して開幕ローテーションに入り、3戦目に先発起用されるなど期待されたが、なかなか結果が出なかった。その後は育成契約を経て2018年オフに退団し、メキシカンリーグや国内独立リーグを経験した。
その途中で、オーバースローからサイドスローに転向し、特に2020年シーズンは独立リーグでかなりの好成績を残したが、NPB球団から声はかからなかった。おそらくだが、NPB球団のピッチャー戦力が不足しているチームで、誰か1人でもケガをして投げられない状況になっていたら、シーズン途中の戦力補強という形で、横山コーチに声がかかっていたのではないか。言い換えると、時と運が揃わなかったということになる。同年の独立リーグシーズン終了を持って現役を引退した。
コーチ就任のきっかけ

こうしたさまざまな経験を持つ横山コーチだが、福島成蹊野球部のコーチに就任したきっかけは何だったのか。
同校の粕川樹コーチ(事務主任)はこう話す。
「ウチには外部コーチが2人いて、そのうちの1人が辞めることになり、私の知人と、横山コーチの知人を介して、ダメ元でお願いしたらOKをもらえたのです」
一方、プロ野球選手が高校・大学などで指導するためには必要な資格を回復する講習を受けなければならない。横山コーチは、現役引退後の2022年2月に資格回復した。当時はコロナ禍だったこともあり、オンラインでの講習だったという。
もっとも、資格回復したのは「何となくで、その時は特にそういった(高校・大学野球の指導者になろうとの)考えはなかった」(横山コーチ)という。
その理由は、自身の仕事があったから。現在、横山コーチは父親が設立した㈲一貴工業の役員を務めており、この秋には父親から社長を引き継ぐ予定。同社は伊達市を拠点にしており、浪江町の自宅があったところは社宅になっている。同社は原町火力発電所プラント工事や発電設備機械設置工事、運搬機設置工事などを手掛ける。従業員は40人ほどで、「父は(会社を興し)0から1にした。従業員やその家族のためにも、自分はそれを3、4に成長させていきたい」と話す。
そうした思いが強く野球から離れていた横山コーチだが、昨年夏、福島県大会のテレビ中継の解説を依頼されたことがきっかけで、野球に対する気持ちが少し再燃した。
そんな中、福島成蹊高校から打診があり、「甲子園出場と、プロ選手輩出を果たしたい」との思いを受け、引き受けることにした。自身の仕事があるため「来られる範囲で構わないので」ということも、引き受けた一因だったろう。
その際、母校・恩師である聖光学院の斎藤智也監督に連絡したところ、「冗談ですけど、『それはあまりいい報告じゃないな』と言われました」とのこと。斎藤監督としても、できれば自分のところに置きたい人材だったということだろう。
コーチングへの思い

コーチ就任は6月15日付。もっとも、前述したように自身の仕事があるため、毎日グラウンドに顔を出せるわけではない。それが母校のコーチをできなかった理由でもあろうが、それはともかくコーチ就任時は夏の県大会が間近に迫っていた。そのため、本誌取材時は「投球練習からいろいろなシチュエーションを想定するように」、「試合で感覚が良くない時や、疲労が出てきた時などは、ベンチでこういうことを試した方がいい」と、試合を想定した練習意識や、すぐに使えるテクニックを伝えていた。
加えて、コーチングに当たってはこんな思いを口にした。
「野球をはじめたころは楽しかったものが、高いレベルを目指していくと(壁にぶつかり)、楽しくなくなったり、辛いと思うことが増えていきます。結局は、練習をするしかないんですけど、野球を楽しいと思い続けられるような指導をしていきたい」
横山コーチが楽天退団後、海外でプレー先を探していた際、いろいろなチームの練習などに参加し、最終的にメキシカンリーグのチームに所属することになったのだが、海外チームのコーチは「今日はここがよかった」と、とにかくいいところを褒めてくれたという。その経験がそうした発想につながっているのだろう。そのほかにも、メンタル面の指導に定評がある聖光学院・斎藤監督、戦術面に長けた早稲田大・應武篤良監督を筆頭に、プロ野球、独立リーグ、海外リーグでさまざまな指導者に出会ってきた。それで得たものを今後のコーチングにどう生かしていくのかが楽しみだ。
この夏、福島成蹊は1回戦の勿来工業戦は5―1で勝利したが、2回戦は第6シードの相馬に大接戦の末、3―4で敗れた。いくら元プロ選手に指導を受けても、すぐに結果が出るわけではない。ましてや、コーチ就任から1カ月ほどしか経っていない。本格的なコーチング、チーム強化はこれからだ。
ちなみに、横山コーチは学生時代、バッティングも得意だった。3年夏の甲子園ではクリーンアップを任され、県大会ではホームランも放っている。早稲田大学が所属する東京6大学野球連盟は、日本の大学野球リーグで唯一、指名打者制を採用していないため、大学時代も打席に立っている。
ただ、バッティングに関しては、金子淳監督、粕川コーチらに任せ、ピッチャーのコーチングに専念するという。
最後に、ちょっと意地悪な質問をしてみた。「師弟対決ということも注目されると思うが、聖光と成蹊が対戦することになったら……」と。
横山コーチの返答はこうだ。
「師弟対決というのはあまり意識しません。聖光と成蹊の対戦は……ノーコメントで(苦笑)」
「とにかく選手を大きく育てたい」という横山コーチのもと、甲子園初出場、プロ選手輩出を達成してほしい。
▽あとがき(記者の記憶)△

横山コーチを取材して、あることを思い出した。
2008年10月。横山コーチが高校2年時にエースとして出場した秋季東北大会(準々決勝)を宮城県名取市の愛島球場で観戦した。相手は青森県の光星学院(現・八戸学院光星)で、同校には後にソフトバンクホークスに入団する右腕・下沖勇樹投手のほか、左投げの六埜雅司投手がおり、左右の2枚看板が売りだった。どちらが投げるにしても「聖光学院・横山VS光星学院の2枚看板」の投げ合いが注目だった。
試合は予想通りの投手戦となり、9回を終わって0―0で延長戦に突入した。延長10回表に光星学院が3点を挙げ、聖光学院はその裏に1点を返すも、3―1で光星学院が勝利し、その勢いのまま東北大会を制した。
その日、同球場では2試合が組まれていた。聖光学院と光星学院は第2試合で、第1試合も延長戦にもつれ込んでいた。前の試合が延長になると、ピッチャーは調整が難しいとされる。いつ試合が終わるか分からないため、どのタイミングで肩のウオーミングアップを開始すればいいか読めず、気持ちを入れ、試合に向けて集中力を高めていくのが難しいからだ。そのため、延長戦の次の試合では、優れたピッチャーでも序盤に失点してしまうケースが高校野球ではよくある。ただ、そんな難しい状況でも、両チームの投手ともにきっちり試合に入って力を発揮した。その辺は、さすがと感じた。
そんな記憶とは別に、こんな〝失態〟も。筆者は第1試合の終盤に球場に入った。第1試合は花巻東(岩手県)と東陵(宮城県)の一戦で、外野席で寝そべって何となく見ていたのだが、遠巻きながら「花巻東のピッチャーもすごそう」と思っていた。後で分かったことだが、その時に投げていた花巻東のピッチャーは、現在メジャーリーグで活躍する菊池雄星投手だった。後のメジャーリーガーを外野席から何となく眺め、何なら「次の『聖光学院・横山VS光星学院の2枚看板』の投げ合いが楽しみ。早く(第一試合が)終わらないかな」くらいの気持ちだった。あの時の自分に「バックネット裏に移動して、もっとしっかり見ておいた方がいい」と言ってやりたい。