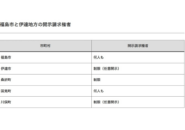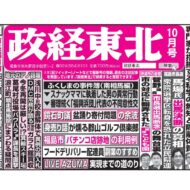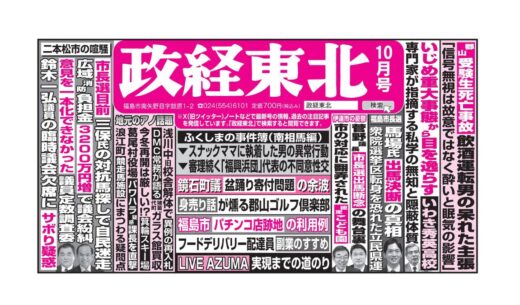矢祭町議会が2008年から採用していた「議員報酬日当制」が廃止されることになった。同町議会は昨年10月、「議会議員の報酬に関する調査特別委員会」を立ち上げ、日当制の是非について検証し、月額制に戻すことを決めた。全国初の試みとして注目を集めた議員報酬日当制とは、何だったのか。(末永)
月額制に戻しても町議選は依然低調

同町議会が議員報酬日当制を導入したのは2008年3月。それに先立ち、調査特別委員会を立ち上げて検討を進め、2007年12月に議員報酬日当制を盛り込んだ「町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例」を可決した。2008年3月に町議選が行われ、新議員の任期スタートと同じ、同年3月31日から同条例が施行された。
日当は3万円で、町課長相当職の平均年収を平均出勤数で割り、それに7掛けして算出した。日当が支給されるのは本会議や委員会、全員協議会などに限られ、おおよそ年間40日が支給対象となる。年間の報酬支給額は約120万円。これにより、年間約2000万円超の節約になる。導入から16年が経っているから、この間で3億2000万円が浮いた計算である。
ただ、導入からしばらくすると、議員報酬日当制のあり方を再検証する動きも出るようになった。全員協議会などで日当制の是非について話し合いが行われることがあったほか、いまから9年前の2015年3月には、「議会議員の報酬に関する特別委員会」を設置して、そのあり方を議論した。議長を除く全議員(9人)が委員となり、議長はオブザーバーという形で参加したため、事実上、全議員が議論に加わったことになる。
当時の特別委では、日当制の問題点として、以下のような点が挙げられた。
「日当制の場合、稼働した日は議員としての活動ができ、調査もできるが、それ以外の日に活動しようと思っても、できないという不利な点があるのは事実だと思う」
「矢祭町議会は委員会活動が制限されている。近隣町村では少子化問題特別委員会、地方創生に関する委員会などが存在しており、週2、3回ずつやっているところもあるようだが、もし矢祭町で週2、3回ずつやったとすると、月額制のときの報酬を超えてしまう」
そのほか、「議員は日当の支給日だけでなく、365日、議員として考えている」、「議員報酬は生活給になっている部分もある」、
「議員になると、冠婚葬祭に呼ばれることも多い」との意見もあった。
一方で、こんな意見も出た。
「私は3年前の選挙に出たが、日当制を頭において議員に立候補した。報酬をもらえるから議員活動をやるというのではなく、ボランティアに近いものだと思っている。昔は名誉職のようなもので、何の報酬もなかったと聞いている。3年間やってきて不自由は全然なかった」
「議員報酬は町民が額に汗した税金が入っている。月給から日当制になり、議員報酬は3分の1に減った。その分、社会福祉なり、住民サービスの向上につながったのではないかと思う」
「議員は1期4年で評価される。いまの議員は3年目でまだ1期も終わらない。次の選挙で当選した人がもう1回この話を進めるべきだと思う。いまの形で行くと、数ありきで何でも通るというのが見え見えで、それは町民にもハッキリと聞こえている。そういう感覚を町民に与えたことは、矢祭町にとってマイナスだと思う」
こうして意見を出し合った結果、オブザーバーの議長、同特別委の委員長を除くと、日当制維持派が4人、月額制への変更派が4人で同数になった。そのため、同委員会は同年4月に「本特別委員会の調査結果は、議員報酬を現状の日額制を維持するのか、月額報酬制にするのかの意見統一は不可能」との報告書をまとめ、委員会調査を終了した。
要するに、日当制を維持するか、月額制に変えるかの結論を出すには至らなかったのだ。
当時は「翌2016年3月に議員選挙があるから、改選後に再議論することになるのでは」と言われていたが、その後しばらくは、そうした動きはなかった。
調査特別委を設置
再び動きがあったのは昨年10月。議会内に「議会議員の報酬に関する調査特別委員会」を立ち上げ、昨年10月から今年2月までに4回にわたって調査・検討してきた。そのうえで3月4日までに調査報告書をまとめた。
その概要(各議員の意見)は以下の通り。
○委員会半数である4人の委員(大森泰幸委員、郡司浩子委員、鈴木正美委員、鈴木敏男委員)は、議員報酬日当制は、議員活動において弊害となっており、活動の妨げ、議員のなり手不足にもつながり、その解消のためには、2008年以前の「町議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例」に基づく月額制に戻し、期末手当も支給するとの意見だった。
○ほかの4人はそれぞれ意見が異なった。
○藤井隆治委員は、議員の基本年収を200万円(月16・6万円)とし、役員報酬として議長は100万円、副議長は50万円をそれぞれプラスすることが妥当と考えるとの意見だった。
○片野一也委員は、議員の実働日数は町長の実働日数である280日の4分の1以下、つまり70日以下で、これを町長報酬52万3000円に乗じて算出すべきとの意見だった。これに基づくと、議員の報酬月額は13万円(期末手当込みで年額200万円)、近隣町村の例にならって副議長月額は1・1倍の14万3000円(期末手当込みで年額215万円)、議長月額は1・4倍の18万2000円(期末手当込みで年額273万円)が議員活動の対価となる。
○本多勇也委員は、月額報酬制には賛成だが、月額10万円くらいが町民の理解を得られるのではないか、との意見だった。いま、物価高騰などで町民の暮らしは決して楽ではなく、政治とカネの問題がクローズアップされる中で、慎重に議論しなければならない。
○鈴木一委員は、日当制でも問題はないとの意見で、月額制にするなら、矢祭町職員の給与に関する条例を参考に、議員は1級1号同額の16万5300円、副議長は1級12号同額の17万8400円、議長は1級22号同額の19万3200円。
こうして意見が出された中で、2008年以前の「町議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例」に基づく月額制に戻すことに対する採決が行われ、賛成4、反対4の同数となった。そのため、委員長裁決により、同条例に戻すことを決めた。
その後、同特別委は3月議会にこの報告書を提出し、全会一致で可決された。今後は、前述の条例案が提出され、可決されれば、正式に日当制廃止、月額制への移行となる。3月末に開かれる予定の臨時議会で議案上程、採決されることになっているが、本稿締め切りの3月26日時点ではまだ臨時議会は開かれていない。ただ、特別委報告を全会一致で可決しているから、条例案も問題なく可決されるだろう。
2008年以前の「町議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例」に倣うと、月額20万8000円に加え、期末手当が支給される。前段で「日当制により、年間約2000万円超の節約になる」と書いたが、それがなくなる。つまりは議員報酬は合計で2000万円増、単純計算で1人当たり200万円増になる。
日当制導入時の宣言
こうして、1つの時代(制度)が終わったわけだが、議員報酬日当制は何をもたらしたのか。それを紐解く前に、2008年に議員報酬日当制を導入する際、関連議案提案理由として読み上げられた宣言文を振り返ってみる。
× × × ×
矢祭町議会は平成13(2001)年10月31日、議員提案によって「合併しない矢祭町宣言」を行った。同宣言は全国自治体への励ましとなり、目標となっている。こうしたことを踏まえ、われわれは議員報酬を日当制にすることを決意した。国会議員・地方議員に厳しい目が向けられている中で、有権者の信頼を取り戻すには、これしかないと考えたからである。(中略)
いま、日本に暗雲が立ち込めている。国の指導者が国民の立場に立っておらず、自分本位の判断に終始しているからだ。だが、矢祭町に限っては、役場・議会・町民が一体となって第3次総合計画を策定し、「元気な子どもの声が聞こえる町づくり」を進めている。それを実現するため、自治基本条例を制定し、町議の責務を「町民の信託を受けた町民の代表で、町の発展、町民の幸せのため、議会活動に努める」としている。町民の生活こそが、日々の議員活動の中で最も重要な課題である。
われわれが受け取っている議員報酬は町民が汗を流して納めた税金であることを忘れてはならない。議員報酬が上がり続けた経緯を振り返ると、執行部とのもたれ合いの中で、報酬審議会を隠れ蓑に、住民の目が届かないところで決めてきたのは否めない。右肩上がりの時代からお手盛りを重ねてきた結果が、現在の議員報酬である。50年後100年後も安定した矢祭町をつくるため、議会はもう一度、原点に立ち返らなければならない。(中略)
日当制は実費支給が原則だから、透明性が高く、議員活動への対価の意味合いが強くなる。これによって、報酬目当ての議員がいなくなり、町を憂える若者や女性が進出しやすくなり、有権者の選択肢が広がる。また、日当制導入によって「金のかからない選挙」が実現できるから、選挙運動のあり方にも一石を投じることになる。何より、経費の削減によって生まれる余財を、町民生活を豊かにする政策に向けることができるのを喜びたい。
この問題に正面から取り組むことは、決して地方自治を卑しめるものではない。むしろ、地方自治本来の姿を体現するもので、全国自治体の模範になると確信している。「合併しない宣言」を決議した矢祭町議会だからこそ、因習を打破できたと自負している。今回のわれわれの決断が、全国の郷土を愛する人々に受け入れられることを期待する。
× × × ×
ここにあるように、原点にあるのは同町議会が2001年10月に提案・可決した「合併しない宣言」である。国の方針で1999年ごろから「平成の大合併」議論が巻き起こった中、同町は早々に「単独の道」を選択した。当然、そのためには行財政改革などの自助努力が求められる。そうした過程で、議員報酬日当制を導入したのである。
もっとも、議員報酬日当制がベストなものだったかというと、決してそうとは言えない。議員は、議会に出席して、執行部が提案してきた議案を審議するのが一番の仕事だが、それだけではない。普段の生活で町民がどんなことに困っているのかをリサーチし、一般質問などを通して執行部に伝え、町政に反映させることも大きな役割だ。
「日当制にしたら、議会本会議や委員会以外は議員として活動しないのか」という話になり、実際、当時は町内でそんな声も耳にした。その点では、特別委で出た「議員活動は日当が発生する日だけではない」といった指摘はもっとも。
一方で、日当が発生する日は年間約40日で、議員報酬は3万円×40日で年額約120万円だったが、それをそのまま月額制にすればそういった問題は解決できた。つまり、年額120万円を12カ月で割り、月10万円の月額報酬制にすれば、同様の節約効果が期待できると同時に、日当発生に縛られ、委員会や調査などの活動が制限されることもなくなる。
その方がより分かりやすかったのは間違いない。
ただ、「議会が『合併しない宣言』を提案・可決した覚悟を示す」という点では、単に「議員報酬を月額10万円に減額します」というだけでは伝わりにくい。よりセンセーショナルに覚悟を表す、という点で議員報酬日当制は意味があったのだ。
2015年に設置された特別委で、藤田玄夫議員(今改選前の議長)が次のような発言をしている。
「なぜ、先輩議員さんが日当制にしたのか。当時、自分はいち農家でしたが、県の事業、国の事業に、町村が1割補助を出してくれるというところがほとんどでした。そういう形で大変保護が厚かったのですが、矢祭町は『合併しない宣言』をしてから財政調整基金が少ない。そういうことで行財政改革が始まり、その中で、議会の定数の見直し、報酬の見直しが行われ、現状があると認識しています。当時、自分が農家だったころは、町全体が頑張っているのだから我慢しなきゃな、自分たちも頑張らなきゃな、という思いでやっていました。行革、議会改革をしてきたうえで、いろいろな行政サービスが生まれてきたことは確かだと思います。そういう中で、財調に余裕が出てきたから報酬を見直すとか、そういうありきたりでは、なかなか町民の人たちは納得してくれないと思います」
藤田議員は、議員報酬日当制導入時はいち農家として、「町全体が頑張っているのだから我慢しなきゃな、自分たちも頑張らなきゃな」と思い、その中で、後に自分も議員として町のために働きたいとして議員になった。そう考えると、「議会の覚悟」はきちんと伝わっていたことがうかがえよう。
「古い選挙」からの脱却
もう1つは「古い体質の選挙」からの脱却だ。当時を知る関係者はこう話す。
「かつての選挙は、議員(候補者)が事務所(自宅)で支持者に飲食をふるまうなど、『選挙=支持者への接待』のような意味合いがあった。支持者側も『年間数十日の活動で相応の報酬がもらえるのだから、このくらいは当然』と遠慮がなかった。議員報酬日当制を導入したころは、そこまで大っぴらではなかったものの、まだまだその名残があった。だから、『(議員側が)われわれも大した報酬をもらっているわけではないから、そういう(選挙=支持者への接待のような)選挙はヤメる』という意味もあった」
前段で紹介した日当制導入の際の宣言文に「金のかからない選挙が実現でき、選挙運動のあり方にも一石を投じる」とあった。一見、格好よく聞こえるが、実際はそういった古い体質の選挙が行われており、それを変えていく意味合いがあったということだ。日当制導入後はそうした体質は薄れていき、いまでは完全になくなった。この点も、議員報酬日当制導入の効果と言える。
ところで、同町では3月19日告示で町議選が行われた。定数10に対し、現職の10人が立候補し、無投票での当選が決まった。町選管によると、無投票は1963年の町制施行以来初めてという(補選は除く)。
矢祭町議選当選者(届け出順)
藤井隆治 (54) 無現
大森泰幸 (75) 共現
藤田玄夫 (65) 無現
片野一也 (65) 無現
緑川裕之 (66) 無現
鈴木正美 (66) 無現
鈴木敏男 (71) 無現
本多勇也 (67) 無現
鈴木 一 (72) 無現
郡司浩子 (60) 無現
議員報酬を月額制に戻す議論の中で、「月額制に戻すことで、なり手不足解消につながる」、「新しい人が目指しやすくなる」といったメリットが挙げられていたが、今回の選挙では新人の立候補はなかった。
町内の有力者は「何人か若い人に声をかけてみたけど、立候補には至らなかった。確かに、報酬が月額制になったことで、新たな動きを期待する声はあったが、決まったのは選挙直前でしたからね」と話した。
「合併しない宣言」後の改革が終焉
本誌は町議選告示日に、町内で議員報酬日当制廃止の是非について聞いてみた。
「少なくとも、(なぜ日当制を廃止したのかと)騒ぎになっているということはないですね。(告示日午前中の時点で)今回の選挙が無投票になりそうなこともそうだけど、関心が薄れているということもあるのかもしれません。それにしても、とにかく静かな選挙ですね。(自宅周辺には)まだ1台も選挙カーが来てないですよ」(年配の女性)
「当時は、『緊縮、緊縮』、『切り詰め、切り詰め』という風潮だった。日当制を廃止したことに対しては、それぞれ思うことはあるんだろうけど、『合併しない宣言』後の『改革の時代』から変わってきているということだろうね。無投票については、うーん……どうなんだろうね。町民が『あと4年はいまの議員に任せられる』と考えたと見ることもできなくはないけど、関心が薄れているということの方が強いんじゃないかな」(年配の男性)
藤田玄夫議長(改選前)に話を聞いた。ちなみに、藤田議長は、前段で過去の特別委での発言を紹介した。今回は、議長として、特別委に調査を付託し、報告を受けた立場になる。
「私は日当制になってから議員になったので、それ(日当制)が当たり前でした。一方で、私が議長になってからは、事務局と相談しながら、なるべく委員会を開催するようにはしてきましたけど、どうしても報酬(日当)が絡むので委員会開催に遠慮があるというか、そういう側面もありました。月額制になれば、委員会活動などが活発になると思いますが、当然、責任も伴います。自分たちの代で制度を変えたわけですからね。もう1つは、(議員を目指す人が増えるなどの)新しい流れが生まれることを期待していましたが、今回の町議選ではそうならなかったのは残念です」
前述したように、議員報酬日当制は議会の覚悟を示すことが最大の目的で、町民に「町、議会も頑張っているから」と思ってもらえるなど、一定の成果はあった。同時に、古い体質の選挙から脱却することにもつながった。かつて、同町は「改革の先進地」として知られ、全国からの視察などが多かった。議員報酬日当制もその改革の1つだが、「合併しない宣言」から続いた「改革の時代」が終わったということだろう。