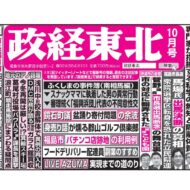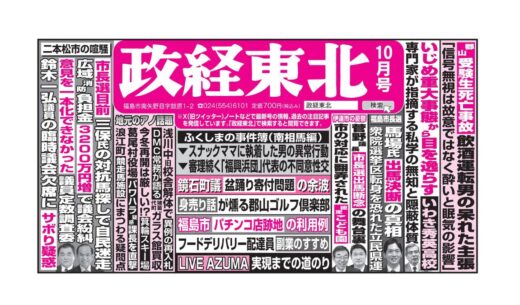東京電力福島第一原発事故後の廃炉作業に伴う問題について、責任を持つ東電と政府が一般市民に説明する会が7月9日、福島市で開かれた。東電・政府が市民代表の質問に答える場。廃炉のトラブルは起こるたびに報じられるが、問題点の整理のために会の様子を伝える。
「内部は未知」と再確認できた説明会

会の名称は「『ALPS処理汚染水』と廃炉等についての国・東電と住民との説明意見交換会」。国や東電に福島第一原発事故対応や廃炉の諸課題について、公開説明を求めている市民団体「住民説明会県北実行委員会」が主催した。同様の市民団体ネットワークが県内に複数あり、各地に経産省や東電の職員を招いて説明の場を設けている。
東電・政府は、原発構内で放射能汚染物質に触れて生じた汚染水を特殊な除去設備を通して薄めたものをALPS処理水と呼んでいる。放射性トリチウム以外の核種を除去し、基準値を大幅に下回るように薄めたとして、「健康被害を与えるものではなく安全性を確保している」との立場から「処理水」と呼び、多くのメディアでも準じている。
一方で、ALPS処理水の海洋放出に反対する立場の市民らは、核災害で出た汚染水は薄めて海に放出したとしても、流し続ければ海に溜まる放射性物質の総量は増え、トリチウム以外の核種も複数含まれていることから「汚染水の海洋投棄」と表現している。会の名称からも分かるように双方譲れない立場があり、「説明会」とは言うものの市民側から東電・政府への追及が目立った。
出席者は次の通り。
▽市民側
電気主任技術者の増子英一氏(郡山市)
農家の小池光一氏(福島市)
福島大共生システム理工学類教授で、地下水の流れを調べる水文地質学が専門の柴崎直明氏

▽政府・東電側
経済産業省の木野正登氏
原子力規制庁の佐藤暁氏、南山力生氏
東電HDの佐藤暢秀氏、佐藤雄一氏、高原憲一氏
まずは、経産省と東電が公表資料を基にそれぞれ公式見解を再度説明した。その後、市民側が政府・東電側に質問し、担当者が答えた。電気技術者の増子氏は、4月24日に作業員がコンクリートのはつり作業(削る、穴を開けるなどの作業)中に誤って深く掘り、埋まっていた電線を切断し、処理水放出が一時停止したトラブルについて質問した。
増子氏「地中に電線が通っているのは分かっていたはずだ」
東電・高原氏「現場では砂利が敷き詰められ、その表層がコンクリートで覆われていた。(ミスが起こった)電線管の周りは通常よりも深い40㌢のコンクリートで覆われていた。目的はコンクリートの剥離だったが、深さの目安と誤信していた砂利が出てこないので、通常よりも掘り進めてしまった」
増子氏「6000ボルトの高圧線だ。作業員は危険性を分かっていたのか」
高原氏「その作業員は高圧電線を扱う現場で作業してきたベテランだ。ただ、慣れがあったのだと思う。前日も現場で10㌢だけコンクリートを剥離する作業を行っており、40㌢の厚さのところもコンクリートは浅い部分しかないと勘違いしていた」
増子氏「作業員の腕に裂傷があったと聞いた。電撃による傷ではないのか」
高原氏「アーク(放電でできる火花のようなもの)による火傷だ」
増子氏「その日はIAEA(国際原子力機関)が来ていた。きちんと報告したのか」
高原氏「もちろん電線の事故は伝えた。ただ、あくまでもIAEAは処理水の海洋放出が正しくなされているかの評価に来た。停電でALPS処理水放出は一度止まった。IAEAには海洋放出を安全に止めていることを評価してもらったと理解している」
福島大教授の柴崎氏は主に原子炉建屋への地下水の流入についておさらいする質問をした。
柴崎氏「汚染水は常に発生しているが、地下水はどこから建屋内に流入したのか」
経産省・木野氏「原子炉建屋や地下通路のトレンチなどに貫通孔があり、事故後は放射線量が高くて近づけずメンテナンスができないので流入している」
柴崎氏「私が怒っているのは、たびたび地震に見舞われていることで把握している貫通孔以外に建屋の壁が損傷して、新たな穴が開いているのではないかという疑念だ」
木野氏「残念ながら、建屋内は非常に放射線量が高く、入って確認できない」
柴崎氏「建屋内への流入量を計測して公表しているが、スパンが毎日ではなく毎週の理由は」
東電・高原氏「計量するのに時間が掛かり、短い期間では数値として表れてこない。現在1週間レベルで評価しているが、低い値でも正確に計測できるようになれば、短期間で区切りたい」
柴崎氏「2022年と23年を比較すると3号機建屋内の滞留水は減っている。ただ公表されている放射性物質の量を見ると、3号機は増えている。なぜか」
高原氏「厳密な評価はないので確認中だ。水位が下がっていることが影響しているのかどうかも含めて確認中だ」
柴崎氏「2022年3月に発生した最大震度6強の福島県沖地震で、3月以降、急激にトリチウム濃度が上がっている。それが理由では」
高原氏「現段階では評価できていないので今後も評価していきたい」
柴崎氏「ALPS処理水の海洋放出は(廃棄物の海洋投棄を規制した)ロンドン条約に違反しないのか」
原子力規制庁・佐藤氏「違反している認識はない」
柴崎氏「理由は」
佐藤氏「法令に基づいて処理した水は諸外国でも同様の扱いをしている。よその国と異なる対応をしているとは認識していない」
柴崎氏「今年の海洋放出計画では10月まで放出することになっているが、県の廃炉安全監視協議会(柴崎氏が所属)の専門委員からは『安全だと言っても海水浴シーズンの7、8月は風評被害の観点からやめてほしい』と意見が上がった。それでも素案を変更しなかったのはなぜか」
経産省・木野氏「海水浴シーズンでやめてほしいという意見があったのは確か。ただ、処理水を減らすのも大事だ。安全上問題ないので我々としては素案通り進めた」
この後、観客席からの質問を受け付ける場があり、市民側が怒りをぶつけて会は紛糾。東電・政府側はそそくさと会場を後にした。事故から13年が経ち、単なるガス抜きの場と化していないか顧みる必要がある。