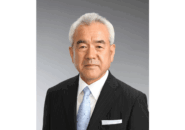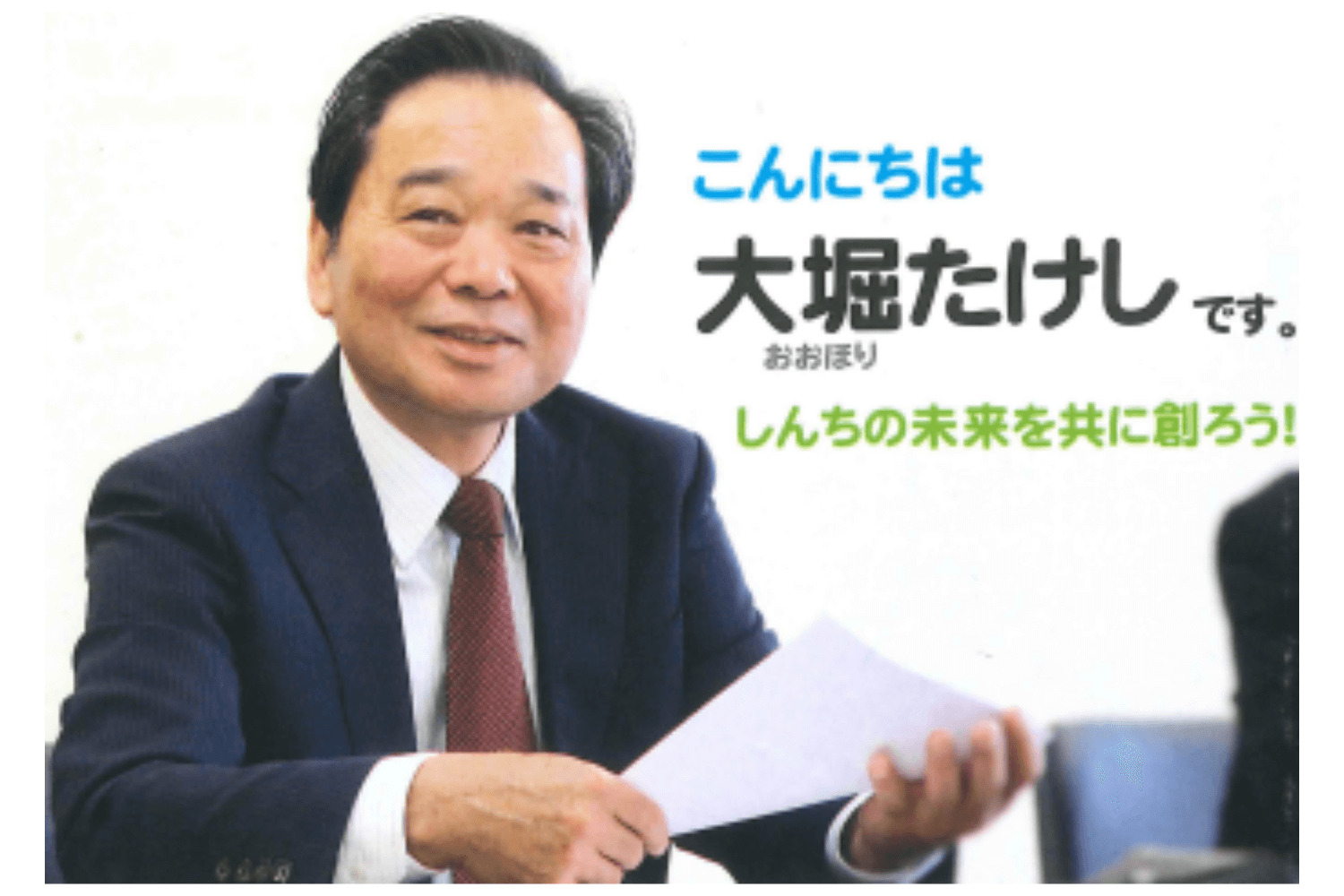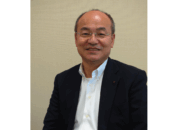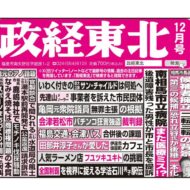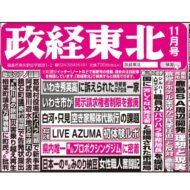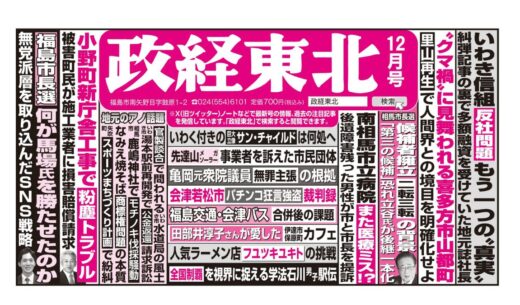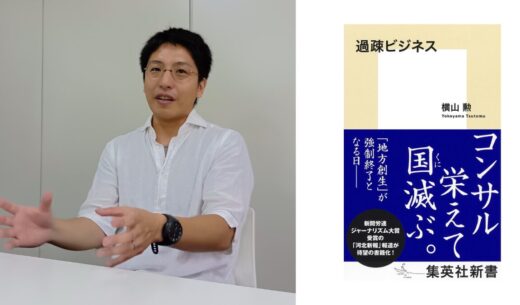ねもと・たく 1986年生まれ。東大法学部・法科大学院(首席)卒業、ハーバード大法科大学院卒業。国際弁護士として働いた後、アメリカやフランスの企業・国際機関で活躍。2024年の衆議院選挙で初当選(比例東北)を果たす。
昨年10月の衆議院選挙で初当選し、新しい世代の政治家として注目を集める根本拓衆議院議員(38)。国際弁護士としてのキャリアを生かし、デジタル政策や国際問題、そして長年の課題である被災地の復興や農業政策に至るまで、幅広い分野で精力的に活動している。政治活動に込める信念や未来への展望について根本議員に話を聞いた。
――8月8日に自民党両院議員総会が開かれましたが、今後の党の方向性についてどうお考えですか。
「7月の参議院選挙の結果も含めて感じているのは、自民党に対する信頼が損なわれていること、そして自民党が何をしたいのかというメッセージが明確に示せていないことの二つです。
信頼回復のためには、まず政治がクリーンでなければなりません。私自身、いわゆる派閥の不記載問題という逆風の中で厳しい衆議院選挙を強いられました。今一度、政治とカネの問題に厳正に対処し、議員一人ひとりが徹底的にクリーンであることが求められています。
また、世代交代を進め、若々しさと活気に満ちた政党であることも示していかなければなりません。選挙区を回る中で一番多くいただくお言葉は『あなたのような若い政治家がもっと活躍すべき』というものです。若い世代が活躍する政党であることを示し、現役世代の方々にも親近感を持ってもらう必要があります。
保守政党の原点に立ち戻ることも重要です。地元を日々歩く中で町内会や消防団、民生委員、各種青年団体など様々な方の公共的な活動があって初めて地域が成り立っていることを実感しています。本来の『保守』とは先人たちが築いてきた社会のあり方や制度、さらには人々の生活を支える様々な地域共同体を大切にしながら、時代に合わせて一歩ずつ前進することだと考えています。インターネット上で流れる耳障りの良い言葉で世論が動く時代だからこそ、むしろ逆に、地域を支える方たちとともに地に足のついた活動をしていくことが私たちに求められていると思います」
――参議院選挙で示された自民党への民意をどう受け止めますか。
「政治とカネの問題への厳しいご指摘や、自民党が何をしたいのか見えないという不信感を国民の皆様が持たれていることを痛感しました。特に物価高や重い社会保険料の負担に苦しむ現役世代からは『給与明細を見て悲しい気持ちになる』との声も聞きます。野党が掲げる消費税減税が日本全体を良くする処方箋にならないのだとしたら自民党は代わりに何をするのか、そのメッセージを明確に示していく必要があります」
――国会では厚生労働、農林水産委員会などに所属されていますね。
「国際弁護士としての経験が政治活動に生かされる場面が想像以上に多いと感じています。私は弁護士としてデジタル政策や国際ルールづくり、海外とのネットワーク構築などに携わってきましたが、自民党は思っていた以上に実力主義の組織で、1期生でもこれらの知見を生かす場を数多く得られています。例えば自民党のデジタル社会推進本部の提言では『データ戦略』パートの骨子を全て私が考え、官僚の方々と議論しながら内容を固めました。また、自民党青年局の幹部として訪問した台湾では、現地の政界や経済界の方々と、時には通訳を介さず英語で交流し、福島産品について一部残る輸入規制の撤廃を訴え、また日本や福島への観光や投資を呼び掛けました。
これまで取り組んだことのない分野でも法律のプロとしての経験が生かされています。農林水産委員会での森林経営管理法案に関する質疑では、民法の規定を応用したより効率的な森林管理のやり方を提案し、質疑後に林野庁の担当官から『今まで考えたこともなかったが、議論を進めていきたい』と前向きな連絡をもらいました」
――震災・原発事故からの復興についてはどのようにお考えですか。
「復興で特に重要な問題の一つが除染作業で生じた『除去土壌』です。中間貯蔵施設に集められた除去土壌は再生利用可能なものと最終的に埋め立て処分するものの二つに分かれます。しかし、このいずれもを『除去土壌』と呼ぶことによって、国際的に安全性が確認されている再生利用可能な土まで危険なものだという誤解を招き、国民の理解醸成を阻害しています。
私はこれを打開するため、再生利用可能な土を『復興再生利用土』などと呼称することを提言しています。安全性を明確に伝え、かつ福島の復興を応援することにつながるメッセージ性のある呼称が必要なのです。最初は担当官僚に『除去土壌は法律上の名称なので……』などと難色を示されましたが、私は様々な場でしつこいくらい何度も呼称変更の重要性を訴えました。その結果、先日発表された政府方針に『再生利用可能な除去土壌の呼称の在り方を検討する』との文言が盛り込まれました。官僚にはできない仕事をすること、すなわち地元を歩いて感じた課題を提言し、強い思いを持って自分事として政策を進めていくことが私の役割だと考えています」
――国民の関心が高い米問題や、後継者不足が深刻な農業の現状についてはどのようにお考えですか。
「農業分野には特に力を入れており、地元の農業者のお話をたくさんうかがってきました。農業は担い手の平均年齢が70歳近く、担い手の数も2040年代には現在の約4分の1の30万人にまで減少すると言われています。この厳しい現実を受け止め、少ない担い手によっても持続可能な農業を目指さなければなりません。そのためには、中山間地域で農業を営んでくださる方を食料安全保障の観点から支援しつつも、農業を主たる収入源とする専業農家を重点的に支援していくことが大切です。この方たちが安心して農業に取り組めるよう、農産物価格の安定化や米の流通改革が必要です。また、既存の収入保険など以外の生活の支援も、きめ細かく検討すべきです。
大規模化・機械化も重要です。少数の担い手で多くの農地を耕すためには、圃場整備に多くの予算を投入し、細かく分かれて機械化や効率化を阻んでいる農地をまとめる必要があります。自動操縦のトラクターやドローンといったテクノロジーの開発・活用も進めれば、さらに効率的に農作業ができます。
意欲と能力をお持ちの地元農業者に数多く出会ってきました。このような覚悟をもって前向きに農業に従事してくださる方たちが、地域の農地の主な担い手となり、しっかりと利益を出せる構造に農業を変えていくことが、持続可能な農業の実現につながると信じています」
――有権者に向けて一言。
「少しでも福島や日本を良くしたいとの一心で政治家を志しました。そのためには地域の皆さまから教えを受け、福島・日本になくてはならないと思われるような大きな政治家へと育てていただきたいと願っています。若さと情熱をもって地元に根ざした活動を一生懸命続け、自分の持てるもの全てをかけて一つひとつ成果を積み上げて参りますので、これからもよろしくお願い致します」